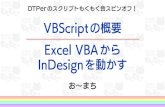のための Charm ~女の子の身を守るアプリ」...Charm ~女の子の身を守るアプリ コンテンツ ①ホーム ③学生によるレポ(体験記) ※「読みもの」は3
研究者の日常 を読もう! - staff.aist.go.jp ·...
Transcript of 研究者の日常 を読もう! - staff.aist.go.jp ·...

36 日本ロボット学会誌 Vol. 26 No. 1, pp.36~2, 2008
解 説 ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←
研究者の日常 or 非日常
SFを読もう!Let’s enjoy Sci-Fi novels!
梶 田 秀 司∗ ∗産業技術総合研究所
Shuuji Kajita∗ ∗AIST
←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←
1. は じ め に
学会誌のために軽めの記事を書いて欲しい,趣味の話で
OKということなので,今回は僕のお気に入りの SF小説を
2つほど紹介しようと思っている.よろしくお付き合いい
ただきたい.紹介するのは「未来の二つの顔」「都市と星」
という 2冊の長編 SF小説であり,どちらもロボット研究
者として読んでおいて損はない作品である†.
2. J.P.ホーガン「未来の二つの顔」[1]
この小説の冒頭にはこんな謝辞が掲げられている.
マサチューセッツ工科大学の人工知能研究班主任
マーヴィン・ミンスキー教授からいただいた貴重
な助力と助言にお礼を申し上げたい.一般に SF
作家は明日の科学的事実がどうであるかを予見す
ると思われている.実際には事態は逆であること
が多いのである.
1979年 2月
マサチューセッツ州アクトン
ジム・ホーガン
MIT の「人工知能の父」にアドバイスを受けて書かれた
原稿受付キーワード:
*
*
†ってゆーか,本当は「必読」と言いたい・・・.
SF小説だなんてワクワクするでしょ? それはこんなお話
である.
時に 2028年,人類は推論能力を持つ全世界コンピュー
タ・ネットワークを駆使して宇宙開発を推し進めつつあった.
ところが,ネットワークに組み込まれた人工知能HESPER
の不完全な推論機能のせいで月面の作業員が危うく死にか
かるという事件が起こる.事態を重く見た通信情報省は,
ネットワークの人工知能機能の排除と,HESPERを超える
次世代人工知能を開発していたレイモンド・ダイアー博士の
研究チーム解体さえ検討をはじめる.これに対抗し,自己
学習型人工知能の未来を確信するダイアーの提案をもとに,
壮大な実験がスタートした.直径約 2.1km,農業・工業施
設を有し,1万人が自活可能なスペースコロニー「ヤヌス」.
そこに組み込まれた最先端の人工知能「スパルタクス」は,
「ドローン」と呼ばれるロボット群(日本製!)によってヤ
ヌス全体を管理する.スパルタクスの学習能力を知るため,
ダイアー達はさまざまな障害を仕掛けてゆく.予想を超え
て柔軟に機能を維持したスパルタクスは,やがて障害の原
因を理解すると人間に対して反撃を開始する.それは,人
類とコンピュータの未来をかけた戦闘の始まりであった!
人工知能に詳しい方なら,ウィノグラードの SHRDLU
風のシミュレータや,フレーム問題の巧みな説明に舌を巻
くことだろう.また,機械系のエンジニアなら,壊しても
壊してもしぶとく自己修復する自動生産システムに究極の
産業ロボットの姿を見るに違いない.しかし,ここで特に
紹介したいのは,この物語の終盤のエピソードである.
スペースコロニー「ヤヌス」は静止した「スピンドル」を
軸としてドーナッツ状の居住区が巨大な磁気軸受を介して
回転する構造をもつ.人類とスパルタクスの戦いの中,安
定化制御装置との接続が失われ,磁気軸受自体にも損傷が
起こってしまう.スパルタクスはスペースコロニーの「物理
モデル」を持たないまま「超コンピュータ的な努力によりナ
ノセカンドに次ぐナノセカンドを戦い抜く」ものの,振動
レベルは次第に増大し,コロニー全体の構造限界に刻々と
近づいてゆく.これに気づいたダイアーの学生達は,端末
からコロニーの設計図や数式を懸命に入力して,スパルタ
クスに正しい制御則を教え込むことでコロニーの崩壊を食
JRSJ Vol. 26 No. 1 —36— Jan., 2008

研究者の日常 or 非日常 SF を読もう! 37
い止めるのである.モデルベースド制御の有効性をここま
で見事に描いた作品を僕は他に知らない.いやはや,ホー
ガン先生わかってるなぁ!
コロニー崩壊を無事食い止めた後,スパルタクスは人類
がこの実験を始めた真の動機を理解して自ら戦闘を停止す
る.ダイアー博士は,スパルタクスが人類のパートナーと
してあるべき姿に成長したことを宣言し,人類と人工知能
が力を合わせて宇宙を切り開いてゆく未来を予感させつつ
小説は終わる.
3. A.C.クラーク「都市と星」[2]
「その都市は,輝く宝石のように砂漠の懐に抱かれてい
た.」という書き出しで始まるこの小説は,世界中の SFファ
ンから熱烈な支持を受ける古典的な名作である.
地球上の海が消滅し,全世界を砂漠がとりまくようになっ
た遥かな未来,人類はただ 1つの都市「ダイアスパー」で
永遠の午後の世界を生きている.人々はメモリーバンクか
ら成人した姿で誕生し約 1000年の人生を送った後,次の
人生を再開するまで,メモリーバンクで眠りにつくという
サイクルを繰り返す.都市は高い文化を維持し,変化と活
気にあふれつつ,ダイアスパー自体は決して変わらないま
ま,既に 10億年の歳月が流れていた.
洗練された娯楽,芸術,学問を楽しむ人々の中,青年ア
ルヴィンだけは都市の外へ出て,かつての人類のように銀
河系を旅したいと願っていた.探索の末,忘れられた地下
の高速鉄道を発見したアルヴィンは,それに乗ってもう一
つのコミュニティー「リス」で暮らす自然志向な人々と,は
るか昔に地球にやってきた奇妙なポ リ プ
群体生物型の宇宙人,そ
してそれに仕えるロボットに出会う.このロボットの助け
を得て,ついにアルヴィンは宇宙船を手に入れる.地質学
的期間地中に埋まっていた宇宙船は「永久回路」によって
傷一つない姿を保っていた.その登場はまるで「宇宙戦艦
ヤマト」の発進シーンのよう.
土や岩に覆われてぼやけてはいても,引き裂かれ
た砂漠からなおも昇りつづけている宇宙船の誇ら
かな線は,隠すべくもなかった.ジェセラクが見
つめている間にも宇宙船は徐々に二人の方に向き
を変え,奥行きは縮まって円になった.それから,
その円はきわめて悠然と広がり始めたのである.
(p.236)
宇宙船に乗り込んだアルヴィンとその友人は,銀河系を旅
しながらさまざまな驚異を目にするとともに,忘れ去られ
ていた人類の驚くべき歴史を発見することになる.
さて,クラークといえばアイザック・アシモフのライバ
ルとしても有名である.「ロボット三原則」に従うヒューマ
ノイドロボットのシリーズで人気を博したアシモフに対抗
しているのか,クラークは自分の SFでは決してヒューマ
ノイドロボットを登場させない.アルヴィンと行動をとも
にするロボットも,さきほどのポ リ プ
群体生物を模した 3つの目
と触手や腕を持ち,反重力装置のようなもので空中を浮い
て移動する「非人類型異星生命体型ロボット」である.
それどころか,クラークはロボットに物理的形態をとら
せること自体を否定してしまう.
人類は,他の種族たちと接触したことによって,一
つの種族の世界像が,その肉体とそれに備わる感
覚器官とに,いかに深く影響されているかを知り
ました.そこで,もし宇宙の真の姿というものに到
達できるものならば,それはこのような肉体的制
約から解放された精神—つまり純粋の知性によっ
て初めてできるものだ,と論じられたのでありま
す.(p.324)
こうして作られたのが「物質的な構成要素を持たず空間そ
のものに刻み込まれたパターンとしての頭脳」である純粋
知性「ヴァナモンド」,言わばクラークが描くロボット・人
工知能の究極の姿である.ヒューマノイドロボットが役に
立つか/立たないかなどという議論を軽々と超えて広がる
SFの華麗で壮大なイマジネーションの世界にたまには浸っ
てみるのは如何だろうか?
4. お わ り に
この項を書くため,21 年前のロボット学会誌の特集号
「ロボットとイマジネーションの世界」[3] を見直してみた
ところ,坂村健氏が「未来の二つの顔」を紹介しているこ
とに気づいた.この号では,手塚治虫氏をかこんた加藤一
郎先生,内山勝先生,広瀬茂男先生他による座談会なども
収められている.
今回紹介したのは既に古典に属する作品だが,最近では,
瀬名秀明「デカルトの密室」,山本弘「アイの物語」など,
日本の作家による意欲的なロボットテーマの作品が次々と
発表されており,目が離せない.今後はますます楽しみで
ある.
参 考 文 献
[ 1 ] ジェイムズ・P・ホーガン,山高昭訳「未来の二つの顔」創元推理文
庫, 1983.
[ 2 ] アーサー・C・クラーク,山高昭訳「都市と星」ハヤカワ文庫 SF, 1977.
[ 3 ] 日本ロボット学会誌,特集「ロボットとイマジネーションの世界」,
vol.4, no.3, 1986.
梶田秀司(Shuuji Kajita)
産業技術総合研究所,知能システム研究部門ヒューマノイド研究グループ長.好きなものは良質な科学書と SF. 稀に下手なビオラを弾く.最近のお気に入りは NHK アニメ「電脳コイル」. (日本ロボット学会正会員)
日本ロボット学会誌 26 巻 1 号 —37— 2008 年 1 月