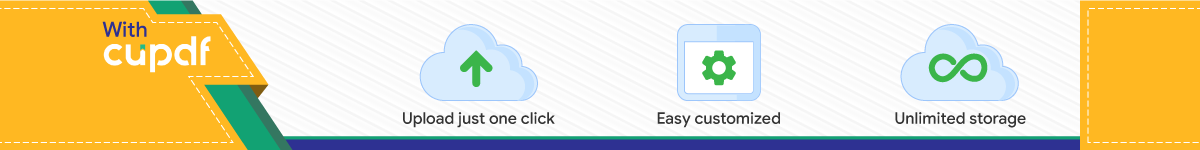
02 今月の特集大枠合意に達した日EU・EPA
20 アジア インサイト日台租税協定の適用における軽減税率の利用KPMG台北事務所 パートナー 公認会計士 友野 浩司氏KPMG税理士法人 パートナー 税理士 三浦 晃裕氏
11 グローバル インサイト流動化する欧州情勢と企業が留意すべきリスク有限責任監査法人トーマツディレクター 茂木 寿氏
北米市場の新たな中心地テキサス州テキサス日本事務所 代表 渡邉 博之氏
NAFTA再交渉に注目が集まるなか自動車生産は引き続き好調なメキシコみずほ銀行 国際戦略情報部 調査役 佐々木 宏行
24 今月のトピックスメキシコみずほ銀行レオン出張所の開設についてメキシコみずほ銀行レオン出張所
2017NOV&DEC
vol.94
日EU・EPA交渉大枠合意の概要みずほ総合研究所 政策調査部 主席研究員 菅原 淳一
大枠合意に達した日EU・EPA
巨大経済圏の構築と日EU規制協力の進展 2017年7月6日の日本とEU(欧州連合)の首脳会議において、EPA(経済連携協定)(以下、日EU・EPA)交渉が大枠合意に至った。今後、年内に最終的に合意した後、それぞれの国内(域内)手続きを経て、2019年の早い時期に発効に至ることが目標とされている。 日EU・EPAが実現すれば、日本企業は人口5億人、域内GDP16.4兆米ドルのEU市場へのアクセスがより容易となる。また、日EU間でモノ、サービス、人、資本、情報等の双方向の移動が活発化し、GDPで世界の3割弱を占める経済圏が構築されることになる。 特にEUは、日本の主要輸出品目である自動車等に先進国としては比較的高率の関税を課している一方、韓国に対してはEU・韓国FTA(自由貿易協定)によりそれらの関税をすでに撤廃している。そのため、自動車メーカー等の日本企業は現在、EU域内において韓国企業との競争上不利な立場に置かれている。日EU・EPAが発効すれば、日本企業は韓国企業とEU域内で同等の競争条件を確保することができるようになる。 さらに、日EU・EPAを土台として、規制や基準・規格といったルール形成における日EU協力が進展することが期待される。日本は、国際的な規制や標準作りで強い影響力を持つEUとの協力によって、日本にとって望ましい規制や基準・規格をグローバルな規制・標準とすることで、日本企業の競争力向上につなげることを目指しており、日EU・EPAがその基盤になると見ている。EU側も国際的な規制・標準化団体での日EU間の緊密な協力や、気候変動問題等のグローバルな課題への対処における日EU協力を日EU・EPAに基づいて進めようとしている。 現在、日EU間では、自動車、化学、情報通信技術(ICT)、医療機器、医薬品、繊維等の分野で規制協力を一層進めるべく業界対話が行われており、日EU・EPAがこれらの規制協力の制度的基盤として機能することが期待されている。
大枠合意の注目点(1)物品市場アクセス EUは日本にとって、輸出では米国、中国、ASEAN(東南アジア諸国連合)に次ぐ相手で、輸出総額の11.4%
(約8.0兆円)を占める。輸入では、中国、ASEANに次ぎ、輸入総額の12.3%(約8.2兆円)を占める。 日本は、協定発効時にEUからの輸入の91%
(関税品目数ベースでは86%)に当たる関税を 撤 廃し、最 終 的(15年間の経過期間後)には99%(同97%)に つき関 税を撤 廃する(図表1)。
特 集
図表1. 日EU・EPAにおける関税撤廃率
(注)「最終」は15年間の経過期間を経た後の最終的な関税撤廃率。括弧内は関税品目数ベースの数値。「工業製品」は経済産業省所管品目に限る
(資料)「全体」は欧州委員会資料、「工業製品」は日本政府資料より、みずほ総合研究所作成
日本の輸入 EUの輸入
発効時 最終 発効時 最終
全体91% 99% 75% 約100%
(86%) (97%) (96%) (99%)
工業製品(現在)77.3% 100% (現在)38.5% 100%
→96.2% (100%) →81.7% (100%)
2/25mizuho global news | 2017 NOV&DEC vol.94
大枠合意に達した日EU・EPA
EUは、協定発効時に日本からの輸入の75%(同96%)に当たる関税を撤廃し、最終的にはほぼ100%(同99%)につき関税を撤廃する。 日本の自由化約束は、TPP(環太平洋パートナーシップ)とほぼ同水準となったが、一部の農産品や加工食品ではTPPを上回る自由化を約束している。代表的な例では、ワイン(現行関税率:15%または125円/Lの低い方等)はTPPでは協定発効8年目の撤廃であったが、EUに対しては協定発効時の撤廃(即時撤廃)を約束した。また、パスタ(スパゲティ・マカロニ、現行関税率:30円/kg)は、TPPでは協定発効9年目に12円/kgまで段階的に引き下げることを約束したが、EUに対しては協定発効11年目の撤廃を約束した。 交渉の最終局面で最大の争点といわれたチーズ(現行関税率:29.8%等)では、ハード系チーズ(チェダー、ゴーダ等)等についてはTPP同様協定発効16年目の関税撤廃を約束した。他方、ソフト系チーズ(カマンベール等)については、TPPで関税を維持した品目(カマンベール、モッツァレラ等)に加え、関税削減(ブルーチーズ)や関税撤廃(粉チーズ等)した品目も含めた品目横断的な関税割当(初年度2万トン、16年目に3.1万トン)を設定し、枠内税率は16年目に無税となる段階的撤廃を約束している。 他方、コメについては、TPPでは米国とオーストラリアに輸入枠を設定したが、日EU・EPAでは自由化対象から除外した。 工業製品については、現在EUからの輸入の77.3%が無税であるが、無税割合は協定発効時に96.2%となり、最終的には100%となる。 EUの自由化約束をみると、農産物・加工食品の関税については、醤油等調味料(同7.7%等)や緑茶(同3.2%)、牛肉(同12.8%+141.4〜304.1ユーロ/100kg)、アルコール飲料(同無税〜32ユーロ/100L)等、多くの品目で即時撤廃を約束した。非関税措置についても、単式蒸留焼酎の容器容量規制が緩和され、四合瓶や一升瓶での輸入が協定発効後には認められることになった。 ただし、豚肉、鶏肉、鶏卵、乳製品等、現在日本からの輸入が認められていない品目が多数存在する。日本からの輸出拡大には、EU側の輸入解禁やその他の非関税措置の緩和・撤廃が不可欠である。 また、EUは工業製品全体で現在日本からの輸入の38.5%を無税としているが、無税割合は協定発効時に81.7%となり、最終的には100%となる。日本が最重視していた乗用車(現行関税率:10%)は、協定発効後8年目の撤廃、自動車部品(同2.7〜4.5%)は日本からの輸入の92.1%につき即時撤廃する(図表2)。
(2)自動車 自動車分野に関しては、非関税措置や国際標準形成における日EU間協力等に関する附属書が策定されるようである。同附属書では、基準・規格として国際連合欧州経済委員会(UNECE)規則を適用し、日本が同規則の適用を停止したり、除去された非関税措置を再導入した際等には、EUは同措置によって影響を受けた製品につき引き下げた関税を元に戻すことができるというセーフガード措置(スナップバック)が設けられるようである。 乗用車の原産地規則は、非原産割合(工場渡し価格)を最大45%としつつ、6年間の経過期間が設けられ
特 集
図表2. EUの工業製品関税譲許(例)
(注)括弧内は関税品目数ベースの数値(資料)経済産業省資料より、みずほ総合研究所作成
品目 現行関税率 EPAでの約束 品目 現行関税率 EPAでの約束
乗用車 10% 8年目に撤廃 一般機械 86.6%につき即時撤廃
二輪車(500cc以下) 8% 6年目に撤廃 産業用ロボット 1.7% 即時撤廃
二輪車(500cc超) 6% 4年目に撤廃 ベアリング 7.7〜8% 即時/6年目/8年目に撤廃
自動車部品 92.1%(91.5%)につき即時撤廃 化学製品 88.4%につき即時撤廃
ガソリンエンジン 2.7〜4.2% 即時撤廃 医薬品原料 4〜6.5% 即時撤廃/4年目に撤廃
ディーゼルエンジン 2.7〜4.2% 即時撤廃/4年目に撤廃 印刷用・筆記具用カラーインキ 6.5% 4年目/8年目に撤廃
クランクシャフト 4% 6年目に撤廃 電気機器 91.2%につき即時撤廃
ギヤボックス 3〜4.5% 即時撤廃 リチウムイオン電池 2.7% 即時撤廃
乗用車用ゴム製空気タイヤ 4.5% 即時撤廃 カラーテレビ 14% 6年目に撤廃
3/25mizuho global news | 2017 NOV&DEC vol.94
大枠合意に達した日EU・EPA
ており、協定発効後最初の3年間は同55%、次の3年間は同50%となっている。(3)電子商取引 電子商取引に関しては、「電子的送信に対する関税不賦課」等、TPPと同様の規定が盛り込まれたようである。ただし、「TPP3原則」とも呼ばれる①電子的手段による情報の越境移転の自由の確保、②コンピュータ関連設備の設置・利用要求の禁止、③ソースコードの移転・アクセス要求の禁止、については、③のみが規定された。①および②については、今後再検討する方向になっている。 なお、7月の日EU首脳会議において「個人データの越境移転に関する政治宣言」が発出されており、越境データ流通について「2018年の早い時期までに」合意に至ることが目標とされている。
(4)政府調達 EUが重視していた政府調達では、日本は新たに市場を開放した。日本とEUはともにWTO(世界貿易機関)政府調達協定の締約国であり、対象機関における一定の基準額以上の調達をすでに相互に開放している。日本は、TPPにおいても同協定と同水準の市場開放を約束している。 WTO政府調達協定ならびにTPPにおいて、日本は地方政府については47都道府県と20政令指定都市の対象となる調達を開放していたが、日EU・EPAでは初めて48の中核市を協定の対象とした。ただし、中核市については、建設サービスを除外し、「これまでどおり入札参加者の事業所の所在地を資格要件として定めることを可能としつつ、EU供給者も参加できるように」(外務省資料)した。対象となる基準額等は明らかにされていないが、高市早苗総務大臣(当時)は、日EU・EPAの規定は「『WTOルールの中核市以下への拡大』ではなく、『中核市の一定の入札に限って特別なルールを適用』すること」であり、「地域経済への影響は極めて限定的」であるとしている(平成29年7月7日、閣議後記者会見)。 また、争点の1つであった鉄道分野の調達において、日本はWTO政府調達協定ならびにTPPでは例外としていた「運転上の安全に関連する調達」を対象に含めた。EUも、同分野で日本へ開放する調達を拡大した。
年内最終合意に期待 大枠合意の全貌は必ずしも明らかではないが、いくつかの問題が積み残されたようである。そのうち、最大の争点となっているのが投資における「投資家と国との間の紛争解決」(ISDS)である。これについては、日本はTPPやこれまでのEPA・投資協定で採用してきた投資紛争を国際仲裁に付託する方式(従来のISDS)を日EU・EPAにおいても採用するよう主張しているが、EUは従来のISDSはもはや過去のものであるとしてその採用を拒否し、代わりに最近のベトナムやカナダとのFTAですでに採用している常設で二審制の投資裁判所制度(ICS)の採用を求め、合意に至っていない。 日EU・EPAの発効には、最終合意後に日EU双方で議会承認等の国内(域内)手続きが必要となる。それらに要する時間を考えると、目標とされる2019年の早い時期の発効のためには、2017年内に最終合意に至ることが期待される。
特 集
図表3. 日EU・EPA発効までの主な手続き
(注)日EU・EPAが「混合協定」とされた場合に想定される主な手続。上段が日本国内、下段がEU域内の手続。「暫定適用」により関税削減・撤廃が開始される(資料)欧州委員会資料より、みずほ総合研究所作成
大枠合意
最終合意
署名
暫定適用
(正式)発効
閣議決定
EU理決定
国会承認
欧州議会承認
全加盟国
議会承認
4/25mizuho global news | 2017 NOV&DEC vol.94
大枠合意に達した日EU・EPA 特 集
日EU・EPAが日本の欧州ビジネスに与える影響日本貿易振興機構(ジェトロ) 海外調査部欧州ロシアCIS課長 田中 晋氏
日EU経済連携協定(EPA)交渉は2017年7月に大枠合意に達した。同EPA交渉は2013年4月の開始からすでに4年以上の歳月が経過。2011年7月に暫定適用が始まったEU韓国FTAからはすでに6年遅れている。EU韓国FTAの交渉開始は2007年5月であり、自動車や同部品、電気・電子機器分野を中心に、日本の産業界が対等な競争環境(レベル・プレイング・フィールド)を求め、10年以上待ち望んだ日EU・EPA交渉が最終合意に近づいている。官民関係者の長年の努力が間もなく実を結ぼうとしている。
欧州進出日系企業の約3割がメリット大と回答 ジェトロが毎年実施している欧州進出日系企業調査の結果によれば、日EU・EPAについて「メリットが大きい」とする回答企業数が2016年調査(9〜10月実施)で300社近くに達した(図表1)。2008年のリーマンショック、2010年の欧州債務危機で後退した欧州景気は2012〜13年を底に徐々に回復してきており、欧州市場に対する期待の高まりに呼応しているといえる。 「メリットが大きい」と回答した企業数を業種別に見ると、製造業では輸送用機器部品(自動車・二輪車)が最多で、化学品・石油製品/ゴム製品(タイヤを除く)、一般機械(金型・機械工具、加工を含む)、電気機械・電子機器、輸送用機器(自動車・二輪等)、電気機械・電子機器部品、食品・農水産加工が続いている。工業製品の中で、EUが高関税を課している品目として、代表的なのものは乗用車(関税率10%)やカラーテレビ
(同14%)だが、両分野とも高関税率を理由に、韓国メーカーとの競争も意識し、2000年代に2006年をピークに、欧州での現地生産への移行、もしくは現地生産拡大が大きく進んだ経緯がある。こうした完成品メーカーの動きに付随して、部品メーカーの現地進出も進んだが、上述のジェトロ欧州進出日系企業調査
(2016年)では、EUに進出する日系企業の32.2%(製造業で29.0%、非製造業で38.4%)が日本から部品・原材料を調達している、もしくは製品を輸入していることも示された。このことは、現地生産化できていない、もしくは現地化が困難、東南アジアや中国などから輸入できない部品・原材料等が3割程度残っており、日EU・EPAで当該品目の関税率が低下・撤廃された場合のコスト効果が一定程度あることを示している。こうした部品・原材料の中には、EPA発効後に関税が即時撤廃されるものも多い。
図表1. 日EU・EPAを「メリット大」と回答した企業比率の推移
(注)nは同設問全体の有効回答企業数(社)(出所)ジェトロ欧州進出日系企業実態調査(各年結果)
2012年(n=449社)
300(単位:社) (単位:%)
250
200
150
100
50
0
45.0回答比率中小企業数(社)回答企業数(社)
43.2 44.4 37.1
34.937.8
293
233247252
194
15
37 32 27 37
35.0
30.0
40.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.02013年
(n=568社)2014年
(n=666社)2015年
(n=667社)2016年
(n=775社)
5/25mizuho global news | 2017 NOV&DEC vol.94
大枠合意に達した日EU・EPA 特 集
メリット大の企業数が最多の自動車部品業界 経済産業省の発表資料によれば、同省が所管する工業製品について、日本側の即時撤廃率が貿易額ベースで96.2%、EU側が81.7%としている。特に自動車部品についてはEU側の即時撤廃率が92.1%になるとしており、上述した「メリットが大きい」との回答企業が最多だった輸送用機器部品分野の期待と一致する。 日本自動車部品工業会が会員企業に対して毎年実施している海外事業概要調査の2016年度版によれば、欧州地域での2015年の日系メーカー以外への販売比率は2009年と比べて大きく増えており、他地域との比較でも顕著だ。日系、非日系を問わず、販売先が広がっている傾向がうかがえ、日EU・EPAの締結はこうした日欧企業の連携を後押しする契機になると見られている。 また、日本からEU向け輸出額で上位にランクされる品目のうち、ターボジェット・プロペラの部品の関税
(2.7〜4.1%)が4年目に撤廃されるほか、リチウムイオン蓄電池(2.7%)や溶接器部品(2.7%)、化合織の糸・織物(3.8〜8.0%)、送受信機器(モニター含む)部品(5%)などの関税が即時撤廃になるため、自動車部品に次いでコスト効果が大きい分野だといえる。
日本食ブームでEPAの効果が期待される食品分野 他方、EU向けの食品輸出で金額が大きい品目を見ると、ウイスキー、ホタテ貝、緑茶、ソース混合調味料、しょうゆ、牛肉、日本酒、味噌などの品目が上位を占める(図表2)。欧州での日本食ブームと相まって、当該品目のEU向け輸出は年々増加している。最も顕著な伸びを示しているのはウイスキーだが、すでに関税が0%であるため、日EU・EPAによる効果は特にない。続くホタテ貝は関税率が8%で、冷凍もので8年目に撤廃、緑茶とソース混合調味料はそれぞれ3.2%(3kg以下の小口用)、最大で10.2%で、即時撤廃となるため、日EU・EPAによるメリットが大きい分野といえる。緑茶について、EU市場では有機栽培の抹茶のニーズが高く、残留農薬基準を満たすことができるため、輸出が拡大している。また、ソース混合調味料については、スペインでのカップ焼きそば発売にともなう焼きそばブームの広がりなどもあり、焼きそばソースの輸出が増加している。加えて、照り焼きソースなども、欧州市場に浸透しつつある。これらのソースは関税率が7.7%であるため、メリットが大きい分野といえる。ただし、ソース類は小口の取引も大きいため、EPA活用には社内体制整備のコストも考慮した戦略が必要となる。また、同様に関税率が7.7%のしょうゆや味噌のEU市場向け輸出も日本食レストランの増加にともなう需要増から年々拡大傾向にある。さらに、2014年6月に解禁となったEU向け牛肉輸出も、高級レストランや高級食材店を中心に、順調に輸出を伸ばしている。牛肉の関税率は12.8%+最大304.1ユーロ/100kgで、即時撤廃となっているため、その効果は大きい。
図表2. 日本からのEU向け主要食品輸出額の推移
(出所)財務省貿易統計
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(年)
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
(単位:100万円)
ウイスキー
ホタテ貝(生・蔵・凍・塩・乾)
緑茶
ソース混合調味料
しょうゆ
牛肉(くず肉含む)
メントール
日本酒
味噌
清涼飲料水等
6/25mizuho global news | 2017 NOV&DEC vol.94
大枠合意に達した日EU・EPA 特 集
GI導入で相互保護体制を整備 加えて、日EU双方の地理的表示(GI)法による相互保護制度が採用されたことで、EU市場において、日本産品のブランド化や保護が促進される。たとえば、EUでは、オーストラリア産の神戸ビーフが現在、市場に出回っているが、日EU・EPAにおいて神戸ビーフがGIの対象として認定されれば、オーストラリア産は販売できなくなる。日本側で31産品、EU側で71産品について現在、公示手続きが進んでいる。これらの産品以外では、日本酒が日本の米を原料として国内で製造された清酒として、また、地域レベルでは山形、白山がGI対象として指定されている。ワインについても山梨がGI対象として指定されている。さらに、ワインについて、EU域外からEU域内への輸出は、EUワイン醸造規則に適合したものしか認められていなかったが、日EU・EPAでは、日本ワインの醸造方法(補糖、補酸、ブドウ品種の承認等)が容認されることになった。 日EU・EPAは最終合意に向け、投資分野などの残されている論点の解決に向けた交渉が今なお続いている。最終合意後にテキスト案の法的精査、EU側での公用語への翻訳作業などを経て、署名、批准手続きへと進んでいくため、日EU・EPAの詳細が公表されるまでには、もう少し時間を要すると見られている。ただし、品目別の関税率削減スケジュール作成や原産地規則に関する技術的な作業が並行して進められており、これらの詳細情報は準備が整い次第、公表される可能性がある。
節目となる英国のEU離脱と次回欧州議会選挙のタイミング EU側は2019年4〜5月に、次回欧州議会選挙を控えていることもあり、同年の早期発効に向け、交渉を急いでいる。日EU・EPAがEUの批准手続きのみで発効できる協定になるのか、EU加盟国と権限を共有する分野も含む混合協定になるかはまだ確定していない。仮に混合協定になった場合でも、関税率削減などのEUが排他的権限を有する分野についての暫定適用を2019年の早期に開始できるようなタイミングで最終合意に達することができるかどうかが次の節目になる。 日本企業にとって、2018年は早期の日EU・EPAの発効も視野に入れ、欧州戦略の強化や見直しを行うには良いタイミングとなるだろう。加えて、英国が2019年3月末のEU離脱に向けた交渉をEUと進めていることにも留意が必要だ。日EU・EPAが発効する前に、英国がEUを離脱する可能性もあり、日英EPAの交渉はさらに先になると見られることや、英国がEUを離脱した後に、一定の移行期間が設けられる可能性も高まってきており、企業はさまざまなオプションを考慮に入れながら、日EU・EPAを活用するための準備をしていく必要がある。 英国では2017年7月6日の日EU・EPAの大枠合意後、同EPAを支持しつつも、EU離脱後の英国のリスクを指摘する論調が多く、万が一、英国とEUとの新たなパートナーシップ協定が日EU・EPAより劣る場合、日本の英国拠点が大陸に移転し、英国の製造業が競争力を失う懸念も指摘されている。日本企業にとっては日EU・EPAもさることながら、欧州に進出する約5,800社の日系企業のうちの約15%が集積する英国とEU27ヵ国との貿易・投資協定がどのような仕上がりになるかが決定的に重要である。日本企業にとって、目前に迫った日EU・EPA締結のみならず、さらに先の英国・EUの新たな関係、将来の日英EPAも睨んだ欧州戦略の再構築が不可欠となりそうだ。
産業デジタル化にともなう各種規制の導入にも留意 そのほか、EUでは現在、産業の競争力強化に向けて、デジタル化への取り組みを加速している。EUはその基盤として、デジタル単一市場の構築を目指しており、同過程でオンラインプラットフォームの促進やジオブロッキングの禁止などに関する新たな規制が導入されようとしている。並行して人権保護に基づく個人データ保護規則が2018年5月から適用開始される予定であり、欧州ビジネスを進めるにあたり、こうした法令順守対策の入念な準備も一層重要になる。
田中 晋氏 プロフィール1987〜1989年に経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部(在パリ)勤務。1990年4月に日本貿易振興会(現・日本貿易振興機構)入会。1995年3月〜1998年9月にパリ、2000年1月〜2007年3月、2010年10月〜2015年6月にブリュッセルに駐在し、EUを中心とする欧州ビジネス関連調査に従事。2016年10月より現職。著書は『欧州経済の基礎知識』(編著)など
7/25mizuho global news | 2017 NOV&DEC vol.94
大枠合意に達した日EU・EPA 特 集
日EU・EPAのメリットおよび駐日欧州連合代表部の取り組みについて駐日欧州連合代表部 公使参事官・通商部部長 マリュット・ハンノネン氏
はじめに 2017年7月6日、日本と欧州連合(EU)は経済連携協定(Economic Partnership Agreement=以下、EPA)および戦略的パートナーシップ協定(Strategic Partnership Agreement=以下、SPA)の主要な部分について、大枠合意に達した。第24回日EU定期首脳協議の開催中、ユンカー欧州委員会委員長とトゥスク欧州理事会常任議長が、安倍総理とともに大枠合意の達成を発表した。 「高度に野心的で包括的なEPAは、我々の確固とした、そして進化を続ける貿易・経済連携を強化し、未来への道を開く。この協定は、物品・サービス、投資ならびに鉄道を含む調達における市場アクセスに関連する問題とともに、非関税措置、地理的表示および知的財産権の保護に関連する問題に対処することにより、日本とEUの経済をより緊密にする。この協定は、将来のさらなる緊密な協力を視野に、国際標準に対する日本とEUの共同のコミットメントを新たにし、強化することを可能にする。同時に、今回のEPA大枠合意により、日本と欧州は、双方の価値を十分に尊重し強化する明確かつ透明なルールに基づく自由貿易が、我々の社会の繁栄をもたらす重要なツールであることを世界および我々の市民に対し示す。日EU・EPAは、保護主義に対抗する自由かつ公正な貿易のための戦略的なパートナーシップの基礎となる」と、共同首脳声明に記されている。
日EU・EPAがもたらす便益 日本とのEPAは、EUが締結する二者間の通商協定の中で、最も重要なものとなる。EUにとって6番目に大きな通商相手国である日本へは、毎時およそ1,000万ユーロの製品とサービスを輸出している。輸入もまたほぼ同額に達している。他方、5,000社に近い日系企業がEU域内に投資し、50万人超の雇用を生み出している。EUとその加盟国には、日本とのEPAにより、毎年EU企業が支払っている総額10億ユーロの関税の大半が撤廃されるという便益がもたらされる。 日本において、または日本を相手にビジネスを行うことに関心のある欧州の企業には、新たな商機が生み出されることにもなる。これは、EUから輸入をしている日本の企業にとっても同様である。EUからの対日輸出額については、200億ユーロに及ぶ増大が見込まれ、農業、食品、皮革、衣類と履物、医療品、医療機器など、EU域内の数多くの産業部門において、貿易の機会と雇用が創出されることとなる。また一方では、日本の消費者は、高品質の欧州製品を購入する際に、選択肢が増えるという便益を享受することになる。
日EU・EPAの主要項目 日EU・EPAの主要な項目を以下に示す。
(出典)欧州委員会
図. EUの対日貿易の現状、日EU・EPAにより想定される効果
EUの対日製品輸出額は580億ユーロ
EUの対日サービス輸出額は280億ユーロ
EUの対日輸出関連ビジネスに60万人が従事
EU域内において日本企業が55万人を雇用
EUの対日輸出業者が支払っている関税総額は毎年10億ユーロ
EUの対日輸出が16~24%増大するとの予測
EUの加工食品の対日輸出が170~180%、もしくは最大100億ユーロ増との予測
EUの化学製品の対日輸出が最大で22%もしくは30億ユーロ増との予測
EUの電気機器の対日輸出が最大で16%もしくは6億5,000万ユーロ増との予測
およそ7万4,000社ものEU企業が日本に輸出をしており、その78%が中小企業
8/25mizuho global news | 2017 NOV&DEC vol.94
大枠合意に達した日EU・EPA
関税の撤廃 同協定により日EU間貿易の大幅な自由化が実現する。発効時に、日本はEUからの輸入の91%を自由化する。移行期間の終了時には、同率は99%となる。残り1%の輸入は、主に農業および食品部門におけるものであり、関税割り当て・削減により部分的な自由化が実現する。これは、毎年およそ10億ユーロの関税を支払っているEUの対日輸出業者にとって、大きな費用削減を意味する。日本は、EUの農家や食品メーカーにとって、極めて貴重な輸出市場であり、年間輸出額は57億ユーロを超え、すでにEUの農産品輸出にとって4番目に大きな市場となっている。将来的には、EU農産品や食品の約85%(関税表の品目ベース)が、無税で日本市場に入ることが可能となる。これは、現在の農産品・食品の輸出総額の87%に相当する。 また、EUが最大の関心を寄せている農産品に関しては、関税の撤廃もしくは大幅な削減が実施されることとなっている。なかでも最大の輸出量を有する豚肉製品においては、加工豚肉製品の関税は段階的に撤廃、豚肉の関税も大幅に削減される。牛肉に課される関税も15年をかけて38.5%から9%に削減される。 EUの対日ワイン輸出はすでに10億ユーロに達しており、対日輸出品目の中で、金額ベースにして2番目に大きなものとなっている。ワインの関税は、大半の酒類とともに即時撤廃となる。 現在でも日本のチーズ市場において、EUは大きな割合を占めているが、その輸出に関しては、ゴーダやチェダーなどのハードタイプのチーズに課せられている高い関税(現行29.8%)が撤廃されるとともに、モッツァレラなどのその他のチーズには関税割り当てが設定され、将来的には枠内関税は撤廃される。さらに、パスタ、チョコレート、ココアパウダー、キャンディ、菓子類、ビスケット、でんぷん由来製品、トマト加工品、トマトソースなどの農産加工品に関しては、現行の関税は(移行期間を設けて)撤廃となる。また、モルト、馬鈴薯でんぷん、脱脂粉乳、バター、ホエイ*のEUからの輸出に関しても、大きな関税割り当て(無税もしくは減税)が設置される。 水産品の関税は双方が撤廃することになっているため、EUの消費者には価格の低下という便益がもたらされるとともに、EUの水産業界には大きな輸出機会が生まれることになる。 また、全ての林産物の関税も完全撤廃となる。その中で、EUにとっての最重要品目については、7年の段階的削減を経て撤廃される。その他の品目も、その大半の関税が即時撤廃になるが、重要性の低いものについては10年をかけて撤廃される。 工業製品に関しても、EUが高い競争力を有する部門である化学製品、プラスチック製品、繊維・衣類などの関税が、完全に撤廃される。皮革および履物に関しては、現行の割当制度をEPA発効と同時に撤廃する。履物の関税は、発効時に30%から21%に削減され、残りは10年をかけて撤廃される。ハンドバッグなどEUが輸出する皮革製品の関税も10年をかけて撤廃される。スポーツシューズやスキー靴などについても同様の措置が取られる。地理的表示 欧州の特定の地域で生産された200を超す農産品について、その特別なステータスを認め、保護を提供する制度である地理的表示(GI)が、日本市場でも適用されることになる。対象となる品目は、ロックフォール、アチェート・バルサミコ・ディ・モディナ、プロセッコ、ジャンボン・ダルデンヌ、ティローラーシュペック、ポルスカ・ヴトゥカ、ケソ・マンチェーゴ、リューベッカー・マジパン、アイリッシュ・ウイスキーなどであり、EU域内と同じ水準の保護が、日本においても与えられることになる。非関税障壁 日本の技術要件や認証手続きの中で、安全な欧州製品を日本に輸出することを困難にしているとEU企業が懸念している非関税障壁については、その多くが今回の交渉により撤廃される。サービス貿易 EUは、約280億ユーロに上る金融、運輸、通信、流通等のサービスを毎年日本に輸出している。EPAにより利益率の高い日本市場におけるサービスの提供が容易になる。公共調達 日本の48の「中核都市」において、EU企業が日本企業と同じ条件で入札に参加することができるようになる。また、鉄道部門における調達に関する既存の障壁が撤廃される。
特 集
9/25mizuho global news | 2017 NOV&DEC vol.94
大枠合意に達した日EU・EPA
知的財産権(IPR) EPAでは、日本とEUの双方が、知的財産権の分野における世界貿易機関(WTO)でのコミットメントを一層強化するとともにEUの法律とも整合性を取っていく。具体的には、営業上の秘密、商標、著作権保護、特許、医療品などの試験データに関する最小共通ルール、民事上の法執行などに関する条約が規定されている。今後のスケジュール 2017年7月に達成された大枠合意には、日EU・EPAの主要な要素の大半が包含されている。いくつかの章に関しては、さらに技術的詳細を詰める必要があるとともに、大枠合意の枠外に置かれたままの章もある。 大枠合意に基づいて、日本とEU双方の交渉担当官は作業を継続し、残りの全ての技術的問題を解決し、EPAの条文について本年末までの最終合意を目指す。その後、欧州委員会は条文の法的検証と全てのEU公用語への翻訳の作業に入り、最後にEU加盟国と欧州議会に提出し、承認を得る。
駐日欧州連合代表部とは 駐日欧州連合(EU)代表部は、日本においてEUを代表する正式な外交公館であり、EU大使が代表部の長として、その活動を統括しています。
駐日EU代表部の任務・日本においてEUを代表し、その利益および価値を促進し、進展させること・日本とEU間の政治、経済、文化、教育、科学などの分野における協力を発展、強化させること・必要に応じ、日本との協力を通じて、EUが世界中で、また地域において、自らの利益や価値観をより一層推進できるように努めること
通商部 通商部は、日本国内の通商・貿易に関する動向をつぶさに追っています。日本政府のみならず日欧の経済団体とも密接に協力しながら、航空、通信、エネルギー、環境、製造業から農業までと、広範な分野を網羅しています。また、大枠合意した日EU・EPAの最終合意に向けた交渉を支援する役割も担っています。
最新の情報や行事に関しては当代表部のフェイスブックやツイッター・ページを、またEUの事象や政策についてより深い知識を得るには、オンライン広報誌の「EUMAG」(日本語)をご覧になることをお勧めします。
特 集
* 乳(牛乳)から乳脂肪分やカゼインなどを除いた水溶液
10/25mizuho global news | 2017 NOV&DEC vol.94
Top Related