u L c ´ Õ © ç ¬ ¼ E à w E R ¼ m V Ö vota/hansobodoannaishiryo-1.pdfQ l £ E z V · 2009 N 5...
Transcript of u L c ´ Õ © ç ¬ ¼ E à w E R ¼ m V Ö vota/hansobodoannaishiryo-1.pdfQ l £ E z V · 2009 N 5...

「豊田橋跡から小松・金指・奥山半僧坊へ」

○ 方広寺と奥山半僧坊
深奥山方広高寿禅寺 (略 して深奥山方広寺)は臨済宗方広寺挑Ω大本山で,
後醍醐天皇の皇子,無文元選禅師が井伊氏の一族奥山六郎次郎朝藤の招きを受
けて,建徳 2年 (1371)に 開創 した。本尊は釈迦牟尼仏,脇侍は文殊菩薩・普賢菩薩で観応 3年 (1352)の 作。共に国指定重要文化財。境内の各所
には五百羅漢の石像が安置されている。
奥山半僧坊は,奥山半僧坊大権現と呼ばれ,方広寺の鎮守である。半僧坊真
殿に祀られている。
伝説によると,無文元選禅師が中国より帰国の時,海で暴風にあつたが,鼻の高い一人の異人が現れ,船を無事博多の港に導いた。そして禅師が方広寺を
開いた時,再び現れ,こ の山の鎮守とならんと言い,半ば僧に似ているところ
から半僧坊と名乗 り姿を消した。以来方広寺を護る鎮守として祀られたという。
江戸時代の半僧坊信仰はふるわなかった。方広寺は,幾度か火災にあったが,
明治 14年の大火で,半僧坊は類焼を免れたところから,た ちまちすぐれた霊
験をもつものと,信仰を広く集めるようになった。
厄難消滅 。海上安全・火災消除・諸願満足の御利益があるという。
○ 半僧坊道
半僧坊道は遠州を代表する信仰の道である。天竜川以西の半僧坊へのルー ト
は,浜松中央から三方原,金指へのルー ト,豊田橋から笠井・小松 (あ るいは
西ヶ崎)・ 三方原・金指へのルー ト,安間 (あ るいは池田橋)から市野 。三方
原 ,金指へのルー ト,宮 日から都田 。金指ルー ト,浜名湖東岸や北岸のルー ト
など,い くつもある。また,時代により道筋は変化 している。
明治 16年に天竜川の池田橋や豊田橋が開通したことと合わせて,引佐・住玉郡長であつた松島吉平 (十湖)が ,明治 17年,諸国からの半僧坊への参詣
者の便を図るために,音頭取 りとなって,方広寺から浜松 。本坂・市野・笠井。宮日,渋川等へ通じる道路へ町石を建立したと記録がある。明治十年代後半
には多くの町石や道標が建てられた。
本案内資料は,豊田橋から笠井 。小松・三方原 。金指へのルー トについて,
案内する。豊田橋のたもとにあつた町石によると,半僧坊までの道のりは,
六里拾丁三十五間 (約 24.7km)である。
○ 半僧坊道の復元について
本資料の道筋は,大 日本帝国陸地測量部が明治 23年に測量した二万分の一
の地図をもとにし,地元の人の話も参考にして,明治十年代後半から二十年代
初め頃の道筋を現在の地図上に復元 した。現在の地図は,国土地理院の 「電子
国土ポータル」を活用した。
○ 参考文献・建築新聞 2009年 5月 神谷昌志・浜松の石造文化財 浜松市石造文化財調査会・秋葉街道 静岡県教育委員会・遠江の道 しるべ 静岡新聞 昭和 52・ 53年・ふるさとよもやま話 細江町農業協同組合・愛称標識の由来 都田地区愛称標識設置委員会・浜松市石造文化財所在 日録 浜松市石造文化財調査会・半僧坊道の野仏と道じるべ 東海展望 1975年 1月 ~ 9月 号。遠州の寺社・霊場 神谷昌志・酢山隆 静岡新聞社・遠州歴史散歩 神谷昌志 静岡新聞社・わが町文化誌 「笠井」 笠井公民館・はままつ城めぐり 浜松市博物館・浜松市博物館報 14号 浜松市博物館
・研究紀要 12-1号 静岡県立大学短期大学部・浜北市史通史 上巻 浜北市。東方見聞録 東区役所・浜松の史跡 浜松市史跡調査顕彰会・姥ヶ谷史 姥ヶ谷町内会。わが郷土 人・仕事 。心 浜松市立笠井中学校。浜松の史跡 続編 浜松市史跡調査顕彰会・愛称標識ガイ ドマップ笠井地区 浜松市・浜松歴史散歩 神谷昌志 静岡新聞社・静岡県明治銅版画風景集 羽衣出版・郷土の住まい 静岡県の住宅 静岡県住宅振興協議会・引佐の石仏 引佐町教育委員会
作成 平成 24年 3月 30日 改訂 平成 26年 6月 2
浜松市浜北区寺島 816 太田隆雄
TEL 053-587-3063

貫樹■
讐鳳r√伊平.
蓄ナFJ ヤV 鷺ェル
り:粒 I・dP
糧 穴
貝 、真壮
掘 磐
`11・ Fl:
上 平
ホR 一
:・‐1■ .「
i ti′~・
1丘 i
償,障
l!(
”」
‐
,ヽ一侵
″
上野部
ハ珈
中郡 :
in
鵬ヘ
:llll11lL:
rlttl ttγ
{
,半、 _メ」
蟷I:_119ピ
´ 半僧坊道
亀
「
歩

道標
案内資料における半僧坊道の道標と町石
資料番号
NO 3
6
8
11202225272931333435363945追カロ
47556970追加
78
(2基 ) 左 半僧坊道
左 平口 気賀 金指道
(不明)
右 中善地わたし舟
右 奥山半僧坊
左 平口ふどう
(左)半僧坊
左 奥山半僧坊道
右 奥山半僧道
左 みやこだ かなさし けが道
右 半僧坊道
左 かなさし道
右 半僧坊
右 かさいみち
左 半僧坊道
右 金さしをくやま道
左 金指井伊谷奥山道
左 犬居秋葉道 右 浜松市野道
半僧坊ヘ
左 奥山半僧坊ヱ
半僧坊
右 け賀 左 加 さい
はうかう寺
右 半僧坊大権現道
以上は
半僧坊または半僧坊道に関わる
刻銘のみ表示
亥」 銘 建立年月
明治 15.(不明)
明治 17明治 14.明治 17.
(不明 )
(不明 )
明治 17明治 17.明治 2
(不明)
(不明 )
明治 15.宝暦
明治 17.大正元.1大正 4ごろ
明和 2.8(不明)
明治 18.明治 16文化 2. 6
(不明 )
断目不口1 6.
8 町 石
常夜灯
5
6
資料番号
NO. 211(道 標 )
14追加
22(道 標 )
2427(道 標 )
3236(道 標 )
追加
38追加
47(道 標 )
追加
追カロ
52追加
55(道 標 )
5669(道 標 )
70追加
7475(2基 )
76778283849072
追カロ
92
5
4
六里拾丁二十五間
五里三十二丁四十六間
五里十五丁
五里十五丁
(五里十)四丁
(五里十)二丁
四里三十壱丁
四里十六丁
四里
四里十 ( )三里十 ( )式匡十九 (丁 )
弐 (里拾七丁)
弐里九丁
弐里人丁三十五間二里 ( )弐里二丁
弐里四町
弐里
壼里壼丁
三十六丁目一里
二拾七町
第拾武 (丁 目)
(第拾)萱丁 目
十二 (丁 )
第拾丁 目
第参丁 目
第弐丁 目
第萱丁 目
四丁 目半僧坊大権現 秋葉山大権現
半僧大権現 秋葉大権現
半イ曽坊大権現夜燈
亥1
6
0
銘
7
12
建立年月
明治 17.6明治 17.6明治 18.4
(不明)
(不明)
(不明)
明治 17.5明治 17明治 17.6明治 1( )明治 17明治 16
(不明)
明治 16明治 16明治 37.3明治 (不明)
明治 18.7明治 16明治 16明治 15。 6
明治 37.3明治 17.1明治 15明治 15明治 37.3明治 15明治 15明治 15明治 15(不明).3安永 5.12
(不明)
致:化 4. 1 (道標)は道標を兼ね
ているもの
( )は 不明
( )内 に数字・文字がある
きるものや他の町石や記録か 2
ものは,推定で
推定できるもの

酬赳
1 豊田橋跡
天竜川豊田橋は明治 16年 2月 , 豊田郡末嶋村|(現浜松市豊西町)よ り豊
田郡匂坂中村 (現磐田市匂坂中)に架けられた有料橋で,長 さ816間 (約 1
|
==→|
豊田橋 「静岡県明治銅版画風景集」
(羽衣出版)よ り
470m)幅 2間 (3.6m)の木橋であつた。松島吉平 (十
湖)な どが架橋発起人 とな り「豊田社」を創立 して経営 し
た。交通上の便益は増 し,地域発展に大いに役立ったが ,
6年後の明治 22年の洪水に
より流失 した。完全復旧はで
きず,いつ しか昔の渡船に変
わり,土地の渡 し守により細々と戦前まで続けられた。
残 された橋脚
2 半僧坊町石
かささぎ大橋の碑 と並んで半僧坊ヘ
の道の りを示す大きな町石が建てられ
ている。正面に「奥山半僧坊 六里拾
丁三十五間」,裏に 「明治十七年六月建
立」「末島村 川合貞一郎 (他 12名 の
氏名 )」 と刻まれている。川合貞一郎は
後の豊西村村長である。豊田橋開通直
後の道標で,以前は豊田橋のたもとに
建てられていた。
豊田橋が開通後,十湖は 「春風 も吹渡也橋あ
らた」「夏の夜や長き渡 りの豊田橋」と句を詠ん
でいる。
豊田橋流失から120年 ,平成 9年 にかささ
ぎ大橋が開通 した。
豊田橋跡 より家並みの間を半僧坊道が通つて
いる。
3 +湖 百句塚と道標
百句塚は明治 39年 に笠
井町福来寺に大木随虎・松
島十湖 らによって建立され ,
その後 ,御殿 山か ら法永寺
に移転 し,平成 22年 にこ
の地に移転築造 された。芭
蕉翁の句 「ものいへば唇寒
し秋の風」 を中心に 100基以上の句碑が建てられている。
百句塚の人 口横に, 2つ の道標が建
てられている。もとは笠井上町より小
松へ向か う半僧坊道の交差点にあつた
が,法永寺に移転後 さらに百句塚 と共
にこの地に移 された。 1つ は「左半僧坊道」「明治十五年人月建之」 と刻ま
れ,も う一つは 「直秋葉山 左 平口
気賀 金指道Jと 刻まれている。
4 百人一句塚
百人一句塚は,御嶽神社境内に明治29年松島十湖が当時の俳人たちを勧
誘 して建てたものである。地元の人た
ちが多いが,やや大きな一基には,芭蕉をはじめ,十湖の師匠である烏玉 (有
賀豊秋),夷 自 (欄木要右衛門)な どの句が刻まれている。芭蕉の句 「ふる
池や蛙 とびこむ水のおと」がある。

〓‐,IL一 L
‐‐」■́■「‐‐′・.V
・=1‐‐‐‐ギ
‐ヽヽ
‐‐、/てヽ1
・‐‐‐‐11‐―‐―‐十
/年ヽ卜脚
・ “
‐卜4=̈.
‐ぃ
・■■一 ”
/
卜==‐―■――‐
顆「
―
―
I
Ч
∃
一「「―――――
F
‐‐――
5 +湖池
豊田川沿いの堤防の西にあつた池で,約 1
ha程の広さがあった。慶応 4年 (1868)5月 の暴風雨により天竜川堤防が切れ,そ の
勢いでこの堤防も破堤 した。濁流は水田のあつた場所に底な しといわれるほど深い池を残
した。地主であった松島十湖の名前から十湖
池 と呼ばれるようになった。昭和 45年豊田
川の改修で一部が埋め立てられたが,現在ビ
オ トープ (生物空間)と して再生させ地元の
6 撫松庵跡と道標
豊西町上公会堂の所に,明治 12年に松島十湖が建てた撫松庵があり,県会議員など政治家として活躍している中,閑詠自適の一時を過ごした。庵の前の
築山に,芭蕉や俳諧の師であつた夷白・嵐牛 。烏玉などの句碑を建てた。そして引佐色玉郡長を勤めていた明治 17年に「志らぬ間にふえた白髪や秋の風」
有志が活動している。
松島吉平 (十湖)邸の銅版画には,撫松庵へ西に
向か う半僧坊道の曲が り角に,半僧坊大鳥居が描か
れている。
の句を十湖第一号をょ嚇 ュしている。中央の大きな 職 に階望碑」 (親 を懐か
しみ仰ぎ見る)は明治 25年亡母の忌 日に
あたり建てた。
築山の西側にある道標は,「長上郡笠井
鳥田勘□」「明治十七年建□」とあるが,
その他は不明である。
7 水難供養塔
公会堂北側の墓地には,明治 10年に建てられた天竜
川水難者の供養塔がある。上に石仏が安置されたこの石
塔は安政 5年 (1858)以 降の水難者 30名 の戒名 と
松島吉_平 (十湖)の碑文が刻まれ,そ の傍 らにも明治 1
5年に建てられた石塔に 7名 の水難者の戒名が列記 して
ある。いずれも松島吉平が建てたものである。この水難者供養塔の左手に「西国三十三所順祀観音」
「同行三拾七人」「元禄十二己卯年二月」(1699)と刻まれた古い石仏がある。
8 道標
恒武町六所神社の前に道標がある。正面の
上部に地蔵が彫 られ,「右 中善地 わたし舟かすい斎 左 笠井二俣 道」,左面に 「右
市野安間道」右面に 「明治十四年己五月・辰年二歳男設立」 と刻まれている。元は道の東側
に建てられていた。天竜川の渡 しは明治 16年に豊田橋架橋により途絶えたが,明 治 22年橋の流失により,再び渡 しが戦前まで続け
られた。
9 遠陽市場跡
江戸時代より笠井村では「笠井市」が開かれ ,
遠江国における流通経済の拠点であったが ,
出店商人の増加に伴い,明治 23年に豊西村
恒武に新 しい市場を開設 した。浜松や各地の
商人により合計 40の店舗が並び,賑わった。
明治 32年には笠井街道が市場の中を通つた
が,鉄道の開通や物産流通の変化などにより,
賑わいは大正の時代と共に衰えていった。「静岡県明治銅版画風景集」 (羽衣出版)
2‐

と,こ の角に建てられていた半僧坊の道標 (明 治 17年)力 あ`る。
11 道標 と鳥居紀念碑
安国山養円寺境内に,大きな道標 と鳥居紀念碑がある。
道標は表に「右 奥山半僧坊 五里三十二丁四十六間」,
裏に 「明治十七年六月建之」「石寄附 豊田郡掛下村 横
井伊二郎 (他 3名 )世話人 村田新平 (他 5名 )」 と亥1ま
店」は江戸時代終わり頃の創業で,当 時は金物などをいろいろ扱っていた。その
他街道沿いには 「あぶらや」「おびや」「かまどや」「あまざけや」などの昔の屋
号が残つているが,最近は町屋の建物が少なくなってしまった。
半僧坊道はこの交差
点を右折 し,笠井の町
並みに入る。遠陽市場の銅版画を見ると,この角の手前に半僧坊鳥
居が描かれている。
北の養円寺には,鳥居紀念碑 (明 治 32年 )
10 町屋と店蔵
笠井の町屋は南北の道を挟んで西側 と東
側の二列に連なり,奥行きの長い細長い町
屋 となっていた。度々の大火により,石造
り。レンガ造 りの建物や土蔵造 りの店蔵も
見られた。本町の蔵店 「こうじや」は明治
20年代の建築で笠井街道で最古とい う。
大正の初め,みそ 0こ うじを作って売 り始
めた。また,中 町の町屋造 りの 「鍋屋呉服
れている。 もとは本町 (下
組)の南端の角にあつた。
鳥居改築を記念す る鳥居
紀念碑は表に 「半僧坊鳥居
紀念碑」,裏 に「明治廿二年五月建之」ほか寄附人 と世
話人の名を列記 している。
12 秋葉山常夜灯
中町の街道から西に入つたもと薬師堂の
前にある常夜灯である。「秋葉山常夜燈」「中
町講中」「御広前」「享和四甲子正月吉 日」
(1804)。 石工は三河国岡崎十王町
今井佐兵衛である。元は中町の街道沿いに
あつた。また,笠井町春 日神社に,天保 5
年 (1834)の 秋葉山常夜灯があり,もとは本町 (下組)南端の木戸付近に建てら
れていた。
\ ミヽI二113 笠井観音
集めてきたと語 り伝えられている。正月十 日は,観音様の縁 日と笠井市の初市の日で 「だるま市 。十 日市」と呼ば
れ,賑わう。約 120年前からだるまが売 り出された。観音様で左目に墨をいれ ,
祈祷 してもらつて持ち帰るのが習わしとなっている。
福来寺は, 17世紀の初期,寛永のころの創立と伝えられる。もともと笠井観
音を守る寺として建立された。 (P4「 笠井市場について」参照)
観光山福来寺の笠井観音 (聖観音菩薩像の本造立像)が ,笠井の里に現れたのは大
同元年 (806).色 玉川が洪水になった
後,川瀬で光を発 していたものが発見され
た。井戸水で清め,笠をかぶせて,笠井の
里の真ん中の大樹の下に安置 してお祀 りを
したた総う。願い事をよく叶えてくれる笠井の笠冠 り観音様 と呼ばれて,参詣の人を
…3¨

○笠井市場について「笠井市」は,湖北の 「金指市」,北遠の「二俣市」と共に,江戸時代遠江
における流通経済の拠点として大きな役割を果たした。
笠井村は皆畑の村で,収穫量が少なく,年貢は金納で負担が重かつた。その
ため村人は農作物や手工業品などを売つたり,古着などを買い出してきて市で
売つたりして換金 した。また,近郷のものたちもとれた産物などを売つたり交
換したりした。さらに城下の商人たちが表店を借 り受けて商売をしたので,その貸し賃を得た。特に塩町の専売である塩,肴町の専売である海産物を求めて
市の日には多くの人が集まり,笠井市を繁栄させたという。
市は,朔 日・五 日。十 日・十五日・二十 日・二十五 日の六斎市で,上組 (上
町)。 中組 (中 町)・ 下組 (本 町)の三組で交互に月 2回ずつ開かれ,それぞ
れ上市 。中市 。下市と呼ばれた。
幕末から明治の初期には,新たな技術導入により遠州綿業 0生糸業の基礎が
つくられ,笠井市場は,繊維製品の取引が大きなウエイ トを占めるようになっ
た。明治 23年には遠陽市場も開設されたが,東海道本線の開通や経済交通運
輸など時代の変革とともに大正時代には衰退 していつた。
今では 1月 10日 の市神様の祭典や笠井観音 (福来寺)の 「だるま市・十日
市」が音をしのぶよすがとなっている。
‐4¨

15 +湖 俳句の里 (源長院)
曹洞宗源長院は松島十湖の普提寺である。長屋門造りの山門がある。十湖 (吉
平)は,嘉永 2年 (1849)豊 田郡中善地村 (浜松市豊西町)に生まれた。
幼い頃,源長院住職西尾恵全に読み書きを学ぶ。 15才で棚木夷白に俳諧を学
び, 17才 で宗匠となり,名 を知られた。小田原の福山滝助翁から報徳仕法を
学んで実践し,ま た県会議員,引佐色玉郡長など地方政治家として活躍した。
14 半僧坊町石
笠井観音 (福来寺)の裏通りを少し北へ進み,
細道を左折して進むと,半僧坊町石が建てられ
ている。正面に「五里十五丁」,左面に「長上
郡上村 鈴木和三郎 鈴木勝馬」,右面に「明
治十八年四月□□」と亥1ま れている。この道は
寺島大伝寺前の半僧坊道に向かう近道の細道で
ある。
もつようになったという。天穂 日命は織物をつかさどる神であり,創建当時この
あたりに織物に関係をもつ職人の集団がいたことをうかがわせる。境内からは奈
良時代の須恵器ぉ。く,■顔鮮 などが発見されている。境内には明和 7年 ,文政 9年の
秋葉山常夜灯や小栗廣伴の和歌の碑が建てられている。
16 服織神社
社伝によると,創建は奈良
時代元明天皇の和銅元年 (708)。 延喜式神名帳に所載の
藤靡滋盛とされ廟 主維 と祭神は
天穂 日命 と建御名方命。古事
記によると天穂 日命の二十数
代のちにあたる者が遠江介に
任ぜ られ,遠江 とかかわ りを
17 かなきんさま
服織神社のすぐ南に祠がある。祭神は,昔 この土地
の困つている人を救つてくれた高名な武将とも高僧と
もいわれている。祠は,い ぼ神様として地域の信仰を
集めている。いぼをとってもらうには,住所,氏名 ,
年齢を書き,洗米と賽銭をあげ,願いが叶つたときは
小さな鳥居 (木製かブリキ製)ま たは松笠 (30個位)
を奉納するという。祠に祀られているのは, 14世紀
半ばごろ造立の宝筐印塔 (高 さ約 110cm)で ある。
祠が建てられる以前,こ の場所に中世の墳墓があり,
その上に宝筐印塔が建てられていた可能性が高い。
俳句の里には十湖の
句 「世の中に籍あてば
やすすはらい」「浜松は
出世城な り初松魚」の
他 ,門 人知友の句が並
んでいる。
18 半僧坊道標跡
笠井上の交差点に道標 2基あったが,法永寺
に移され, さらに豊西町の 「十湖百句塚」に移
されている。 1つ は 「左半僧坊道」「明治十五
年八月建之」と亥1ま れ, もう一つは 「直秋葉山
左 平口 気賀 金指道」と刻まれている。
(No.3参照)
半僧坊道は笠井上交差点を左折 して,笠井上町から
浜北区寺島方面に向かう。

ら上村に向かう怪火を見た人々が次々と現れた。源右衛門は反省 して改めて一つ
の墓に埋めて供養 した鼻安こと。権七の住んでいた所には,お地蔵様が祀られた。上村の字名をとって 「韮極地蔵尊」とも「お松地蔵」とも呼ばれる。
19 謹極地蔵尊
今から150年 も前の悲恋の物
語がある。松小池村の源右衛門の
娘お松が笠井上村の権七と恋仲に
なつたが,源右衛門に許 されず ,
ふたりは松小池の池に入水 した。ふたりはそれぞれの村の墓地に埋
葬されたが,夜になると松小池か
21 水野久 平の碑
寺島大伝寺の入 口左手に,町の発明家 といわれた水野
久平の碑がある。江戸時代から笠井周辺では木綿の栽培
が行われ,笠井市場はその集散地 として木綿が取 り引き
された。明治十年代には笠井縞から遠州繊物が発展 し全
国的に知 られた。 この時期,久平は笠井に来て織物の研
究,改良,数多くの発明考護鰭∴ り,遠州織物の品質向
上発展に寄与 した。通称 「機具久 さ」 と慕われた。この
碑は昭和九年二月,弟子たちによつて建てられた。
また,大伝寺には侠客寺島一家を継いだ都田の源人 と
子の常吉・梅吉たちが眠る墓があり,供養されている。
1メ 2,, ., 7,Om-
20 道祖神
双体道祖神で,風化が進んでいる。下
が少 しコンクリー トの台座に埋まってい
る。村境や辻に建てられた魔除けや行路の安全の神である。男女の神は良縁,出産,夫婦円満などを願 うものでもある。
双体道祖神は浜北区では二基のみとい
う。左側面に「左平口不どう」と刻まれ ,
以前は,右面に「右宮口庚申Jあ るいは「辰」の文字が読みとれたという。
22 半僧坊町石
さが り橋を渡つて最初の小さな交差点の
左角に,ブ ロックで囲まれた町石がある。
正面上部の文字が欠けてしまっている。「□
□四丁」と読める。建立年月は不明である。
おそらく五里十四丁の町石 と思われる。半
僧坊道は袴田誠二氏宅の前を斜め左に曲が
つていた。町石はもとはその曲が り角にあ
つたという。
23 秋葉山常夜灯
龍燈 (鞘堂)内 の秋葉山常夜灯には「秋葉山夜燈」「明和五年戊子霜月吉
祥 日」(1768)「寺嶋村郷中」と刻
まれている。秋葉山常夜灯としては古い時期のものである。池田 。笠井より「秋葉街道貴布祢の道標」に向かう道
に沿つて建てられてお り,も とは少 し
南にあった。
24 半僧坊町石
袴田誠二氏宅前から西に進むと,市り|1正
昭氏宅の向かいに町石がある。もとは少 し
東にあつたという。上部が欠けている。正
面に「□□二丁」,右側面に 「大村武平
中安吉平」と刻まれている。おそらく五里
十二丁の町石と思われる。大村武平は,明治 10年代の寺島村戸長である。

′ 一〉H
〉 一) ¨
m ・
』 ¨
く笠井上町の追加>
○馬頭観音
笠井上町の交差点を左折 してカーブ
を曲がると,降所橋の右手に馬頭観音
が祀 られている。風化して像の姿はは
つきりしない。上町のかつての太田た
んす店主が競馬の馬を飼つていて,馬の供養のために建てたとい う。
<寺島の追加 >
ONO.22半 僧坊町石の追加
袴田誠二氏宅前は,小松方面への半僧坊道 と貴布祢方面との分岐点になって
いた。裏の角の町石は,も とはその分岐点にあった。正面中央に「□□□四丁」
と刻まれているが,その左に 「□ 半僧坊」,右に「□ □水□」らしき文字も
読みとれ,道標を兼ねていたと思われる。
○秋葉山常夜灯笠井上町の春 日神社に秋葉山常夜灯
が建てられている。正面に 「常夜燈」
裏面に 「天明九年己酉正月吉 日」 (1789),左 面に「上村中」 と亥1ま れ
ている。村名の上部の文字が意図的に
削られている。明治 8年に笠井新田村
より分村 したためかと思われる。火袋
に秋葉神社の札が納められている。
○半僧坊町石
袴 田重一氏宅地内北西の半僧坊道に
接 した角に,半僧坊町石がある。道路の拡張に伴い宅地内に移 されたとい
う。正面に「五里十五丁」 と刻まれ,左
面に 「寺島村 袴 田□□□ 袴田□□
□ □□□□□」 と亥1ま れている。建
立年月日は不明である。
〈 6-2 〉

半僧坊道は寺島から中条東に入 り,細道をぬけて,笠井・小松線の広い道路に出
中条交差点の西を右折 踏切を渡つて斜め左
25 道標・秋葉大鳥居 0秋葉山常夜灯
秋葉街道と半僧坊道の交差点の道標には,正面に 「右秋葉三
尺坊 左 奥山半僧坊 道」と刻まれている。他の面ははつき
りしないが 「明治十七年建之」「袴田唯吉 竹内伊太郎 (他数
名 )」 と亥1ま れている。半僧坊道は交差点を左折 し北西に進む。
秋業大鳥居は田町の 「一の鳥居」に対 し,「二の鳥居」とい
て西進する。中条交差点のすぐ西の細道を北へ右折し,中条北の交
差点を北西に直進する。踏切を渡つた所を斜め左の細道へ進む。二
俣街道に出てすぐ右手が秋葉大鳥
居の小松東町交差点である。
半僧坊道は,道標のあつた小松交番西交差点を左折して ,
少し進むと,斜め右のやや細い道に入る。,
九
′一
‘にれ
26 道標
小松交番西交差点の西北角に建てられてい
る。正面に 「右 みや ぐち あたご 左 ふ
どう おくやま かなさし きが 道」,裏面に 2名 の生まれ年や年齢が刻まれ ,「協同
建立」「明治□十一年二月」と刻まれている。
隣接の竹内正而氏によると,竹内家・野末家で建立したという。
nii
す
われ,文政 5年 (1822)岡 崎の
石工によつて建てられた。龍燈の中の秋葉山常夜灯は,「永代常夜燈」「願
主小松村中」「明和五成子六月吉目」「右あきはみち」と刻まれ,道標を兼
ねている。 (秋 葉大鳥居 と秋葉山常
夜灯は市指定文化財 )
27 道標三叉路の向かいに道標が建てられている。
正面に 「右 奥山半僧道 四里三十壱丁 左
有玉半田道」,右面に 「□□□□袴田唯吉
□□□□ 山下新□ □田□□」,左面に「明
治十七年五月建之」と刻まれている。
半僧坊道は三叉路を右折する。
28 袴国家長屋門
半僧坊道の左に長屋門が見える。初代枡屋
袴田勘左衛門 (喜祖)は ,豊田郡二俣村の名
主袴田甚右衛門 (喜和)の双子 (兄喜長)の弟で,小松村に分家 し,醸造業から発足 し,
大地主に成長 した人物である。明治銅版画を
見ると,醸造蔵が大小 3棟描かれている。兄
は秋戸,弟 は南素と名乗る俳人でもあつた。
29 道標
半僧坊道は袴田家の裏の角を左折 し,す ぐ
斜め右に進むが,そ の角の電柱の横に道標が
ある。南面には 「左 みやこだ かなさし
けが 道」, 画面に iま 「右 かさい いけ
だ はま つゝ 道」,北面には 「左 きぶね
みや ぐち かじま 道」,東面には 「予時明
治二年己巳初夏 町田両家補佐之時 帰山翁一′い□□貞□長」と刻まれている。

袴国家の裏を斜め左に進むと,遠州の侠客小松村の七五郎の菩提寺である紹隆寺がある。七五郎は甲
州生まれで小松村松本家に入 り婿になり,仁義に厚
く温厚な人柄で村人の面倒もよく見,信頼されてい
た。万延元年,石松が襲われたとき,七五郎がかく
まい諭したが,石松は再び襲われ亡くなった。その
後七五郎は次郎長の子分になり,遠州一円の火場所
を廻り,親分の為に尽くしたが,病のため明治 5年世を去つた。この七五郎に因
んで「七五郎もなか」がなゆた浜北の西側,長栄堂で売られている。|
30 藤兵衛の十人力 (村上神社)
昔,付近の平野一統の藤兵衛は体格・腕力
に優れ十人力あつたと言われている。ある秋のこと,藤兵衛が頬かぶ りをして稲架を作つ
ていると,一人の武士が道を尋ねた。藤兵衛が稲架の上から教えたので,武士に無礼と言
われたかぶれで藤兵衛が棒で躍 りかかつた。
そして大 平まで武士を追つていくと,武士が「我は村上」と藤兵衛に斬 りかかつたので,藤
兵衛が棒を振るうと,武士は打たれて死んでしまつた。
その後,平野一統に眼病を患うものが多く,占つてもらうと「村上のたたり」
と言われ,祠 を建てて祭Wiiを怠らなかった。以後眼病もなく,ま た目の病に御利
益があると参拝者が多いと言われている.
31 半僧坊道標
高さ lm程の自然石に「右 半僧坊道」 と
刻まれている。設置者や年月 日は不明である。
半僧坊道はこの三叉路を右折 し,馬込川の
橋を波る。
平成 28年に撤去処分 され,現存 しない
32 半僧坊町石
橋本理容店前の空き地に町石が建てられて
いる。正面に「四里十六丁」,左面に 「長上郡
小松村 内山文四郎 内山信太郎」,右面に「明
治十七年建之」と刻まれている。
33 道標
自然石に,はつきりしないところがあるが,
「(種子)□ ふどう 左 かなさし道」と刻
まれている。建立者や年月は刻まれていない。
半僧坊道は,道標の左手を進むが,途中か
ら土地改良のため,御陣屋川の所まで消えて
しまっている。
34 道標と馬頭観音
御陣屋川の橋を渡 り,秋葉常夜灯のある左
手の細道を進むと,角 に道標が建てられてい
る。正面に「右 半僧坊 左 濱粂 (松 )池J
左面に「明治十五年四月 浜松紺屋町 内藤
弥吉 笠井村 山下伊太郎」と刻まれている。
隣には,馬頭観音が建てられている。
半僧坊道は道標の右手,妙蓮寺の横を通 り,真 つ直
ぐ段重に登る道の跡があるが,現在は途申で止められ
ていて通行ができない。
8‐

.1 1
. こ .
だ/
か 、
妙蓮寺横から段丘を上がった半僧坊道は, 二部は消滅 してしまったが,その途
中に半僧坊町石だけが残されている。
○半僧坊町石
小松良雄氏宅前に建てられている.半分
下が埋められていて判読できないが,正面
に「四里十□口」,右面に「長上郡笠井□
El□ □□J,左面に「明治十日□」と刻まれ
ている。小松氏によると,も とは少 し南の
半僧坊道の脇に建てられていたが,土地改
良の時ここに移されたという。
半僧坊道は,小松氏宅前を斜めに通り,磯部氏宅の裏を斜めに通つて,片桐氏
宅とビニルハウスの間の坂を上がり,坂の上の道に出ている。
小松氏宅前 片桐氏宅とハウスの間 坂の上の道
く1-2〉
○二本ヶ谷積石塚群
5世紀中葉頃に築かれた古墳群で,台地縁辺部の谷の中に 28基の積石塚が確
認 されている。一辺が 10m程 度の方墳で木椰の埋葬施設がある。
他地域の渡来人との関係が うかがえる
積石塚 と構造などが類似する点,丘陵上
に築かれる盛土の古墳 と隔絶 された立地
状況などから,渡来系集団の墓ではない
かと考えられている。平成 25年 3月 に
6基が県指定史跡 となった。
<P8の 追加 >
○失せ物稲荷
紹隆寺の東側に稲荷神社があり,言い伝えが残 されている。
江戸時代の末,小松村の庄屋をしていた袴田家に滞在 していた一人の行者がお礼だと言つて,「大事な物を忘れた
時,お願いすれば出てくる稲荷だ。Jと ,
稲荷を置いていった。袴田家では祠を
造って近所の人たちと大切に祀つてい
た。
ある日,袴 田家のお嫁 さんのお母 さんが亡くなった時,お母さんに借 りがあるという人が,「お金を返すので預かった
物を返してほしい。Jと 尋ねてきた。家の人が探したが見つからず,困 つて稲荷に
お願いをしたところ,夢に稲荷が現われ探している物の場所を教えてくれた。お
かげで見つかつて助かったという。
稲荷に失せ物が見つかるようにお願いして,見つかつた人たちが大勢いるそ うだ。 (「 小野口の四方山話」 (山 内中 著より)
復元された積石塚

ノ 日日′
―・ ―二芋――[「・ '一
1 平匡
|
t i― ~
(′ )
35 道標
道標付近は,新 しい道路が作られて半僧
坊道は消滅 し,こ の道標だけが残 された。
正面に「観音様」といわれる像が浮き彫
りされている。右側面に 「宝暦□ 右かさ
いみち」,左側面に 「左あきはみち 施主
□□」と亥1ま れている。もとはこの上の台
地にあり,体兵坂を通 り貴布祢に向かう秋
葉道との分岐点にあつたという。
36 道標
台地を上がった都田大平道 との分岐点に
建てられている。正面に 「左 半僧坊道是ヨリ四里」,右面に 「右 都田大平道」,左面に 「長上郡笠井世話人 嶋田嘉平 中村
茂吉 今田定吉 中村注吉 神谷実太郎
明治十七年六月建之」と刻まれる。
半僧坊道は西に向かつて進むが,自 昭上
の交差点あたりまでは消滅 している。
一一一一 ・=ギ‐上一
一・」・
一
△77.7
(2)
9

38 半僧坊町石・三界高霊塔
半僧坊道沿いの袴田材木店西側より少 し北側へ入つたマキ囲いの中に,半僧
坊町石が建てられている。下部が埋められて不明であるが,正面に「三里十□
□」,左面に 「長上郡笠井村 竹内□□ 寺田□□」,右面に「明治十七□□」
と刻まれている.
37 郷ヶ平 4号墳
古墳時代後期 (6世紀前半)に築かれた前
方後円墳で,周 囲には堀が巡 らされ,墳丘に
は埴輪 (円 筒・朝顔 。武人・馬)が並べ られ
ていた。規模は小 さいが,昔のままの形態を
残 している。葬 られた人物は都 田川流域を支
配 していた豪族の一人と推定される。 (市指定
史跡 )
ている。二軒屋街道 と県道 316号線 との交差点に地蔵菩薩が祀られている。里
帰 りの途中に殺された女性を供養する地蔵という。明治 33年に建立。
半僧坊道となっている現在の市道137号線は「二軒屋街道」と呼ば
れている。この街道の西,桜が丘団
地から東の萩丘都田線に至る地域は,
江戸時代のころは民家が 2軒 しかな
く,「 もちや」「ふじや」という茶屋
であった。二軒屋という地名も残つ
39 道標
地蔵菩薩の光背に,「持妙地蔵」,「右金 さ
しをくやま道 左きがとよかわ道」と刻まれ ,
道標を兼ねている。奥山半僧坊や豊川稲荷ヘ
の参詣者が通つたものと想像 される。大正元
年十月九日の建立。
40 恩塚山古墳
今から約 1300年 前 (7世紀前半)につ
くられた。本来は,直径 1lmほ どの円墳だ
つた。通路である羨道 と玄室を備え,横穴式
石室である。一般的な横穴式石室の玄室は縦
長であるが,恩塚山古墳の石室は横長の玄室
をもつ珍 しい形で,県内では唯一のものであ
る。 (市指定史跡 )
41 デコロボー坂 (瀬戸の坂 )
桜が丘団地造成で以前の道は消滅 したが ,
都田町一色と細江町中川を結ぶ坂道があった。
昔,坂の上の村境に一本の杉の巨木があり,
村人は神木として祀つていた。ある年の暮れ
の夜,何者かに切 り倒 された。役人は犯人を
捜 したが見つからなかった。そこで木の倒れ
た方向の一色から犯人を差 し出すよう命 じた
ので,村人たちは震え上がった。このとき諸
国を巡る了念 とい う僧が, この話を聞き,村
また,同所に三界高霊
塔がある。正面に「三界
高霊」,裏面に 「権少教
正今井東明J(奥山方広
寺住職)と 刻まれている。
明治 17年建立。地元の
人たちがお祀 りし,彼岸
や盆に円福寺住職がお経
をあげている。
人の苦難を救 うため犯人となり,処刑 された。村人は僧を仏様の化身として日々
その首の前で念仏を唱えた。ところが,こ の首が毎夜付近の坂をごろごろと転げ
回つたので,村人は首と遺骸をそろえて手厚く埋葬した。そして正月の餅をやめ,
僧の恩を忘れないようにしたと言い伝えられている。
1̈0‐

瀬戸の坂 (通 称デコロボー坂)を 下つて貯
水池を過ぎ,半僧坊道から分かれた右手の道
に秋葉山常夜灯がある。隣に地蔵堂があり,
一体の地蔵が祀 られている。デコロボー坂の
史話にまつわるもので,処刑 された者の霊を
供養するものという。
しばらく進む と,旧 祝田坂を下つてきた 1日
金指街道 と合流する。
蔵は,実業家・政治家で,県立引佐高校を創立した。
屋敷の前に,家門繁栄子孫長久を祈つた「大乗妙典一字一石塔J(天保十五年 )
が建てられている。
`1 0 250m
-
43 旧脱昌橋跡現在の新祝 田橋の上流 50mの 所に 「祝
田の高橋」と呼ばれた木造の旧祝田橋が ,
明治時代から架けられていた。
大正 3年 11月 元城から金指間で開通 し
た軽便鉄道は,昭和 39年 に廃止 となった
が,軽便鉄道の橋があつた位置に,昭和 45年 3月 国道 257号 線の新祝田橋が架け
られた。そのため 1日 祝田橋は役 目を終えた。
44 仙応和尚の碑 uき江戸時代の初期まで,堰が都 田川下流の
牙1部村にあつたため,祝田村に水が引けず ,
困つて領主に懇願 した。 しかし祝田村は旗
本領,刑部村は大名領のため聞き入れ られ
なかつた。そこで祝田村の磯部源吉は,数多くの苦難の末,鳳来寺岩本院の住職にま
でな り,将軍の許 しを得て, 1658年 下
流にあつた堰を祝田地内に移築 した。 これ
42 伊東家長屋門
伊東家は長屋門,馬屋や蔵
等を備え,主屋が延 160坪の大きな屋敷である。明治申
期に伊東要蔵が建てた。先祖
は伊豆の伊東より移 り住んだ
と伝えられ,長い問代官級の
家柄の庄屋であつた。伊東要
により祝田
伝えるため,
升1部地区の水田に水を期 善。そ丼乳な農かにした。この業績を後世に
明治 34年 10月 に「権大僧都仙應師碑」が建てられた。
45 道標この碑の近 くに道標があるが,二つ折れ
て しまっている。左面に 「右 三方原演松
左 金指井伊谷奥山 道」,右面に「(右 )
祝田観世音 (都 田) 左 田米寺氣賀豊川
道」 と刻まれている。建立年や建立者は
刻まれていないが,大正 4年ごろという。
46 祝田厄除観音
祝田山善明寺は,奈良時代行基によって
開創 されたと伝えられ,そ の後長い間衰退
していたものを,黙厳禅師が申興 した。本
尊の聖観世音菩薩は厄除観音 といわれ,古くから厄難消除・心願成就の霊仏 として広
く知 られている。 1月 6目 が例祭 目。難波
中納言の姫が遠江国浅羽の庄司の妻になり,
薬師如来 と如意輪観世音を,庄司も阿弥陀
如来を安置した由来などが伝えられている。

口
道
―
と
,―屋
<祝田の追加 >○辻屋と道標
半僧坊道と旧金指街道の合流点角の片桐氏宅は,も と「辻屋」という旅籠で
あり,明 治時代まで営んでいたという。当時使用された皿が残されている.
辻
絆i t`
ン
同宅内の北西角には,観音像がのった道標があ
る。正面に「右 演松 市野 道」,左面に 「た
大居秋葉道」,右面に「念佛講中 若者連中」,裏面に「明和二乙酉 (1765)人 月吉日 下石田
村石工 源之黙 (丞 )」 と刻まれている。西の祝
田の木橋方向から秋葉山または浜松方面に向かう
き、え ` 日呵
ざヽ
ための道標である。
もう一基,浜松方向からの「右あきは」の
道標が入 回付近にあつ
たが,コ ンクリー ト管の上あたりに埋められ
ているという。左 もと辻屋
○木橋跡
明治の1日 祝田橋ができる前は,現在の新祝田橋より250m位 上流 (伊東家より東側)で ,tll田川の木橋を渡つた。橋は丸太を組み, 20枚の板が敷かれ
ていた。板には穴をあけ,縄が結んであった。川の南北の集落で 10枚ずつ管理し,出水すれば夜中でも総出で岸へ引き上げた。橋の高さは平水時でも腰位の高さであった。
く||…2)

半僧坊道は厄除観音の手前を北に向かうが,富士通ゼネラルエ場によつて分断
されている。工場の北側に秋葉道との分岐′点があり,そ こから北へ進み,踏切を
渡ると道標がある。
されている (市指定文化財 )。 方丈の西側に龍文堂があり,龍文坊が祀られている。
独湛禅師の弟子で火災予防・盗難除去 として信仰を集めている。寺の東の道沿い
の谷間には,中 国の石工によつて刻まれた五如来の石仏がある。また,山腹には
近藤貞用を初めとする近藤家の墓所がある。
47半層傍町石であるが,道標を兼ねている。 |
下部が埋められて見えないが,正面に 「半僧
坊へ弐 (里拾七丁 )」 ,右面に 「す ぐはままつ |へ三里半 左 秋葉道 官 ロヘ (二里)(二俣へ四里 )」 ,左面に 「色玉郡宮 口村 明壽講 |
世話□□□」 と刻まれている。 もとはゼネ ラ |
ルエ場の北側の秋葉道 との分岐点にあつた。 ||
48 宝林寺
初山宝林寺は,江戸時代初期,寛文 4年 (1
6■∴)に旗本金指近藤家二代目当主,登之助貞用公の招きに応 じた明国の僧,独湛禅師
によつて開創された黄栗宗の寺院で遠州地方
における黄栄の拠点である。以来金指近藤 ,
気賀近藤両家の菩提寺となつている。仏殿は,
寛文 7年 (1667)に 建立され,申 国明朝
仏 殿 風の建築様式を伝える。方丈は,住職の起居堂
として,ま た修行僧を指導する禅問答の場として,正徳 6年 (1716)に 建立
された。仏殿・方丈とも国指定重要文化財。報恩堂には近藤家代々の位牌が安置
半僧坊道は再び国道に出て,金指駅の方向に進むが,現在は住宅地となってい
る。そして金指駅前交差点から古い町並みに入る。
47の道標を左折し,大岩の前
を通 り,マ キ囲いの家を右手に進
むが,不通である。国道に出て金
指街道との交差点にある畳店の裏
手の細道に進む。
49 稲翁碑
翁は早戸仙次郎といい,細江町石岡の人で ,
若くして三遠農学社に学び,そ の実践に務めた。
特に稲作において耕作や栽培の研究を重ね,大収穫をあげ三老農の一人といわれた。この功績
を称え,明 治 38年三遠農学社を中心に碑が建
てられた。碑文は郡長松島十湖である。
貞用の墓 。近藤家墓所
2‐
150 市神様
交差点の所に市神様が祀られている。領主近
藤石見守季用が慶長 2年 (1597)初 めてこ
の地に市を開き,毎月二と人の日に六度の市を
立てた。町衆は商売繁栄を祈願する市神を祀つ
た。以前は町の各所に祀られていた。市は江戸
中期あたりから本格的に活発になり,大正の頃
まで開かれた。「田舎なれども金指 しや名所
月に三度の市がたつ」と口ずさまれたとい う。

<石岡の追カロ>
祝田から北上し踏み切 りを越え,道標を兼ねた半僧坊町石 (NO.47)の あ
る交差点を左折し, 50m進むと大岩があり,その下に半僧坊町石が建てられて
いる。
47道標
富士通ゼ
寺 ¨
卍罫恥‥
84
口 |
ネ
ぶ'I II・
|弔 二=´ :.::′
'レ |ょ……Ⅲ…嘉琳
4事
近藤家墓所
`8
日 Fl
○半僧坊町石 |右上部が破損欠落 しているが,正面|
に 「式里十九□」,左面に 「色玉郡宮 口
村 伊藤 □□J,右面に 「明治十六年建
之」 と亥1ま れている。
この町石 は,NO.47の 道標 (弐 |
里拾七丁)が もとあつた富士通ゼネ ラ|
ル北の交差点か らさらに東 の地点にあ
つたもの と思われる。
く12-2)

51 金指関所跡
慶長 6年 (1601)に 気賀関所が設け
られた後,延宝 3年 (1675)以 前には
金指番所が設けられていた。金指近藤氏の
陣屋代官が上番を勤めた。宝永 2年 (1705)の 検地帳に,「関所の表は 7間 1尺で
敷地は 161坪 」と記 されている。鳳来寺
道を南北交流する人 と物資の動きを監視す
る地 として明治に至るまで治安上重要な役
割を果たした。
52 半僧坊町石
少し左へ曲がった道の交差点左角に,半僧坊町石がある。正面に「奥山半僧坊大植現へ二里□□」とあり,下部の部分
は埋められ見えない。左面に「明治二十七年二月建之 美濃
島十湖の肝いりで明治 17年に建てられた。同時に,十湖の句碑 「何事も かか
る浮世か 月の雲」が隣に建てられた。
53 渡辺謙堂の碑
急坂を登 り実相寺門前に至ると,渡辺兵治
謙堂の顕彰碑がある。謙堂は文化 6年 (1809)に 金指に生まれた。実相寺や初山宝林
寺の和尚について和漢の学を修め,浜松藩の
原田団兵衛に師事 した。天文 `地理 0和算・
測量の術に秀で,嘉永 5年 (1852)木 版
刷 りの遠州の地図 「遠江小図」を刊行 した。
碑は, 47歳 での死を惜 しんで,郡長の松
` ヽ 国土岐郡泉村 寄付人 亀山芳子」と刻まれている。
これと同形で同年月,同美濃
国土岐郡泉村の人たちが建立し
た町石が,三方原追分交差点と
奥山交差点付近,栃窪,中区布
橋さいが崖バス停前にも建てら
れている。
庭 園 季用夫婦の墓 堂は弘化 2年 (1845)に そ
れぞれ再建。観音堂の厄除聖観音は天正 8年 (1590)の 作という。
枯山水庭園は,江戸時代初期の本格的な庭園で鳳来寺東照宮へ参詣した浜松城
主もここで憩われている。 (県指定名勝) ボタンを押すと解説の録音が流れる。
本堂と観音堂
54 寅相寺
開山悦翁和尚は方広寺開山無
文元選禅師の第一弟子できだ極正
院を開創 した。旗本近藤貞用が
寛永 5年 (1628)に 寺をこ
の地に移し,寺号ぬ醜め,金指近藤始祖である父季用の菩提寺
とした。円墳を築き季用の墓を
移 し,後 に母の石塔を建立した。
火災に遭い,本堂は延宝 6年(1678)に 再建,鐘楼門は享
保 2年 (1717),観 音堂は
元禄 15年 (1702),´ 庚申
3¨
55 道標
半僧坊町石であるが,道標を兼ねている。
正面に 「左 奥山半僧坊ェ弐里四町」,右面
に 「右 三嶽神社ェ三十人町」,左面に 「明
治十八年七月建之 都田村 (4名 の氏名)金指村 (4名 の氏名 )」 と刻まれている。二つ
に折れた跡があり,補修されている。
半僧坊道は,こ の道標を左折 し, しばらく
進むと山中の急な下り坂となる。

<金指の追加 >○半僧坊町石
三石屋北となりの秋田氏宅の前庭に,二基の半僧坊町石が建てられている。
ヽ
左手の町石は保存状態が良く,正面
に「式里人丁三十五間J,右面に「引佐
郡三和村〇善蔵 明治十六年建之」,
左面に「従是官ロヘニ里十五丁十五間」
と刻まれている。秋田氏宅の場所には,
もとは〇 (ま るいち)旅館があつた。
○半僧坊町石
賞相寺門前にある渡辺謙堂の碑の後ろあ
た りに,半僧坊町石がある。正面に「弐里
二丁」,左面は一部が欠け 「明治□□」,右面の建立者名はなぜか意図的に削 り取 られ
ている。 もとはもつと先の賞相寺裏の坂を
下つてい く途中にあつたものと思われるが
定かではない。
右手の町石は,正面に「弐里九丁」,
右面に 「色玉郡□□鍵屋□□」,左面
に「明治十六年建立」と刻まれている。
元は別の所にあつたが,秋田氏がここ
に移 したという。
(13-2〉

レンガ塀のある家の右手をさらに下ると,半僧坊町石が建てられている。
趣ま「
二 折れて下つていく。
日日
57 井伊谷宮
南北朝時代,延元 3年 (1338)吉 野朝の後醍醐天皇の命により征東将軍
に任ぜられた宗良親王は,井伊道政・高顕父子に迎えられ井伊谷城に入つた。
以後,三岳城・千頭峯城・鴨江城・大平城などを拠′点に,北朝方と戦つたが敗
れ去った。その後越中・越後・信濃と進んだが,晩年この地へ訪れ,元中2年
58 龍渾寺
高松山龍渾禅寺は,天平 5年 (733)行 基の開基と伝えられる。井伊家 。
宗良親王菩提寺である。山門 。本堂 。開山堂・霊屋・庫裏 とも江戸時代の建立
で県指定文化財である。
本堂は江戸初期の延宝 4年 (1676)の 再亀nbぅ杏場の虚空蔵菩薩が安置
されている。廊下は鶯張りである。開山堂は開山黙 宗瑞淵の木像が安置されて
いる。堂の一負鰐左甚五郎作 と伝えられる龍の彫亥Jが ある。井伊家霊屋には,
歴代の位牌や共保・直盛 。直政の像が安置されている。 24代直政は,徳川家
康に仕え,井伊の赤鬼 と恐れ られる活躍をし,四天王の筆頭に出世,関 ヶ原合戦後,彦根に移る。
小堀遠州作の庭園は国指定名勝であり,江戸時
代初めに作庭 された池泉鑑賞式庭園である。小堀
遠州は,滋賀 。長浜の出身で 「遠州流」の茶道を
興 し,二条城二の丸庭園の作庭等をした当代一の
文化人であつた。
開山堂の西側には,井伊家歴代の墓所がある。
(1385)亮 御 された。墓は
本殿の背後にあり,西に向か
って 「冷湛寺殿」と亥1ま れた
宝筐印塔が建てられている。
親王は和歌に秀で,歌集「李
花集」を残 している。親王は
学問の神様 として信仰 され尊
ばれている。
59 共保出生の井
龍渾寺の南,田 圃の中に,井伊氏始祖井伊共保出生の井戸として往古から伝
えられている。平安時代中頃の寛弘年間,藤原備中守共資が遠江介として村櫛へ下向し,渭伊神社へ参拝後,井戸の傍らに嬰児を見つけ己が子とした。子は
後年郷名に因み井伊共保と称し,当 地方の宰主となり井伊氏の基を開いたとい
う。また,別の史説も案内板に書かれている。
4¨
井伊家歴代墓所

~言・ミ
、1、、
半僧坊道は,井伊谷小学校の校庭によつて分断さ
れている。小学校の北側を西に進む。
雇用促進住宅が建っている所に,井伊谷近藤陣屋
があった。近藤氏の領地は,分知によつて旗本五近藤となり,
井伊谷近藤氏が,こ の地に陣屋を置いた。
60 井伊谷城跡
浜名湖北東部一体に勢力を振るつた井伊氏の居城跡で,南北朝時代に南朝方
に属した井伊道政は,延元 3年 (1338)後醍醐天皇の皇子宗良親王を迎え,
三岳城を本城として井伊谷城・奥山城・千頭ヶ峯城など城網群によつて北朝方
と戦つたが,翌年落城し,南朝勢力は一掃されてしまつた。井伊氏はその後今
川氏に服属し,戦国期には今川氏の西遠江の押さえとして活躍するが,直盛 0
直親の死後,直政が徳川家康に仕えて四天王の一人となり,彦根城主井伊家の
61た 長真対社多道間守と宗良親王の二柱を祭神としてい
る。往古は三宅神社といい,井伊郷の荘司三
宅氏の始祖多道間守の霊を祀る式内社であつ
た。垂仁天皇の勅譴に応え常世の国から橘を
将来したのが多道間守である。井伊家は渭伊
神社を象徴する井桁 と二宅神社の橘とを家紋
にしている。宗良親王が亮 じて霊を合祀し,
二官神社とした。
62 足切観音
祖 となった。
山頂に本曲輪の平坦地があり,一部に土
つた。親王は益々信仰を高め,
二宮山円通寺の本尊,足切観世音は,弘法大
師の作 といわれ,南北朝の争乱に宗良親王が
信仰 した仏であるとい う。親王が戦いの中,
敵の矢にあたつて落馬 したが,不思議と傷が
なかつた。その夜,親王が観音を夢見たため,
塁が残る。一段高い所に御所丸跡が
ある。現在は城山
公園として整備 さ
れている。
(市才旨穴型史』珈0
翌朝観音へ参拝 し扉を開けると,観音は親王
の身替わりとなり片足が血に染まった姿であ
終生の守 り本尊として祈願 したという。
はこれを憐れみ,末弟井伊直元公に乞い,供養のため両者の塚を築き,遺骸魔納
めて輪塔を建て塚の上に一本の松を植えたと言い伝えられている。以来 「濫塔の
松」「井殿の塚」と称している。嘉永 5年大老井伊直弼がこの墓所を礼拝し,石垣
などを寄進 したと伝えられる。
川館に召喚され,遂に傷害されるに至った。里人
63 井殿 の塚
天文 13年 (1544)井伊直満・直義兄弟は,
今川・武田両軍の対立に
際し,家老小野和泉守道
高の識言により駿河の今
64 木食仏
健康 0文化センターに引佐町狩宿の寿龍院
辰奏員鳥れていた木食仏が展示 されている。
木食五行は江戸後期の甲斐の遊行僧で,晩年
に日本廻国と千体仏像造を発願 し各地を遍歴 ,
特異な木彫仏を残 した。冥界にあつて亡者の
罪業を裁判する閻魔大王を初めとするょ沸
ふ,二途の■で亡者の衣服をはぎ取る葬頭河
婆像 (脱衣婆)が展示されている。

国・
神宮寺交差点角に,紅屋製菓があり,奥浜名湖・湖北
名物 「紅屋のみそまん」が売 られている。黒糖を入れて
旨みを出した鰻頭だが,味噌が入つているような色をし
ているため,「みそまん」と名付けられた。無添カロでモチ
モチとした手作 りの優頭である。「みそまん」は,引佐・
細江・三ヶ口の 12店で,そ れぞれ工夫を盛 り込んで作
られている。
65 消夕神社・天自磐産遺跡
延喜式神名帳に渭伊神社とあり,井伊家祖先共保,寛弘 7年その神井より出
生したと伝えられ,以来産神として信仰が厚かつた。往古,今の龍渾寺境内に
あったが,南北朝兵乱の時, この地に移されたという。
天白磐座遺跡 (県指定史跡)は,本殿の背後にある薬師山の頂上に位置し,
約40m四 方に群在する巨石群を神の依代 (磐座)と した我が国屈指の規模を
もつ古代祭祀遺跡である。古墳時代前期 (4世紀後葉)か ら平安時代に至る祭
引佐南中バス停の所に「白岩道」と刻まれた道標があり,
半僧坊道から別れ,北の坂を上がっていくと,自 岩水神社
に至る。
が霊表されると伝えられている。井戸は引佐町花平の川底や信州諏訪湖,佐倉の
桜ヶ池海原に通じているという各種の伝説がある。
野沢酒店前の引佐横尾バス停より少 し手前で,半僧坊
道はしばらく県道から右手の細道に入る。
途中寺院跡で,半僧坊道は分断されている。
67 開明座
東四村コミュニティセンター内に,横尾歌舞伎が行われる「開明座」がある。
横尾歌舞伎は,横尾・白岩地区に江戸時代から連綿と伝えられた農村歌舞伎で
ある。役者,三味線,囃子,振付師をはじめ,衣装の着付け,床 山,化粧,大道具,小道具まで全て地域の保存会の会員によつて運営されている。横尾の氏
神人桂神社, 自岩の氏神六所神社の祭礼の余興 として行われている。毎年 10月第 2土・ 日曜に公演される。県指定無形民俗文化財。
祀場であつた。 こ
の遺跡は渭伊神社の創祀が古墳時代
前期までさかのぼ
ることを語る。
66 うなぎ井戸
白岩水神社には,太古より霊水がわき出
て,清流をなしている。
石灰岩の岩盤でできた
井戸に,今 もなお, うなぎの先祖で神 と崇め
られていた巨大 うなぎ
半僧坊道は,コ ミュニティセ ンターの北か ら裏の細道
を通 り,県道へ出る。
6¨
隣に横尾歌舞伎資料
館 と,県道沿いに 「横
尾歌舞伎発祥之地」の
石碑がある。

もあつた。
両隣には,「文化五辰十一月吉 目」(1808)建 立の 「念仏供養之塔」や「第二紀州紀三井寺」と刻まれた観音像がある。紀三井寺は西国三十三カ所観音
霊場の二番札所である。
68 廻国供養塔
正面に 「□大乗妙典六十六部 日本廻國供
養塔 天下泰平 日月晴明 □□明王同行
要順本浄」,右面に「明和六己丑天二月吉
日」 (1769),左 面に 「遠協引佐郡栃久
保村住人」と刻まれている。六十六部は六
部ともいわれ,日 本全国 66か所を巡ネLし ,
1国 1箇所の霊場に法華経を 1部ずつ納め
る宗教者で,近世には俗人が行 う廻国巡礼
0 250m′,
1 -´ _一、、
粂蔵」と亥1ま れ,ち ょうど半僧坊ヘー里の道のりを示 している.
もう一つは,道標で正面に「右 け賀 左 力日さい 道」,裏面に「馬 ノト(法 )
輪童子菩提 文化二年丑六月□日」(1805)と 刻まれている。もとは少し東の
気賀と笠井への分岐点にあつたものと思われる。
71 正法寺
正法寺は,雲庵重治和尚が開山,当 山 7世黙宗和尚は龍渾寺を開山した。山
門の建立は江戸時代後期 といわれる。山門の瓦に方広寺塔頭寺院の証とされる
菊の紋がある。また,山 門に左甚五郎作と伝えられる龍の彫刻がある。「ある夏の日のこと,奥山川の水が急に減 り,龍が川の水を飲むと知らされた
村人たちは困り,龍の眼を潰 してしまうとり||へ は行けないだろうと,恐れなが
らも近寄つて龍の眼を潰 してしまった。 しかし,翌 日村人が見に行 くと,眼を
潰された龍は,そ の眼を見開いて村人たちを温かく見守ってくれた」という伝
説が残つている。
69 道標
半僧坊町石であるが,道標を兼ねている。
正面に 「半僧坊壼里壼丁」,右面に 「右
氣賀道壼里萱丁 従是宮日村道 三里廿
丁」,左面に 「営所 ヨリ官 回村 道教□□
発起人 □□屋源一郎 亀田屋久二郎 新
藤屋房吉 柳屋字平 石工 濱松紺屋町
佐藤善一郎」, 裏面に 「明治十六年建之」
と刻まれている。
70 道標
竜ヶ岩洞入 ロバス停の先
に二つの道標が建て られて
いる。一つは,半僧坊町石で ,
正面に「奥山半僧坊大植現」,
左面に 「明治十五年六月
二十六丁目」,右面に 「奉納
営國長上郡下石 田村 金子
=・撃″ ス
ー
7¨
72ま ぁ葉山常夜灯馬門バス停前の鞘堂に,秋葉山常夜灯が置
かれている。柱には 「秋葉山大檀現 半僧坊
大槽現」,「安永五年申ノ十二月 日建之」 (1776)と 亥1ま れている。二つの大権現を祀
る常夜灯は珍しい。
∵ ■
―r

蒼ヶ岩胴
<栃窪から馬門の追加 >
○ 半僧坊町石
NO.70の 道標 と半僧坊町石のすぐ
上に,大型の半僧坊町石が横たわってい
る。正面に 「奥山半僧坊大槽現ヘー里」,
左面に 「明治三十七年二月建之 美濃國
土岐郡泉村 寄附人 山村要子」 と刻ま
れている。同年月,同 泉村の人たちが建
立した町石は,中 区布橋,三方原追分 ,
金指,奥 山にも建てられている。
○ 五輪塔他
道沿いに五輪塔 と宝筐印塔が 2基があ
る.約 700年 前,紀州熊野の城主青山
但馬守善六郎長範が,宗良親王の援軍と
して来た り住んだとい う。このいずれか
が但馬守の墓で,他は一門当主の墓であ
ろうといわれる。
υヽう。この本はご神木として,青山氏宅など3軒が交代で毎年 3月 9日 前後に清掃 し,
重箱 (も ち 5個)を用意し,おみき野菜をお供えしている。
○椋の木
川の北側に,市指定天然記念物の椋の木がある。エレ科の落葉高木で春に緑色の小
花を開く。周囲6m,高 さ28,9m,推定樹齢 700余年とされる古木である。
椋の木の下に石碑があり,「権現熊野神
社」 (昭 和46年青山氏建立)と 刻まれている。青山但馬守が郷里の熊野神社の分身を迎え,社殿を建て戦捷祈願した。その際の記念木として植えたのが椋の本であると
〈17-2〉

ツC IЪ 中本寸
Π
L
6)後醍醐天皇の皇子宗良親王を遠江に最初に迎えた城という説がある。永禄 5
年 (1582)に 今川勢に攻められ落城した。今はみかん畑となつている。
半僧坊道は,中村公民館手前で ,
右手のやや高い細道に入つて しば
らく進み,小齋藤バス停手前で再
び県道へ降 りる。真っ直 ぐに降 り
る道が旧道であるが,不通である。
73 奥山館 (今城 )
鎌倉時代後期に初代奥山領主であった
井伊奥山朝晴の居城 として築かれたとい
う。また南北朝時代に南朝方の奥山朝藤
が築いたとも伝わる。東西 70m南 北 6
0mの長方形の曲輪。延元元年 (133
たヽ、_
0 250m
小齋藤ポケットパークには,
74 半僧坊町石
気賀方面から半僧坊へ向か う道で,後藤家の
少 し南に建てられている。上部が欠けているが,
正面に 「二拾七町」,左面に 「中川村 今泉正
健」,右面に 「明治十七年一月建之」 と亥1ま れ
ている。
軽便鉄道の案内板がある。
軽便鉄道の終点奥山駅の手前に鉄橋が一部残されている。
昭和 54年 ,県道に神宮寺川の花見橋が架けられるまで使われた,半僧坊道の
旧橋の跡がある。
鉄橋の一部
午年」と刻まれている。建立者名は読みとれない。
2基 とも同型で同年に建てられたが,文字から上下一つのものではない。大き
な一基は,こ の先の坂を上がった所に建てられていたものと思われる。
旧橋へ 旧橋から
75 半僧坊町石
1目 橋跡を渡つた先の電柱の脇に,十二丁目
と十一丁目と思われる半僧坊町石がある。
小さな一基は,下部が欠損 して文字が不明
であるが,正面に 「第拾式」,右面に 「明治
十五壬」と刻まれ,左面は不明である。
大きな一基は,上部が欠損 して文字が不明
であるが,正面に 「壼丁 目」,右面に 「五壬
8‐

Π常
○ 青地蔵他
半僧坊道が県道に下りる手前に,大小の自然石の仏が祀られている。大きい
方には,「南無阿爾陀佛」など,左面に「□□□清浄」と刻まれている。左側の小さな自然石には真ん中に「南無地蔵菩薩」,右に「依里附水精」,左
に「一切□□霊」,下に「施主敬自」と刻まれ,青地蔵と呼ばれている。青地蔵に雨乞いをしたという。戦争前まで部落行事として田植え後の精進の時,川で
楔ぎをして地蔵を祀った。
○ 馬頭観音 (道標)
神宮寺川の橋を渡つて中村に入る。すぐ
右手の沖田氏宅と杉山氏宅の間の細道に馬
頭観音が 2基ある。自然石の大きい方には「馬頭観世音」,そ の右に「はうかう寺み
ち」,左 に 「さくはみち」と刻まれ,道標を兼ねている。建立時期は不明。この細道
を進み坂を上がっていくと,次の常夜灯に
至り, さらに方広寺に向かう。
○ 常夜灯
半僧坊道から少し上がった所に常夜灯が
建てられている。柱の正面に「半僧大植現」
(坊は書かれていない),右面に「秋葉大
槽現」と刻まれている。建立年月は不明で
ある。 2つ の大権現を進拝するための常夜
灯は馬門にもあつた。(NO,72参 照)
青地蔵
く18´ 2〉

li l■
H耕・
半 町
`
`
.¬ 1 0. _ 響q=m
76 半僧坊町石
旧法界門跡に,十二丁目の半僧坊町石
が建てられている。正面に 「奥山半僧坊
大植現へ十二□」とあり下部が埋められ
て見えない。左面に 「明治三十七年二月
建之 美濃国土岐郡泉村 寄イ十人 山村
欽一」と刻まれている。これと同型で同年,同美濃国土岐郡泉
村の人たちが建立した町石が三方原追分
と金指,栃窪,中 区布橋さいが崖バス停
前にもある。(NO.52参 照)
77 半僧坊町石
奥山体育センター入国の坂の下に,十丁目の町石が建てられている。正面に「第
拾丁目」,左面に「三河国渥美郡□□□」,
右面に 「明治十五□□年」と刻まれ,下部は埋められ見えない。十二丁目 。十一
丁目の町石と同型で同年に建てられてい
る。
78 道標
軽便鉄道奥山駅前から半僧坊へ向か う
坂の下に建てられている。正面に 「奉納
献燈 右 半僧坊大植現道」,裏面に「昭
和十六年十二月 寄附人 四国市 日永町
堀満弥」と刻まれている。軽便鉄道は大
正 12年に開通 し,多 くの人たちが利用
して半僧坊へ参詣した。
半僧坊の名物として,大あんまき 。大
あぶらげがある。野沢製菓の大あんまき
は,「奥山半僧坊」の焼き印が押され ,
縁起物の土産にもなっている。中尾商店の大あぶらげは,明治 14年の大火の直
後,初代万次郎が江戸の豆腐油揚職人を
連れて焼け跡に創設。百年以上の伝統と
技術を守つている。
79 総門 (黒門)
入日となる総門は,常に単層 (一階建
て)になってお り,方広寺の総門は通称「黒門」とよばれている。上部には 「地
自有霊」 (地 自ら霊有 り)と 揮竃された
大扁額が掲げられている。管長を務めて
いた足利紫山老師が筆をとつたものであ
る。
80 山門
朱塗 りの山門は足利紫山老師の代に再
建されたもので,地形に合ゎせ辞J)ぶ 鬱lξ造られこいる。正式には空。無相・無作の三解脱を標識するので三門という。
正面の護国の掲額は高松官宣仁親王の
筆になり,裏の吉雲関の額は,足利紫山
老師の書かれたものである。
9…

′
/ 1
石
4 」躙
澤 ぎ払̈81 五百羅漢
羅漢は正式には阿羅漢といい,月 乗ヽの悟 り
を極めた仏弟子のこと。羅漢がこの世に現存
して仏法を護ることや 500人 の修行僧が開
山lEl明 大師の弟子として参禅 していたことな
どを象徴 して, 500然を明和 7年 (1770)に境内全域に祀つた。
82 半僧坊町石
三丁目の半僧坊町石である。正面に「第参
丁目」,右面に「明治十五壬午年」,左面に「三
河国渥美郡高塚村 願主 小野田松次郎 早
川平作 朝倉藤次郎」と刻まれている。
同型,同年,同三河国渥美郡の人たちが建
立した町石は,十丁目があり,字形は十一丁
目,十二丁 目の町石も同じである。 (NO・
三丁目の町石を過ぎると,参道が左右に分かれてい
る。左の表参道を進むと,「哲学の道」の八 日付近
に杉の切 り株がある。
表参道の鳥居の手前で,1日 参道は右に曲がるが
は羅漢が並べられ,通行はできない。
羅漢が並ぶ旧参道脇に,町石が建てられている。
杉の切 り株には,内部に焼け跡が残つてい
る。明治 14年に本堂などを焼失する大火が
あつたが,杉は枯死せず生き残 り,近 くの沢
から水分を吸収 し,高 さ約 30m,直 径 2m近い大木に育ったとみられる。平成 23年の
台風の影響で倒れかかつた杉を伐採 して見つ
75077参 照)
かった。
83 半僧坊町石
正面に 「第弐丁 目」,右面に 「明治十五壬
午年」,左面に 「三河国渥美郡七根村 願主
高橋小十郎」と亥1ま れている。
(NO.75077・ 82参照)
羅漢との組み合わせがほほえましい。
旧参道は,大慈閣前を通る参道へと上がっ
ていく。大慈閣前に町石が建てられている。
84 半僧坊町石
半僧坊道一丁目の町石である。正面に 「第
壼丁目」,右面に 「明治十五壬午年」,左面に「三河国渥美郡七根村 願主 高橋小十郎」
と刻まれている。二丁目と同じ建立者である。
以前は 30m程 先にあつたという。
(NO.75077082・ 83参照 )
現在
85 半僧杉
根回 り7.55m, 日通 り5.75m,樹 高 43m,樹齢推定 600年 で,当 地方第一の大杉である。明治 1
4年の大火で,半僧坊 と七尊菩薩堂だけが焼失を免れ ,
大杉も残つたため,以来この杉は方広寺の御神木,すな
わち方広寺 「半僧杉」として語 り継がれている。市指定
天然記念物。

口|
8本堂
昇天した。苦しみから脱した龍神は永久にこの山の水を守護することを誓った。この龍神は,嘗て坂上田村麻呂将軍が蝦夷征伐の折,美女と化して将軍と契 り
を結び,田 村俊光公を産んだ大蛇で,その霊験はあらたかで,奥山の里は水不足
に悩んだことはなく,お祈 りすれば必ず雨に恵まれるので,全国からお参 りする
人が絶えないという。。
6 椎河龍王堂
無文元選禅師が中国で修行を終え帰国し行
脚の途中,鹿島のあたりで増水した河を波れ
ず難儀をしていた時,龍神が現れ,そ の身を
橋 として禅師を渡 したという。禅師が方広寺
に入つた後,龍神が再び姿を現 し,蛇身の苦
しみから解脱させてほしいと懇願 したので,
禅師がこれを哀れみ,教典でその蛇身を撫で
ると,た ちまち五百年の苦しみから解脱 して
87 七尊菩薩堂
建物の中奥にある小 さな
堂は,応永 8年 (1401)建立の棟札を有する県下最
古の本造建築物である。富士浅間大菩薩・春 日大明神など七神を合わせて祀
る鎮守堂である。こけら葺きの一間社流れ造 りは優美で ,
を今に伝えている。国指定重要文化財である。
88 本堂
建徳 2年 (1371)に 建てられた本堂は,数度の山火事による類焼を受けた。明
治 14年の火災で焼失。現在の本堂は大正4年に完成 した。本尊釈迦如来,脇侍に文
殊・普賢の二菩薩が安置 されている。国指定重要文化財。観応 3年 (1352)に 彫
刻 された木像で,元禄のころ水戸徳川光囲
畠拿埠ふ島軋層見η藻裟暑]芳異蔦暴県措げられている。
霊塔」があり,
なっている。
89 開山堂
勅使門の奥に開山堂が建てられている。
開山無文元選禅師は後醍醐天皇の皇子で ,
建徳 2年 (1371)に 開創。開基は,井伊氏の一族である奥山六郎次郎朝藤であ
る。この寺で修行に励む僧は常時 500人いたといい,禅師は数多くの弟子を育てた。
現在の開山堂は昭和 10年 ,足利紫山老師が建立した。
背後の山に登ると,無文元選禅師の「黙
奥山朝藤の墓があるが,現在は通行禁上に後醍醐天皇の遺髪塔 ,
鎌倉末期の建築様式
90 半僧坊町石
開山堂の左手角に,四 丁目の町石が建て
られている。上部が欠損 している。正面に「□□坊大灌現」,右面に「□□年二月吉
日 四丁 目」,左面に「四丁 目 流膿洗療
治 湊吉雄」と亥1ま れている。建立年は不
明である。もとは山門と総門の間あた りの
四丁目に建てられていたものと思われる。
…21‐

912奥の院
坊真殿
♯|タ
一k
広寺の鎮守として祀られている。厄難消滅 。海上安全・火災消除・諸願満足の御
利益があり,全国的に信仰を集めている。毎年 10月 第 2日 曜 日に大祭が開かれ
る。
真殿は,明治 14年の大火で類焼を免れたが,現在の真殿は,明 治 18年 に三
河の工匠によつて再建された権現造りの建物である。向拝に付いている昇り龍 。
降り龍は,彫師岩五郎の傑作である。真殿前には,明 治 13年に浜松市燈籠講が
奉納した大型の常夜灯が建てられている。
日 日
91 半僧坊真殿
伝説によると,無文元選禅師が中国で修
行 しての帰 り,海上で暴風に遭遇したとき,
船首に鼻が高く眼光のするどい一人の異人
が現れ,無事博多の港に導いた。次に禅師
が奥山に方広寺を開いたとき再び現れ,この山の鎮守とならんと言 うと,半分僧の力
量ありと言われて半僧坊 と名乗るようにな
つたという。以来半僧坊大権現は深奥山方
真殿の左手 (西側)に廻ると,「奥之院道」「奥之院道
二丁」の道標がある。奥の院橋を波 り山を登る。「従是奥
之院一丁」を経て,奥の院に着く。
-0 50m
92 奥の院
半僧坊大権現の奥の院で,再建されている
る。奥の院の前に 「半僧坊大檀現夜燈」「文
化四丁卯正月吉目」(1807)「 施主 鼠野
村□□」と亥1ま れた石造 りの常夜灯が建てら
れている。
‐22¨
![a v Ç v v i } ] o v i v v i À } ] o v À Ç o · v É Z l } u µ v ] Z · 2020-01-23 · } À l É u µ } l i v i l ] } o Ç v } À „E ] l } q l } } Ì v u } l l v v i a v v i](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5ecfd6c771ea7905db54f289/a-v-v-v-i-o-v-i-v-v-i-o-v-o-v-z-l-u-v-z-2020-01-23.jpg)


![W ( ] o o - Mindtree | IT Consulting & Technology ….../E l /E } u v Ç l v l E u K ( 'D ~ rDKE rzzzz / v À } & ] E u / v À } D ] o E u / v À } > E u & Z l, µ v & ] E u & Z l,](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5f249329fe49734c412c9232/w-o-o-mindtree-it-consulting-technology-e-l-e-u-v-l-v-l.jpg)

![E l } ] v i ] } Ì v } o ] l } ] Z À l ( µ v ~/W r ì ò r î ...€¦ · ] Î ] À v i ] u î ì í ó X P } ] v X ^ l v ] W ^< r ^ < o U W t W } o } i U E i< t E i ]](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/602f53aaa750c91e884cb41b/e-l-v-i-oe-v-o-l-z-l-v-w-r-r-v.jpg)


![X a ¸ l< `h E à · 2017-09-25 · X £ ` É a ¤¶Í t l< `h E w à E > ¤¶Í Õ _ {° ` öOT Ðw óoM D ó QUôMwpxsMpT`h ¸ ]w wSÉw0 tÉpx C_^ d p`hU Ï `l ¤¶Íw](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5ea63c61ff517674815cb11c/x-a-l-h-e-2017-09-25-x-a-t-l-h-e-w-e-.jpg)

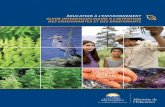
![Supersymmetric Dark Matter - KAISTyoo.kaist.ac.kr/lectures/2019/2/files/students/...À ] v ( } Æ ] v } ( l D & ] Ì Á ] l Ç. À ] v ( } Æ ] v } ( l D Z } ] } v µ À } ( E' ò](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/603f96d541d9cc246873a284/supersymmetric-dark-matter-v-v-l-d-oe-l-.jpg)

![W ] } ] Ç ^ µ Á r } ( ó l î î l î ì î ì > E u & ] E u ^ µ ... · > E u & ] E u ^ µ s o ] h v ] o Z ] À u v } v D l v Ì ] > À o ð ò l ï ì l î ì î ì r ô l ð](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/600ee31d6aa5034f513878e4/w-r-l-l-e-u-e-u-.jpg)

![E E < ^D E P ' D7b ~ } l µ Ì Ç o º o m v ] À ] ] î ì í ò r ... · í E E < ^D E P ' D7b ~ } l µ Ì Ç o º o m v ] À ] ] î ì í ò r î ì î ì v u ] Z l Ç f](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/5f11c08e2f47e65b3425adb5/e-e-d-e-p-d7b-l-oe-o-o-m-v-r-e.jpg)
![Foundation - Shang Han Lun · SHANG HAN LUN DIFFERENTIATION / 'EK^/^ ^/'E^ E ^zDWdKD^dKE'h Wh>^ d / z E' t ] v l & À U À ] } v } } o U ] ( (](https://static.fdocuments.us/doc/165x107/60bff9075d91cf2999056e5e/foundation-shang-han-lun-shang-han-lun-differentiation-ek-e-e-zdwdkddkeh.jpg)


