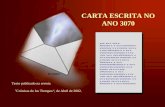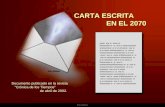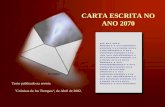Îl G¶ w]/ ßwS&M · 2018. 7. 24. · O`h r hjx¶ 6w 0 w Éz ^sr JQ oS^ _ s§ Aqb q Ìtfz Uj¼q...
Transcript of Îl G¶ w]/ ßwS&M · 2018. 7. 24. · O`h r hjx¶ 6w 0 w Éz ^sr JQ oS^ _ s§ Aqb q Ìtfz Uj¼q...
-
[発行日]平成30 年7月[発 行]国立大学法人 滋賀大学[編 集]滋賀大学広報室 〒522-8522 滋賀県彦根市馬場一丁目 1-1
TEL.0749-27-7524
滋賀大学広報誌
伊藤忠商事株式会社 横澤
和貴
さん
同志社小学校
教諭 江間
記世
さん
特
集卒業生の
いま
Vol.48
滋賀大学のいま
―産学公連携―
Vol.48 2018.07
学生に対する修学、留学、研修等へのご支援のほか、滋賀大学を幅広く支えて頂く「3つのご支援」をお願いしています。(所得控除等の対象です。)皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
滋賀大学基金室(総務課内)〒522-8522 滋賀県彦根市馬場1-1-1TEL 0749-27-1005 FAX 0749-27-1129 E-mail [email protected]
1.修学へのご支援・経済的理由により修学が困難な学生に対する支援です。 ※個人からのご寄附の場合「税額控除」の対象になります。
2.学生への様々なご支援/グローバル・社会連携推進等へのご支援・滋賀大学の教育・研究・国際連携・社会連携を幅広く支えて頂きます。
3.データサイエンス教育研究推進のためのご支援・日本の将来を担う高度なデータ分析人材育成のため、多様な連携を通じ、日本最高水準の データサイエンス教育研究拠点を形成する本学活動に特化したご支援です。
滋賀大学へのご寄附のお願い
-3つのご支援̶
詳しくは寄附金ホームページをご覧ください。 http://www.shiga-u.ac.jp/kikin/
<お問い合わせ先>
滋賀大学オリジナルキャラクター「カモンちゃん」日本の開国を主導した井伊直弼公をモチーフにした
滋賀大学の公式キャラクター。
名前は直弼公の官位、掃部頭(かもんのかみ)に由来。
彦根と滋賀大学に”come on”という意味も掛けられている。
-
3
CONTENTSVol.48
3 学長からのメッセージ滋賀大学の産学公連携 ―社会と大学の新しい関係―
滋賀大学のいま ― 産学公連携 ―
滋賀大学長 位田 隆一
滋賀大学の産学公連携 ― 社会と大学の新しい関係 ―
滋賀大学長 位田 隆一い だ りゅう いち
学 長 か ら の メ ッ セ ー ジ
クラブ&サークル インフォメーション書道部男子バスケットボール部株式投資研究会アメリカンフットボール部
20大津キャンパス
大津キャンパス
彦根キャンパス
彦根キャンパス
表紙解説小幡篤次郎訳『英氏経済論』首里城とその周辺
23
留学体験記ニューヨーク留学体験記 経済学部企業経営学科 4回生 梶原 孝明
17
留学生紹介言語学習を通じて 経済学部特別聴講学生 ヴェガ ロペス エダリック マルティン アリ
17
学生支援課
学生支援 22
卒業生のいま江間 記世 さん (同志社小学校 教諭)横澤 和貴 さん (伊藤忠商事株式会社)
18
いま大学は「知の拠点」といわれ、社会との関係、とりわけ
大学と産業界や地域との連携が求められるようになった。
Society 5.0やIndustry 4.0といわれるように社会の構造が
変化しつつあるこの時代には、大学とそれを取り巻く多様
なステークホルダーとの連携は大学の責務でもある。
滋賀大学も、今や産業界や地方自治体、公的機関と広く
連携を進めている。これまで社会連携研究センターが、金融
関係や商工会議所を中心に連携協定を結んできたほか、
学び直し塾等の人材育成、企業の海外展開支援や公民連携
(PPP)フォーラム等の事業創出・地域創生支援、そして受託
研究やコンサルティング等を行ってきた。
そうした中で、一昨年のデータサイエンス教育研究セン
ター、昨年のデータサイエンス学部の設置により、産学公
連携の範囲は大きく拡大している。ビッグデータ時代に、
企業や自治体、公的機関は多様で大量のデータの中から
新しい価値の創造・発見が今後の社会発展の鍵を握るこ
とを理解しており、滋賀大学に期待するところが極めて大
きい。そのため、この2年間で、40を超す様々な分野の企
業・自治体・公的機関と連携協定を結んできた。その分野
も非常に多様で、地方銀行などの金融関係、保険業界、
データ関連企業、統計関連の公的機関、最適な製造過程
を模索する製造業界等、広範であって、データサイエンス
学部の存在意義は絶大である。
他方で、経済学部や教育学部も連携を広めつつある。教
育学部は特に県や市の教育委員会との関係を緊密に保ち、
滋賀県の教員養成の重責を担ってきたが、第3期中期目標
期間には滋賀県内での採用率を30%まで引き上げるべく
努めている。経済学部も、一昨年は彦根仏壇事業協同組合
との協定に至ったほか、地域連携教育推進室を中心に学生
にも地域との連携の重要性を理解させるよう努めている。
もう一つ、新しい活動として滋賀大学文化事業 Shiga U
Arte もあげておきたい。これは多くの企業の協賛を得て、
滋賀大学の持つ文化分野の人的物的資源を社会に還元す
る新しい事業である。去る3月末には、ノーベル賞詩人イェ
イツの書いた狂言と音楽とのコラボをびわ湖ホールで披露
し、満員の会場を感動させた。
このように、滋賀大学は社会との関係を密にしつつ、きら
きら輝く姿を示しつつある。教職員のみでなく、学生諸君も
同じクルーとして、新しい可能性を切り開いていこう。
特集4
在学生のいま「“先生”として学校へ」「社会人経験を活かした教育実習」「子どもたちの“楽しい!!”が聞けるならいくらでも…」「All Englishでの外国語活動の挑戦」「データサイエンス学部に入学したきっかけ」「データサイエンス学部で1年を過ごして」「人生が変わった43日間の航海」「自分への挑戦と成長~Ship for World Youth Leaders~」「世界に羽ばたく第一歩」「多彩な挑戦!私のキャンパスライフ」
12
3
CONTENTSVol.48
3 学長からのメッセージ滋賀大学の産学公連携 ―社会と大学の新しい関係―
滋賀大学のいま ― 産学公連携 ―
滋賀大学長 位田 隆一
滋賀大学の産学公連携 ― 社会と大学の新しい関係 ―
滋賀大学長 位田 隆一い だ りゅう いち
学 長 か ら の メ ッ セ ー ジ
クラブ&サークル インフォメーション書道部男子バスケットボール部株式投資研究会アメリカンフットボール部
20大津キャンパス
大津キャンパス
彦根キャンパス
彦根キャンパス
表紙解説小幡篤次郎訳『英氏経済論』首里城とその周辺
23
留学体験記ニューヨーク留学体験記 経済学部企業経営学科 4回生 梶原 孝明
17
留学生紹介言語学習を通じて 経済学部特別聴講学生 ヴェガ ロペス エダリック マルティン アリ
17
学生支援課
学生支援 22
卒業生のいま江間 記世 さん (同志社小学校 教諭)横澤 和貴 さん (伊藤忠商事株式会社)
18
いま大学は「知の拠点」といわれ、社会との関係、とりわけ
大学と産業界や地域との連携が求められるようになった。
Society 5.0やIndustry 4.0といわれるように社会の構造が
変化しつつあるこの時代には、大学とそれを取り巻く多様
なステークホルダーとの連携は大学の責務でもある。
滋賀大学も、今や産業界や地方自治体、公的機関と広く
連携を進めている。これまで社会連携研究センターが、金融
関係や商工会議所を中心に連携協定を結んできたほか、
学び直し塾等の人材育成、企業の海外展開支援や公民連携
(PPP)フォーラム等の事業創出・地域創生支援、そして受託
研究やコンサルティング等を行ってきた。
そうした中で、一昨年のデータサイエンス教育研究セン
ター、昨年のデータサイエンス学部の設置により、産学公
連携の範囲は大きく拡大している。ビッグデータ時代に、
企業や自治体、公的機関は多様で大量のデータの中から
新しい価値の創造・発見が今後の社会発展の鍵を握るこ
とを理解しており、滋賀大学に期待するところが極めて大
きい。そのため、この2年間で、40を超す様々な分野の企
業・自治体・公的機関と連携協定を結んできた。その分野
も非常に多様で、地方銀行などの金融関係、保険業界、
データ関連企業、統計関連の公的機関、最適な製造過程
を模索する製造業界等、広範であって、データサイエンス
学部の存在意義は絶大である。
他方で、経済学部や教育学部も連携を広めつつある。教
育学部は特に県や市の教育委員会との関係を緊密に保ち、
滋賀県の教員養成の重責を担ってきたが、第3期中期目標
期間には滋賀県内での採用率を30%まで引き上げるべく
努めている。経済学部も、一昨年は彦根仏壇事業協同組合
との協定に至ったほか、地域連携教育推進室を中心に学生
にも地域との連携の重要性を理解させるよう努めている。
もう一つ、新しい活動として滋賀大学文化事業 Shiga U
Arte もあげておきたい。これは多くの企業の協賛を得て、
滋賀大学の持つ文化分野の人的物的資源を社会に還元す
る新しい事業である。去る3月末には、ノーベル賞詩人イェ
イツの書いた狂言と音楽とのコラボをびわ湖ホールで披露
し、満員の会場を感動させた。
このように、滋賀大学は社会との関係を密にしつつ、きら
きら輝く姿を示しつつある。教職員のみでなく、学生諸君も
同じクルーとして、新しい可能性を切り開いていこう。
特集4
在学生のいま「“先生”として学校へ」「社会人経験を活かした教育実習」「子どもたちの“楽しい!!”が聞けるならいくらでも…」「All Englishでの外国語活動の挑戦」「データサイエンス学部に入学したきっかけ」「データサイエンス学部で1年を過ごして」「人生が変わった43日間の航海」「自分への挑戦と成長~Ship for World Youth Leaders~」「世界に羽ばたく第一歩」「多彩な挑戦!私のキャンパスライフ」
12
-
滋賀県の小中学生の学力は、全国学力・学習状況調査におい
て、残念ながら全国平均を下回ると報告されています。この課題
に取り組むため、本学部と滋賀県教育委員会は平成26年度に学
ぶ力向上専門委員会を立ち上げました。まずは学力・学習状況
調査の結果を分析し、県下の児童・生徒の強みと弱みを検討しま
した。さらにその結果を踏まえて、児童・生徒の学力向上に向け
た教材づくりや授業案作成を、市町教育委員会や教育学部附属
学校を交えて行っています。同様に、地元大津市とも学力充実専
門部会を設置し、市のおおつ学力充実チームと連携して、学校や
教員への支援・助言を実施しています。これらの活動を通じて、
本学部は地域の学校・教員の教える力の育成と、子どもたちの学
ぶ力の向上に寄与しています。
また、滋賀県教育委員会と緊密に連携しつつ、平成29年4月に
教職大学院(教育学研究科高度教職実践専攻)を設置しました。
ここでは、学校マネジメント力の向上に焦点をあてた学校経営力
開発コースと、授業力・学級経営力等を含む実践力の向上に焦点
をあてた教育実践力開発コースにおいて、新たな教育実践を創
成し地域の公立学校においてそれをリードできるスクール・リー
ダーと、必要な知識・技能を絶え間なく刷新しつつ教職生活全体
を通じて学び続けることのできる教員の育成を行っています。
いじめ問題は、今日の我が国全体における喫緊の教育課題
の1つです。本学部は滋賀県教育委員会と協働し、平成26年度
に「いじめ・不登校専門委員会」を立ち上げ、定期的に情報交換
を重ねつつ、いじめ・不登校問題の解決に向けた実践的な研究
と啓蒙活動に取り組んできました。
その一環として研究フォーラムを協同開催し、いじめ・不登校
問題に関する最新の学術的知見の提供や意見交換を行いまし
た。第1回(平成27年度)は、『イギリスにおける学校でのいじ
めの理解と対策』について開催しました。イギリスのシェフィー
ルド・ハラム大学講師のマーク・ヒートン氏が「イギリスにおけ
る学校での『いじめ』の理解と対策」と題する講演を、滋賀県教
育委員会の梅本剛雄氏が「滋賀県のいじめの状況と課題」の講
演をされ、その後両氏を交えた意見交換を行いました。第2回
(平成28年度)は『日本における予防教育について』と題し、国
内の研究者・医師・スクールカウンセラー合計4名を講師に招
いて、いじめ予防の具体的方策を紹介し合い、その有効性につ
いて議論を行いました。そして第3回(平成29年度)は『教育に
おけるマインドフルネスの導入』をめぐり、ケビン・ホーキンス、
エイミー・バーク夫妻に、いま世界的に注目されているマイン
ドフルネスを教育現場で活用するヒントについてご講演いた
だきました。いずれも滋賀県・市町の教育委員会、学校関係者、
卒業生など多
くの参加者が
あり、いじめ・
不登校対策に
ついて学ぶ機
会を広く関係
者に提供する
ことができま
した。
今日の公立小中学校の通常学級において、発達障害や学習障
害を有する子どもたちが6.5%程度いるという報告があります。こ
うした子どもたちは、学習の遅れや対人関係の困難さなどを抱え
ており、さまざまな支援を必要とすると同時に、それが原因と
なって不登校に至らないよう、安心感が持てる居場所作りが大切
です。本学部は、子どもたちへの個別指導や保護者への教育相
談を行っているNPO法人SKCキッズカレッジと、平成29年6月に
連携協定を結びました。そして、こうした子どもたちを対象にSKC
キッズカレッジが行う相談活動や、教育学部の院生・学生に対す
る研修活動に関して、連携した活動を開始しました。また、子育て
のさまざまな悩みや不安を保護者が語り合うサロンも学内施設
で定期的に開催され、本学部に関係する障害児教育や臨床心理
学の専門家がアドバイスを行っています。この活動は新聞でも報
道され(2017年2月21日朝日新聞)、大きな反響を呼びました。
本学部の教員は、それぞれの専門性を活かし、企業等との共同
研究や受託研究を積極的に行っています。例えば平成28年度に
は、日本無線株式会社「睡眠環境と睡眠状態の関係」(大平雅子准
教授)、地方独立行政法人京都市産業技術研究所「無機材料の構
造解析と高機能化」(徳田陽明准教授)、国立研究開発法人科学技
術振興機構「多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学
要因分析」(加納圭准教授)、守山市「守山市子どもの体力向上プ
ロジェクト」(奥田援史教授)、国立大学法人福島大学「教育行政に
おける放射線リスク管理体制」(藤岡達也教授)などがありました。
また附属小学校では、総務省「若年層に対するプログラミング
教育の普及推進」事業や財務省「財政教育プログラム」を実施し
4
滋 賀 大 学滋 賀 大 学 い まい まのの
教育学部
5
特集
て、国の教育政策の推進に貢献しました。この財政教育プログラ
ムは、財務省と国立大学附属学校等との連携による事業です。こ
れまでは中学校や小学校高学年で行われてきましたが、今回は
全国国立大学附属学校PTA連合会にも協力していただき、全
国で初めて小学校2年生において生活科学習の一環として実施
されました。財務省ならびに文部科学省関係者や全国の附属学
校園の関係者、大学教員、地域の教育関係者、および附属学校園
PTA関係者など60名近い参加者の前で、アクティブ・ラーニング、
ICT機器活用、学部人材活用を含む新しい総合学習の在り方を
提案し、高い評価をいただきました。
滋賀大学教育学部は、地域密接型を目指すという大学方針の
もと、これまでも滋賀県教育委員会等との連携により、地域の教
員養成の中核的役割を担うとともに、教育・研究や社会貢献活動
等を通じて、我が国の教育の発展・向上に寄与することを目指し
てきました。これからも積極的に産学公連携を推進し、さまざま
な地域課題の解決に専門的知見を活かして貢献できる学部で
あり続けたいと思います。
―産学公連携―
学力向上への取組
支援を要する子どもたちへの取組
地域に必要とされる学部を目指して
共同研究や受託研究
教職大学院開設記念講演会
いじめ問題への取組
SKCキッズカレッジ相談室
大平准教授の実験の様子
財政教育プログラム
さまざまな地域課題の解決に専門的知見を活かして貢献する
教育学部教授 渡部 雅之
いじめ・不登校研究フォーラム(第3回)
滋賀県の小中学生の学力は、全国学力・学習状況調査におい
て、残念ながら全国平均を下回ると報告されています。この課題
に取り組むため、本学部と滋賀県教育委員会は平成26年度に学
ぶ力向上専門委員会を立ち上げました。まずは学力・学習状況
調査の結果を分析し、県下の児童・生徒の強みと弱みを検討しま
した。さらにその結果を踏まえて、児童・生徒の学力向上に向け
た教材づくりや授業案作成を、市町教育委員会や教育学部附属
学校を交えて行っています。同様に、地元大津市とも学力充実専
門部会を設置し、市のおおつ学力充実チームと連携して、学校や
教員への支援・助言を実施しています。これらの活動を通じて、
本学部は地域の学校・教員の教える力の育成と、子どもたちの学
ぶ力の向上に寄与しています。
また、滋賀県教育委員会と緊密に連携しつつ、平成29年4月に
教職大学院(教育学研究科高度教職実践専攻)を設置しました。
ここでは、学校マネジメント力の向上に焦点をあてた学校経営力
開発コースと、授業力・学級経営力等を含む実践力の向上に焦点
をあてた教育実践力開発コースにおいて、新たな教育実践を創
成し地域の公立学校においてそれをリードできるスクール・リー
ダーと、必要な知識・技能を絶え間なく刷新しつつ教職生活全体
を通じて学び続けることのできる教員の育成を行っています。
いじめ問題は、今日の我が国全体における喫緊の教育課題
の1つです。本学部は滋賀県教育委員会と協働し、平成26年度
に「いじめ・不登校専門委員会」を立ち上げ、定期的に情報交換
を重ねつつ、いじめ・不登校問題の解決に向けた実践的な研究
と啓蒙活動に取り組んできました。
その一環として研究フォーラムを協同開催し、いじめ・不登校
問題に関する最新の学術的知見の提供や意見交換を行いまし
た。第1回(平成27年度)は、『イギリスにおける学校でのいじ
めの理解と対策』について開催しました。イギリスのシェフィー
ルド・ハラム大学講師のマーク・ヒートン氏が「イギリスにおけ
る学校での『いじめ』の理解と対策」と題する講演を、滋賀県教
育委員会の梅本剛雄氏が「滋賀県のいじめの状況と課題」の講
演をされ、その後両氏を交えた意見交換を行いました。第2回
(平成28年度)は『日本における予防教育について』と題し、国
内の研究者・医師・スクールカウンセラー合計4名を講師に招
いて、いじめ予防の具体的方策を紹介し合い、その有効性につ
いて議論を行いました。そして第3回(平成29年度)は『教育に
おけるマインドフルネスの導入』をめぐり、ケビン・ホーキンス、
エイミー・バーク夫妻に、いま世界的に注目されているマイン
ドフルネスを教育現場で活用するヒントについてご講演いた
だきました。いずれも滋賀県・市町の教育委員会、学校関係者、
卒業生など多
くの参加者が
あり、いじめ・
不登校対策に
ついて学ぶ機
会を広く関係
者に提供する
ことができま
した。
今日の公立小中学校の通常学級において、発達障害や学習障
害を有する子どもたちが6.5%程度いるという報告があります。こ
うした子どもたちは、学習の遅れや対人関係の困難さなどを抱え
ており、さまざまな支援を必要とすると同時に、それが原因と
なって不登校に至らないよう、安心感が持てる居場所作りが大切
です。本学部は、子どもたちへの個別指導や保護者への教育相
談を行っているNPO法人SKCキッズカレッジと、平成29年6月に
連携協定を結びました。そして、こうした子どもたちを対象にSKC
キッズカレッジが行う相談活動や、教育学部の院生・学生に対す
る研修活動に関して、連携した活動を開始しました。また、子育て
のさまざまな悩みや不安を保護者が語り合うサロンも学内施設
で定期的に開催され、本学部に関係する障害児教育や臨床心理
学の専門家がアドバイスを行っています。この活動は新聞でも報
道され(2017年2月21日朝日新聞)、大きな反響を呼びました。
本学部の教員は、それぞれの専門性を活かし、企業等との共同
研究や受託研究を積極的に行っています。例えば平成28年度に
は、日本無線株式会社「睡眠環境と睡眠状態の関係」(大平雅子准
教授)、地方独立行政法人京都市産業技術研究所「無機材料の構
造解析と高機能化」(徳田陽明准教授)、国立研究開発法人科学技
術振興機構「多様なイノベーションを支える女子生徒数物系進学
要因分析」(加納圭准教授)、守山市「守山市子どもの体力向上プ
ロジェクト」(奥田援史教授)、国立大学法人福島大学「教育行政に
おける放射線リスク管理体制」(藤岡達也教授)などがありました。
また附属小学校では、総務省「若年層に対するプログラミング
教育の普及推進」事業や財務省「財政教育プログラム」を実施し
4
滋 賀 大 学滋 賀 大 学 い まい まのの
教育学部
5
特集
て、国の教育政策の推進に貢献しました。この財政教育プログラ
ムは、財務省と国立大学附属学校等との連携による事業です。こ
れまでは中学校や小学校高学年で行われてきましたが、今回は
全国国立大学附属学校PTA連合会にも協力していただき、全
国で初めて小学校2年生において生活科学習の一環として実施
されました。財務省ならびに文部科学省関係者や全国の附属学
校園の関係者、大学教員、地域の教育関係者、および附属学校園
PTA関係者など60名近い参加者の前で、アクティブ・ラーニング、
ICT機器活用、学部人材活用を含む新しい総合学習の在り方を
提案し、高い評価をいただきました。
滋賀大学教育学部は、地域密接型を目指すという大学方針の
もと、これまでも滋賀県教育委員会等との連携により、地域の教
員養成の中核的役割を担うとともに、教育・研究や社会貢献活動
等を通じて、我が国の教育の発展・向上に寄与することを目指し
てきました。これからも積極的に産学公連携を推進し、さまざま
な地域課題の解決に専門的知見を活かして貢献できる学部で
あり続けたいと思います。
―産学公連携―
学力向上への取組
支援を要する子どもたちへの取組
地域に必要とされる学部を目指して
共同研究や受託研究
教職大学院開設記念講演会
いじめ問題への取組
SKCキッズカレッジ相談室
大平准教授の実験の様子
財政教育プログラム
さまざまな地域課題の解決に専門的知見を活かして貢献する
教育学部教授 渡部 雅之
いじめ・不登校研究フォーラム(第3回)
-
6 7
特集|滋賀大学のいま ―産学公連携―
経 済 学 部
PwCあらた有限責任監査法人(以下、PwCあらた監査法人)と
本学データサイエンス学部、経済学部は、2016年11月から「デー
タサイエンスの会計分野への応用」に関する共同研究を行って
きました。基本的には、東京の丸の内や大手町のPwCあらた監
査法人のオフィスや本学で隔月の研究会を開催しています。
PwCあらた監査法人からは、PwCあらた基礎研究所の山口峰男
所長や同品質管理本部の木村章展ディレクター、専門研究員で
明治大学専任准教授の姚俊先生が出席され、毎回興味深い資
料や論文の紹介、問題提起の報告をしていただいています。
本学からは、データサイエンス学部の竹村彰通学部長と齋藤
邦彦副学部長、岩山幸治助教、そして経済学部から私が参加して
います。
なお、PwCあらた有限責任監査法人では、未来の会計・監査に
は「ピープル」と「イノベーション」が命であるとの考えのもと、設
立以来10年以上にわたりPwCあらた基礎研究所の活動が続け
られています。滋賀大学とのデータサイエンス分野における幅広
い連携は、既存の学問領域を超えた「知のダイバーシティ」を目
指すものと位置づけられています。
研究会での毎回研究報告とディスカッションを重ね、昨年9月
には、大手町のPwCあらた監査法人で、「データサイエンスと次
世代における会計監査」のテーマで共同セミナーを開催しまし
た。当日は主に民間企業のAI推進室や監査室、研究所などから
100名の出席者を確保して講演と質疑応答を行いました。当日の
公演の主なテーマは表1にまとめてありますが、2018年1月発
行のPwC’s View Vol.12では講演者全員の講演要旨が紹介され
ています。
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/pwcs-view/2017012.html
2017年末からは、本学の研究リソースを提供するために、
PwCあらた監査法人所属の公認会計士の先生方を対象とし
た研修を実施しています。本年2月15日には大手町での研修
を筆者が担当し、70名の規模で「不正会計検出のための統計
モデルの展開と可能性」のテーマで実施しました。冒頭で、山
口峰男所長からのイントロダクションの解説をいただいた
後、約80分のプレゼンテーション形式でのレクチャーと、その
後40分間の質疑応答を行いました。研修内容は表2にまとめ
てあります。
主な研修内容は、1990年から現在に及ぶまでの利益操作
や不正会計の検出に関する代表的な学術論文の研究成果を
要約し、その特徴を解説するというものでした。1980年代から
1990年代にかけて、筆者自身が多変量解析を応用して会計数
値の有用性に関する研究を行ってきたこともあり、線形判別
関数や多変量回帰分析、非線形回帰分析の手法を用いた主
要な研究手法の説明に重点をおきました。とくに1990年代以
降の利益調整の研究は、最新の研究課題とも言える不正会計
の検出モデルの研究にも応用されており、利益操作を検出す
る指標など、とくに重要な指標の説明に活用しました。さらに、
ここ10年の間に登場したAIアルゴリズムを応用して不正を検
出する研究の主要な論文を取り上げ、検出力や今後の可能性
についても解説しました。また、すでに本学の講義科目である
財務諸表分析論Ⅱの2017年度の課題として筆者が作成した
演習問題なども紹介し、本学での教育面での応用例について
紹介しました。
参加者がまさに実務の最前線で監査を経験されているプ
ロフェッショナルな先生方であり、質疑応答とディスカッション
PwCあらた有限責任監査法人での公認会計士向け研修~不正会計検出のための統計モデルの展開と可能性~
経済学部 会計情報学科長・経営系学系長 宮西 賢次
のセクションでは、興味深い質問やコメントを多数いただくこ
とができました。「Aのアルゴリズムを使って分析した場合に、
クライアントにどのように説明できるのか」、「実務を担当して
いる者からしても、統計モデルやAIによる分析結果は直感的
に納得がいく」、「不正会計と不適切会計の違いはなにか」な
ど、興味深く示唆に富むご質問やコメントを多数いただき、筆
者自身にとっても大変勉強になる有意義な経験となりました。
今回の研修内容を踏まえ、2018年5月発行のPwC’s View
Vol.14では、データアナリティクスの最前線の連載企画の一つ
として、「テクノロジー駆動型不正会計検出システムの構築に
向けて」というテーマで不正会計検出モデルの研究の到達点
と課題を筆者が紹介していますので、以下のサイトをご参照く
ださい。
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/pwcs-view/201805.html
今回ご紹介させていただいた研修以外にも、本学データ
サイエンス学部のスタッフによるAI関係の研修も提供されて
います。そして、研修を通じて実感しましたが、不正会計の検
出は、多様な分野のアカデミックな研究者と監査実務の最前
線を担うプロフェッショナルが共同で研究すべき格好のテー
マとなっています。監査法人やクライアント企業のみならず、
学術的な面でも価値を生み出すため、今後さらに独自な手
法の開発に向けた共同研究と研修に力を注ぎたいと思って
います。
末筆ですが、このような研修提供の機会を与えていただき
ましたPwCあらた監査法人、とりわけ山口峰男所長に心から
感謝いたします。
2017年1月 大手町のオフィスでの第1回目の研究会
夏の共同セミナーでの講演の様子
研修会で熱弁をふるう筆者
PwCあらた有限責任監査法人と本学との共同研究
共同セミナー「データサイエンスと次世代における会計監査」
不正会計検出モデルについての監査法人での研修
表1 共同セミナーの講演テーマと講演者リスト
講演テーマ 講演者
次世代におけるデータサイエンス研究 竹村 彰通
データサイエンスと次世代における会計監査~共同研究に期待するもの~
山口 峰男
不正会計検出の統計モデルの展開と可能性 宮西 賢次
日本におけるAI研究のいま~会計監査へのAI応用を考える~
齋藤 邦彦
表2 研修内容のリスト
ケロッグビジネススクールでの経験:エンロン事件
利益調整の証拠
利益調整の研究
倒産予測モデルの研究
不正会計検出モデルの展開
AI手法を用いた不正検出モデル
可能性と展望
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
6 7
特集|滋賀大学のいま ―産学公連携―
経 済 学 部
PwCあらた有限責任監査法人(以下、PwCあらた監査法人)と
本学データサイエンス学部、経済学部は、2016年11月から「デー
タサイエンスの会計分野への応用」に関する共同研究を行って
きました。基本的には、東京の丸の内や大手町のPwCあらた監
査法人のオフィスや本学で隔月の研究会を開催しています。
PwCあらた監査法人からは、PwCあらた基礎研究所の山口峰男
所長や同品質管理本部の木村章展ディレクター、専門研究員で
明治大学専任准教授の姚俊先生が出席され、毎回興味深い資
料や論文の紹介、問題提起の報告をしていただいています。
本学からは、データサイエンス学部の竹村彰通学部長と齋藤
邦彦副学部長、岩山幸治助教、そして経済学部から私が参加して
います。
なお、PwCあらた有限責任監査法人では、未来の会計・監査に
は「ピープル」と「イノベーション」が命であるとの考えのもと、設
立以来10年以上にわたりPwCあらた基礎研究所の活動が続け
られています。滋賀大学とのデータサイエンス分野における幅広
い連携は、既存の学問領域を超えた「知のダイバーシティ」を目
指すものと位置づけられています。
研究会での毎回研究報告とディスカッションを重ね、昨年9月
には、大手町のPwCあらた監査法人で、「データサイエンスと次
世代における会計監査」のテーマで共同セミナーを開催しまし
た。当日は主に民間企業のAI推進室や監査室、研究所などから
100名の出席者を確保して講演と質疑応答を行いました。当日の
公演の主なテーマは表1にまとめてありますが、2018年1月発
行のPwC’s View Vol.12では講演者全員の講演要旨が紹介され
ています。
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/pwcs-view/2017012.html
2017年末からは、本学の研究リソースを提供するために、
PwCあらた監査法人所属の公認会計士の先生方を対象とし
た研修を実施しています。本年2月15日には大手町での研修
を筆者が担当し、70名の規模で「不正会計検出のための統計
モデルの展開と可能性」のテーマで実施しました。冒頭で、山
口峰男所長からのイントロダクションの解説をいただいた
後、約80分のプレゼンテーション形式でのレクチャーと、その
後40分間の質疑応答を行いました。研修内容は表2にまとめ
てあります。
主な研修内容は、1990年から現在に及ぶまでの利益操作
や不正会計の検出に関する代表的な学術論文の研究成果を
要約し、その特徴を解説するというものでした。1980年代から
1990年代にかけて、筆者自身が多変量解析を応用して会計数
値の有用性に関する研究を行ってきたこともあり、線形判別
関数や多変量回帰分析、非線形回帰分析の手法を用いた主
要な研究手法の説明に重点をおきました。とくに1990年代以
降の利益調整の研究は、最新の研究課題とも言える不正会計
の検出モデルの研究にも応用されており、利益操作を検出す
る指標など、とくに重要な指標の説明に活用しました。さらに、
ここ10年の間に登場したAIアルゴリズムを応用して不正を検
出する研究の主要な論文を取り上げ、検出力や今後の可能性
についても解説しました。また、すでに本学の講義科目である
財務諸表分析論Ⅱの2017年度の課題として筆者が作成した
演習問題なども紹介し、本学での教育面での応用例について
紹介しました。
参加者がまさに実務の最前線で監査を経験されているプ
ロフェッショナルな先生方であり、質疑応答とディスカッション
PwCあらた有限責任監査法人での公認会計士向け研修~不正会計検出のための統計モデルの展開と可能性~
経済学部 会計情報学科長・経営系学系長 宮西 賢次
のセクションでは、興味深い質問やコメントを多数いただくこ
とができました。「Aのアルゴリズムを使って分析した場合に、
クライアントにどのように説明できるのか」、「実務を担当して
いる者からしても、統計モデルやAIによる分析結果は直感的
に納得がいく」、「不正会計と不適切会計の違いはなにか」な
ど、興味深く示唆に富むご質問やコメントを多数いただき、筆
者自身にとっても大変勉強になる有意義な経験となりました。
今回の研修内容を踏まえ、2018年5月発行のPwC’s View
Vol.14では、データアナリティクスの最前線の連載企画の一つ
として、「テクノロジー駆動型不正会計検出システムの構築に
向けて」というテーマで不正会計検出モデルの研究の到達点
と課題を筆者が紹介していますので、以下のサイトをご参照く
ださい。
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/pwcs-view/201805.html
今回ご紹介させていただいた研修以外にも、本学データ
サイエンス学部のスタッフによるAI関係の研修も提供されて
います。そして、研修を通じて実感しましたが、不正会計の検
出は、多様な分野のアカデミックな研究者と監査実務の最前
線を担うプロフェッショナルが共同で研究すべき格好のテー
マとなっています。監査法人やクライアント企業のみならず、
学術的な面でも価値を生み出すため、今後さらに独自な手
法の開発に向けた共同研究と研修に力を注ぎたいと思って
います。
末筆ですが、このような研修提供の機会を与えていただき
ましたPwCあらた監査法人、とりわけ山口峰男所長に心から
感謝いたします。
2017年1月 大手町のオフィスでの第1回目の研究会
夏の共同セミナーでの講演の様子
研修会で熱弁をふるう筆者
PwCあらた有限責任監査法人と本学との共同研究
共同セミナー「データサイエンスと次世代における会計監査」
不正会計検出モデルについての監査法人での研修
表1 共同セミナーの講演テーマと講演者リスト
講演テーマ 講演者
次世代におけるデータサイエンス研究 竹村 彰通
データサイエンスと次世代における会計監査~共同研究に期待するもの~
山口 峰男
不正会計検出の統計モデルの展開と可能性 宮西 賢次
日本におけるAI研究のいま~会計監査へのAI応用を考える~
齋藤 邦彦
表2 研修内容のリスト
ケロッグビジネススクールでの経験:エンロン事件
利益調整の証拠
利益調整の研究
倒産予測モデルの研究
不正会計検出モデルの展開
AI手法を用いた不正検出モデル
可能性と展望
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅶ
-
日本セーフティソサイエティ研究センター開設
滋賀大学は、2017年3月のあいおいニッセイ同和損害保険株式
会社(以下、あいおいニッセイ同和損保)との産学連携協定の締結
を受け、同年4月1日付けで彦根キャンパスのデータサイエンス棟
内にビッグデータ専門研究拠点JSSRC(日本セーフティソサイエ
ティ研究センター)を設置しました。このセンターは双方からの研究
員によって構成され、同社が保有する自動車の事故データや運転
挙動データなどのビッグデータの分析を通じて、「実データによる
実践的な研究を通じたデータサイエンティストの育成教育」「損保
ビッグデータの高度な分析技術・有効活用の研究」「自動車に関連
し安全な社会構築に寄与する調査研究」について活動しています。
<JSSRCの活動内容紹介>
■ 1. ビッグデータを用いた研究活動
各メンバーが研究テーマを持ち、ビッグデータを活用した
主に安心・安全に関する研究活動を進めています。また約半
月ごとのメンバー間の打ち合わせを行い、各メンバーの研究
テーマの進捗と進め方について密な議論を実施しています。
あいおいニッセイ同和損保からのメンバーは、このような研
究活動を通じて、データサイエンスの実践力を身につけていく
ことを目指しています。
センターでの最初の研究成果発表を2018年度中に行うこと
を目標にしています。
■ 2. 機械学習に関する輪講形式の勉強会
あいおいニッセイ同和損保からのメンバーのデータサイエ
ンス力向上のために、滋賀大からのメンバーの指導・解説の
下、約半年にわたる機械学習の参考書を用いた輪講形式の勉
強・演習を実施しました。
■ 3. クラウドを活用した共同分析環境構築
自動車の運転挙動データなどの大量なデータの分析を行う
ためのインフラとして、Amazon Web Service上に、十分なセ
キュリティ対策・個人情報保護対策を施したビッグデータ分析
環境を構築しました。
■ 4. 各種広報活動
本研究センターの活動内容を広く理解してもらうべく、クリ
エイティブ経済誌「ビジネスタイムライン」での、3回連載によ
る研究センターの活動の紹介や、日経ユニバーシティ・コン
ソーシアム「データサイエンスが拓く未来フォーラム2018」で
のパネルセッション参加などを実施しました。
トヨタ自動車のビッグデータ分析人材育成プログラムを共同実施
滋賀大学とトヨタ自動車株式会社は、トヨタグループのエンジ
ニアをビッグデータ分析の指導者(中核人材)候補として育成す
るための研修プログラムを実施しました。
トヨタ自動車では、製造現場等で取得される幅広い領域の
ビッグデータの活用手法の研究を通じて、ビッグデータ分析に秀
でた人材を育成することを目的に、トヨタ自動車を含むグループ
各社から選抜された41名のエンジニアを対象に2017年5月から
翌3月までの間、研修プログラム「機械学習実践道場」を同社関
連施設で開催しました。
滋賀大学データサイエンス教育研究センターは、この研修プ
ログラムに使用する教材開発の支援および学習補助を行うとと
もに、データサイエンス技術の社会実装の推進を行いました。
研修プログラムでは、午前の部は教授・准教授による講義およ
び分析手法のプログラミング演習を実施し、午後の部では受講
者がそれぞれに持ち寄った課題に対するデータ分析手法等の
指導を行いました。データ分析指導を担当する助教と受講者の
間で活発な議論が行われ、受講者はデータサイエンスに関する
より実践的な知識の習得ができました。
SMBC信託銀行との「金融業におけるデータサイエンスの応用」に
関する共同研究
滋賀大学とSMBC信託銀行は2017年12月に金融業における
データサイエンスの応用に関する共同研究を開始しました。
2018年3月末までの共同研究期間中、遠隔会議を含めて頻繁に
研究会を行い、SMBC信託銀行が保有する各種データに必要な
匿名化・集計化措置をほどこしたデータを共同で分析し、SMBC
銀行のビジネス課題の解決のために有用な知見を得ました。こ
の研究は2018年度も、新たな形で継続する予定です。
滋賀県民の健康寿命延伸に向けた健康データ活用事業
平均寿命や健康寿命について関心が高まる中、滋賀大学デー
タサイエンス教育研究センターは2017年8月25日~2018年3月
31日の間、滋賀県衛生科学センターと滋賀県の長寿要因につい
8
企業や地域への伝道師としてのデータサイエンス学部
広がる企業との連携
9
データサイエンス学部
特集|滋賀大学のいま ―産学公連携―
て共同研究を行いました。78ページにわたる報告書は2018年
5月29日に滋賀県より公表されました。
本研究では、県及び市町における、健康・医療・介護に関する
データや経済状況・ボランティア参加率等の社会環境因子に関
わるデータを一体的に分析・活用し、全国における県の位置づけ
や強み・弱みを把握し、今後の健康政策立案に有用な根拠を示
すことを目指すものです。官学連携による健康データの活用事
業は、データに基づく行政を推奨する国の方針と合致しており、
本取組が滋賀県に有用なものとなるだけではなく、全国の自治
体のベンチマーク事例になることも期待されます。
滋賀県立膳所高等学校野球班データ班との取組み
滋賀大学データサイエンス教育研究センターは滋賀県立膳所
高等学校(以下、膳所高校)野球班にデータ分析の効率化につい
て指導を行いました。膳所高校野球班データ班はこれまで、手作
業によって打者が打った打球の種類や落下地点などのデータの
分析(集計や可視化、解釈など)を実施し、守備シフトの選択など
に活用してきました。これに対し、作業時間の短縮を目指し、統計
解析ソフトRを活用したデータの数値化やグラフの自動作成につ
いて指導を行い、デー
タの解釈についての作
業時間の確保が可能と
なりました。そして第90
回記念選抜高等学校
野球大会では、膳所高
校が実施した極端な守
備シフトは効果を生
み、多くのメディアや世
間から注目を集める結
果となりました。
データサイエンス学部広報委員会
地域や自治体と歩むデータサイエンス学部
メンバーによる打ち合わせの様子
講義の様子
三井住友フィナンシャルグループ及びSMBC信託銀行と連携協力協定を締結
滋賀県との共同研究を開始
平成30年3月19日 京都新聞掲載
日本セーフティソサイエティ研究センター開設
滋賀大学は、2017年3月のあいおいニッセイ同和損害保険株式
会社(以下、あいおいニッセイ同和損保)との産学連携協定の締結
を受け、同年4月1日付けで彦根キャンパスのデータサイエンス棟
内にビッグデータ専門研究拠点JSSRC(日本セーフティソサイエ
ティ研究センター)を設置しました。このセンターは双方からの研究
員によって構成され、同社が保有する自動車の事故データや運転
挙動データなどのビッグデータの分析を通じて、「実データによる
実践的な研究を通じたデータサイエンティストの育成教育」「損保
ビッグデータの高度な分析技術・有効活用の研究」「自動車に関連
し安全な社会構築に寄与する調査研究」について活動しています。
<JSSRCの活動内容紹介>
■ 1. ビッグデータを用いた研究活動
各メンバーが研究テーマを持ち、ビッグデータを活用した
主に安心・安全に関する研究活動を進めています。また約半
月ごとのメンバー間の打ち合わせを行い、各メンバーの研究
テーマの進捗と進め方について密な議論を実施しています。
あいおいニッセイ同和損保からのメンバーは、このような研
究活動を通じて、データサイエンスの実践力を身につけていく
ことを目指しています。
センターでの最初の研究成果発表を2018年度中に行うこと
を目標にしています。
■ 2. 機械学習に関する輪講形式の勉強会
あいおいニッセイ同和損保からのメンバーのデータサイエ
ンス力向上のために、滋賀大からのメンバーの指導・解説の
下、約半年にわたる機械学習の参考書を用いた輪講形式の勉
強・演習を実施しました。
■ 3. クラウドを活用した共同分析環境構築
自動車の運転挙動データなどの大量なデータの分析を行う
ためのインフラとして、Amazon Web Service上に、十分なセ
キュリティ対策・個人情報保護対策を施したビッグデータ分析
環境を構築しました。
■ 4. 各種広報活動
本研究センターの活動内容を広く理解してもらうべく、クリ
エイティブ経済誌「ビジネスタイムライン」での、3回連載によ
る研究センターの活動の紹介や、日経ユニバーシティ・コン
ソーシアム「データサイエンスが拓く未来フォーラム2018」で
のパネルセッション参加などを実施しました。
トヨタ自動車のビッグデータ分析人材育成プログラムを共同実施
滋賀大学とトヨタ自動車株式会社は、トヨタグループのエンジ
ニアをビッグデータ分析の指導者(中核人材)候補として育成す
るための研修プログラムを実施しました。
トヨタ自動車では、製造現場等で取得される幅広い領域の
ビッグデータの活用手法の研究を通じて、ビッグデータ分析に秀
でた人材を育成することを目的に、トヨタ自動車を含むグループ
各社から選抜された41名のエンジニアを対象に2017年5月から
翌3月までの間、研修プログラム「機械学習実践道場」を同社関
連施設で開催しました。
滋賀大学データサイエンス教育研究センターは、この研修プ
ログラムに使用する教材開発の支援および学習補助を行うとと
もに、データサイエンス技術の社会実装の推進を行いました。
研修プログラムでは、午前の部は教授・准教授による講義およ
び分析手法のプログラミング演習を実施し、午後の部では受講
者がそれぞれに持ち寄った課題に対するデータ分析手法等の
指導を行いました。データ分析指導を担当する助教と受講者の
間で活発な議論が行われ、受講者はデータサイエンスに関する
より実践的な知識の習得ができました。
SMBC信託銀行との「金融業におけるデータサイエンスの応用」に
関する共同研究
滋賀大学とSMBC信託銀行は2017年12月に金融業における
データサイエンスの応用に関する共同研究を開始しました。
2018年3月末までの共同研究期間中、遠隔会議を含めて頻繁に
研究会を行い、SMBC信託銀行が保有する各種データに必要な
匿名化・集計化措置をほどこしたデータを共同で分析し、SMBC
銀行のビジネス課題の解決のために有用な知見を得ました。こ
の研究は2018年度も、新たな形で継続する予定です。
滋賀県民の健康寿命延伸に向けた健康データ活用事業
平均寿命や健康寿命について関心が高まる中、滋賀大学デー
タサイエンス教育研究センターは2017年8月25日~2018年3月
31日の間、滋賀県衛生科学センターと滋賀県の長寿要因につい
8
企業や地域への伝道師としてのデータサイエンス学部
広がる企業との連携
9
データサイエンス学部
特集|滋賀大学のいま ―産学公連携―
て共同研究を行いました。78ページにわたる報告書は2018年
5月29日に滋賀県より公表されました。
本研究では、県及び市町における、健康・医療・介護に関する
データや経済状況・ボランティア参加率等の社会環境因子に関
わるデータを一体的に分析・活用し、全国における県の位置づけ
や強み・弱みを把握し、今後の健康政策立案に有用な根拠を示
すことを目指すものです。官学連携による健康データの活用事
業は、データに基づく行政を推奨する国の方針と合致しており、
本取組が滋賀県に有用なものとなるだけではなく、全国の自治
体のベンチマーク事例になることも期待されます。
滋賀県立膳所高等学校野球班データ班との取組み
滋賀大学データサイエンス教育研究センターは滋賀県立膳所
高等学校(以下、膳所高校)野球班にデータ分析の効率化につい
て指導を行いました。膳所高校野球班データ班はこれまで、手作
業によって打者が打った打球の種類や落下地点などのデータの
分析(集計や可視化、解釈など)を実施し、守備シフトの選択など
に活用してきました。これに対し、作業時間の短縮を目指し、統計
解析ソフトRを活用したデータの数値化やグラフの自動作成につ
いて指導を行い、デー
タの解釈についての作
業時間の確保が可能と
なりました。そして第90
回記念選抜高等学校
野球大会では、膳所高
校が実施した極端な守
備シフトは効果を生
み、多くのメディアや世
間から注目を集める結
果となりました。
データサイエンス学部広報委員会
地域や自治体と歩むデータサイエンス学部
メンバーによる打ち合わせの様子
講義の様子
三井住友フィナンシャルグループ及びSMBC信託銀行と連携協力協定を締結
滋賀県との共同研究を開始
平成30年3月19日 京都新聞掲載
-
10 11
特集|滋賀大学のいま ―産学公連携―
学 術 国 際 課
社会連携研究センターが実施する海外展開支援事業は、国内
消費が減少する中で、売上減少分を海外でカバー出来ないかと
考えて取組みをはじめたのが、「小さなコスト、小さなリスクで海
外に販路を開拓する」ビジネスモデル事業です。当該事業では、
日本の食品の最大の輸出地で、関税がほとんどなく、輸送日数も
短い香港をターゲットに取組んでいます。
2015年から開催している「滋賀大学 香港食品商談・視察ミッ
ション」は、大学が海外で商談会を開催するという他の大学にな
いプログラムであり、現地でのマーケティングを行い、本学経済
学部留学生等による商品説明書の翻訳や商談会での通訳等の
協力も得て、3年間で滋賀、京都の企業19社が参加しています。
2017年は7社が、香港SOGO、香港イオン、商社、レストラン
チェーンなど13社と商談を行い、4社が香港、ベトナムへの輸出が
決まるなど、小規模な商談会ですが成果に結びついてきました。
2016年には「マーケティング・カフェ in 香港」を開催、滋賀県
の3社が香港城市大学専上學院の学生60名と、滋賀の食品を試
食しながら香港での商品の提案方法を検討するワークショップ
も行いました。
他にも、香港
向けの商品開発
の取組みを2つ
行っています。
1つは、2015
年に実施した地
元滋賀県の藤居
本家(酒蔵)との
香港向け日本酒
の共同開発で
す。これは、本学
経済学部留学生
が中国、台湾、香
港の訪日観光客に
日本酒の調査を行
い、そのデータをも
とに留学生たちも
仕込みに参加して、
香港向け日本酒を
共同開発しました。
同社はこの商品を
きっかけに、他の商
品も香港に輸出し
ています。
もう1つは、2017
年に実施した香港
向け食器の開発で
す。これには、香港
理工大学デザイン
スクールの学生7名が、香港に好まれるデザインを考え、京都の2
社が製作を担当しました。言葉や考え方の違いは有りましたが、
2018年3月に京都で作品の発表が行われました。
この2つは、日本人向けに作られた商品を、そのまま香港に
持って行って販売するのではなく、香港人をターゲットに考えた
製品作りです。
アジアなどのビザ緩和もあり、2016年には2,404万人の外国
人観光客が日本を訪れ、特に、中国からの観光客は前年度
27.7%増の637万人となり、観光、宿泊、購買行動が多様化し、な
かなか実態が掴みきれていませんでした。
社会連携研究センターでは、2015年より髙島屋京都店とイン
バウンドに関して情報交換を行っていましたが、中国人個人観
光客を対象として、京都市内での観光や消費行動などを分析し
髙島屋京都店での購買に繋がる情報を提供して欲しいという依
頼から、「京都地区及び京都高島屋におけるインバウンドマーケ
ティング対策」をテーマに共同研究契約を締結し、経済学部3教
員の各ゼミ生による調査研究を行うことになりました。
2016年度は5グループ34名、2017年度は4グループ23名が半
年にわたる調査を行い、京都高島屋に対して調査報告及び提案
を行いました。2018年度は24名が、さらに具体的な調査を行い、
インバウンド対策の提案を行う予定です。
インバウンドは、減少する国内消費に代わるものとして注目さ
れているテーマであり、その最前線にある京都高島屋と共同研
究を行えることは、学生にとっても貴重な研究経験になると考え
ています。
社会連携研究センターでは、産学公連携の強化を図るため
に、今年度から新たに「社会連携コーディネーター」を導入し
ます。
これは、対外的な連携のきっかけを創出・増加させるため、社
会連携コーディネーターの活動を一つの起点として、各学部・全
学センターなどにつなげ、波及効果をもたらす体制に移行する
ことで、各部局の同様の事業と合わせて、大学全体の社会貢献へ
の取組み姿勢を明らかにすることを目的としています。
本年4月、主任社会連携コーディネーターとして、前パナソニッ
ク(株)グローバル生活研究所長の上田雄三郎氏を迎えました。
今後、産業支援機関、商工団体、地域金融機関などの協力を得な
がら、様々な企業等との連携を広げてまいりたいと存じます。
滋賀大学は今、データサイエンス学部の新設を契機に企業と
の連携を一層拡大し、新たなムーブメントやビジネスを生み出
すハブとして機能してまいります。
環境総合研究センターでは、地域経済の活性化や人口減少対
策などの社会経済的な課題だけでなく、地域の環境保全や災害
リスクの軽減など、多面的な視点で持続可能なまちづくりに向け
た分析・政策提言を目指して、野洲市との域学連携を通じた共同
研究を2017年度より実施しています。
この連携プロジェクトでは、本学2学部2センター(経済学部、
データサイエンス学部、社会連携研究センター、環境総合研究セ
ンター)の教員により、本学が重点領域として位置付ける3分野(環
境、リスク、データサイエンス)や、まちづくりに対する研究を推進
しており、2017年度には一般市民を対象とした共同アンケートを
実施し、データサイエンスの手法を活用した分析を取り入れ、居
住満足度や地域の課題など幅広い観点で分析を進めています。
また、2018年3月には野洲市との共催で、公開シンポジウム
「滋賀県発の持続可能なまちづくりと地方創生における域学連
携」を開催しました。このシンポジウムでの議論を契機に、「滋賀
県ならではの持続可能なまちづくり」の姿を目指し、その具体化
に向けた研究を進める方針です。
「滋賀県ならで
はの持続可能な
まちづくり」の発
信に向けて、今後
も野洲市との連
携を強化して研
究活動を推進し
ていきます。
マーケティング・カフェin香港(香港城市大学専上學院)
2017年11月の商談会(香港日本人倶楽部)
連携・協力に関する協定書調印式(左:山仲善彰市長、右:位田学長)
食器デザインのミーティング(香港理工大学)
日本酒仕込み(藤居本家)
本学ゼミ生による調査報告及び提案の様子
産学公・地域連携の最前線― 社会連携研究センター/環境総合研究センター ―
海外展開支援事業
京都高島屋との共同研究
社会連携コーディネーターを導入
野洲市との域学連携について
社会連携コーディネーターのイメージ
【お問合せ先】滋賀大学 学術国際課E-mail:[email protected]
企業・自治体
データサイエンス学部
経済学部
教育学部
各研究センターなど
滋 賀 大 学
社会連携コーディネーター
産業支援機関商工団体地域金融機関
連携産学公連携の強化・深化
協力
10 11
特集|滋賀大学のいま ―産学公連携―
学 術 国 際 課
社会連携研究センターが実施する海外展開支援事業は、国内
消費が減少する中で、売上減少分を海外でカバー出来ないかと
考えて取組みをはじめたのが、「小さなコスト、小さなリスクで海
外に販路を開拓する」ビジネスモデル事業です。当該事業では、
日本の食品の最大の輸出地で、関税がほとんどなく、輸送日数も
短い香港をターゲットに取組んでいます。
2015年から開催している「滋賀大学 香港食品商談・視察ミッ
ション」は、大学が海外で商談会を開催するという他の大学にな
いプログラムであり、現地でのマーケティングを行い、本学経済
学部留学生等による商品説明書の翻訳や商談会での通訳等の
協力も得て、3年間で滋賀、京都の企業19社が参加しています。
2017年は7社が、香港SOGO、香港イオン、商社、レストラン
チェーンなど13社と商談を行い、4社が香港、ベトナムへの輸出が
決まるなど、小規模な商談会ですが成果に結びついてきました。
2016年には「マーケティング・カフェ in 香港」を開催、滋賀県
の3社が香港城市大学専上學院の学生60名と、滋賀の食品を試
食しながら香港での商品の提案方法を検討するワークショップ
も行いました。
他にも、香港
向けの商品開発
の取組みを2つ
行っています。
1つは、2015
年に実施した地
元滋賀県の藤居
本家(酒蔵)との
香港向け日本酒
の共同開発で
す。これは、本学
経済学部留学生
が中国、台湾、香
港の訪日観光客に
日本酒の調査を行
い、そのデータをも
とに留学生たちも
仕込みに参加して、
香港向け日本酒を
共同開発しました。
同社はこの商品を
きっかけに、他の商
品も香港に輸出し
ています。
もう1つは、2017
年に実施した香港
向け食器の開発で
す。これには、香港
理工大学デザイン
スクールの学生7名が、香港に好まれるデザインを考え、京都の2
社が製作を担当しました。言葉や考え方の違いは有りましたが、
2018年3月に京都で作品の発表が行われました。
この2つは、日本人向けに作られた商品を、そのまま香港に
持って行って販売するのではなく、香港人をターゲットに考えた
製品作りです。
アジアなどのビザ緩和もあり、2016年には2,404万人の外国
人観光客が日本を訪れ、特に、中国からの観光客は前年度
27.7%増の637万人となり、観光、宿泊、購買行動が多様化し、な
かなか実態が掴みきれていませんでした。
社会連携研究センターでは、2015年より髙島屋京都店とイン
バウンドに関して情報交換を行っていましたが、中国人個人観
光客を対象として、京都市内での観光や消費行動などを分析し
髙島屋京都店での購買に繋がる情報を提供して欲しいという依
頼から、「京都地区及び京都高島屋におけるインバウンドマーケ
ティング対策」をテーマに共同研究契約を締結し、経済学部3教
員の各ゼミ生による調査研究を行うことになりました。
2016年度は5グループ34名、2017年度は4グループ23名が半
年にわたる調査を行い、京都高島屋に対して調査報告及び提案
を行いました。2018年度は24名が、さらに具体的な調査を行い、
インバウンド対策の提案を行う予定です。
インバウンドは、減少する国内消費に代わるものとして注目さ
れているテーマであり、その最前線にある京都高島屋と共同研
究を行えることは、学生にとっても貴重な研究経験になると考え
ています。
社会連携研究センターでは、産学公連携の強化を図るため
に、今年度から新たに「社会連携コーディネーター」を導入し
ます。
これは、対外的な連携のきっかけを創出・増加させるため、社
会連携コーディネーターの活動を一つの起点として、各学部・全
学センターなどにつなげ、波及効果をもたらす体制に移行する
ことで、各部局の同様の事業と合わせて、大学全体の社会貢献へ
の取組み姿勢を明らかにすることを目的としています。
本年4月、主任社会連携コーディネーターとして、前パナソニッ
ク(株)グローバル生活研究所長の上田雄三郎氏を迎えました。
今後、産業支援機関、商工団体、地域金融機関などの協力を得な
がら、様々な企業等との連携を広げてまいりたいと存じます。
滋賀大学は今、データサイエンス学部の新設を契機に企業と
の連携を一層拡大し、新たなムーブメントやビジネスを生み出
すハブとして機能してまいります。
環境総合研究センターでは、地域経済の活性化や人口減少対
策などの社会経済的な課題だけでなく、地域の環境保全や災害
リスクの軽減など、多面的な視点で持続可能なまちづくりに向け
た分析・政策提言を目指して、野洲市との域学連携を通じた共同
研究を2017年度より実施しています。
この連携プロジェクトでは、本学2学部2センター(経済学部、
データサイエンス学部、社会連携研究センター、環境総合研究セ
ンター)の教員により、本学が重点領域として位置付ける3分野(環
境、リスク、データサイエンス)や、まちづくりに対する研究を推進
しており、2017年度には一般市民を対象とした共同アンケートを
実施し、データサイエンスの手法を活用した分析を取り入れ、居
住満足度や地域の課題など幅広い観点で分析を進めています。
また、2018年3月には野洲市との共催で、公開シンポジウム
「滋賀県発の持続可能なまちづくりと地方創生における域学連
携」を開催しました。このシンポジウムでの議論を契機に、「滋賀
県ならではの持続可能なまちづくり」の姿を目指し、その具体化
に向けた研究を進める方針です。
「滋賀県ならで
はの持続可能な
まちづくり」の発
信に向けて、今後
も野洲市との連
携を強化して研
究活動を推進し
ていきます。
マーケティング・カフェin香港(香港城市大学専上學院)
2017年11月の商談会(香港日本人倶楽部)
連携・協力に関する協定書調印式(左:山仲善彰市長、右:位田学長)
食器デザインのミーティング(香港理工大学)
日本酒仕込み(藤居本家)
本学ゼミ生による調査報告及び提案の様子
産学公・地域連携の最前線― 社会連携研究センター/環境総合研究センター ―
海外展開支援事業
京都高島屋との共同研究
社会連携コーディネーターを導入
野洲市との域学連携について
社会連携コーディネーターのイメージ
【お問合せ先】滋賀大学 学術国際課E-mail:[email protected]
企業・自治体
データサイエンス学部
経済学部
教育学部
各研究センターなど
滋 賀 大 学
社会連携コーディネーター
産業支援機関商工団体地域金融機関
連携産学公連携の強化・深化
協力
-
在 生 の い ま学
12 13
「子どもたちの“楽しい!!”が 聞けるならいくらでも…」
私は、教育実習において道徳の授業をしました。道徳の授業では、物語がたくさん掲載されている副読本といわれるものを一般的には使うのですが、どうしても、私は子どもたちにこれを学ばせたいとは思えなかったのです。与えられた子どもたちの貴重な勉強時間で、どれだけ普段の生活に活かし、成長させるきっかけを作るか…ということを考えた時、私は、自分自身の経験を作文にしたものを教材として使い学ばせたい!と思いました。内容としては、高校時代の「全国大会出場」の夢の実現のために部活動を頑張り抜いたというようなものです。それらを基
に、努力することの大切さや、仲間の大切さ、自分の夢は何かを考え、今できることは何かを考えるきっかけづくりをすることができました。この
授業づくりを通して、自分自身が感銘を受けたものや、どうしても子どもたちに学んでほしいものを、工夫して授業を作っていくことがどれだけ大切なのかを学びました。このように、一生懸命作り上げた授業は、自然と子どもたちの大きな学びとなります。
40人近くの生身の子どもたち相手に授業をするということは、授業時間の何倍もの準備の時間が必要になり、実際に苦労することも多いです。しかし、教官や大学の教授、両親、仲間、時には子どもたちからの、たくさんの支えがあったからこそ、4週間の教育実習をやり遂げることができ、自分自身の大きな成長につなげることができました。
教育学部学校教育教員養成課程初等教科専攻家庭専修太田 雅子
長浜北星高校(滋賀県)
楽しく、記憶に残るような授業!?
周りの支えてくれる人の大切さ
「All Englishでの外国語活動の挑戦」
「英語を話せるってかっこいい。自分も話せるようになってみたい。」子どもたちに英語でコミュニケーションをとることを好きになってほしいと思い、外国語活動に挑戦しました。そんな中で、私がAll Englishに取り組んだ理由は、教師がスピーカーとしての見本となることが重要だと考えたからです。教師が一生懸命英語を話す姿を見ること
で、自分も同じようになれるかもしれないと希望を持つことができると考えました。授業では指示やゲームの説明も、ジェスチャーを使ったり顔の表情を変えたりすることで、子どもたちにもわかるような工夫をし
ました。英語で説明することで子どもたちは懸命に聞こうとしている姿が見られ、取り組んでよかったと感じています。
外国語活動の授業における一番のねらいは、子どもたちがお互いに英語を使ってコミュニケーションをとることでした。しかし、会話の活動では子どもたちはすぐに飽きてしまっていました。その反省から、子どもたちが話したいと思う仕掛けを考えなければいけないと感じ、オリジナルのゲームを作成しました。カードを集めるミッションのためには英語で会話をしなければいけないというルールを決めました。ここで気を付けたことは、苦手な子どもでも参加できるように、ペアでカードを集めに行くように工夫したことです。その結果子どもたちが楽しそうに会話をしている姿を見ることができました。
教育学部学校教育教員養成課程教育文化専攻田中 美帆
石山高校(滋賀県)
All Englishを心がけた研究授業
「“先生”として学校へ」
教育実習期間の一日は、ほとんどの時間を子どもと共に過ごします。子どもは、場面によっていろいろな顔を見せてくれます。遊んでいるときの楽しそうな表情、給食の時間のリラックスした表情、授業中の真剣な表情など、実際に一日を共に過ごすことで初めて見えてくる姿がたくさんありました。また、子ども同士でトラブルが起こることもありましたが、そこでの対応は実際に子どもと長い時間一緒にいて、初めて経験できる貴重なものだと感じました。
教育実習では、一つの授業を作るのに多くの時間を使うことができます。他の実習生と相談したり、学校の先生方に教えていただいたりして、どのような授業がよいのか試行錯誤しながら授業を考えました。授業づくりで私が特に意識したのは、“何よりも子どもたちが楽しめる授業にする”ことです。児童にとって、実習生の授業は珍しく、どんな授業なのかととても楽しみにしてくれています。準備をする時間が多くあるからこそ、子どもたちが楽しみながら学べる授業になればと入念に計画を立て、授業に臨みました。授業が終わった後、子どもたちが「先生の授業おもしろかった!」「めっちゃわかりやすかった!」と言ってくれたときは、学校の先生のやりがいを感じられた幸せな瞬間でした。
教育学部学校教育教員養成課程初等理科専攻近藤 美里
米原高校(滋賀県)
子どもと一緒に遊んで・食べて・勉強する
「社会人経験を活かした教育実習」 私は、滋賀大学に入学する前は、海上自衛隊に6年間勤務していました。そこで、社会人の経験をどのように活かして教育実習を過ごしたのか書いていこうと思います。 はじめに、計画を立てて行動することの大切さについて書いていきます。教育実習のみならず、仕事はその場その場でこなしていくことはできません。体力があるうちは、なんとかできるかもしれません。しかし、そのなんとかしていることが体には大
きな負担となり、体力だけでなく心までも疲れてしまいます。そこで、計画を立てる必要が出てきます。 計画は、指導案を点検してもらう日、授
業見学の時間、部活に参加する日などわかる範囲で作成し、実習に慣れてきた頃にもう一度立て直してください。自分の中で計画は何度も見直し、改善をしていくと計画を立てるのがうまくなっていきます。 次に、質問をたくさんすることです。質問をする理由として、相手とのコミュニケーションを取るためです。私の考えですが、コミュニケーション能力といわれるものは、質問できる能力であると考えています。質問をすることで相手のことを知ることができます。質問で得た情報を元に話を繋げていくといつのまにかコミュニケーションが取れるようになっています。ちなみに私が質問していた内容は、仕事のことやプライベートのことなど、ジャンルは様々でした。 最後に、教育実習を楽しんでください。
教育学部学校教育教員養成課程社会科専攻杉野 亨
諫早東高校(長崎県)
子どもたちが楽しめる授業
理想の活動を実現するためのオリジナルゲームの考案
こんな月、見たことある?
授業風景
実験して…どんな形に見えた?
返却プリントには大きな花丸を・・・
関ケ原の戦いをもっと知るために!
授業風景 コレクトゲーム
授業で使ったフラッシュカード言葉のリピート練習(外国語)
教育学部在 生 の い ま学
12 13
「子どもたちの“楽しい!!”が 聞けるならいくらでも…」
私は、教育実習において道徳の授業をしました。道徳の授業では、物語がたくさん掲載されている副読本といわれるものを一般的には使うのですが、どうしても、私は子どもたちにこれを学ばせたいとは思えなかったのです。与えられた子どもたちの貴重な勉強時間で、どれだけ普段の生活に活かし、成長させるきっかけを作るか…ということを考えた時、私は、自分自身の経験を作文にしたものを教材として使い学ばせたい!と思いました。内容としては、高校時代の「全国大会出場」の夢の実現のために部活動を頑張り抜いたというようなものです。それらを基
に、努力することの大切さや、仲間の大切さ、自分の夢は何かを考え、今できることは何かを考えるきっかけづくりをすることができました。この
授業づくりを通して、自分自身が感銘を受けたものや、どうしても子どもたちに学んでほしいものを、工夫して授業を作っていくことがどれだけ大切なのかを学びました。このように、一生懸命作り上げた授業は、自然と子どもたちの大きな学びとなります。
40人近くの生身の子どもたち相手に授業をするということは、授業時間の何倍もの準備の時間が必要になり、実際に苦労することも多いです。しかし、教官や大学の教授、両親、仲間、時には子どもたちからの、たくさんの支えがあったからこそ、4週間の教育実習をやり遂げることができ、自分自身の大きな成長につなげることができました。