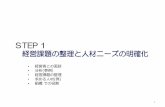経営発達支援計画の概要 - Minister of Economy ... ·...
Transcript of 経営発達支援計画の概要 - Minister of Economy ... ·...
経営発達支援計画の概要
実施者名
(法人番号) 諫早商工会議所(法人番号 1310005004518)
実施期間 平成30年4月1日~平成35年3月31日
目標
1.販路開拓・販売促進支援事業を強化し、「支援先小規模事業者の増収増益」を目指す。
2.創業者の掘り起こしを強化して「年間創業者人数 40人」を目標とする。創業後は丁寧
な伴走支援を行い「創業者の経営存続」を図る。
事業内容
需要を見据えた事業計画の策定・実施に関する伴走支援と需要開拓支援事業の実践によ
り管内小規模事業者の成長発展及び持続的発展に寄与していく。
Ⅰ.経営発達支援事業の内容
1.地域の経済動向調査に関すること
・独自調査(売上・所得前年度比較調査、中小企業景況調査、初任給調査、賃金実
態調査、地元プロサッカーチーム試合観客数調査)
2.経営状況の分析に関すること
・経営分析対象者の掘り起し
・経営分析に関する勉強会の開催 ・経営分析(定性分析、定量分析)結果を「見える形」で提供する 3.事業計画策定支援に関すること
・事業計画策定の意識啓発活動、専門家個別相談会の開催及び事業計画策定完了ま
での伴走支援
・創業時に必要な情報の提供、創業セミナー・個別相談会の開催及び創業事業計画
策定完了までの伴走支援
4.事業計画策定後の実施支援に関すること
・事業計画策定後、創業計画策定後の個別モニタリング、フォローアップ支援
・事業計画に関するPDCAサイクル構築支援
5.需要動向調査に関すること
・需要動向調査データの収集・提供・活用
・消費者ニーズアンケート調査および個別相談会 6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること
・広域型小規模事業者に対する展示会等参加支援等販路開拓支援事業
・地域型小規模事業者に対する顧客管理・集客の強化を図る販売促進支援 ・ITを利用した販売促進支援
・製造業ビジネスマッチング会、創業者交流会の開催
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組
1.第2期諫早市中心市街地活性化基本計画(H26.04~H31.03)の事業の推進 ・「諫早市栄町東西街区第一種市街地再開発事業」の中心市街地への経済波及効果を
高めるために、商業床についてのコンセプトの策定、テナントミックスの検討・
誘致、管理運営方法の具体的計画の策定を支援 2.第3期諫早市中心市街地活性化基本計画(H31.04~H36.03)の事業計画策定の提
言及び事業実施の推進 ・平成29年度に発足した当所まちづくり推進協議会において検討を進めている商
工業者視点による具体的かつ実効性の高い事業を取りまとめ、第3期基本計画へ
の反映を行政に要望 ・平成34年の新幹線西九州ルート開業に向けて第3期基本計画に取り上げられる
べき、諫早駅に隣接する永昌東町商店街及び周辺地区の商業・サービス業・飲食
業等の活性化策の取りまとめを支援
連絡先
諫早商工会議所 中小企業振興部
〒854-0016 長崎県諫早市高城町5番10号
電話番号:0957-22-3323 FAX番号:0957-24-3638
メールアドレス:[email protected]
- 1 -
(別表1)
経営発達支援計画
経営発達支援事業の目標
1.地域の概況
(1)地域の特性
・諫早市は、長崎県の中央に位置し、長崎・島原・西彼杵の各半島の連結部、交通の要衝として
大きな役割を果たしている。また、東は有明海、西は大村湾、南は橘湾と三方が海に面し、北
は多良山系を望み、四季折々の豊かな自然に恵まれている。市の中心部を流れる本明川は市街
地を通って有明海に注ぎ、下流の諫早平野は県下最大の穀倉地帯になっており、肥沃な丘陵地
帯は野菜やみかんの特産地になっている。 ・長崎市と雲仙市や大村市、佐賀県多良町方面を結ぶ国道34号や57号、207号、251号
の広域幹線道路網が形成され、長崎自動車道の諫早インターチェンジもあり利便性に優れてい
る。
(2)現状・課題
①人口
国勢調査の結果によると、諫早商工会議所管内人口は昭和50年から増加を続けてきていたが、
平成18年 1月の 96,660人をピークとして減少に転じ、以後人口減少と少子高齢化が緩やかに
進行している。今後も人口減少が見込まれているが、諫早市が「諫早市長期人口ビジョン」に
示した将来都市像実現のための様々な事業推進による人口減少の抑制効果を期待し、平成37
年における諫早商工会議所管内人口は 91,800 人程度と想定している。
諫早商工会議
所管内人口 96,660 人
(H18/1) → 94,484 人
(H23/1) → 93,874 人
(H29/1) → 91,800 人
(H37/3 推計) (諫早市人口統計)
②産業
産業別の構成比では、第1次産業が6.6%、第2次産業22.2%、第3次産業が67.2%と
なっており、第1次産業と第2次産業の就業者割合がそれぞれ減少している一方で、第3次産
業の就業割合が増加している。 ●管内商工業者数、小規模事業者数等の推移
管内商工業者数 4,057 人 (H18 年事業所統計) → 4,283 人
(H26 年経済センサス)
管内小規模事業者数 3,141 人 (H18 年事業所統計) → 3,297 人
(H26 年経済センサス)
製造品出荷額 248,287 百万円
(H24 年工業統計調査) → 278,130 百万円
(H26 年工業統計調査)
商品販売額 174,262 百万円 (H24 年商業統計調査) → 189,582 百万円
(H26 年商業統計調査)
飲食店数 410 件 (H24 年経済センサス) → 527 件
(H26 年経済センサス)
観光客数 1,553,263 人 (H24 年長崎県観光統計) → 1,869,071 人
(H26 年長崎県観光統計) ●建設業
当市の建設業は、九州新幹線西九州ルート関連工事、地域高規格道路整備工事等の大型公共工
事や住宅団地の造成による住宅着工戸数増加に支えられ、ここ数年好況であったが、技術者の
高齢化、人材の確保と育成面が課題となっている。
- 2 -
●製造業
県内有数の産業集積拠点である「諫早中核工業団地」を有し、平成26年の製造品出荷額は県
下第1位となっている。当団地を中心に電子機器、半導体、航空宇宙関連など先端技術企業の
進出が相次ぎ、従業者数、製造品出荷額等において大幅な伸びを示すなど県内の産業拠点とし
て発展している。また、平成21年に工場用地8.5haの分譲を開始した「諫早流通産業団
地」は既に完売し、平成26年から分譲している「西諫早産業団地」(分譲用地9.8ha)も
約7割の用地に企業の進出が決定している。現在、諫早市では、新たな雇用の創出を図るため、
平成33年の工事完成を目指して新産業団地の整備に着手している。
●商業・サービス業
諫早市の年間商品販売額は消費動向の沈滞化の影響などから平成9年をピークに減少し続けて
おり平成26年にやや持ち直したものの中心市街地における商業施設の空洞化の進行などか
ら、小売商業の活力・魅力が減少している傾向にあるために、緊急な対応が求められている。 特に郊外幹線道路沿いにパワーセンター、ホームセンター、専門店などが立地したこと、地域
中心市街地の大型店が撤退したことにより、高級品、耐久消費材などの購買客が隣接都市の大
型店や郊外店に流出するなど中心市街地の商店街は厳しい状況が続いている。しかしながら、
市役所周辺のアエル中央商店街とJR諫早駅前の永昌東町商店街では、それぞれの商業活性化
のための取組が進められており、その中で、アエル中央商店街では、「諫早市栄町東西街区第一
種市街地再開発事業」が平成30年度末の完成に向けて進んでいる。なお、特に管内で創業希
望者が最も多く新陳代謝が盛んな飲食業は、事前準備が不十分なままで開業するケースも散見
されるので、創業計画策定段階から創業後の伴走支援まで寄り添った支援が必要である。
●観光
石橋として初の国の重要文化財に指定された諫早公園の眼鏡橋、名水百選にも選ばれた轟峡な
どがあり、豊かな自然と歴史に裏打ちされた多くの名産品、名所を有する。観光客、宿泊客は
概ね横ばいで推移している一方、日帰り客は平成25年以降大幅に増加している。その要因と
して、地元プロサッカーチームJ2「V・ファーレン長崎」のホームスタジアム(トランスコ
スモススタジアム)があることや、諫早出身のオリンピック金メダリストである内村選手にち
なんだ内村記念アリーナなどスポーツ振興の施設が充実し、市内外からの利用が増加している
ことによるものである。
●小規模事業者全体の課題
次頁「売上所得前年度比較集計表」は、当所で税務支援を行っている約500名の小規模個人
事業者のうち、前年度との比較が可能であった企業のデータを示している。左側の集計表は、
当所の第1期経営発達支援計画で提示した平成24年と平成25年の比較であり、右側は、平
成27年と平成28年を比較した最新の集計表である。合計欄を比較すると「売上増加」の企
業の割合が微増しているにもかかわらず、「利益増加」の企業の割合が減少しているため、「増
収増益」の企業の割合が大きく減少している。したがって、「売上増加」はもちろん、「利益増
加」の企業数を増やすことが重要な課題となってきている。
- 3 -
2.経営発達支援事業の実績
(1)取組内容
・需要を見据えた事業計画に基づき経営を行う小規模事業者の増加を目指すために、経営分析等を
契機とした事業計画策定を支援するとともに、計画策定後も伴走型支援を行った。 ・小規模事業者を「広域需要指向型」と「地域需要指向型」とに分類し、「広域需要指向型」小規模
事業者には、展示会、商談会等への参加を促進させる事業を実施すると共に商品説明のためのチ
ラシ・パンフレットの内容やプレゼン手法等に関する個別指導を行うなど、訴求力の向上を図っ
た。「地域需要指向型」小規模事業者には、メディアに取り上げてもらうプレスリリースの仕方や
顧客関係性の強化、SNSによる集客力強化セミナーを開催することで、新たな需要の開拓に繋
げ増収増益を達成できるよう支援を行った。 ・創業希望者の掘り起こしを強化するとともに創業希望者との接触機会を増やし、創業に必要な心
構えや基礎知識の習得及び創業計画策定支援を行い、事業計画に基づいた創業を促進させた。ま
た、成長段階に応じて生じる様々な課題の解決や経営存続に向けての支援を行った結果、次頁の
とおり一定の成果が見られた。 (2)取組成果
①支援先小規模事業者の増収増益
上記「売上所得前年度比較集計表(H27 年・H28 年比較)」の数値と当所で事業計画書策定支
援を行った事業者の数値を比較すると、下記のとおり事業計画策定支援先の「売上増加割合」
は5.0ポイント、「利益増加割合」は12.3ポイント、「増収増益割合」は9.5ポイント
上回っている。
実施項目 支援対象
事業所数
2期間比較
可能 売上増加
利益増加
(経常利益) 増収増益
経営計画セミナー・個別面談
を契機とした事業計画作
成支援件数
(売上所得前年度比較表
<H27 年・H28 年比較>と
の対比)
90 58
26
44.8%
(+5.0%)
33
56.9%
(+12.3%)
21
36.2% (+9.5%)
- 4 -
②創業支援実績
創業支援では、創業相談人数、創業人数とも増加してきており、目標創業人数40名に対し、
34名(達成率85%)という実績で順調に増加しており、同時に5年間の経営存続率も84.
2%という非常に高い割合となった。 H20 年度 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度
創業相談人数 22 17 34 28 32 52 53 75 100
創業人数 17 14 25 19 21 31 23 25 34 5年存続人数 13 10 15 16 - - - - - 5 年 存 続 率
(%) 76.5 71.4 60.0 84.2 - - - - -
③事業評価委員会の評価・見直し結果
・事業評価委員会の外部有識者から、第1期の「経営発達支援事業の目標」に記載していた、『事
業計画策定後の伴走支援』について、経営者自らがPDCAサイクルを回せるような支援の手
法が確立していないという指摘があった。この点を踏まえ、事業計画の進捗状況の確認や評
価・改善に取り組む時期等を明確にするための支援ツール「PDCAチェックシート」を第2
期から導入する。共通の支援ツールを用いることは、当所が一貫性のある支援を行う上でも有
効であり、経営指導員等による経営支援会議の資料としても活用していく。
・第1期経営発達支援事業を実施していく中で、事業計画書に基づく経営を継続的に行うには、
事業計画の必要性、有用性に関して経営者の意識を更に高めていく必要性を感じている。した
がって、第2期では、事業計画に基づく経営に移行して経営の発達・改善を実現した具体的な
成功事例などを紹介する資料を作成して、巡回訪問や経営相談等の際に提供し、事業計画の策
定について積極的な提案を行うことで意識啓発を図っていく。
3.当地域の中長期的な小規模事業者に対する振興のあり方
・諫早市では『ひとが輝く創造都市・諫早』を将来都市像として、平成28年3月に今後10年間
の新しい街づくりのビジョンである「第2次諫早市総合計画」を策定し、将来都市像を実現する
ために「輝くひとづくり、活力あるしごとづくり、魅力あるまちづくり」の3つを目標として定
めている。この中の「活力あるしごとづくり」では、「個性と魅力あふれる商業の活性化、安定し
た雇用の創出と人材育成、新たな産業活力の創生」を基本政策に、商業基盤整備の促進、商店街
の魅力づくり、地域産業を支える人材の確保・育成、企業立地の促進、新産業団地の整備促進等
の施策が展開されている。 ・諫早商工会議所としては、人口減少や中心市街地の衰退などにより疲弊した地域活力を取り戻す
ために、経営環境が厳しくなっている地域小規模事業者への伴走型支援策として、経験や勘に頼
った従来の経営からの脱却並びに経営面の意識改革を図り、小規模事業者への支援を関係する支
援機関と連携して推進する。また、平成34年春の九州新幹線西九州ルート開通を見据えたJR
諫早駅周辺整備計画と商店街の取り組みとを連動させ、新幹線開業効果を高めることで、地域小
規模事業者のビジネスチャンス拡大に繋げていく。さらに、地方都市において人口減少・超高齢
化が急速に進む中、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的
に推進するコンパクトなまちづくりが求められており、また、多くの小規模事業者が中心市街地
を営業基盤としていることから、中心市街地活性化に取り組む必要がある。そこで、地域の多様
な機関で構成され、当所が中核を成し事務局を担う諫早市中心市街地活性化協議会において策定
した「諫早市中心市街地活性化基本計画」の推進を図っていく。
・諫早商工会議所では、豊かな地域社会の振興発展と管内商工業者の成長発展の支援を活動の両輪 として、時代の変化や環境の変化に“チャレンジ精神”をもって果敢に対応し、行政をはじめ地 域の各種団体や機関、商工業者との“連携”と“協働”により地域総合経済団体としての役割を 果たしていくことを基本理念とする。その基本理念に基づき小規模事業者に対する支援について は10年後のビジョンを『小規模事業者の経営の安定と持続的な発展、創業支援による事業所数
- 5 -
の維持・拡大と地域経済基盤の強化による新たな雇用の創出』と定め、以下の方針で取り組んで いく。 ①小規模事業者の声を代弁し行政施策等に反映させるための「意見集約活動」と「意見要望活動」
を推進して、小規模事業者のビジネスチャンス拡大を図る。 ②「経営改善普及事業で長年培ってきた小規模事業者支援のノウハウ」「地域に密着した顔の見え
る支援」「行政や各種支援機関との連携」という当所の強みを活かした「ワンストップ型の相談
窓口体制」を強化して、「きめ細やかな伴走型支援」を実施する。 ③経験や勘に頼った経営ではなく、小規模事業者自らが経営状況を計数的に把握する「計数管理
経営」への転換を促していく。 4.経営発達支援事業の目標及び目標達成に向けた方針
上述した地域の現状と課題、第1期経営発達支援事業の実績と評価・見直し結果、中長期的な小規
模事業者に対する振興のあり方を踏まえ、当所の第2期経営発達支援事業の目標を以下のとおり設
定する。目標は第1期と同じであるが、目標達成に向けた事業は改善策を盛り込み取り組んでいく。
●目標達成に向けた方針
①小規模事業者の成長発展・持続的発展に向け、「事業計画に基づく経営」を継続的に行えるよ
う、伴走型の継続支援を行い事業計画作成の支援と販売力強化事業を実施する。 ②地域内に多様な形態で存在する「地域資源」を活用した、新商品開発や販路開拓に取り組む小
規模事業者に対し、重点的な支援を推進する。 ③地域経済の活性化に必要不可欠な「創業」、新分野進出を行う「第二創業」、革新的な経営を行
う「経営革新」に取り組む事業者への支援を強化し、交流人口の拡大、雇用の創出等、地域経
済の牽引役となる小規模事業者を育成する。 ④長崎県、諫早市、地域金融機関、その他支援機関と十分連携しながら、国等の支援施策や中小
企業診断士等の専門家派遣制度を活用して、小規模事業者の経営支援体制を確立する。
目標①『支援先小規模事業者の増収増益』
目標②『年間創業人数40人の確保と創業者の経営存続』
- 6 -
経営発達支援事業の内容及び実施期間
(1)経営発達支援事業の実施期間 (平成30年4月1日~平成35年3月31日) (2)経営発達支援事業の内容
Ⅰ.経営発達支援事業の内容
1.地域の経済動向調査に関すること【指針③】
1)事業内容・活用方法
①売上・所得前年度比較調査(拡充実施)
毎年1回、確定申告期限後に当所税務支援先及び事業計画作成支援先などを対象に行っている「売
上・所得前年度比較」は、実際に業務で得た利益金額に近づけるために減価償却費を調査項目に
追加して450社を対象に実施する。また、売上・所得金額の推移を分析し、事業計画作成支援
などの経営支援が増収増益に結びついているかどうかを検証し、ホームページで公表するなど事
業計画策定の重要性を啓発するためのデータとして活用する。
②中小企業景況調査(拡充実施)
・中小機構が四半期ごとに公表している「中小企業景況調査」の結果と管内50社への景況調査
(年4回)の結果について比較を行ってきたが、調査対象の50社は小売業・サービス業が多
数を占めているため、調査対象数が少ない業種(製造業・建設業・卸売業)を数社追加し、さ
<第1期における取組と成果、課題>
・「売上所得前年度比較」は、税務支援先を中心に以前より実施していたが、事業計画作成支援先
を新たに比較対象として追加して調査を実施し、事業者の売上・所得の推移から支援効果の測定
に活用することができた。しかし、減価償却費を把握していなかったため所得金額の実態を捉え
にくいと事業評価委員会で指摘を受けた。 ・「中小企業景況調査」は、全国と諫早の調査結果を比較して、大まかな地域景況の特徴を把握し、
事業計画策定支援の際に活用することができた。但し、当調査は日本商工会議所からの委託業務
で調査対象の業種に偏りがあり、管内の景況データとしては不足があるため、調査対象数の少な
い業種を追加して調査をする必要がある。 ・以前より実施している「賃金実態調査」は、経営発達支援計画の策定、見直しに活用でき、調査
結果を調査協力事業所へ提供することで、各事業所で従業員の賃金額を決定する際の参考になっ
ている。 ・「商店街通行量調査」「新設住宅着工戸数」、「県内短観」について、事業者への提供は少なかった
が、当所の計画策定や方向性の見直しなどには活用できた。しかし、事業評価委員会では、支援
の現場に即した調査に絞り込んで実施すべきであり、調査実施項目は対象企業のニーズ、消費者
の購買行動の変化などにあわせて当初の目的から逸脱しない範囲で臨機応変に変えるべきとの
指摘を受けたため、従来通り調査事業は継続実施するが、当計画上では利用しないことにした。
<今回の申請における取組の方向性>
上記を踏まえ、以前から実施している調査・収集を行う項目のうち、地域の経済動向を事業計画
策定時やその他巡回・窓口支援に活用しやすいものはそのまま継続し、見直しが必要なものは改
善・拡充することで、より活用しやすいデータを収集するための調査を実施する。また、これら
のデータを事業計画策定時やその他巡回・窓口相談時に小規模事業者へ提供し、ホームページで
公表すると共に、地域の経済動向を反映した経営を促し、販路開拓や商品開発等へ活用する。
- 7 -
らに全体数も増やして調査を実施する。平成30年度は65社を対象に調査を実施し、対象を
毎年2社ずつ増加させ実施する。
・調査項目は、「売上額、資金繰り、仕入単価、採算、従業員、外部人材、業況、長・短期資金借
入難度、借入金利」等とする。
・業種別の前期比・前年同期比の集計結果を、全国・九州・諫早で比較することにより、諫早で
の傾向把握に活用する。
・日本政策金融公庫から四半期に一度発表されている「長崎県内中小企業動向調査結果(小企業
編)【DI値】」は、経営上の問題点が4項目(売上額、資金繰り、採算、業況)に絞られてお
り、景況調査と類似した内容となっているため、比較材料として使用する。
・調査は、年4回実施し、調査票を対象事業所に郵送し事業主に回答してもらい、返信(郵送ま
たはFAX)してもらう方法で実施する。未返信事業所には指導員が巡回し、聞き取りを実施
することで回収率を上げる。
・比較分析を行ったデータは、ホームページにて公表する。
③賃金実態調査、初任給調査(拡充実施)
・以前より実施していた「賃金実態調査(毎年1回12月に実施)」に、当所独自に調査している
「初任給調査(毎年1回6月に実施)」を加えて実施する。賃金実態調査は70社、初任給調査
は110社を対象に実施する。比較資料として毎年2月に公表されている「厚生労働省 賃金構
造基本統計調査」の結果を用い分析を行う。
・調査結果は、当所の計画策定や見直しの際に活用する。また、従業員を新たに雇用する場合に
小規模事業者へも提供する。さらに、ホームページで公表すると共に、小規模事業者の事業計
画策定支援に活用する。
④地元プロサッカーチームの試合観客数調査(新規)
・地元プロサッカーチームJ2「V・ファーレン長崎」ホームゲームにおいて、6月・9月・1
2月の年3回、1試合毎の観客数(公開されているデータ)の調査を実施する。
・年間パスポート購入者については年1回、V・ファーレン長崎よりデータの提供を受け、属性
(性別、年代別、住所等)の把握・分析を行う。
・現状では1試合あたり約 5,000 人の観客数が見込まれ、さらに、今後はJ1昇格の可能性があ
り、J1の著名なチームとのホームゲームでの対戦では、現在の2倍以上の集客が見込め、宣
伝効果もあると考えられるため、これらの調査結果をホームページで公表及び事業者へ直接提
供することで、スタジアム敷地内での臨時飲食出店を促すと共に事業計画策定の際に活用する。
2)実施時期と目標
・各調査の実施時期と実施頻度については前述の通り。 ・独自調査の継続実施及び支援に有効なデータの収集を行い、事業計画策定支援時やその他窓口相
談時などに提供することにより事業者の増収増益を目指す。
<年度ごとの目標値>
調査内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度
①売上所得前年度比較調査回数
公表回数
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
②中小企業景況調査回数
公表回数 ※日本政策金融公庫データとの比較含む
4回
4回
4回
4回
4回
4回
4回
4回
4回
4回
③賃金実態調査回数
公表回数
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
③初任給調査回数
公表回数
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
1回
④地元プロサッカーチームの
試合観客数及び属性調査回数
公表回数
4回
4回
4回
4回
4回
4回
4回
4回
4回
4回
- 8 -
2.経営状況の分析に関すること【指針①】
1)事業内容・活用方法
①経営分析対象者の掘り起し(継続)
・小規模事業者が事業を持続的発展させるためには、事業の方向性を明確化し、事業主が描く自
社の将来像に向けた目標を定め、それを実現させるための具体的な行動を計画し、実行する一
連の流れを描く事業計画書の策定が重要になる。この事業計画を策定するためには自社の経営
状況の分析を行い、財務状況や内部・外部の強み・弱みなどの現状を深く知り、把握すること
が必須である。
・経営指導員の窓口での各種相談対応時や巡回時、勉強会開催時、ホームページ等を通じて、小
規模事業者に経営分析の重要性を周知・啓発し、経営分析を必要とする対象者の掘り起しを行
う。
②経営分析に関する勉強会の実施(新規)
・セミナーでは一定の知識や情報の取得は可能だが、理解を深めたり、自社の現状を経営分析手
法に適用するなどの機会が少ない。そのため、新たな取り組みとして経営分析に関心のある小
規模事業者4、5名の小人数でのワークショップ形式の勉強会を企画する。
・勉強会では、経営分析の重要性を学び、自社の経営状況や経営課題を把握する手法を身に付け、
自社の経営分析(財務分析、定性分析、知的資産経営、資金繰り、収支計画など)に取り組ん
でもらい、自ら自社の経営分析ができるようフォローする。
・後述の「3.事業計画策定支援に関すること」の支援対象者の掘り起しも兼ねて取り組み、事
業計画策定支援および策定後支援へつなげる。
<第1期における取組と成果、課題>
・経営分析は、事業計画策定等の相談時において、部門別・商品別売上分析やSWOT分析などの
分析方法を用いて実施した。その分析結果は、主に融資や各種補助事業申請支援の一環として活
用し、事業者とのやり取りの際に口頭で伝えたために、紙ベースの明確な資料提供につながるケ
ースが少なかった。
・小規模事業者を対象に「経営課題や支援ニーズに関するアンケート」を実施し、集計した結果、
支援ニーズに挙がった回答を反映し、「経営計画作成支援セミナー」、「IT(SNS)セミナー」
の開催へつなげた。しかし、「経営状況の分析」や「事業計画作成支援」を要望回答した事業者
に対しては、セミナー等への誘導にとどまり、個別支援へつなげることが少なかった。事業者が
抱える悩みは多様化・複雑化しており、アンケート形式では事業者の様々な個別の課題や支援ニ
ーズを拾い上げることが困難であったため、事業評価委員の意見を踏まえ、個別面談時のヒアリ
ング調査に切り替えることとした。
・小規模事業者が現状の理解を深めるためには分析データを「見える形」で提供する事が、事業計
画策定の際に活用しやすく効果的であると事業評価委員からの助言があった。
<今回の申請における取組の方向性>
・事業所の財務状況の分析に加え、商品や営業手法の強みや弱み、課題や改善の方向性、経営方針
や事業承継を含めて調査し、個別事業所ごとの経営状況の分析を実施する。 ・経営分析に関しては「定量分析」と「定性分析」を明確に区分し、定性分析には自社の今後の方
向性を明確にし、社内での価値観を共有するために、新たに「知的資産経営」を取り入れる。 ・綿密な分析が必要となった場合は専門家を招聘し、事業者の個別相談に対応する。 ・経営分析結果は、事業計画策定及び事業計画策定後の実施支援にて活用し、支援先小規模事業者
の増収増益の実現へ結び付けていく。
- 9 -
③経営分析の実施(拡充実施)
・小規模事業者に対して経営指導員による個別面談にて経営分析を随時実施する。経営分析を行
った際には紙ベースで分析結果を提供し、判明した経営課題の対策材料とするほか、小規模事
業者の事業計画策定のための基本資料として活用する。
・分析結果からさらに綿密な分析が必要となった場合は、長崎県よろず支援拠点、長崎県産業振
興財団等と連携し、専門家派遣制度を活用して事業者の個別相談に対応する。
・経営分析を行った結果、経営革新や事業承継の必要性が明らかになった小規模事業者に対して
は、後述の「3.事業計画策定支援に関すること」の「2)①(ⅲ)第二創業(経営革新・事
業承継)相談会開催による第二創業計画の策定支援」へつなげて支援する。
【定量分析】
財務分析は財務諸表等を材料に各種分析ツールを積極的に用いて、数値の観点から問題点を明
らかにする。
(ⅰ)分析種類
・比較貸借対照表
・比較損益計算書
・部門別売上分析
・商品別売上分析
・各種経営計数分析
(ⅱ)分析ツール
・経済産業省のローカルベンチマーク
・中小企業基盤整備機構の経営自己診断システム
・日本政策金融公庫の財務診断サービス
【定性分析】
・定性分析は従来通りSWOT分析等を行い、自社の強みや弱みを明らかにする。また、新た
な分析手法として「知的資産経営」の考え方を取り入れる。
・自社の強みである知的資産(財務諸表に計上されている以外の無形資産、人材、技術、ノウ
ハウ、知的財産、組織力、顧客とのネットワーク等)を把握し、それを“見える化=レポー
ト化”することで、企業の経営活動に活かし、業績向上に結び付けていく。
・これを活用することで、これまで伝えきれていなかった自社の今後の方向性や独自の強みを
取引先や金融機関(外部)、後継者や従業員(内部)に明確に伝えることができる。
(ⅰ)分析種類
・SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)
・知的資産経営(目に見えない知的資産を把握し、経営活動に活かす手法)
(ⅱ)知的資産経営
・知的資産経営の分析のために以下の項目を調査する。その調査結果を経営レポートとして
整備し、事業者が営業のツールや経営戦略資料として経営活動に活かしていくほか、事業
計画策定のための資料として活用する。
<基本項目>
・企業概要(創業年、伝統、立地、営業日時、従業員数、平均客数)
・事業内容
・業界、地域の動向
・顧客ニーズ
・競合(シェア、競合店)
<自社の強み(知的資産)を明確にし、「見える化」する項目>
・商品やサービスの強み
・人に関する強み(営業力、ノウハウ、技術・技能、経験、経営者の能力や発言力)
・組織に関する強み(組織の柔軟性、人材育成の仕組み、顧客データベース、各種手続
きやクレーム対応の仕組み)
- 10 -
・外部とのつながりに関する強み(企業イメージ、顧客満足度、取引先や顧客との良好
な関係・ネットワーク、人脈)
2)実施時期と目標
・経営分析に関する勉強会の実施時期は7月から11月の間とする。
・経営分析の実施時期は通年とする。 ・定量分析と定性分析により支援先小規模事業者の経営の状況を明らかにして、事業計画策定支援
につなげていく。 <年度ごとの目標値>
支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度
②経営分析に関する勉強会の
開催数・参加者数
1回
4社
2回
8社
2回
10社
3回
12社
3回
15社
③経営分析件数 80件 80件 85件 85件 90件
- 11 -
3.事業計画策定支援に関すること【指針②】
<第1期における取組と成果、課題>
・経営課題支援ニーズ調査において要望が多かった事業計画策定支援については、これまで当所が
実施してきたセミナーや個別指導の実施を通じて、支援対象事業者の策定スキルの底上げをはか
ることが出来た。また、創業セミナーや個別相談会等創業者向けの事業を、市報や地元誌を通じ
て広報してきたことで当所の支援機関として認知度も高まってきている。各種補助金申請等以外
でも需要を見据えた恒常的な事業計画策定意識の向上や実現可能性の高い計画策定手順の認識、
策定後の実行まで(Plan〔計画〕→ Do〔実行〕)は概ね進められた。
・限られた当所支援体制(人員)においては、より効率的でスピーディーな支援が必要であるが、
本来の意味でのきめ細やかなより一歩踏み込んだ伴走型支援を行うには、支援対象事業者の事業
計画策定に取り組む意欲に大きく左右される。実際、当所の経営指導員による支援の際も、事業
者ごとに進捗に大きな差が生じ、担当する経営指導員主導による事業計画策定となってしまった
ケースがあった。
<今回の申請における取組の方向性>
事業計画は、あくまで事業者自身の自発的かつ自主的な意志により、身の丈に合った実現可能な
ものでなければならない。また、単に補助金申請や資金調達のみを目的とした一時的なものでは
なく、将来に亘ってPDCAサイクルを回すことで継続的に改善されるものでなければならな
い。したがって、事業計画策定支援の第一歩は、事業の持続的な発展のためには継続的な事業計
画策定が不可欠であることへの理解を代表者自身に深めてもらうことである。第1期の反省点を
踏まえ、今回は事業計画策定に関する啓発活動にも注力して、より増収・増益につながる効果的
な事業計画の策定支援を行っていく。
【既存事業者の事業計画策定支援】
1)事業計画策定支援対象者
前述の「2.経営状況の分析に関すること」において経営分析を行った小規模事業者
2)事業計画策定支援実施内容
・前述の「2.経営状況の分析に関すること」において経営分析を実施した小規模事業者のうち、
特に意欲のある事業者又は必要のある事業者を対象に担当する経営指導員を選任、個別の事業
計画策定支援を随時実施する。さらに、後述の「Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた
支援力向上のための取組み」の「2.経営指導員等の資質向上等に関すること」にも記載のと
おり、経営指導員、経営支援員全員(以下、経営指導員等)がチーム一丸となった支援を実施
する。
・困難な案件の場合は、支援機関である長崎県よろず支援拠点や長崎県中小企業診断士協会等の
専門家、事業者のメインバンクや顧問税理士等からの協力も仰ぎながらより効果が高い事業計
画策定ができるよう努める。
①事業計画策定の手段・手法
(ⅰ)事業計画策定の意識啓発活動(新規)
事業計画策定の必要性、策定への意欲を向上させるための取り組みとして、以下の活動を実施
する。また、この際には、需要を見据えた事業計画に基づく経営の成功事例、経験談など経営
者の生の声も紹介し、実施効果を高めるように努める。
<巡回訪問時>経営指導員等が、小規模事業者からの経営相談等を受ける際に、事業計画の必
要性について説明し、策定について積極的な提案を行う。
<窓口対応時>経営指導員等に限らず、一般職員も窓口対応の際には後述の個別相談会のチラ
シ配布などを通じて意識啓発につなげる。
<そ の 他>当所ホームページへ事業計画の必要性、成功事例などを紹介する記事を掲載、
後述の個別相談会案内等の掲載も行って意識啓発につなげる。
(ⅱ)事業計画策定個別相談会開催による事業計画の策定支援(拡充実施)
専門家招聘による個別相談会も開催、上記経営指導員による個別の事業計画策定支援のブラッ
- 12 -
シュアップ、さらなる意識啓発の向上にも役立てる。
〔開催時期:7月~11月の年2回〕
(ⅲ)第二創業(経営革新・事業承継)相談会開催による第二創業計画の策定支援(新規)
第二創業に関する相談会を開催し、経営革新(経営力向上計画含)及び事業承継の事業計画の策
定を支援する。
〔開催時期:7月~11月の年2回〕
②事業計画策定に向けてのアクションプランの策定
事業計画策定に先立ち、前述の「2.経営状況の分析に関すること」で出された分析結果も活用
しつつ、支援対象者とともに経営管理、商品・製品管理、営業管理、労務管理、店舗・機械設備
管理、財務管理ごとの実施時期や具体的な取り組み内容、目標を定めたアクションプランを設定
する。
③事業計画書の内容
当所が策定を支援する事業計画書の基本体系は以下のとおり。
・事業計画の概要
・経営の現状と課題の総括
・ビジネスモデルの状況(俯瞰図と評価)
・現状と課題(経営、財務、商品・製品、営業・サービス、労務、店舗・機械)
・業界・消費者需要動向
・自社を取り巻く環境
・SWOT分析
・経営方針、経営戦略
・予想損益計算書
・予想貸借対照表
・予想年度資金繰り表
3)実施時期と目標
実施時期は通年。需要を見据えた事業計画、実現可能性の高い事業計画策定に資する伴走型支援を
実施して、事業計画に基づく経営を行う小規模事業者の増加を目指し、下記のとおり目標値を設定
する。
<年度ごとの目標値>
支援内容 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度
①(ⅱ)事業計画策定個別相談
会開催回数・参加者数
2回
30社
2回
30社
2回
30社
2回
30社
2回
30社
①(ⅲ)第二創業相談会開催回
数・参加者数
1回
7社
1回
7社
1回
7社
1回
7社
1回
7社
③事業計画策定事業者数 50件 50件 55件 55件 60件
③第二創業計画策定事業者数 1件 1件 1件 2件 2件
【創業事業所の計画策定支援】
1)創業計画策定支援対象者
創業を目指す市民、Uターン・Iターン希望者、定年後の高齢者、農商工連携事業・6次産業化
に取り組みたい生産者とその家族。広報としては、諫早市報、地元誌、当所ホームページへの掲
- 13 -
載を行う。
2)創業計画策定支援実施内容
・創業者や事業経過年数が短い方の中には、創業計画を策定していないために「目標」がはっき
りと定まっていない方や、創業準備が不十分なままで創業したことが原因と見られる深刻な課
題を抱えているケースが多数見られるため、創業希望者との接触する機会を増加させ、創業の
準備や実現可能性の高い事業計画の策定する「創業事業計画の策定支援」が重要である。
・別表4の通り、当地域内に本支店を置く金融機関、長崎県信用保証協会、日本政策金融公庫長
崎支店国民生活事業、長崎県産業振興財団、九州北部税理士会諫早支部と連携するとともに、
産業競争力強化法に基づき整備された「諫早市創業支援ネットワーク協議会」においても創業
者情報の共有化を図りつつ、創業希望者向け専用チラシを作成して、創業を目指す市民、Uタ
ーン・Iターン希望者、定年後の高齢者、農商工連携事業・6次産業化に取り組みたい生産者
とその家族など幅広い層の創業者の掘り起こしを行い、創業セミナー、創業スクール、専門家
による創業個別相談会を拡充開催して、創業に必要な心構えや基礎知識の習得及び創業計画の
策定を支援していく。
①創業時に必要な情報の提供(拡充実施)
・開業場所の選定などに活用:諫早市統計データ、経済センサス、商圏分析ツール(j STAT
MAP)による周辺人口や世帯数調査結果を提供する。
・店 舗 探 し に 活 用 :長崎県宅地建物取引業協会が運営しているwebサイト「たっけ
んくんネット」を紹介(空き店舗情報)、不動産業者や地元内装業
者などの情報を提供する。
・資 金 調 達 に 活 用 :制度資金一覧表や補助金情報を提供する。
・開 業 準 備 に 活 用 :社会保険労務士や税理士などの専門家リスト、営業許認可等申請
先一覧を提供する。
・創業計画書策定に活用 :日本政策金融公庫提供の経営指標等を提供する。
②創業計画策定支援の手段・手法
(ⅰ)創業セミナー・個別相談会開催による創業計画の策定支援(拡充実施)
今後も創業セミナーを開催し、創業希望者の基本的知識の習得から創業計画(ビジネスプラン)
の策定までを行うことにより、創業支援を実施する。
〔開催時期:7月~11月の年2回〕
(ⅱ)創業支援における事業計画策定支援(新規)
当所の上記創業セミナーを受講(修了)した後、別途要望がある創業希望者に対して、個別に
よる創業計画書策定の支援を行う。この場合は担当する経営指導員に加え、必要に応じて支援
機関である長崎県よろず支援拠点からの協力も仰ぐ。
3)実施時期と目標
実施時期は通年。創業事業者の掘り起こしを強化し、実現可能性の高い創業計画策定に資する伴走
型支援を実施して、下記のとおり目標値を設定する。 <年度ごとの目標値>
支援内容 H30 年度 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度
②(ⅰ)創業セミナー開催回
数・参加者数
2回
35社
2回
35社
2回
35社
2回
35社
2回
35社
②(ⅰ)創業個別相談会開催
回数・参加者数
2回
15社
2回
15社
2回
15社
2回
15社
2回
15社
②(ⅱ)創業計画策定事業者
数 15件 15件 15件 15件 15件
- 14 -
4.事業計画策定後の実施支援に関すること【指針②】
<第1期における取組と成果、課題>
・前述の「3.事業計画策定支援に関すること」のとおり、事業計画策定の有用性や策定手法の認
識、策定後の実行まで(Plan〔計画〕→ Do〔実行〕)は概ね進められた一方で、多種多様な事
業計画に対する画一的な評価(Check〔評価〕)は困難であり、同計画の見直し(Act〔改善〕)も
含めて多忙な対象事業者自身によるPDCAサイクルの構築までに至ったケースは少なかった。
理由としては、事業者自身の意欲やスキルの問題と、それを補うための支援を行う当所の支援内
容が曖昧で手法も確立していなかったことが挙げられる。 ・当所の経営指導員による事業計画策定後の支援内容は、経営指導員個々のこれまでの経験やノ
ウハウに依存するケースが多く、新人指導員や支援員などには分かりづらく、一貫性に欠ける
部分があった。今後は経営指導員のみならず、当所職員全員が理解しやすい支援手法の確立が
必要で、その支援手法自体にもPDCAサイクルの概念を持たせる必要がある。
・第1期計画でPDCAサイクルをまわす支援を行うための目標値としていた巡回訪問は達成率が
低かったが、事業評価委員からは当所の地域性である来所型での指導が従来より定着しており、
効果も確認できるのでそれほど巡回にこだわる必要はないとのアドバイスがあった。
<今回の申請における取組の方向性>
今後は、経営指導員等の個々の経験やノウハウに依存するのではなく、共通の支援ツールを用い
て一貫性のある実施支援を行い、事業者自らが需要を見据えた事業計画に基づくPDCAサイク
ルをまわす仕組みづくりの構築を目指す。
1)事業計画策定後の支援体系
①支援体制
基本的には、事業計画策定時に担当した経営指導員による継続支援を行うが、策定時同様に経営
指導員等がチーム一丸となった支援体制(月1回の経営支援会議)を継続、必要に応じて支援機
関の協力を仰ぐ。
②支援内容
まずは策定された事業計画の進捗状況の確認を行う。担当する経営指導員は伴走型支援を方針と
するので、以降のPDCAサイクルの進捗状況は下記ツール「PDCAチェックシート」を用い
て、支援対象事業者にもわかりやすく、上記の経営指導員等による経営支援会議における資料と
しても活用する。
- 15 -
2)事業内容・活用方法 ①事業計画策定後の個別モニタリング、フォローアップ(拡充実施) ・前述の「3.事業計画策定支援に関すること」で事業計画(第二創業計画含)の策定を支援し
た全事業者に対し、経営指導員が四半期に1度進捗状況の確認を行う。進捗がおもわしくない
場合は、必要に応じて、中小企業庁のミラサポ、長崎県産業振興財団、長崎県よろず支援拠点、
長崎県中小企業診断士協会、長崎県信用保証協会等の各専門家と連携しつつ、問題点を検証し、
支援対象事業者とともに解決策(事業計画修正案)の策定のための支援を行う。金融支援が必
要となった場合は、日本政策金融公庫のマル経融資をはじめ、別表4に定める金融機関の市内
各支店窓口を経由しての長崎県・諫早市の制度融資の推薦・斡旋を行い、更に融資実行後の返
済面のフォローも行う。
・上記の結果、フォローの頻度については、当該事業者と協議のうえ進捗状況に応じて適宜増減
する。
②創業計画策定後の個別モニタリング、フォローアップ(拡充実施)
創業者に対しては、上記①の支援に加えて、事業開始の諸手続、記帳決算申告指導、資金繰り、
従業員雇用、諸規定の作成など成長段階に応じて生じる様々な課題について、よりきめ細かな伴
走型の支援を行う。
3)実施時期と目標 実施時期は通年。四半期に1度の事業計画の進捗状況確認を通じて、経営のPDCAサイクルを回す支援を行い、支援先事業者の持続的発展を目指す。創業者には、成長段階に応じたきめ細やかな伴走支援を実施し、事業の存続に寄与する。
<年度ごとの目標値>
支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度
①事業計画策定後の個別モニタリング、フォローアップ延べ回数
200回 200回 220回 220回 240回
②第二創業計画策定後の個別モニタリング、フォローアップ延べ回数
4回 4回 4回 8回 8回
③創業計画策定後の個別モニタリング、フォローアップ延べ回数
60回 60回 60回 60回 60回
- 16 -
5.需要動向調査に関すること【指針③】
<第1期における取組と成果、課題>
・経営計画セミナーや個別支援の事業計画策定支援において、支援先小規模事業者が取り扱う商品・
サービスの品目レベルでの需要動向情報を収集・分析し、提供することができた。
・事業者へ個別に提供した情報の所内蓄積・職員共有化は達成できた。
・平成27年度の需要動向調査に関して、事業評価委員から支援先小規模事業者にどのような情報
を提供したのかという管理が不十分であると指摘があったため、平成28年度から需要動向情報
を紙ベースで提供し、所内蓄積・職員共有化のためデータベース化を実施した。改善後、資料提
供は支援先小規模事業者にとって役立っていると評価を得ている。
・今後は、新たな販路開拓や新商品の開発等に活かすことが出来る消費者の生の声やBtoBの促進
に役立つ買い手のニーズ調査など当所独自の需要動向調査を実施して、支援先小規模事業者へ提
供する需要動向情報の内容をより充実させていくことが課題と言える。
<今回の申請における取組の方向性>
・後述する「Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組」<第1期における取組と成果、課題>に記載し
た「諫早地域活性化検討委員会」の構成員であった菓子製造業者は、委員会終了後も地元の特産
にこだわった新商品開発を活発に行っている。また、前述の目標「管内商工業者数・小規模事業
者数等の推移」に記載した飲食店数は増加しており、需要動向調査結果の提供のニーズが高いた
めに「飲食業者」や「食料品製造小売業者」に対して重点支援を行う。
・新たな取り組みとして、飲食業者や食料品製造小売業者が新商品を開発や改善等をする際に、消
費者の評価や意見を短期間のうちに効率よく収集出来るように、当市で開催される集客力が高い
イベントの来場者を対象として、試作品試食に関する消費者ニーズアンケート調査を実施する。
・需要動向調査で得られたデータ等は、既存商品等の改善点の整理や新商品の開発に活用するとと
もに、事業計画策定の際の参考や事業計画策定後の実施支援の際の消費者の評価としても活用す
る。また、販路開拓等に向けた展示会・商談会等への出展支援へつなげる。
・需要動向情報の紙ベースでの提供と所内蓄積・職員共有化は継続実施する。 1)事業内容・活用方法
①需要動向調査データの収集・提供・活用(新規)
●対 象 製造業(菓子等含む)、卸小売業、サービス業(飲食業含む)
●実施時期 随時
●実施場所 当該事業者のニーズに応じて店舗または諫早商工会議所において実施。
(1事業者あたり1~2時間)
●実施方法 新たな販路の開拓や新商品の開発を希望する小規模事業者からの依頼を受けて、バ
イヤー等(現役バイヤー、バイヤー経験があるコンサルタント・中小企業診断士)
を招聘し、買手のニーズや市場動向等を踏まえた新商品・新サービスの開発や既存
商品・サービスの改善のための情報提供と指導アドバイスを個々に行う。バイヤー
等から収集した情報を、当該事業者のニーズに応じて整理したデータとして当該事
業者へフィードバックする。
●調査項目 食味、価格、分量、パッケージ等
●調 査 数 1事業者あたり1~3品目
●活用方法 小規模事業者が展開する商品・サービス等に応じて、上記データを事業計画策定支
援時や個別相談会時に提供し、マーケットインの考え方に基づく今後の効果的な商
品開発や改善、商品ラインナップの見直し等の商品戦略への活用を促し、支援先小
規模事業者の販路開拓に向けた展示会・商談会等への出展支援や増収増益の実現に
結びつけていく。
②消費者ニーズアンケート調査および個別相談会(新規)
・飲食業者(製造小売業含む)の新商品・新メニューの開発支援として、地元消費者から新商品
に関する率直な意見や感想を聴き商品化に役立てるために、当所が主催する「のんのこ諫早ま
- 17 -
つり」のイベント会場で消費者ニーズアンケート調査を実施する。
・新商品・新メニューの消費者ニーズアンケート調査支援を行う小規模事業者とは、事前にアン
ケート調査項目の選定や精査のため、専門家と経営指導員を交えた個別相談会を行う。
・アンケート実施後にも、専門家と経営指導員を交えた個別相談会を行い、得られた調査結果を
分析し、支援先小規模事業者にフィードバックして、商品化や事業計画策定時の根拠資料とし
て提供する。
・「消費者ニーズアンケート調査および個別相談会」の調査内容は以下の通り。
●対 象 飲食業(和食、洋食、中華)、菓子製造業(和菓子、洋菓子)(製造小売業を含む)
●実施時期 ・消費者ニーズアンケート調査:毎年9月(「のんのこ諫早まつり」の開催日)
・個別相談会:調査日の前後に各 1回
●調査方法 まつり出店ブースの一角に試作品試食コーナーを設け、アンケート回答を条件に
試作品の提供を行う。試作品の提供は実施事業者。アンケート回収と集計は当所
の臨時雇用調査員が行う。
●調査項目 食味・価格・分量等は各事業者の商品毎に事前の個別相談会で協議し、消費者ニ
ーズを把握し、その事業者の商品開発・改善へつながる調査項目を商品毎に作成
したものを使用する。
【アンケート調査項目例】
・商 品に関する項目:食味、価格、分量、パッケージ等
・消費者に関する項目:地域、性別、年齢、家族構成等
●調 査 数 200名分(試作品毎)
1事業者あたり1~2品の試作品を商品毎に試食してもらいながら来場者(消費
者)に調査する。
●活用方法 アンケート結果は、地域・性別・年齢・家族構成等に分析し、消費者ニーズに合
った商品の開発・改善に活かす事業計画策定時(販路開拓先を模索する際)の参
考資料や地元商談会等に参加する際の支援材料として活用する。
2)実施時期と目標
・実施時期は前述の通り。
・支援先小規模事業者の商品や役務に関する需要動向を調査・収集し、買い手・消費者のニーズを
踏まえた商品開発・商品戦略等に役立つよう整理・分析した情報を支援先小規模事業者に提供し、
マーケットインの考え方を浸透させていく。
<年度ごとの目標値>
支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度
①需要動向調査データの提供等を
行う個社支援数 7社 7社 9社 9社 11社
②消費者ニーズアンケート調査
および個別相談会を行う個社支
援数
6社 8社 10社 10社 10社
- 18 -
6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること【指針④】
1)支援対象
小規模事業者を『広域型事業者』、『地域型事業者』に分類し、事業者が販路開拓につなげられるよ
うそれぞれのニーズに対応した支援事業を実施する。『広域型事業者』、『地域型事業者』は下記のよ
うに定義する。
※『広域型事業者』=全国的な販売展開を目指し、独特な商品・サービスを持つ製造業者や専門サ
ービス業などの広域需要志向型小規模事業者
※『地域型事業者』=地元など限られた市場のなかでいわゆる“顧客の囲い込み”に活路を求める
卸小売業や理美容業など地域需要志向型の小規模事業者
<第1期における取組と成果、課題>
・東京でのテストマーケティング事業に参加するため、事前に「展示会出展者向けブラッシュアッ
プセミナー」で出展計画書作成支援を実施、その後の個別支援では、試食をしてもらう方法、お
客様への声のかけ方等についてフォローアップをして新規取引先の開拓につながった。但し、自
社商品をブラッシュアップすれば「強み」が際立つことに気づいていない事業者が多いため継続
的な支援の必要性が感じられた。また、事業評価委員会では、安価な商品しか売れないという固
定観念を捨てることや取引先と商談するときは仕様変更等細かな要望にも対応していくことの
重要性を支援先小規模事業者へ伝えていくよう助言を受けた。
・地元商談会としては、諫早市のふるさと納税特産品への登録を促す勉強会の実施及び商談会の見
学会を実施した。なお、当初計画していた地元の通販業者と地域型小規模事業者のマッチングと
いう内容の地元商談会は、地元通販業者の協力が得られなかったため開催を見送った。
・販路拡大セミナーや情報発信セミナーでは「プレスリリース作成講座」「LINE@活用セミナ
ー」等を実施し、いずれも関心の高いテーマであったため参加者数は目標を達成した。また、情
報発信セミナーでは「個別相談会」の需要が高いために、平成29年度から個別相談会の充実を
図り、改善を行った。事業評価委員会でセミナー受講者のその後の実施状況等を追跡調査しては
どうかと指摘を受けた。
・創業5年未満の小規模事業者を対象とした創業者交流会を開催し「創業者同士」の交流を通じて、
事業の継続・拡大のための情報交換を行うことができ、新たな販路開拓につながった。事業評価
委員からは、創業者だけではなく先輩事業者にも参加してもらい、さらなる販路開拓の場として
利用できないかとのアドバイスを受けた。
・商店街連合会、福祉介護施設と連携して「共同移動販売事業」を年に数回実施したが、販売実績
が伸びず参加企業も固定化しているため、第2期経営発達支援計画の事業からは除外する。
<今回の申請における取組の方向性>
・地域内の小規模事業者の売上拡大・販路開拓に資するために、食品製造業のみならず、地域産物
を使用した新たな加工商品の製造に取り組む商業、サービス業等の事業所も対象とした展示会、
商談会への参加を支援する。
・各種セミナーや個別相談会を実施し、販路開拓支援を行う。
・小規模製造業者に対しては、中規模金属機械製造業者とのBtoBの機会を作り、販路開拓を支援
する。
・以上の支援において、必要な事業については金融機関や長崎県産業振興財団などとの連携、当所
職員の事後のフォローアップを実施することで支援効果を高め、販路開拓へつなげていく。
- 19 -
2)実施内容
①展示会・商談会の出展支援(拡充実施)
全国規模で開催される商談会、展示会等の販促イベント情報と長崎県、長崎県産業振興財団、
近隣商工会議所などが主催する地元の商談会、展示会等の情報(開催日時、申込方法など)
を収集し、年間イベントスケジュールを当所ホームページに掲載し、その規模や特徴、募集
要項等を整理した上で支援対象となる小規模事業者に下記の支援を行う。
(ⅰ)全国規模商談会への出展支援
広域型事業者に対しては、毎年2月に開催されるスーパーマーケット・トレードショーへの
出展を促し、出展する小規模事業者がより高い成果を得られるように展示会に向けたブラッ
シュアップセミナーや個別相談会を実施する。また、出展後も成約に向けたフォローアップ
を引き続き実施する。
(イ)実施時期・頻度 ブラッシュアップセミナー:9月・1回
出展者に対する個別相談会:10~12月・必要に応じて1社2回
出展後の成約に向けた支援:2月・1社2回
(ロ)実施方法 ブラッシュアップセミナーの周知・募集は、当所ホームページや募集
チラシの他、事業計画策定支援先小規模事業者には直接参加を促し、
連携先金融機関等には、出展見込み者情報の提供及び勧誘を要請する。
ブラッシュアップセミナーの講師は、バイヤー経験のある方を招聘。
ブラッシュアップセミナー参加者を対象として、後日、専門家による
個別相談会を開催する。出展後も専門家によるフォローアップを実施
する。
(ハ)実施目的 9月に実施するブラッシュアップセミナーで商談会や展示会時に成約
につながるノウハウ、販売時の商品陳列(フェイシング)や接客対応
技術を習得し、商品を認知してもらうためのより効果的な方法を学び、
2月に東京で開催される商談会で成約につなげ、全国に販路を拡大す
るため。
(ⅱ)地元商談会への出展支援
全国的な販売展開が難しい地域型事業者に対しては、長崎県、長崎県産業振興財団、近隣商
工会議所などが主催する地元の商談会への出展を促し、今後少しずつでも販路を開拓できる
よう支援を行う。また、商談会終了後も引き続きフォローアップを実施する。
(イ)実施時期・頻度 随時(地元での商談会開催時)
(ロ)実施方法 長崎県、長崎県産業振興財団、近隣商工会議所などが主催する地元の
商談会、展示会等の情報(開催日時、申込方法など)を収集し、年間
イベントスケジュールを当所ホームページに掲載して、出展する事業
者を募る。また、支援先小規模事業者等へは電話等による個別案内を
行い、個別相談による支援を行う。商談会終了後、専門家を招聘して、
成約につながるフォローアップを実施する。また、今後出展が見込め
る事業者に対しても、商談会の見学や、今後の出展に向けた支援を実
施する。
(ハ)実施目的 県内の商談会や展示会の現状を把握し、成約につながるノウハウを習
得し、今後の販路開拓や、増収・増益につなげるため。 ②ITを利用した販売促進支援(拡充実施)
・広域型事業者、地域型事業者ともにフェイスブック・インスタグラム・LINE@などのSN
Sを含むITを利用した販売促進に直結する情報発信に関する支援を実施する。
・上記に関するセミナーを開催し、情報発信の具体的な事例や有効的な活用法を学び、セミナー
受講者を対象に専門家を招聘して実施する個別相談会では、広域型事業者・地域型事業者それ
ぞれに対応した個社支援を行う。
(ⅰ)実施時期・頻度 毎年7~12月にセミナーを2回、個別相談会も1~2回実施する。
- 20 -
(ⅱ)実施方法 セミナー参加者の募集は、当所ホームページや当所の窓口に募集チラ
シを設置して行う。講師には、ITを利用した販売促進の実績を持つ
方を招聘。セミナー受講者を対象に、後日専門家による個別相談会を
実施する。セミナー受講者及び個別相談会を実施した事業者へは実際
に導入や指摘事項の改善が行えたか追跡調査を実施する。
(ⅲ)実施目的 広域型事業者、地域型事業者共に情報発信による販路開拓を行うため。
③顧客管理・集客の強化を図る販売促進支援(拡充実施)
・広域型事業者・地域型事業者ともに、POSレジやEXCEL等による顧客管理、プレスリリ
ースやDM等による集客の強化を図る販売促進支援を実施する。
・上記に関するセミナーを開催し、顧客管理や集客の効果的な方法を学び、セミナー受講者を対
象に専門家を招聘して実施する個別相談会では、広域型事業者・地域型事業者それぞれに対応
した個社支援を行う。
(ⅰ)実施時期・頻度 毎年7~12月にセミナーを3回、個別相談会を2~3回実施する
(ⅱ)実施方法 セミナー参加者の募集は、当所ホームページや当所の窓口に募集チラ
シを設置して行う。講師には、それぞれの専門分野の専門家を招聘。
セミナー受講者を対象に、後日専門家による個別相談会を実施する。
セミナー受講者及び個別相談会を実施した事業者へは実際に導入や指
摘事項の改善が行えたか追跡調査を実施する。
(ⅲ)実施目的 広域型事業者、地域型事業者ともに顧客管理・集客の強化を図るため。
④「製造業ビジネスマッチング会」の実施(拡充実施)
・地元小規模製造業者を対象に、管内の工業団地等に所在する中規模金属機械製造業者からの需
要を受注につなげるため、新規取引先に求める製造技術・部品等に関する需要、ニーズ調査を
実施して、ビジネスマッチング会を開催する。
(ⅰ)実施時期 ニーズ調査 :毎年9月
マッチング会:毎年11月
(ⅱ)実施方法 ニーズ調査 :諫早中核工業団地自治振興会(立地企業数143社)や長崎
県金属工業協同組合(組合員数7社)、諫早工業会(会員企業
数25社)等に協力を要請し、各会に所属している企業に対
して、新規取引先に求める製造技術・部品等に関する要望、
ニーズ調査票を送付し、書面で回答して頂いたデータを当所
で整理・登録する。
マッチング会:発注企業(地元中規模金属機械製造業者)と受注を希望する
企業(地元小規模製造業者)との個別商談会方式で開催。受
注企業は事業計画策定支援を行った小規模製造業者に参加を
促す他、当所ホームページや当所の窓口に募集チラシを設置
して行う。マッチング会開催後も引き続き職員がフォローア
ップを行うことで、成約につなげていく。
(ⅲ)実施目的 中規模金属機械製造業者からの需要を地元小規模製造業者の受注につなげ、
小規模製造業者の販路開拓、取引拡大を目指すため。
⑤「創業者交流会」の実施(拡充実施)
創業5年未満の小規模事業者を対象に「創業者交流会」を開催する。また、事業評価委員会から
のアドバイスにより、参加される創業者の販路開拓先となる業種の事業者にも参加を呼びかけ、
創業者の販路開拓に結びつける。
(ⅰ)実施時期 毎年1月
(ⅱ)実施頻度 年に1回
(ⅲ)実施方法 当所が創業支援及び創業後の伴走型支援を実施している創業5年未満の小規
模事業者に直接参加を促し、参加される創業者の販路開拓先となる業種の事
業者には、当所ホームページや当所の窓口に募集チラシを設置して参加者を
- 21 -
募る。創業者交流会では、始めに創業者から自社PRを行い、その後、名刺
交換、個別面談の時間を設ける。参加した創業者へは追跡調査を実施し、販
路開拓に向けたフォローアップや新たなマッチングの場を提供する。
(ⅳ)実施目的 創業者の販路開拓と人脈形成のため。
※①~⑤の情報については、当所ホームページ等で告知や経過報告を随時行うことで、小規模事
業者等の販路開拓を支援する。
3)実施時期と目標
実施時期は前述の通り。具体的な数値目標を下記の通り設定する。 <年度ごとの目標値>
①(ⅰ)全国規模商談会
支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度
展示会出展者向けブラッシュアップ
セミナー開催数 1回 1回 1回 1回 1回
受講者数 12社 14社 16社 18社 20社
個別相談支援者数 3社 3社 4社 4社 5社
展示会出展者数 3社 3社 4社 4社 5社
成約数 3件 3件 4件 4件 5件
①(ⅱ)地元商談会
支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度
近隣商工会議所が開催している商
談会への参加支援者数 4社 4社 5社 5社 6社
成約数 2件 2件 3件 3件 4件
②ITを利用した情報発信
支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度
セミナー開催数 2回 2回 2回 2回 2回
受講者数 40社 40社 45社 45社 50社
個別相談支援者数 6社 6社 7社 7社 8社
売上増加者数(導入・改善者数) 20社 21社 24社 24社 27社
③顧客管理・集客の強化を図る販売促進支援
支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度
セミナー開催数 3回 3回 3回 3回 3回
受講者数 60社 60社 65社 65社 70社
個別相談支援者数 8社 8社 10社 10社 11社
売上増加者数(導入・改善者数) 30社 31社 34社 35社 38社
④製造業ビジネスマッチング会
支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度
参加企業数 10社 10社 12社 12社 14社
個別商談会件数 5件 6件 6件 7件 7件
成約数 3件 3件 3件 4件 4件
⑤創業者交流会
支援内容 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度
参加者数 15社 15社 15社 15社 15社
成約数 3件 3件 3件 3件 3件
- 22 -
Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組
<第1期における取組と成果、課題>
①産・学・官連携の「諫早地域活性化検討委員会」による地域経済活性化策の策定と実現
地域経済活性化策の策定と実現では、地域資源を活用し、交流人口の拡大に効果的で実現性の高
い『スポーツツーリズム分野』、『「食」「土産品」創出分野』、『本明川河川敷を活用したイベン
ト創出分野』の3分野における地域経済活性化策を以下の通り策定した。また、事業評価委員会
では、「食・土産品等創出分野」に関連して、6次産業化に取り組まれている事業者、農協・漁
協などの関係機関に所属し、加工・販売も手掛ける事業者との接点を増やしていけばどうかとの
意見をもらい、長崎県央振興局の「県央地域加工業務用産地育成協議会加工部会」の構成員にな
り積極的に参加している。 ●スポーツツーリズム分野
長崎がんばらんば国体・大会で整備されたスポーツ施設やソフト面でのノウハウを活用し、更
なる学校スポーツ合宿等の誘致の仕組みづくりと必要な条件整備を策定し、その実現により交
流人口拡大を図る活性化策を諫早市や(一社)諫早市観光物産コンベンション協会へ提言した。 ●「食」「土産品」創出分野
諫早の地域資源を活用した新たな「食」「土産品」について試作・開発に取り組み、地元事業
者によるその事業化を実現して、九州新幹線西九州ルート開通までに諫早ならではの特産品を
創出し定着させる活性化策を提案した。各事業所で商品開発は継続して行われている。 ●本明川河川敷を活用したイベント創出分野
諫早駅と中心商店街を結ぶ最短の回遊路としての親水性豊かな本明川河川敷は当市の観光資
源であり、この本明川河川敷において、集客力のある新たなイベントを創出し、恒久的なイベ
ントとするための実施体制の整備を図ることによって、交流人口の拡大に繋げる活性化策を諫
早市や国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所へ提言した。 ②中心市街地活性化事業
諫早市中心市街地活性化協議会構成員の意見と要望を反映させた「第2期諫早市中心市街地活
性化基本計画」(H26.04~H31.03)」が現在進行中であり、平成29年3月現在、全 52 事業の
うち5事業が完了、実施中 41 事業、未実施 6 事業と順調な進捗状況にある。人口減少・少子
高齢化を見据えたコンパクトでコミュニティ機能を有した街づくりを目指した第2期基本計
画の核となる「諫早市栄町東西街区第一種市街地再開発事業」では、中央商店街(アエル商店
街)に分譲マンション65戸、保育所、子ども・子育て総合センター、さらに商業床、駐車場
を組み合わせた複合施設が平成31年開業予定である。また、平成34年開通予定の九州新幹
線西九州ルート建設に伴うJR諫早駅及び周辺を含む整備事業も、在来線駅と新幹線駅とを結
ぶ自由通路並びに再開発ビルの建設が進んでおり、平成32年度末までに完成予定である。 <今回の申請における取組の方向性> ・地方都市において人口減少・超高齢化が急速に進む中、中心市街地における都市機能の増進及
び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するコンパクトなまちづくりが求められており、
また、多くの小規模事業者が中心市街地を営業基盤としていることから、中心市街地活性化に
取り組む必要がある。そこで、地域の多様な機関で構成され、当所が中核を成し事務局を担う
諫早市中心市街地活性化協議会において「諫早市中心市街地活性化基本計画」の推進を図って
いく。 ・当所は、引き続き「第2期諫早市中心市街地活性化基本計画」(H26.04~H31.03)の取り組み
を推進するとともに、今後は、第2期基本計画の核事業である「諫早市栄町東西街区第一種市
街地再開発事業」の中心市街地への経済波及効果を高めるために、商業床についてのコンセプ
トの策定、テナントミックスの検討・誘致、管理運営方法の具体的計画の策定を進めていく。 ・諫早市においてこれから策定作業が進められる「第3期諫早市中心市街地活性化基本計画」
(H31.04~H36.03 予定)については、平成29年度に発足した当所まちづくり推進協議会に
おいて検討を進めている商工業者視点による具体的かつ実効性の高い事業を取り纏め、第3期
- 23 -
基本計画への反映を行政に要望していく。また、平成34年の新幹線西九州ルート開業に向け
て第3期基本計画に取り上げられるべき、諫早駅に隣接する永昌東町商店街及び周辺地区の商
業・サービス業・飲食業等の活性化策の取り纏めを支援する。 ・さらに、地域の多様な機関で構成される諫早市中心市街地活性化協議会において、第3期基本
計画の内容を十分に考査・検証し行政に対して提言する。 1)事業内容
①「第2期諫早市中心市街地活性化基本計画」(H26.04~H31.03)の事業の推進
1)継続実施中の事業の推進
(ⅰ)当所が実施主体となって行うイベント
・諫早万灯川まつり(毎年7月開催 来場者 5.1万人)
・のんのこ諫早まつり(毎年9月開催 来場者 10万人 飲食コーナーへの出店 42団体)
(ⅱ)中心市街地の商店街がおこなうコミュニティ型ソフト事業に対する支援
・アエル中央商店街 100円商店街
・ 〃 川まつりナイトフェスタ
・ 〃 秋の街並み美術展
・永昌東町商店街 夏まつり
・ 〃 バル&ウォーク
・天満町商工振興会 天満祭り
・八坂町共栄会 八坂ぎおん祭り
(ⅲ)諫早市栄町東西街区第一種市街地再開発事業の推進
2)未実施の事業の推進 (ⅰ)諫早市栄町東西街区第一種市街地再開発事業の商業床テナントミックス事業の支援
(ⅱ)諫早市中心市街地活性化協議会がおこなうコミュニティ型ソフト事業
・「得する街のゼミナール」(通称:まちゼミ)の開催
②「第3期諫早市中心市街地活性化基本計画」(H31.04~H36.03)の事業計画策定の提言及び事業実
施の推進
・当所まちづくり推進協議会における商工業者による中心市街地活性化策の取り纏め及び第3期
基本計画への反映の要望
・諫早駅に隣接する永昌東町商店街及び周辺地区の商業・サービス業・飲食業の活性化策の取り
纏めの支援
・諫早市中心市街地活性化協議会における第3期基本計画の考査・検証及び提言。
・第3期基本計画の事業の推進。
- 24 -
<連携フロー図(イメージ)>
連携・調整
諫早市 ・中心市街地活性化基本計画の策定 ・事業(ハード、ソフト事業)の推進
協
議
諫早市栄町商店街協同組合、諫早市永昌東町商店街協同組合、天満町商工振興会、JR九州諫
早駅、島原鉄道(株)、長崎県交通局、(有)諫早観光ホテル道具屋、日本郵便(株)諫早郵便
局、国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所、いさはや国際交流センター、元諫早地域
審議会、栄町町内会、諫早銀行協会(たちばな信用金庫)、(一社)諫早青年会議所、(一社)
諫早観光物産コンベンション協会、(公社)長崎県宅地建物取引業協会諫早支部、天満太鼓、
高齢者福祉施設、長崎ウエスレヤン大学、長崎ビジネス支援プラザ、諫早ケーブルテレビジョ
ン放送(株)、諫早タクシー協会、諫早図書館友の会
諫早市中心市街地活性化協議会
+ 諫 早 商 工 会 議 所 (株)まちづくり諫早
提
言
提
言
事業実施主体 諫早市、諫早商工会議所、諫早観光物産 コンベンション協会、商店街連合会、各種団体等
協
議
- 25 -
Ⅲ.経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上のための取組み
1.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること
1)事業内容
①他の支援機関(商工会議所)との連携構築及び情報交換会の開催(拡充実施)
・長崎県商工会議所連合会主催の長崎県内商工会議所中小企業相談所長等が参加する「中小企業
相談所長会議(年2回開催)」において、経営発達支援事業の取組状況等に関する情報交換で、
支援ノウハウ、支援の現状について協議し、情報の収集と共有化を図る。
・九州商工会議所連合会主催の九州圏内商工会議所中小企業相談所長等が参加する「九州ブロッ
ク中小企業相談所長会議並びに中小企業支援先進事例普及研修会(年1回開催)」において、経
営発達支援事業の取組状況等に関する情報交換で、支援ノウハウ、支援の現状について協議し、
情報の収集と共有化を図る。
②関係機関(九州北部税理士会)との連携と情報交換会の開催(継続)
九州北部税理士会との「税務相談懇談会(年1回開催)」、において、関係機関ごとにその組織や
業務・機能の特性に基づく個別情報であるために他の支援機関では入手困難なものが多くある情
報を共有し活用し合うことで、当所が行う経営支援がより高度なレベルで実施できることになる。
③金融機関(日本政策金融公庫)との連携と情報交換会の開催(継続)
日本政策金融公庫長崎支店国民生活事業との「金融懇談会(年1回開催)」、「推薦団体連絡協議会
(年1回開催)」、において、金融機関ごとにその組織や業務・機能の特性に基づく個別情報であ
るために他の支援機関では入手困難なものが多くある情報を共有し活用し合うことで、当所が行
う経営支援がより高度なレベルで実施できることになる。
<第1期における取組と成果、課題>
長崎県内「中小企業相談所長会議」や「九州ブロック中小企業相談所長会議」等で情報交換は
十分に行うことが出来ているために、今後はこの会議を利用して当所の支援事例を積極的に外
部に紹介していくことで、他所経営指導員等から参考意見を事業にフィードバックする。また、
事業評価委員会でも特段の指摘を受けることはなかった。 <今回の申請における取組の方向性> 他の商工会議所・商工会等の支援機関、及び関係機関と連携し、支援を行うための情報の交換 と共有を図り、支援ノウハウの習得と蓄積と活用を積極的に行う。支援ノウハウ等の情報は、 各支援機関、関係機関ごとにその組織や業務・機能の特性に基づく個別情報であり、他の各支 援機関、関係機関では入手困難なものが多くある。そこで、各情報を共有し活用し合うことで、 当所のみが行う経営支援より高度な支援の実施が可能となる。この交換された情報を活用する ことで、事業者への経営改善、経営発達に資する事業計画の策定、経営革新や農商工連携事業 等の取り組み、創業・第二創業、販路開拓の各種の支援が高度に、かつ効率的に実施できるも のと期待できる。ただし、個人情報や支援ノウハウの関係者以外への流出が無いようにセキュ リティには万全を図る。
- 26 -
2.経営指導員等の資質向上等に関すること
1)事業内容
①会議所内部研修会の開催(新規)
前述の「2.経営状況の分析に関すること」に記載している「知的資産経営」の効果を高めるた
めに「対話能力・ヒヤリング能力」の向上の研修を実施する。 (諫早商工会議所単独開催)
・経営指導員、経営支援員、一般職員の「対話能力・ヒヤリング能力」向上を図る当所単独研修
会を独立行政法人中小企業基盤整備機構九州支部の支援を受け実施し、職員のスキルアップを
図る。
(長崎県内商工会議所との合同開催)
・長崎商工会議所等県内商工会議所等と過去の事例を基にして、職員の「技術・サービスレベル」
向上のために、独立行政法人中小企業基盤整備機構九州支部の支援を受けながら合同研修会を
実施し、職員それぞれのスキルアップを図る。
②経営支援会議等の開催、OJTの実施(拡充実施)
・経営指導員、経営支援員による「経営支援会議」を毎月1回以上開催し、経営分析、事業計画
書作成支援、マル経推薦書作成等に関する意見交換を行うと共に、研修会や専門家派遣で得た
支援ノウハウ等についての資料を発表し、支援ノウハウの共有や支援情報の共有化を図る目的
の会議を実施する。 ・経営支援会議の中で年に1回講師を招聘して、実際の相談案件を講師とともに考えるなどの時
間を設けるようにする。 ・若手経営指導員については、ベテラン経営指導員とチームで個別相談に対応することを通じて、
指導、助言内容、情報収集方法を学ぶなど、OJTにより伴走型の支援能力の向上を図る。
・企業へ各分野の専門家を派遣する場合には、同行することで、売上や利益を確保することを重
視した支援能力の向上を図る。
・会議所内部人事異動で支援ノウハウを持った経営指導員が異動しても、随時OJTをしていく。 ・毎月実施している事務局会議において、組織全体で情報交換・勉強会を行い、職員の能力向上、
ノウハウの共有化を行う。 ③研修会・説明会等への参加(継続)
・長崎県商工会議所連合会、長崎県商工会連合会が主催する「経営指導員応用研修会」、「経営支
援員研修会」をはじめ、日本商工会議所が主催する各種研修会に参加し、総合的な支援能力の
向上に努める。
<第1期における取組と成果、課題>
経営指導員等の資質向上のために「研修会・説明会」に参加することを実施し、そこで得た知
識や情報などを支援に活かせてきた。今後は、小規模事業者支援に直接関係する『対話能力や
ヒヤリング能力の向上』を図ること、『情報の共有の場である経営支援会議の内容充実』を図る
ことについて事業評価委員会で指摘された。 <今回の申請における取組の方向性> 支援ノウハウや関連情報の管理、外部で習得した情報、小規模事業者の経営情報、外部環境情 報、事業計画策定及び事業計画書情報、経営革新・農商工連携事業等の支援ノウハウを、当所 のデータベースとして一元管理する。この情報は、当所経営指導員がパソコン上で閲覧できる と共に支援ノウハウの確認と習得を内部研修会として実施する。また年に1回は外部専門家を 招聘して支援ノウハウ習得の研修会を実施する。また、当所経営指導員及び全職員は、前節の 他の支援機関や関係機関等からの情報、専門家からの支援ノウハウの習得の他、積極的に新た な支援ノウハウ修得のために、関連する各種セミナーや勉強会に参加し、全職員での資質の向 上を図り、人事異動にも対応できるようにする。
- 27 -
・経営指導員は、中小企業大学校等が主催する「専門研修」に参加し、総合的な支援能力の向上
に努める。
・長崎県が主催する「施策普及説明会」、諫早税務署が主催する「決算説明会」等に参加し、総合
的な支援能力の向上に努める。
・経営指導員、経営支援員、一般職員には、中小企業診断士の資格取得を勧奨し、該当する研修
等への参加を通して、総合的、専門的な支援ノウハウの蓄積を図る。
・一般職員は、担当している業務に応じて、日本商工会議所等が主催する「観光振興、IT活用、
商店街振興」等に関する研修会へ参加し、長崎県内商工会議所「事業別担当者会議」に出席し
て、スキルアップとノウハウの共有化に努める。
④データベースの共有化(拡充実施)
・小規模事業者の経営情報、外部環境情報、事業計画策定及び事業計画書情報、経営革新・農商
工連携事業等の支援ノウハウや関連情報の管理、外部で習得した情報を、当所のデータベース
として一元管理する。 ・経営支援に役立つ資料や作成した経営分析結果、事業計画書等は支援の手順や経緯がわかるよ
う工夫してデータ化し、所定の場所に保存して情報を共有化し、人事異動にも対応できるよう
にする。
- 28 -
3.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること
1)事業内容
①事業検証の仕組み(継続)
・当所の会員ではない外部の中小企業診断士、大学教授等の外部有識者から、事業計画策定、実
施支援等、事業支援に係る項目に対して、客観的な立場から半年に一度の頻度で検証をしても
らい、評価と改善点がある場合の指摘をしてもらう ・事業計画策定と実施支援の状況、各種セミナー等の実施と参加人数、効果の評価としての事業
検証を行う。この事業検証は、本経営発達支援計画の「計画P(プラン)、実施D(ドゥー)、
進捗確認と評価としての事業検証であるC(チェック)、その検証でのアドバイスや練り直し活
動の実行であるA(アクション)」のマネジメントサイクルの一貫活動であり、全ての事業に適
応する。 ・事業検証であるC(チェック)は、各事業の数値目標の達成度合い、未達の場合の原因と対策、
支援ノウハウや情報等の活用状況を、事業の種類ごとに年に2回の期間で検証(モニタリング)
する。 ・会議所事務局会議において、達成状況や外部有識者からの助言を考慮した評価・見直しの方針
を決定する。
②検証結果の公開(継続)
事業の成果・評価・見直しの結果については、常議員会へ報告し、承認を受ける。その後、事業
の成果・評価・見直しの結果を諫早商工会議所のホームページ(http://www.isahayacci.com/)
で計画期間中公表する。
<第1期における取組と成果、課題>
毎年度、本計画に記載する事業の実施状況及び成果について、計画の通り実施でき、事業評価委
員会でも特段の指摘を受けることはなかった。
<今回の申請における取組の方向性> 半年に1度の頻度で、本計画に記載の事業の実施状況及び成果についての検証を、外部有識者を
活用して実施する。この検証にて、事業の推進方法の是正を図り、支援事業全体の効果を高める。
また、この検証活動は外部公開するものとする。
- 29 -
(別表2)
経営発達支援事業の実施体制
経営発達支援事業の実施体制
(平成29年4月現在)
(1)組織体制
諫早商工会議所 事務局 専務理事:1名 事務局長:1名
総 務 部:部長1名
総 務 課:一般職員1名、嘱託1名
業 務 課:一般職員4名、嘱託1名
情報管理課:一般職員2名
【経営発達支援事業の実施体制】
中小企業振興部指導課に所属する経営指導員4名と経営支援員2名、一般職員1名を中心に実施。
小規模事業者への事業所訪問による地域経済の活性化に資する取り組みについては、事務局全体で
推進する。
(2)連絡先
諫早商工会議所 中小企業振興部
〒854-0016 長崎県諫早市高城町5番10号
TEL 0957-22-3323 FAX 0957-24-3638
URL http://www.isahayacci.com
E-mail [email protected]
中小企業振興部:課長1名(経営指導員)
指 導 課:経営指導員3名、経営支援員2名、一般職員1名
- 30 -
(別表3)
経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
(単位 千円)
H30年度 (H30年4月以降)
H31年度 H32年度 H33年度 H34年度
必要な資金の額(①+②) 21,040 20,040 20,040 20,040 20,040
① 小規模事業特別会計
(人件費、事務局長設置費を
除く)
※経営発達支援事業関係
講習会開催費
販路拡大支援事業
経営計画作成支援事業
創業支援事業
消費税転嫁対策
中小企業景況調査
② 一般会計
※経営発達支援事業関係
中心市街地活性化事業
部会委員会活動費
地域活性化事業 (まちづくり推進協、地域活性化検討委)
11,290
1,100
200
200
100
100
400
100
9,750
7,250
1,500
1,000
11,290
1,100
200
200
100
100
400
100
8,750
7,250
1,500
未定
11,290
700
200
200
100
100
0
100
8,750
7,250
1,500
未定
11,290
700
200
200
100
100
0
100
8,750
7,250
1,500
未定
11,290
700
200
200
100
100
0
100
8,750
7,250
1,500
未定
(備考)必要な資金の額については、見込み額を記載すること。
調達方法
会費、国補助金、県補助金、市補助金、事業受託費、参加費
(備考)調達方法については、想定される調達方法を記載すること。
- 31 -
(別表4)
商工会及び商工会議所以外の者と連携して経営発達支援事業を実施する場合の連携に関する事項
連携する内容
・「2.経営状況の分析に関すること」においては、長崎県よろず支援拠点、長崎県産業振興財団と連
携して実施する。
・「3.事業計画策定支援に関すること」における「事業計画策定支援」については、長崎県よろず支
援拠点、長崎県中小企業診断士協会と連携。「創業支援」については、諫早市内に本店支店を置く金
融機関と長崎県信用保証協会、日本政策金融公庫長崎支店国民生活事業、長崎県産業振興財団、九州
北部税理士会諫早支部、長崎県宅地建物取引業協会と連携して実施する。
・「4.事業計画策定後の実施支援に関すること」については、中小企業庁のミラサポ、長崎県産業振
興財団、長崎県よろず支援拠点、長崎県中小企業診断士協会、長崎県信用保証協会、諫早市内に本店
支店を置く金融機関と日本政策金融公庫長崎支店国民生活事業と連携して実施する。
・「6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」①展示会・商談会の出展支援について、諫早
市内に本店支店を置く金融機関、長崎県産業振興財団と連携して実施する。
・「6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」④製造関連事業者のマッチング会について、
諫早中核工業団地自治振興会、長崎県金属工業協同組合、諫早工業会と連携して実施する。
・「Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組」②中心市街地活性化事業においては、(株)まちづくり諫早と
ともに当所が設置する「諫早市中心市街地活性化協議会」に、商店街協同組合、公共交通機関、住民
代表、地域経済団体、医療・福祉関係者、有識者、地域メディアなど中心市街地に関係する幅広い構
成団体に参画して頂き、諫早市と連携しながら、「諫早市中心市街地活性化基本計画」で掲げた「賑
わうまち」「ひとが集うまち」「安心して生活できるまち」という活性化の目標を共有し、「協働」で
中心市街地活性化事業に取り組んでいく。
- 32 -
連携者及びその役割
「2.経営状況の分析に関すること」に関する連携 ※連携者は次の通り。役割は、連携体制図に記載する。
名 称 代表者名 住 所 電話番号
長崎県よろず支援拠点
長崎県商工会連合会
会長 宅島壽雄 長崎県長崎市桜町 4番1号長崎商工会館9階
095-828-1462
公益財団法人
長崎県産業振興財団
理事長
田川伸一
長崎県長崎市出島町
2番11号
095-820-3091
「3.事業計画策定支援に関すること」に関する連携 ※連携者は次の通り。役割は、連携体制図に記載する。
名 称 代表者名 住 所 電話番号
公益財団法人
長崎県産業振興財団
理事長
田川伸一
長崎県長崎市出島町
2番11号
095-820-3091
長崎県信用保証協会
会長
田中桂之助
長崎県長崎市桜町
4番1号
095-822-9171
株式会社日本政策金融公庫
長崎支店国民生活事業
支店長兼国民生活事業統括
鶴丸真介 長崎県長崎市大黒町
10番4号
095-824-3141
株式会社十八銀行 代表執行役
森 拓二郎 長崎県長崎市銅座町
1番11号
095-824-1818
株式会社親和銀行 取締役頭取
吉澤俊介
長崎県佐世保市島瀬町
10番12号
0956-23-3576
株式会社西日本シティ銀行
諫早支店
支店長
林 弘喜
長崎県諫早市八天町
5番27号
0957-22-1313
株式会社長崎銀行
諫早支店
支店長
松崎昭彦
長崎県諫早市上町
3番13号
0957-22-3347
たちばな信用金庫 理事長
塚元哲也
長崎県諫早市八坂町
1番10号
0957-22-1379
九州ひぜん信用金庫
諫早支店
支店長
月元 浩
長崎県諫早市永昌町
18番1号
0957-26-3556
九州北部税理士会諫早支部
支部長
光石尚彦
長崎県諫早市本町
6番3号
0957-47-6666
公益社団法人
長崎県宅地建物取引業協会
会長 三上浩二
長崎県長崎市目覚町 3番19号4階
095-848-3888
長崎県よろず支援拠点
長崎県商工会連合会
会長 宅島壽雄 長崎県長崎市桜町 4番1号長崎商工会館9階
095-828-1462
一般社団法人
長崎県中小企業診断士協会
会長 前田愼一郎
長崎県長崎市大黒町 3番1号長崎交通産業会館5階
095-832-7011
諫早市(商工振興部商工観
光課)
市長
宮本明雄
長崎県諫早市東小路町 7番1号
0957-22-1500
- 33 -
「4.事業計画策定後の実施支援に関すること」に関する連携 ※連携者は次の通り。役割は、連携体制図に記載する。
名 称 代表者名 住 所 電話番号
公益財団法人
長崎県産業振興財団
理事長
田川伸一
長崎県長崎市出島町
2番11号
095-820-3091
長崎県信用保証協会
会長
田中桂之助
長崎県長崎市桜町
4番1号
095-822-9171
株式会社日本政策金融公庫
長崎支店国民生活事業
支店長兼国民生活事業統括
鶴丸真介 長崎県長崎市大黒町
10番4号
095-824-3141
株式会社十八銀行 代表執行役
森 拓二郎 長崎県長崎市銅座町
1番11号
095-824-1818
株式会社親和銀行 取締役頭取
吉澤俊介
長崎県佐世保市島瀬町
10番12号
0956-23-3576
株式会社西日本シティ銀行
諫早支店
支店長
林 弘喜
長崎県諫早市八天町
5番27号
0957-22-1313
株式会社長崎銀行
諫早支店
支店長
松崎昭彦
長崎県諫早市上町
3番13号
0957-22-3347
たちばな信用金庫 理事長
塚元哲也
長崎県諫早市八坂町
1番10号
0957-22-1379
九州ひぜん信用金庫
諫早支店
支店長
月元 浩
長崎県諫早市永昌町
18番1号
0957-26-3556
長崎県よろず支援拠点
長崎県商工会連合会
会長 宅島壽雄 長崎県長崎市桜町 4番1号長崎商工会館9階
095-828-1462
一般社団法人
長崎県中小企業診断士協会
会長 前田愼一郎
長崎県長崎市大黒町 3番1号長崎交通産業会館5階
095-832-7011
- 34 -
「6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」①展示会・商談会の出展支援に関する支援等における連携 ※連携先である金融機関や長崎県産業振興財団が主催、共催または後援する商談会等のイベント情報
及び参加する小規模事業者に関する情報の提供を依頼する。
※連携者は次の通り。役割は、連携体制図に記載する。
名 称 代表者名 住 所 電話番号
公益財団法人
長崎県産業振興財団
理事長
田川伸一
長崎県長崎市出島町
2番11号
095-820-3091
株式会社十八銀行 代表執行役
森 拓二郎 長崎県長崎市銅座町
1番11号
095-824-1818
株式会社親和銀行 取締役頭取
吉澤俊介
長崎県佐世保市島瀬町
10番12号
0956-23-3576
株式会社西日本シティ銀行
諫早支店
支店長
林 弘喜
長崎県諫早市八天町
5番27号
0957-22-1313
株式会社長崎銀行
諫早支店
支店長
松崎昭彦
長崎県諫早市上町
3番13号
0957-22-3347
たちばな信用金庫 理事長
塚元哲也
長崎県諫早市八坂町
1番10号
0957-22-1379
九州ひぜん信用金庫
諫早支店
支店長
月元 浩
長崎県諫早市永昌町
18番1号
0957-26-3556
「6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」④製造業ビジネスマッチング会の実施に関する支援等における連携 ※連携先である諫早中核工業団地自治振興会や長崎県金属工業協同組合、諫早工業会に新規取引先
に求める製造技術・部品等に関する要望提出を依頼する。
※連携者は次の通り。役割は、連携体制図に記載する。
名 称 代表者名 住 所 電話番号
諫早中核工業団地
自治振興会
会長
栗林宏光
長崎県諫早市津久葉町
5番49号
0957-25-3333
長崎県金属工業協同組合 代表理事
原田 功
長崎県諫早市貝津町
2148番2号
0957-26-1900
諫早工業会 会長
栗林宏光
長崎県諫早市高城町
5番10号
0957-22-3323
- 35 -
「Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組」②中心市街地活性化事業における連携、③諫早商工会議所 まちづくり推進協議会における連携 ※中心市街地活性化事業では、「諫早市中心市街地活性化協議会」の構成員と連携し、共通の目標を
見据えたうえで、それぞれの立場から中心市街地の活性化に向けた意見を出し合い、活性化事業を
協働で推進していく。
※構成員は次の通り、役割は連携体制図に記載する。
諫早市中心市街地活性化協議会構成員 事業所名 役職 氏 名 住 所
協議会を組織できる者 諫早商工会議所 会頭 黒田 隆雄 諫早市高城町5番10号
協議会を組織できる者 (株)まちづくり諫早 代表取締役 山田 和弘 諫早市本町3番11号
商業活性化 諫早市栄町商店街協同組合 理事長 平野 吉隆 諫早市栄町3番25号
諫早市永昌東町商店街協同組合 副理事長 本田 一修 諫早市永昌東町9番23号
天満町商工振興会 会長 中原 信行 諫早市天満町3番4号
公共交通機関 JR九州諫早駅 駅長 井手 靖則 諫早市永昌町1番1号
島原鉄道(株)常務取締役 常務取締役 林田 邦彦 島原市弁天町2丁目7385番1号
長崎県交通局 営業部長 小川 雅純 長崎市八千代町3番1号
市街地の整備改善 (有)諫早観光ホテル道具屋 代表取締役 藤原 貞明 諫早市金谷町8番7号
住民代表 いさはや国際交流センター 事務局 岩本 頼子 諫早市多良見町化屋1800番
元諫早地域審議会 元会長 勢野 雄一 諫早市日の出町52番1号
栄町町内会 町内会長 栄木 剛洋 諫早市栄町3番26号
地域経済代表 日本郵便(株)諫早郵便局 郵便担当局長 下村 英雄 諫早市八坂町1番7号
諫早銀行協会(たちばな信用金庫) 本店営業部長 早田 義教 諫早市八坂町1番10号
(一社)諫早青年会議所 理事長 嶋田 雅之 諫早市宇都町9番2号諫早文化会館内
(一社)諫早観光物産コンベンション協会 会長 酒井 明仁 諫早市高城町5番10号
開発・整備 (公社)長崎県宅地建物取引業協会諫早支部 支部長 敷島 知章 長崎市目覚町3番19号長崎県不動産会館
医療・福祉 天満太鼓 指導者 友永 綾子 諫早市天満町1650番
高齢者福祉施設 代表者 園田 義夫 諫早市幸町12番9号(株)思想念
有識者 長崎ウエスレヤン大学 学長 佐藤 快信 諫早市西栄田町1212番1
長崎ビジネス支援プラザ 所長 山口 由里子 長崎市出島町2番11号出島交流会館8階
地域メディア 諫早ケーブルテレビジョン放送(株) 代表取締役 南 浩一郎 諫早市福田町18番23号
環境・コミュニティ 諫早タクシー協会(湯江タクシー(有)) 会長 内田 輝美 諫早市高来町三部壱397番3号
諫早図書館友の会 副会長 野田 告枝 諫早市松里町749番1号
行政 国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務所 副所長 平井 新太郎 長崎市宿町316番1号
諫早市 諫早市商工振興部 商工振興部長 藤山 哲 諫早市東小路町7番1号
諫早商工会議所 諫早商工会議所 専務理事 森 康則 諫早市高城町5番10号
- 37 -
「3.事業計画策定支援に関すること」における連携体制図
長崎県
産業振興財団
長崎県
よろず支援拠点
諫早商工会議所
九州北部税理士会
諫早支部
十八銀行
親和銀行
西日本シティ銀行
諫早支店
長崎銀行諫早支店 たちばな信用金庫
九州ひぜん信用金庫
諫早支店
日本政策金融公庫
長崎支店国民生活事業
<金融機関>
長崎県
信用保証協会
長崎県宅地建物
取引業協会
長崎県中小企業
診断士協会
創業窓口・情報共有 税務支援
情報提供・専門家派遣 創業セミナー
情報共有
専門家派遣
情報共有
専門家派遣
新事業・創業
支援 空き店舗
情報提供
創業フォロー
情報共有
諫早市
創業窓口 情報共有
金融支援・創業窓口・情報共有
- 38 -
「4.事業計画策定後の実施支援に関すること」に関する連携体制図
長崎県
産業振興財団
長崎県
よろず支援拠点
諫早商工会議所
九州北部税理士会
諫早支部
十八銀行
親和銀行
西日本シティ銀行
諫早支店
長崎銀行諫早支店 たちばな信用金庫
九州ひぜん信用金庫
諫早支店
日本政策金融公庫
長崎支店国民生活事業
<金融機関> 長崎県
信用保証協会
長崎県中小企業
診断士協会
情報共有・税務支援 情報提供・専門家派遣
情報共有
専門家派遣
各種セミナー
情報共有
専門家派遣
金融支援 情報共有
情報共有 信用保証
長崎県
諫早市
- 39 -
「6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」①展示会・商談会の出展支援に関する支援等における連携体制図
地域小規模事業者
商談会・展示会等
への参加・出店
新たな需要の開拓
・各種商談会・展示会の
情報提供 ・事前準備、事後フォロ
ーに関する支援
諫早商工会議所
・各種商談会、セミナー
の開催 ・参加申込受付
たちばな信用金庫
・各種商談会、セミナー
の開催
親和銀行 ・各種商談会の開催 ・参加申込受付
十八銀行
・各種商談会の開催 (百貨店・スーパー等)
西日本シティ銀行
諫早支店
・各種商談会の開催 ・参加申込受付
長崎銀行
諫早支店
・商談会説明会の開催 ・参加申込受付
九州ひぜん信用金庫
諫早支店
・各種商談会の開催 長崎県産業振興財団
- 40 -
「6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること」④製造業ビジネスマッチング会に関する支援等における連携体制図
地域小規模事業者
製造業マッチング会
への参加・商談
新たな需要の開拓
・ニーズ調査の実施 ・データの整理・登録 ・事前準備、事後フォロ
ーに関する支援
諫早商工会議所
製造技術・部品等に関す
る要望、ニーズの提供
諫早中核工業団地
自治振興会
製造技術・部品等に関す
る要望、ニーズの提供
長崎県金属工業
協同組合
製造技術・部品等に関す
る要望、ニーズの提供
諫早工業会
- 41 -
「Ⅱ.地域経済の活性化に資する取組」②中心市街地活性化事業に関する連携体制図
諫早市中心市街地活性化協議会
諫早市栄町商店街協同組合、諫早市永昌東町商店街協
同組合、天満町商工振興会、JR九州諫早駅、島原鉄
道(株)、長崎県交通局、(有)諫早観光ホテル道具屋、 日本郵便(株)諫早郵便局、国土交通省九州地方整備
局長崎河川国道事務所、いさはや国際交流センター 元諫早地域審議会、栄町町内会、諫早銀行協会、(一
社)諫早青年会議所、(一社)諫早観光物産コンベン
ション協会、(公社)長崎県宅地建物取引業協会諫早
支部、天満太鼓、高齢者福祉施設、長崎ウエスレヤン
大学、長崎ビジネス支援プラザ、諫早ケーブルテレビ
ジョン放送(株)、諫早タクシー協会、諫早図書館友
の会
(株)まちづくり諫早 諫早商工会議所 + 中心市街地活性化
基本計画
諫早市
商工観光課 都市政策課 企画政策課 地域振興課
生活安全交通課 福祉総務課
・基本計画に関する検討及び意見提出 ・民間事業に関する発掘・調査、事業支援 ・中心市街地の活性化に関する社会調査の検討及び実施 ・まちづくりセミナー等の開催 ・先進地事例の調査、研究
意見具申
報 告
中心市街地活性化
「賑わうまち」
「ひとが集うまち」
「安心して生活できるまち」
中心市街地の賑わい創出
・中心市街地活性化基本計画の推進・実施