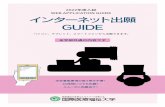平成29年度 試験研究成果普及カード - Gifu Prefecture · 2018-03-28 · 1...
Transcript of 平成29年度 試験研究成果普及カード - Gifu Prefecture · 2018-03-28 · 1...

平成29年度
試験研究成果普及カード
農業技術センター
中山間農業研究所
畜産研究所
水産研究所
岐阜県
平成30年3月

目 次
【農業技術センター】
・トマト独立ポット耕冬春作型における葉先枯れ症軽減技術 1
・トマト土耕栽培(冬春・夏秋作型)における葉先枯れ症軽減のためのカリ施肥基準 3
・トマト土耕栽培(冬春・夏秋作型)における葉先枯れ症の摘葉処理による発生軽減 5
・高糖度でサクサクとした食感を持つカキ新品種「ねおスイート」 7
・パッションフルーツ夏実の収量向上のための仕立て方法及び基肥一発施肥方法 9
・カキの樹幹害虫対策はヒメコスカシバを中心に体系的に組み立てる 11
・茶の各種樹体情報に基づいた被覆可否の判断基準 13
・水田及び畑土壌の可給態窒素が簡易迅速に評価できる 15
【中山間農業研究所】
・東濃地域で栽培されているエゴマ品種系統の特性と最適な作期 17
・夏秋トマトのナス台木を利用した晩期セル苗直接定植作型 19
・飛騨地域の夏秋トマト栽培に適した品種「麗月」、「桃太郎ワンダー」 21
・ホウレンソウ調製作業の省力化のための高能率調製機の開発 23
・「宿儺かぼちゃ」の早期作型は高品質、多収化に有効である 25
・リンゴ「ふじ」のミツ入り状態を判別する市販の判定機で長期貯蔵向け果実を
判別できる
27
・フランネルフラワーの発芽率を低下させない種子の貯蔵法 29
【畜産研究所】
・基幹種雄牛として選抜された「孝た か
隆りゅう
平だいら
」の特徴 31
・過剰排卵処理と経腟採卵を組み合わせた乳用牛胚の大量生産技術 33
・県内で生産される牧草のミネラル組成と土壌化学性 35
・肥育豚への精米給与が豚肉のおいしさに及ぼす影響 37
・採卵鶏における飼料用米(籾)の長期給与 39
【水産研究所】
・アユの遡上のない河川でのアユ早期小型放流技術の有効性 41

- 1 -
トマト独立ポット耕冬春作型における葉先枯れ症軽減技術
【要約】トマト独立ポット耕冬春作型において、培養液中のカリウム濃度を6me/L まで
高めると、収量を低下させることなく葉先枯れの発症が軽減される。また、葉面散布を組み
合わせることで葉先枯れ症がさらに軽減される。
農業技術センター 野菜・果樹部 【連絡先】058-239-3133
【背景・ねらい】
トマトの葉先枯れ症は、一般に葉中のカリウム不足が原因とされる生理障害である。その
発症部位は灰色かび病の一次感染源となり、収量の減少を招くため、産地で問題となっている。
そこで、トマト独立ポット耕の冬春作型における培養液中のカリウム濃度の差異並びに配合
肥料の葉面散布による葉先枯れ症の軽減効果について明らかにする。
【成果の内容・特徴】
1 葉先枯れの発症程度は、栽培期間を通して培養液中のカリウム濃度(慣行濃度4me/L、
高濃度6 me/L、極高濃度8 me/L)を高めるにつれて、発症程度が小さくなる(図1)。
2 培養液中のカリウム濃度を高め(6 me/L)、カリウム主体の葉面散布剤を 100 倍希釈で
2週間に1回、茎葉及び果房に散布すると、慣行濃度より葉先枯れの発症程度が大幅に
小さくなる(図2)。
3 培養液中のカリウム濃度を高めると、慣行濃度より可販果1果重がやや減少するが、可販
果収量では大きな差はみられない(表1)。極高濃度(8 me/L)では、6月に尻腐れ果の
発生が多くみられる(データ略)。
4 葉面散布を行うと、可販果 1 果重、可販果収量がやや増加する(表2)。
【成果の活用・留意点】
1 供試品種を「CF 桃太郎 J」とし、栽植密度は 2,500 本/10a、冬春作型(8月上旬定植、
6月下旬栽培終了)で得られた結果である。
2 培養液組成は、山崎トマト処方を基にカリウム濃度のみを異にし、硝酸カリ、第一リン酸
カリ、硫酸カリで調整した。他の培養液処方では組成が異なるため、各処方でカリウム濃度
の調整及び適正値の決定が必要である。
3 本試験では、カリウム濃度を高めたことによる果実糖度への影響はみられなかった。
4 本試験では、灰色かび病予防として定期的に殺菌剤の散布を行ったため、灰色かび病に
よる収量の減少はみられなかった。
5 葉面散布により株が濡れ、病害の発生が懸念されるため、葉面散布を行う際は、散布した
液が乾きやすい条件下で行う。

- 2 -
【具体的データ】
表1 培養液中のカリウム濃度の違いが収量に及ぼす影響(平成 27~28年)
表2 培養液中のカリウム濃度の違い及び葉面散布の有無が収量に及ぼす影響(平成 27~28年)
研究課題名:戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「次世代農林水産業創造技術」良果率
向上によるトマト高品質・多収栽培管理技術の開発および実証(平成 26~30年度)
研究担当者:前田健、小田桃子
総収量 可販果収量 可販果1果重 尻腐れ果
(g/株) (g/株) (g) (個/株)
極高濃度 11,139 10,307 143 8.8
高濃度 11,921 10,944 143 4.4
慣行濃度 10,794 10,404 151 0.6
試験区
図1 培養液中のカリウム濃度の違いが
葉先枯れ発症程度に及ぼす影響
(平成 27~28年)
図2 培養液中のカリウム濃度の違い
及び葉面散布の有無が葉先枯れ
発症程度に及ぼす影響
(平成 27~28年)
総収量 可販果収量 可販果1果重 尻腐れ果
培養液 葉面散布 (g/株) (g/株) (g) (個/株)
無散布 10,735 9,973 151 3.4
散布 11,239 10,427 155 3.6
無散布 10,811 10,065 159 2.8
散布 11,855 11,180 165 1.5
試験区
高濃度
慣行濃度
0
10
20
30
40
50
60
70
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
発症
程度
調査月
慣行濃度 高濃度 極高濃度
0
10
20
30
40
50
60
70
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
発症
程度
調査月
慣行・無散布
慣行・散布
高濃度・無散布
高濃度・散布
※発症程度は障害の程度により 0~4の 5段階で
評価し、調査葉の合計値×100/調査葉数×4で
算出した

- 3 -
トマト土耕栽培(冬春・夏秋作型)における葉先枯れ症軽減のためのカリ施肥基準
【要約】トマト土耕栽培(冬春・夏秋作型)における葉先枯れ症を軽減するために、施肥前
の土壌中の交換性カリ含量と果実の目標収量に基づいた施肥基準を設定した。
農業技術センター 土壌化学部、野菜・果樹部 【連絡先】058-239-3135
中山間農業研究所 試験研究部(①)、中津川支所(②) 【連絡先】①0577-73-2029 ②0573-72-2711
【背景・ねらい】
トマト葉先枯れ症の発生部位は難防除病害である灰色かび病の発生源となるため、県内産地
で大きな問題となっている。そこで、発生の主な要因はカリウム欠乏とされていることから、
土耕栽培(冬春・夏秋作型)における葉先枯れ症を軽減するために必要なカリの施肥量を明ら
かにし、施肥基準を設定する。
【成果の内容・特徴】
1 冬春作型、夏秋作型でのトマトの栽培期間中のカリ吸収量は、果実総収量1t あたり4kg
程度である(表1)。
2 トマト作物体中のカリウム濃度は土壌中の交換性カリ含量が高まると上昇し、次第に頭打
ちとなる。この傾向は土壌の種類が異なっても同様であり、交換性カリ 30mg/100g における
作物体のカリウム濃度の指数は 95%程度となる(図1)。
3 葉先枯れ症の発生軽減のためには、作土の交換性カリ含量 30mg/100g以上を確保した上で、
吸収量分として目標総収量1tあたり4kg/10aを施肥することを基準とする(表2)。
4 基準量の施肥により、葉先枯れ症の軽減、葉中のカリウム濃度の上昇及び秀優品収量の
増加効果が認められる(図2、図3、表3)。
5 施肥量の増加により、葉中のカリウム濃度及び葉先枯れ症軽減効果は高まるものの、過剰
量となった場合はともに頭打ちになる(図2、図3)。
6 施肥量が過剰となった場合の収量への影響は判然としない(表3)。
【成果の活用・留意点】
1 本試験では不足分を補うためのカリ資材に硫酸カリを用いている。
2 施肥量は、施肥前の土壌診断により土壌中の交換性カリ含量を把握した上で基準に基づい
て算出する。
3 土壌診断の結果、土壌中の交換性カリ含量が 30mg/100g 以上であった場合は、余剰分を
吸収量分から減らして施肥することが可能である。
4 カリ施肥量の計算には、基肥の他、土壌診断後施用される堆肥等や作付け期間中の液肥
から供給される量も含める。
5 カリの適正量施肥に摘葉処理やカリ資材の葉面散布を組み合わせることで、発生軽減効果
はより高くなる。

- 4 -
【具体的データ】
研究課題名:清流の国ぎふ・農畜水産ナンバー1 プロジェクト事業「岐阜県発のオリジナルトマト栽培システムを発展させた革新的(安い、簡単、獲れる)技術による生産量倍増」 葉先枯れ症の対策技術の確立(平成 26~30年度)
研究担当者:鈴木郁子、小田桃子、浅野雄二、服部哲也
試験区の( )内:[施肥前の土壌中カリ含量(mg/100g)] +[カリ施肥量(kg/10a)]
吸収量分施肥量:表 2 の計算式に基づき、吸収量分として施肥した量。「-10」は 30mg/100g への不足量を示し、吸収量分は0
葉中のカリウム濃度:ピンポン玉大果房の直下葉の先端 3 小葉を調査、凡例の( )内:表3の「吸収量分施肥量」と同じ
表1 トマトのカリ吸収量
指数:同一試験区内での最大値を 100 とした時の値
表2 カリ施肥基準
表3 施肥量の果実収量への影響
図2 施肥量の発生程度への影響
(平成 25-26年、冬春作型)
0
20
40
60
80
100
120
0 10 20 30 40 50 60 70
指数
(作物体中のカリウム濃度
)
土壌中の交換性カリ含量(mg/100g)
褐色森林土(CEC8.2)
褐色低地土M(CEC9.8)
褐色低地土N(CEC15.6)
黒ボク土(CEC37.5)
図1 土壌中のカリ含量とトマトのカリ吸収の
関係(ポット試験)
*仮比重が不明な場合は、おおよその値として黒ボク土は0.7、その他の土壌は1を用いる
土壌中の交換性カリ含量(30mg/100g)
カリ吸収量(4kg/t×目標収量t/10a)+カリ施肥量 =
作土部分のカリ含量を30mg/100g以上を確保し、目標収量に必要なカリ量を施肥
計算式
カリ施肥量(kg/10a)= [(30-土壌中の交換性カリ含量)(mg/100g)× ×仮比重] + 4(kg/t)×目標収量(t/10a)作土深(cm)
10
土壌中のカリ含量の補正分 吸収量分
不足 基準 過剰 不足 基準 過剰 不足1 不足2 基準 過剰1 過剰2吸収量分施肥量(kg/10a) -10 92 156 10 107 158 3 73 40 88 160収穫果数 (果/株) 110 116 109 142 144 140 146 151 58 58 57平均果重 (g/果) 177 177 198 162 171 181 191 204 185 183 188粗収量 (t/10a) 19.5 20.6 21.6 23.1 24.7 25.4 28.0 30.8 10.8 10.7 10.7可販収量 (t/10a) 17.2 20.0 20.8 21.7 23.4 24.7 25.5 28.9 9.1 8.9 9.0秀優品収量 (t/10a) 14.0 16.5 16.6 16.5 17.9 18.4 15.1 17.6 7.6 7.0 7.2
H25-26 冬春 H26-27 冬春 H27-28 冬春 H29 夏秋
0
2
4
6
12/25 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25
葉中のカリウム濃度(%) 不足(-10)
基準(92)
過剰(156)
0
10
20
30
40
50
12/25 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25
発生程度
不足(-10)
基準(92)
過剰(156)
図3 施肥量の葉中のカリウム濃度への影響
(平成 25-26年、冬春作型) 発生程度:開花花房直下葉から下 5 枚の発生程度を、発生位置に基づいて以下の 5 段階で評価、数値化した。発生なし→0、先端小葉のみ→25、先端から 1/3 まで→50、先端から 2/3 まで→75、先端から 2/3以上→100、凡例の( )内:表3の「吸収量分施肥量」と同じ
面積あたり 収量あたり(t/10a) (kg/10a) (kg/t)
冬春 H26-27 (11+48) 23.1 80.1 3.5(24+120) 24.7 89.4 3.6(49+120) 25.4 97.5 3.8
H27-28 (20+23) 28.0 87.9 3.1(16+106) 30.8 108.3 3.5
H28-29 (22+101) 24.9 97.5 3.9夏秋 H25 (45+31) 16.0 60.2 3.8
(45+56) 15.6 61.1 3.9
果実収量カリ吸収量
試験区

- 5 -
トマト土耕栽培(冬春・夏秋作型)における葉先枯れ症の摘葉処理による発生軽減
【要約】トマト土耕栽培(冬春・夏秋作型)では、開花花房の反対側に位置する複葉を取り
除く「摘葉処理」により、葉先枯れ症が軽減できる。
農業技術センター 土壌化学部、野菜・果樹部 【連絡先】058-239-3135
中山間農業研究所 試験研究部(①)、中津川支所(②) 【連絡先】①0577-73-2029 ②0573-72-2711
【背景・ねらい】
トマト葉先枯れ症は、発生部位が難防除病害である灰色かび病の発生源となることから大き
な問題となっている。対策としてカリ施肥の適正化を提案しているが、本対策のみでは発生を
完全に抑制することは困難であり、補完的な技術が求められている。
施設トマト栽培において、葉面積指数を適正に管理するとともに果房を充実させる技術とし
て「摘葉処理」が導入されつつある。そこで、冬春作型及び夏秋作型における摘葉処理の葉先
枯れ症の抑制に対する効果を明らかにする。
【成果の内容・特徴】
1 冬春作型、夏秋作型ともに、花房の反対側に位置する複葉の摘葉処理により葉先枯れ症の
発生が軽減される(図1、図2)。
2 摘葉処理により、葉先枯れ症の初発部位である開花花房付近の葉ではカリウム濃度が上昇
する。ピンポン玉大果房付近の葉では、摘葉処理によるカリウム濃度の上昇は見られない
(図3)。
3 発生と開花花房付近の葉中濃度の変動には相反する動きが見られ、葉中のカリウム濃度の
上昇は葉先枯れ症の発生軽減に関与していると考えられる(図1、図3)。
4 冬春作型においては、2 月中旬以降、摘葉処理を止めても葉先枯れ症の発生軽減効果は
持続する傾向が認められる(図4)。
5 摘葉処理による収量への影響は年次により異なり、増減に対する一定の傾向は認められ
ない(表1)。
【成果の活用・留意点】
1 摘葉処理の実施の目安は、開花始め頃までとする。
2 本試験では第3花房から摘葉処理を開始した。
3 冬春作型での発生軽減効果は時期によって異なり、12月頃の発生に対しては、他の時期と
比較して効果が小さい傾向がある。
4 摘葉処理はトマトの樹勢や生育バランスに影響を及ぼすことから、生育状況や日射条件、
葉先枯れ症の発生状況をみて実施を判断する必要があり、樹勢が弱い場合等には避ける。
5 カリの適正量施肥やカリ資材の葉面散布を組み合わせることで、発生軽減効果はより高く
なる。

- 6 -
【具体的データ】
研究課題名:清流の国ぎふ・農畜水産ナンバー1 プロジェクト事業「岐阜県発のオリジナルトマ
ト栽培システムを発展させた革新的(安い、簡単、獲れる)技術による生産量倍増」
葉先枯れ症の対策技術の確立(平成 26~30年度)
研究担当者:鈴木郁子、小田桃子、浅野雄二、服部哲也
調査部位:開花花房もしくはピンポン玉大果房下の葉の先端 3小葉、凡例()内:調査葉の位置
葉位:4 は第 4~5 花房の葉を示す。発生程度:各花房間 3 枚の葉の発生程度、評価方法は図 1 と同じ
凡例の( )内:摘葉処理の終了日、発生程度:図1と同じ
図1 摘葉処理の発生程度への影響
(平成 28~29年、冬春作型)
0
20
40
60
11/10 1/10 3/10 5/10
発生程度
無処理
摘葉
0
20
40
60
4 5 6 7 8 9 10
発生程度
葉位
無処理
摘葉
図2 摘葉処理の発生程度への影響
(平成 29年、夏秋作型)
表1 摘葉処理の果実収量への影
響
図3 摘葉処理の葉中カリウム濃度への影響
(平成 28~29年、冬春作型)
0
20
40
60
2/3 3/3 4/3 5/3
発生程度
無処理 摘葉(2/10)
摘葉(3/25) 摘葉(5/13)
0
2
4
6
11/10 1/10 3/10 5/10
葉中のカリウム濃度(%)
無処理(開花)
摘葉(開花)
無処理(ピンポン玉大)
摘葉(ピンポン玉大)
発生程度:開花花房直下葉から下 5 枚の発生程度を発生位置に基づいて以下の 5 段階で評価、数値化した。発生なし→0、先端小葉のみ→25、先端から 1/3 まで→50、先端から 2/3 まで→75、先端から 2/3 以上→100
無処理 摘葉 無処理 摘葉 無処理 摘葉
収穫果数 (果/株) 148 140 120 117 36 35平均果重 (g/果) 191 188 207 218 201 198粗収量 (t/10a) 28.3 26.3 24.9 25.5 16.1 15.3可販収量 (t/10a) 26.8 24.9 24.5 25.2 13.8 13.2秀優品収量 (t/10a) 16.2 15.3 15.7 14.3 9.8 9.5
H27-28冬春 H28-29冬春 H29夏秋
図4 効果の持続性(平成 27~28年、冬春作型)

- 7 -
高糖度でサクサクとした食感を持つカキ新品種「ねおスイート」
【要約】本県において 10月中下旬に収穫できる完全甘ガキ品種「ねおスイート」を育成した。
果頂部が平均 20度を超える高糖度で、「太秋」の様なサクサクとした食感を有する。
農業技術センター 野菜・果樹部 【連絡先】058-239-3133
【背景・ねらい】
岐阜県は、甘柿主体の産地を形成しているが、品種構成が晩生の「富有」に偏重しており、
労力分散や販売面での出荷期間の延長などにおいて優良な早生・中生の完全甘ガキ品種が求め
られている。中生の「太秋」は、サクサクとした食感を持ち消費者からの評価が高いが、大玉
で値ごろ感が低いこと、樹勢が低下しやすく収量が安定しないことから、現状では基幹品種に
成り得ていない。そこで、①10月に収穫できる完全甘ガキ、②良食味でサクサク感を有する、
③中玉で収量性に富むことを育種目標として品種育成し、特性を明らかにする。
【成果の内容・特徴】
1 育成経過
「ねおスイート」(写真 1)は、平成 17年に「新秋」に「太秋」を交配して得た実生から
選抜し、平成 27年に品種登録出願、平成 29年に品種登録された(登録番号第 25654 号)。
2 特性
(1)生育
育成地における開花期、収穫期などの生育相は「太秋」、「松本早生富有」とほぼ同程度
である(表 1)。生理落果は早期落果、後期落果ともに少ない。
(2)樹の特性
樹勢はやや強く、開帳性であり、良質な結果母枝が多い。雄花、雌花及び完全花を着生
するが、雄花と完全花の着生は下位節から伸びた弱い新梢に多く、上位節からの新梢には
安定的に雌花を着生するため、収量性に影響しない。
(3)果実特性
果実重は 255g(平成 26 年)で「松本早生富有」と同等、「太秋」より 100g 程小さい(L・2L
が 70%)。収穫時の果皮色はカラーチャート値 5.0に達し、「太秋」より着色に優れる(表2)。
収穫果実の糖度 19~20 度ならびに 20 度以上の果実の割合がそれぞれ約 40%を占めて
おり、極めて高糖度である(図1)。糖組成はスクロースが約半分を占め、フルクトース
含量が高いため、糖度以上に甘さを感じる(表3)。
果肉の硬さは「太秋」よりやや硬く、食感は「太秋」と同様にサクサク感を有する。また、
環状で細かい条紋が果頂部周辺に発生しやすい(写真2)が、果頂裂果は認められず、へた
すきの発生は少ない。
【成果の活用・留意点】
1 条紋が発生するため、黒変しやすい。成熟期の降雨が多い年や風通しの悪い園地では、
多発する場合があるため、袋掛けや光反射資材の敷設よる対策が必要である。
2 高接ぎによる増殖は、雄花の増加、樹上軟化や収穫後の日持ち性の低下、条紋の助長等に
よる収量性・商品性への影響が大きくなると考えられるため、導入は苗木の植栽によること
が適当と考えられる。
3 一定品質を満たした系統共販果実は、「天下富舞®」の商標名で JA全農岐阜にて販売されている。

- 8 -
【具体的データ】
研究課題名:カキの岐阜オリジナル品種の育成と新高接ぎ法による品種更新技術の開発
(平成 26~30年度)
研究担当者:杉浦真由、新川猛、鈴木哲也
写真2 果実表面に生じる微細な条紋果実表面に生じる微細な条紋
写真1 ‘ねおスイート’
表1 各品種のほう芽期、展葉期、開花期ならびに収穫期
始期 盛期 終期 始期 盛期 終期ねおスイート 3月21日 4月12日 5月21日 5月22日 5月25日 10月16日 10月23日 11月1日
太秋 3月21日 4月10日 5月19日 5月20日 5月24日 10月16日 10月23日 11月2日松本早生富有 3月19日 4月11日 5月20日 5月22日 5月25日 10月21日 10月28日 10月31日
新秋 3月19日 4月11日 5月19日 5月20日 5月23日 10月11日 10月13日 10月17日
品種名 ほう芽期 展葉期開花期 収穫期
図1 収穫果実の糖度別割合
表2 各品種の収穫時の果皮ならびに果肉のカラーチャート値第4表 各品種の収穫時の果皮ならびに果肉のカラーチャート値
果肉色
果頂部 果胴部 果底部 CC値換算ねおスイート 5.8 5.3 5.0 4.3 10月28日
太秋 4.7 ** 4.0 ** 4.1 ** 3.8 ** 10月30日松本早生富有 5.8 ns 5.5 ns 5.4 ns 4.6 ** 10月30日
新秋 6.2 ns 6.0 ** 5.2 ns 4.9 ** 10月10日ねおスイート 6.0 5.8 5.8 4.3 10月22日
太秋 4.2 ** 3.8 ** 3.6 ** 3.9 ** 10月22日松本早生富有 5.3 ** 5.4 ns 5.9 ns 5.6 ** 10月28日
新秋 5.9 ns 5.2 ns 4.2 ** - 10月15日ねおスイート 6.0 5.6 5.8 - 10月26日
太秋 4.8 ** 4.3 ** 4.0 ** - 10月29日松本早生富有 5.5 ns 5.5 ns 5.9 ns - 10月31日
新秋 5.0 ** 4.4 ** 3.5 ** - 10月11日
2012
・同一年度の列間における**はねおスイートに対してDunnettの多重比較により1%水準で有意であること、nsは有意でないことを示す・-はデータなし
年度 品種名果皮色(カラーチャート値)
調査日
2014
2013
表3 完全甘ガキ中生品種の糖組成(2016年)フルクトース グルコース スクロース 全糖量z ショ糖率y
(%) (%) (%) (%) (%)ねおスイート 7.9 7.3 10.4 25.7 40.6
太秋 4.4 2.6 13.7 20.7 66.3貴秋 7.5 6.9 1.5 15.8 9.2
松本早生富有 3.0 0.1 17.8 20.9 85.4z単糖二類とスクロースの合計y全糖含量の内、ショ糖が占める割合
品種名
(平成 26年)
(平成 24年から平成 26年の平均)
H26
(平成 28年)
H25
H24

- 9 -
パッションフルーツ夏実の収量向上のための仕立て方法及び基肥一発施肥方法
【要約】単年度栽培パッションフルーツにおける夏実の収量向上のための仕立て方法及び
基肥一発施肥方法を確立した。一文字仕立て、窒素施用量 140g/樹、LP コート 100 と IB
化成の組み合わせ割合9:1で栽培することで、収量は約 0.6t/10aとなる。
農業技術センター 野菜・果樹部 【連絡先】058-239-3131
【背景・ねらい】
岐阜県では冬季の気温が低く、露地におけるパッションフルーツの栽培が困難であり、挿し
木苗を4~5月に定植して 12月まで収穫する栽培が行われている。パッションフルーツは夏季
の高温期に花芽が着生しないため、本作型では6~7月と9月に開花し、果実は8~9月
(夏実)と 11 月以降(冬実)に収穫するが、夏実は樹体の生育が十分でないため開花数
が少なく収量は 0.1t/10a 程度と低い。そこで、収量の向上を図るため、仕立て方法及び基肥
一発施肥方法を確立する。
【成果の内容・特徴】
1 一般的な仕立て方法である逆L字仕立てと初期に発生する副梢を主枝上に伸ばし、それに
着生する花芽を利用する一文字仕立て(いずれの栽培も窒素施肥量 50g/樹)の2つ仕立て方
法を比較すると、夏実の開花数は一文字仕立てが逆L字仕立てよりも多くなる(図1、図2)。
2 定植~夏実収穫までの窒素施用量及び施肥資材の検討結果から、収量及び果実重は窒素
施用量 210g/樹と 140 g/樹が 70g/樹よりも優れる(表1)。施肥資材による収量並びに
果実重の差は認められない(表1)。また、窒素施用量、施肥資材による果実品質の差は
認められない(データ略)。
3 定植~夏実収穫までの窒素施用量を 140g/樹として、IB化成単独よりも肥料代や施肥作業
が軽減される LPコート 100と IB化成の組み合わせ施肥方法における施肥資材の割合を検討
した結果、収量、果実重及び果実品質の差は認められない(表2)。
4 肥料代や作業性を加味すると、窒素施用量は 140g/樹、LPコート 100と IB化成の組み合
わせ割合9:1が最も実用的である。なお、本施肥方法により一文字仕立てで栽培した場合
の夏実の収量(栽植密度:株間 2.5m×列間 2.5m、160 樹/10a)は約 0.6t/10a となる。
【成果の活用・留意点】
1 仕立て方法の試験は、岐阜県に約 10 年前に導入され、挿し木繁殖で維持されてきた紫玉
系統、施肥方法の試験は「サマークイーン」を供試した。
2 表1、表2の各試験区は基肥や追肥方法がそれぞれ異なるが、最も実用的であった表2の
LPコート 100:IB化成=90:10区は、基肥として IB 化成を窒素施用量 14g/樹、LPコート
100を窒素施用量 126g/樹施用した。

- 10 -
【具体的データ】
表1 窒素施用量と施肥資材が開花数、収量及び果実重に及ぼす影響(平成28年)
表2 施肥資材の割合が開花数、収量及び果実重に及ぼす影響(平成29年)
研究課題名:露地栽培における加工用パッションフルーツの安定生産技術の開発(平成 26年度)、
内陸部における加工用パッションフルーツの栽培技術開発(平成 28~30 年度)
研究担当者:鈴木哲也、新川猛、杉浦真由
図2 仕立て方法が開花数に及ぼす影響 (平成 26年)
縦線は標準誤差を示す 窒素施用量 50g/樹
図1 仕立て方法 (左:逆L字仕立て、右:一文字仕立て)
第2表 施肥資材の割合が開花数,収量および果実重に及ぼす影響
試験区 開花数/樹 収穫果数/樹 収量/樹 結実率 果実重 肥料代/樹(LPコート100とIB化成の窒素施用量の割合) (花) (果) (kg) (%) (g) (円)
LPコート100:IB化成=90:10 51.8 39.5 3.2 78.3 81.9 95LPコート100:IB化成=75:25 50.5 38.0 3.3 76.2 86.6 117LPコート100:IB化成=50:50 51.5 42.8 3.4 82.9 79.1 153
分散分析z ns ns ns ns ns -z分散分析により,nsは有意差なし
第1表 窒素施用量と施肥資材が開花数,収量および果実重に及ぼす影響
開花数/樹 収穫果数/樹 収量/樹 結実率 果実重 肥料代/樹
(施肥資材) (窒素施用量/樹) (花) (果) (kg) (%) (g) (円)
IB化成 210g 53.0abcz 36.5ab 3.1ab 69.1 83.6 340
140g 51.5bc 35.5ab 3.0ab 69.1 86.0 22770g 54.0abc 32.0ab 2.4bc 59.8 75.0 113
LPコート100+IB化成y 210g 70.4a 45.0a 3.7a 63.6 81.5 230
140g 63.5ab 43.8a 3.6a 69.0 81.1 15370g 41.0c 23.6b 1.8c 58.2 74.7 77
施肥資材 ns ns ns ns ns -
分散分析v 窒素施用量 ** ** ** * ** -
交互作用 ** * * ns ns -zTukey-Kramerの多重検定により,同一列の異符号間に5%水準で有意差あり(n=4~5)yLPコート100とIB化成の窒素施用量の割合は50:50v二元配置分散分析により,**は1%,*は5%水準で有意差あり,nsは有意差なし
試験区
仕立て方法:一文字仕立て
仕立て方法:一文字仕立て

- 11 -
カキの樹幹害虫対策はヒメコスカシバを中心に体系的に組み立てる
【要約】カキの樹幹害虫は2種とされているが、被害の大半はヒメコスカシバによるものと
判断され、樹幹害虫対策はヒメコスカシバの交信攪乱剤と殺虫剤散布を組み合わせた体系
防除で取り組む。
農業技術センター 病理昆虫部 【連絡先】058-239-3135
【背景・ねらい】
カキの樹幹害虫は、ヒメコスカシバとフタモンマダラメイガの2種とされており、とも
に幼虫が樹皮下に潜行し、虫糞を樹表面に噴出させながら形成層付近を食害する。両種の
生態には不明な点が多く、主な加害種や各種防除技術の効果も判然としていない。そこで、
慣行防除園における主要加害種、交信攪乱及び殺虫剤散布の防除効果を明らかにする。
【成果の内容・特徴】
1 慣行防除園において、ヒメコスカシバの被害はカキの栽培期間を通じて確認され、フタモ
ンマダラメイガの被害は8月以降に増加する。被害箇所から確認される幼虫の約 70%は、
ヒメコスカシバである (図1)。そのため、ヒメコスカシバはフタモンマダラメイガよりも
樹幹害虫としての重要度が高い。
2 ヒメコスカシバの交信攪乱剤は栽培期間を通じて効果があり、慣行防除に追加することで、
虫糞噴出箇所数を慣行防除の約 50%に抑制できる (図2)。
3 7月下旬~8月上旬に行われるカキノヘタムシガ防除は、樹幹害虫の同時防除効果が期待
できる(図3)。また、9月中旬にジアミド系殺虫剤散布すると、9月上旬散布と比較して
10月以降の被害抑制効果が高い(図4)。
4 樹幹害虫の被害を安定的に抑制するには、交信攪乱剤と殺虫剤散布を組み合わせた体系
防除で取り組むとよい。
【成果の活用・留意点】
1 これまでの成果をまとめた「樹幹害虫対策の手引き」を平成 30 年3月に作成予定で
ある。
2 ジアミド系殺虫剤(フルベンジアミド、クロラントラニリプロール等)はカメムシ類
に対する効果が低いので、カメムシ多発年の殺虫剤選択には留意する。
3 ジアミド系殺虫剤に対する感受性低下を回避するため、9月にジアミド系殺虫剤を
用いる場合、8月上旬の防除はアセタミプリド水溶剤など他系統の殺虫剤を利用する。

- 12 -
図1 慣行防除園における加害種の比率
(平成 24~28年の平均、本巣市)
図2 交信攪乱剤設置による累積虫糞噴出
箇所数の比較 (平成 29年、大野町)
(H24~28の平均)
図3 カキノヘタムシガ防除による樹幹
害虫の被害抑制効果 (平成 25年)
凡例の( )は散布日を示す
図4 9月防除による樹幹害虫の被害抑制効果
(平成 26年)
凡例の( )は散布日を示す
【具体的データ】
研究課題名:農薬飛散を抑えたカキ病害虫の防除手法の確立(平成 24~26年度)
農薬飛散を抑え、人と自然に優しい害虫防除手法の開発(平成 27~29年度)
研究担当者:杖田浩二
ヒメコスカシバ
フタモンマダラメイガ
慣行防除+
交信攪乱剤
設置区
慣行防除
のみ

- 13 -
茶の各種樹体情報に基づいた被覆可否の判断基準
【要約】茶栽培の直がけ被覆において、次茶期以降の被覆可否は、二番茶生育期の成葉の
全窒素含有率、三番茶萌芽期から1葉期の樹冠面温度及び一番茶摘採時の葉色をもとに判断
できる。
農業技術センター 作物部 【連絡先】058-239-3132
【背景・ねらい】
被覆栽培に取り組む県内茶産地においては、長期被覆や過度な摘採期の延長から、樹勢
衰弱と思われる落葉等の生理障害が発生し、生葉収量や全窒素含有率が低下する問題が
生じている。そこで、各種樹体情報から樹勢を客観的に診断し、次茶期以降の被覆可否を
事前に判断する手法を開発する。
【成果の内容・特徴】
1 摘採期を延長しない被覆栽培では、14 日被覆、21 日被覆ともに被覆がない場合と比べ、
生葉収量は減少し、全窒素含有率は増加し、葉色は濃くなる。無施肥条件下では施肥
条件と比べ、生葉収量はより減少し、全窒素含有率の増加程度は低くなる(表1)。
2 葉色は被覆により濃くなり、無施肥条件下での一番茶被覆時の葉色は SPAD 値で 37
以下となる(表1)。
3 盛夏期(三番茶萌芽期~1葉期)の樹冠面温度は、被覆期間が長いほど無被覆区と
比べ高く、無施肥条件下ではより高温となる(図1)。
4 成葉の全窒素含有率は、各茶期の摘採時期に増加し、二番茶生育期に減少する傾向で、
二番茶生育期の無施肥条件下では 3.3%以下となる(表2)。
5 一番茶の葉色、盛夏期の樹冠面温度、二番茶の成葉の全窒素含有率を「被覆すること
で経営的なメリットが得られる基準」に設定し、被覆の可否が判断できる(表3)。
【成果の活用・留意点】
1 樹冠面温度を測定する場合は、同一圃場に無被覆区画(2~3株分)を設け、照度計
を用いて 10 万 lux 以上の晴天時正午頃に計測する。
2 それまでの更新や年間施肥量を確認し、地域の栽培暦に比べ施肥量が不足する場合は
被覆栽培を中止するとともに、土壌診断結果も勘案しながら施肥改善を行う。

- 14 -
【具体的データ】
表1 茶期別生葉収量、全窒素含有率及び葉色
全窒素 葉色 全窒素 葉色 全窒素 葉色 全窒素 葉色(%) (SPAD値) (%) (SPAD値) (%) (SPAD値) (%) (SPAD値)
無被覆(N-49.8) 772 (100) 4.5 33.4 538 (100) 3.6 34.2 665 (100) 4.2 33.9 344 (100) 3.6 40.314日被覆(N-49.8) 667 (86) 5.4 41.3 508 (94) 3.9 43.8 623 (94) 5.4 39.9 417 (121) 4.1 41.721日被覆(N-49.8) 641 (83) 5.3 40.2 587 (109) 3.9 44.5 570 (86) 5.2 40.4 430 (125) 4.1 47.7無被覆(N-0) 581 (75) 4.1 27.7 328 (61) 3.4 29.2 479 (72) 4.2 31.5 153 (44) 2.8 34.214日被覆(N-0) 476 (62) 4.8 35.1 359 (67) 3.8 37.1 414 (62) 5.1 36.4 187 (54) 3.4 40.321日被覆(N-0) 466 (60) 4.6 35.4 397 (74) 3.7 36.5 399 (60) 4.9 35.3 191 (56) 3.4 39.6
一番茶 二番茶
(kg/10a)生葉収量(kg/10a)
生葉収量(kg/10a)
試験区生葉収量(kg/10a)
生葉収量一番茶
H29(3年目)H28(2年目)二番茶
注1)試験区の()内は 10a当たりの年間窒素施用量を示す。 注2)生葉収量の()内は無被覆(N-49.8)区に対する増減を示す。
図1 無被覆(N-49.8)区との盛夏期の樹冠面温度差 表2 成葉の全窒素含有率(%)
5/16 7/4 5/16 7/4 5/30 7/31無被覆(N-49.8) 3.5 3.6 3.4 3.6 3.2 3.414日被覆(N-49.8) 3.6 3.6 3.7 3.8 3.4 3.621日被覆(N-49.8) 3.5 3.6 3.5 3.7 3.4 3.6無被覆(N-0) 3.2 3.2 3.1 3.1 2.7 3.014日被覆(N-0) 3.2 3.3 3.2 3.2 2.8 3.021日被覆(N-0) 3.3 3.2 3.2 3.2 2.8 3.0
H28(2年目) H29(3年目)H27(1年目)試験区
注)成葉は新芽直下の硬化葉を採取した。 表3 各種樹体情報に基づく被覆可否判断基準
研究課題名:茶樹勢診断技術の開発(平成 27~29年度)
研究担当者:神谷仁
6月 7月 8月 7月
二番茶 秋冬番茶
樹冠の調査
成葉の全窒素含有率
樹冠面温度
葉色
※無被覆と比べ1℃以上高い場合は翌年被覆しない
4月
2年目~
※被覆茶園でSPAD値37未満の場合は以降被覆しない
5月 6月
1年目二番茶終了後~
葉色の調査
二番茶
チェック項目
一番茶
9月~3月
成葉の調査
※3.3%以下の場合は翌年被覆しない

- 15 -
水田及び畑土壌の可給態窒素が簡易迅速に評価できる
【要約】水田及び畑土壌の可給態窒素を分光光度計と化学的酸素要求量(COD)測定用試薬
セットを組み合わせた手法により簡易・迅速に評価する手法を開発した。本手法により評価
した COD は可給態窒素との相関が強く、可給態窒素を精度良く推定可能である。
農業技術センター 土壌化学部 【連絡先】058-239-3135
【背景・ねらい】
土壌から供給される窒素の指標となる可給態窒素は、長期間の培養試験や煩雑な分析操作を
伴うことから土壌診断では診断項目から除外される場合が多いが、近年、水田及び畑土壌に
おいて短期間で簡便な評価が可能な手法(迅速評価法)が開発された。しかし、分析機関向け
の手法は高額な分析機器が必要であり、一方で生産現場向けの手法では、細かい数量把握が
困難であるとともに精度の確保に留意する必要がある。
そこで、分析機関に広く整備されている分光光度計と市販の COD 測定用試薬セットを組み
合わせ、可給態窒素を簡便かつ定量的に評価する手法を開発する。
【成果の内容・特徴】
1 開発した手法により測定した CODと可給態窒素との間には強い正の相関が認められ(水田
土壌;図1左、畑土壌;図1右)、これらの関係から、水田及び畑土壌の可給態窒素を精度
良く推定することが可能である。
2 本手法による COD の測定には、可給態窒素の迅速評価法による抽出液を測定試料として
用いる。水田土壌は絶乾土を 25℃で1時間水振とう抽出した抽出液、畑土壌は風乾土を 80℃
で 16時間水抽出した抽出液である(図2)。
3 本手法では市販の COD 測定用試薬セットの測定法を一部改良し、分析操作が効率的となる
よう反応時間は 30 分である。あわせて、分析コスト抑制の観点から反応系を縮小し、試薬
セット1箱当たりの測定試料点数は標準法の5倍である(図2)。
4 本手法では、グルコースを用いて作成した COD の検量線を基に、迅速評価法抽出液の COD
を定量する(図2)。
【成果の活用・留意点】
1 本手法は、シッパー機能を備えた分光光度計や吸光度を測定する機能を有する分析装置の
利用を前提としている。これらを所有する研究機関、普及指導機関、土壌分析実施機関等に
おいて実施が可能である。
2 COD の定量は反応温度や反応時間に強く影響を受けることから、分析操作は 25℃程度の
室温及び液温で行い、試薬添加後の反応時間を順守する。
3 グルコースを用いた検量線はグルコースの CODの理論値(1 mg/L = 1.0657 mgO/L)を基に、
終濃度で0~8 mgO/L の範囲内で作成する。

- 16 -
【具体的データ】
y = 0.13x - 6.52
R² = 0.87RMSE = 2.55
0
10
20
30
40
50
0 100 200 300 400
可給態窒素(m
g/1
00g)
絶乾土水振とう抽出液のCOD
(mgO/100g)
y = 0.048x - 0.72
R² = 0.82RMSE = 2.30
0
5
10
15
20
25
30
0 100 200 300 400 500 600 700
可給態窒素(m
g/1
00g)
風乾土水抽出液のCOD
(mgO/100g)
図1 迅速評価法抽出液の COD と可給態窒素との関係(左:水田土壌,右:畑土壌)
1) 水田土壌は東ら(2015)が用いた 23 県より採取した合計 100 点の土壌を供試
2) 畑土壌は上薗ら(2010)が用いた 9 県より採取した 53 点の土壌に、岐阜県及び鹿児島県から別途採取
した土壌を加えた合計 141 点の土壌を供試
迅 速 評 価 法 に よ る 抽 出
迅 速 評 価 法 抽 出 液 の C O D の 測 定(分光光度計とCOD測定用試薬セットを組み合わせた手法)
水田土壌 ; 絶乾土25℃1時間水振とう抽出(東ら,2015)
畑土壌 ; 風乾土80℃16時間水抽出(上薗ら,2010)
可 給 態 窒 素 の 算 出
【試薬】
R-1試薬 (試薬セット付属のR-1試薬をそのまま用いる),
R-2溶液 (試薬セット付属のR-2試薬1パックを蒸留水5 mLに溶解する)
【測定方法】
1. 15 mL容試験管に蒸留水3.7~3.8 mLを加える.
2. 迅速評価法抽出液0.1~0.2 mLを加える.
3. すべての試料にR-2溶液1.0 mLを加え,撹拌する.
4. R-1試薬0.1 mLを加えて撹拌し,発色を開始する.
5. 正確に30分間反応後,525 nmの吸光度を測定する.
蒸留水と迅速評価法抽出液は,合計で3.9 mLとなるように加える.
別途,同様の操作により,グルコースを用いたCODの検量線を作成し,抽出液のCODを求める.
グルコースを用いた検量線は,グルコースのCODの理論値 (1 mg/L = 1.0657 mgO/L)を基に,
終濃度で0~8 mgO/Lの範囲内で作成する.
操作は25℃程度の室温および液温にて行い,反応時間は順守する.
すべての試料について事前に操作を行う
一定の間隔(15~30秒)で操作を行う
上記の回帰式から,可給態窒素を算出する.
図2 測定手順
研究課題名:農林水産省委託プロジェクト研究「適正施肥技術」(平成 27~31年度)
「水稲作における土壌可給態窒素の簡易測定に基づく適正施肥技術の開発」
研究担当者:和田巽

- 17 -
東濃地域で栽培されているエゴマ品種系統の特性と最適な作期
【要約】東濃地域で栽培されているエゴマ2系統は、子実収量や油脂含有量が「飛系アルプ
ス1号」とほぼ同等である。2系統は成熟期が異なるが、5月中下旬に播種し6月中下旬に
移植した場合に子実収量が最も多くなり、4月以前又は6月以降の播種は減収する。
中山間農業研究所 中津川支所 【連絡先】0573-72–2711
【背景・ねらい】
東濃地域では古くからエゴマが栽培されてきたが、伝統的な品種系統や栽培技術は継承され
ていない。近年、新たに作付が広がりつつあり、すでに複数系統が導入されているものの、
各系統の地域適性や適正な作期については検証されていない。そこで、東濃地域で栽培されて
いるエゴマ2系統について特性や作期の評価を行う。
【成果の内容・特徴】
1 白川栽培種・中野方栽培種の2系統を中津川支所(標高 390m)において栽培した結果、
子実収量や油脂含有量について、「飛系アルプス1号」とほぼ同等であり(α<0.05、図 1)、
2系統の東濃地域における栽培適性は高い。
2 播種・移植時期にかかわらず、品種系統によって開花・成熟期はほぼ一定であり、成熟期
は中野方栽培種で 10月上旬、白川栽培種は 10月中旬である(表1)。
3 白川及び中野方栽培種は、5月中下旬に播種し、6月中下旬に移植した場合に子実収量が
最も多くなる。4月以前又は6月以降の播種は減収する(図2)。
【成果の活用・留意点】
1 東濃地域のうち、特に恵那地域における成果の活用が期待できる。
2 成熟期の異なる供試2品種系統を作付することで、収穫時期の分散が可能となる。
3 適正な播種・移植期を選択することにより、収量の確保に繋がる。

- 18 -
【具体的データ】
表1 開花日及び成熟日(平成 28年)
研究課題名:飛騨エゴマの機能性に特化した新商品開発と総合技術開発(平成 28~32 年度)
研究担当者:大江栄三
図 1 子実収量及び脂質
(6/1播種:n=3,平成 28年) ・飛系アルプス 1号:飛騨市域の在
来種から選抜された登録品種。
・白川栽培種:飛騨地域の黒種(日
本エゴマ普及協会より提供)。加
茂郡白川町下佐見周辺で自家採
取し、20年程度栽培。
・中野方栽培種:福島県田村市周辺
の在来品種(日本エゴマの会より
購入)。恵那市中野方町で数年、
自家採種。子実は白種。
開始日 満開日
4/25 5/25 9/15 9/21 10/17 31日
5/11 6/15 9/15 9/23 10/17 31日
6/1 6/27 9/17 9/24 10/17 29日
4/25 5/25 9/7 9/15 10/6 28日
5/11 6/15 9/7 9/15 10/7 29日
6/1 6/27 9/8 9/16 10/8 29日
品種・系統
注1)開始日:開花の初見日、満開日:およそ75-100%の花序が開花
注2)成熟日:大半の個体の葉が黄化し、落葉を開始した日とする。
白 川 栽培種
中野方栽培種
播種日 移植日開花日注1)
成熟日注2開花開始から成熟日まで
図2 作期と子実収量の関係
(n=3,平成 28年及び 29年) ※(H28)は平成 28年度、それ以外は平
成 29年度のデータであることを表す。

- 19 -
夏秋トマトのナス台木を利用した晩期セル苗直接定植作型
【要約】夏秋トマト晩期作型のセル苗直接定植(5月下旬~6月)は、通常の育苗に比べ
省力であるが、初期の過繁茂が課題となっている。この作型に「ナス台木トマト」を用いる
と、トマト台木に比べて過繁茂の抑制が可能となり、青枯病の発生も抑制される。
中山間農業研究所 中津川支所 【連絡先】0573-72–2711
【背景・ねらい】
夏秋トマトにおいて気温の低下する9月以降は、出荷量が大きく減少することから、販売
価格が上昇するうえ、労働力にも余剰が発生する。このため、8月中旬以降に収穫が開始され
る晩期作型は経営的メリットがあるため有効な作型であるが、通常のポット苗定植では、育苗
と定植作業が通常作の繁忙期にあたり、労力的に導入が難しい。このため、セル苗直接定植が
有効であるが、晩期作型のセル苗直接定植では、高温・長日条件下のため生育初期の過繁茂が
問題となる。そこで、ナス台木を用いて、セル苗直接定植における生育及び青枯病発生抑制
効果について検討する。
【成果の内容・特徴】
1 ナス台木を用いることで、5月下旬から6月の晩期セル苗直接定植でも過繁茂にならず
(図2)、比較的容易に栽培ができる。
2 青枯病の発生を抑制し、青枯病汚染圃場での栽培が可能となる(図1)。
3 慣行栽培に比べて果実が小玉となるが、A品率は向上する(表1、図2)。
4 慣行の育苗を行った作型に比べて、可販収量は約2割減収する(表1)。
【成果の活用・留意点】
1 本作型は高い収量性を求めることができないので、労力分散が可能な補助作型として経営
の中に導入する。
2 トマト台木に比べてナス台木は強い青枯病抵抗性を示すため、青枯病発生圃場の有効活用
が可能である。
3 尻腐果の発生が多い傾向にあるので(表1)、多めのかん水を行う。
4 穂木からの不定根の発生があるので(図3)、ナス台木部の長さを一定以上確保する。

- 20 -
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ナス台木 慣行
健全株
発病株
6.7% 16.7%
【具体的データ】
研究課題名:革新的接ぎ木法によるナス科野菜の複合土壌病害総合防除技術の開発(平成 25~27年度)
研究担当者:熊崎晃
図2 ナス台木トマトの草姿(平成 25年) 図3 穂木からの不定根(平成 25年)
ナス台木 穂木からの
不定根
※慣行区は台木グリーンガードを用い開花期まで育苗をおこなった。
表1 収量性 収穫果数 平均果重 可販収量 A品率 格外率 空洞果 尻腐果数 裂果数 出荷不可裂果(果/株) (g/果) (kg/10a) (%) (%) (果/株) (果/株) (果/株) (果/株)
(H25年桃太郎8)
20.5 156 9,213 38 19 4.9 1.1 3.1 0.4
20.5 186 10,958 20 15 8.0 0.0 4.8 1.8(H25年麗夏)
23.9 158 10,221 43 23 2.5 3.9 1.6 0.3
20.5 222 11,673 19 21 5.8 0.8 4.1 0.9(H28年桃太郎8)
21.3 142 8,059 31 26 5.2 1.8 3.8 1.1
19.3 195 10,391 28 18 4.3 0.3 4.3 1.6
試験区
ナス台木
慣行
ナス台木
慣行
ナス台木
慣行
※ナス台木は「台太郎」
慣行は台木「グリーンガード」
図1 青枯病発病率(平成 28年)

- 21 -
飛騨地域の夏秋トマト栽培に適した品種「麗月」、「桃太郎ワンダー」
【要約】「麗月」と「桃太郎ワンダー」は、盛夏期の着果性がよく、裂果や空洞果の発生が
少ないため、A品率と収量性が高く、飛騨地域の夏秋栽培に適した品種である。
中山間農業研究所 試験研究部 【連絡先】0577-73-2029
【背景・ねらい】
飛騨地域の夏秋トマト産地(飛騨トマト部会 H29 年度)では、「桃太郎8」、「桃太郎
セレクト」、「桃太郎サニー」、「桃太郎ギフト」、「結夏」が共同出荷の対象品種に指定
されている。しかし、これらの品種では、盛夏期の着果性の悪さや裂果の発生などが問題と
なっている。そこで、着果性・収量性が高く、裂果の少ない飛騨地域の夏秋トマト栽培に適し
た品種を選定する。
【成果の内容・特徴】
1 「麗月」は「桃太郎8」」と比較し、摘果した1~3段以降の着果数が多く、特に盛夏期
の着果性が高い(図1)。また、平均果重は小さいが、裂果や空洞果等の発生が少ないこと
からA品率が高く収量性が高い(表1)。
2 「桃太郎ワンダー」は「桃太郎8」と比較し、裂果や空洞果等の発生が少ないことから
A品率が高く収量が高い(表1)。
3 茎径は「桃太郎ワンダー」、「桃太郎8」、「麗月」の順に太く(図2)、「桃太郎ワン
ダー」はやや強めの草勢となる。
【成果の活用・留意点】
1 「麗月」は、多収性であるがやや小玉なため、大果生産には向かない。また、やや尻腐れ
果等が発生しやすい。
2 「桃太郎ワンダー」は、やや強めの草勢となりやすく、葉先枯れ等が多くなる場合がある
ため必要以上に草勢を強めない。
3 「麗月」及び「桃太郎ワンダー」を導入する場合は、一度に大面積での品種変更を行わず、
必ず試作して圃場条件等に合わせた栽培管理をする。

- 22 -
可販収量 A品率 格外 裂果 空洞果 平均果重(kg/10a) (%) (%) (%) (%) (g)
H27 9,922 28 15 30.0 36.0 198H28 11,264 31 17 6.4 1.4 195H29 10,833 38 19 20.0 19.0 195
平均 10,673 32 17 18.8 18.8 196
H27 12,705 55 15 4.0 13.0 188H28 13,259 48 10 0.0 0.7 173H29 12,472 77 9 0.5 9.2 175
平均 12,812 60 11 1.5 7.6 179H27 10,752 43 26 6.0 2.3 197H28 10,984 42 16 3.7 0.6 194H29 12,032 61 10 14.9 12.0 182
平均 11,256 49 17 8.2 5.0 191
桃太郎8
麗月
桃太郎ワンダー
供試品種
【具体的データ】
表1 各品種の収量・品質
注)播種:穂木 3/中下旬、台木 3/中旬、接ぎ木:4/上中旬、定植:5/中下旬
図1 各品種の着果数の推移(平成 29年)
図2 各品種の茎径の推移(平成 29年)
研究課題名:夏秋トマトの革新的 20t穫り多収栽培システムの開発(平成 26~30年度)
研究担当者:浅野雄二
年度

- 23 -
ホウレンソウ調製作業の省力化のための高能率調製機の開発
【要約】ホウレンソウを1株ずつ静置するだけで、根切り及び子葉、下葉を精度良く除去で
きる調製機械を共同開発した。現行機に比較して作業精度が良く、仕上げ作業にかかる時間
を削減できる。1台あたり2人での作業が可能で、調製作業を省力化できる。
中山間農業研究所 試験研究部 【連絡先】0577-73-2029
【背景・ねらい】
軟弱な葉菜類では、一般に面積あたり労働時間に占める調製、出荷作業の割合が高く、生産
者の労働負担が大きい。本県の夏どりホウレンソウ栽培は、収穫機等の導入により機械化が
進んでいるが、最終段階の調製作業は未だ手作業で行われており、近年、生産者の高齢化や
働き手不足に伴う雇用労働力確保が問題となっている。
ホウレンソウを1株ずつ供給し、根切り及び子葉・下葉の除去を行う機械が市販されている
ものの、作業精度が低く本県ではほとんど普及していない。そこで、市販の現行機と比べて
作業精度が高く、手直しによる調製時間を削減できる高能率調製機を開発する。
【成果の内容・特徴】
1 開発機(全長 2,830×全幅 880×全高 1,060 mm、質量 117 kg、使用電源 100V、消費電力
240W)は、供給部、調製部、搬出部で構成される(図1)。
2 供給ベルトは進行方向に約1°傾いており、供給者がベルト上にホウレンソウを1株ずつ
静置すると、根元が徐々に株元ガイドに軽く押しあてられ切断位置が固定される(図2)。
3 供給ベルトと株押さえベルトで把持された株は、調製部入口の回転刃で根が切り落とされ、
横・縦ブラシ及び高速回転ブレードを通過する間に子葉・下葉が除去される(図3)。
4 開発機では根切り精度及び子葉、下葉除去率が向上したことにより、取り残しの除去など
の仕上げに要する手間が軽減される(表1)。
5 作業能率は現行機(供給1人、仕上げ3人、約 570株/人・h)に対し、開発機(供給1人、
仕上げ1人)が 1.6倍程度(約 900株/人・h)である(表1)。
【成果の活用・留意点】
1 本機で対応可能なホウレンソウは、主に雨よけ栽培した立性の株又は品種で、概ね草丈 20
~45cmである。
2 虫食い、病斑、変色、軸折れ、混入異物等の除去のため、手作業による仕上げが必要で
ある。
3 本機の開発は、農林水産省平成 27~29 年度農業機械等緊急開発事業において、国立研究
開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター、(株)クボタ、
(株)斉藤農機製作所、岩手県県北農業研究所、群馬県農業技術センターとの共同研究で行い、
平成 30年度以降の実用化が見込まれる。

- 24 -
【具体的データ】
研究課題名:軟弱野菜の高能率調製機の開発(農業機械等緊急開発事業 平成 27~29 年度)
研究担当者:中西文信
表1 開発機の性能*1 (平成 29年)
調製精度 作業能率*3
子葉・下葉除去率
(%)
根切り長さ*2平均(mm)
(標準偏差)
作業体系
(人)
作業能率
(株/人・h)
現行機 67.2 10.1
(3.0)
供給 1
仕上げ 3
570
開発機 95.4 5.9
(1.5)
供給 1
仕上げ 1
897
*1:岐阜県中山間農業研究所の試験結果。 品種:「サンホープセブン」
*2:ホウレンソウの株に残った根の長さ。 *3:供試株:150株、23~32cm(飛騨ほうれんそう出荷基準 L品相当)での試験。
図2 供給部の構成
株元ガイド
株元ベルト
供給ベルト
株押さえベルト
図3 調製部の構成
横ブラシ
縦ブラシ
高速回転ブレード
図 1 開発機での作業の様子
供給部
調製部 供給者 仕上げ者
搬出部

- 25 -
「宿儺かぼちゃ」の早期作型は高品質、多収化に有効である
【要約】カボチャ「宿儺かぼちゃ」の定植時期を1か月早め4月下旬とする早期作型は、
1果重が増加することで慣行作型と比べて収量が増加し、糖度は同等以上となる。また、
早期作型の定植初期の晩霜対策には不織布によるトンネル被覆が適する。
中山間農業研究所 試験研究部 【連絡先】0577-73-2029
【背景・ねらい】
飛騨地域特産のカボチャ「宿儺かぼちゃ」は、ユニークな外観と良好な食味を有すること
から、ブランドカボチャとしての引き合いが強い。産地の慣行作型では晩霜害のない5月下旬
に苗を定植して、9月上旬から収穫を行っているが、これが好適作型であるか解明されては
いない。そこで、定植時期を慣行作型から前後させて栽培を行い、より高品質、多収化に向け
た好適作型の検討を行う。
【成果の内容・特徴】
1 定植時期を慣行作型よりも1ヶ月早め4月下旬とする早期作型では、開花始日が6月
4日、収穫始日が8月 14 日となり慣行作型より 20 日程度前進する(図1)。
2 早期作型では1果当たりの重量が増加し、それに伴い 10a 当たりの収量が慣行作型と
比べて 10~17%増加する(表1)。
3 早期作型では果実糖度が慣行作型の同等以上となる(表1)。
4 早期作型では定植初期に晩霜に遭遇する可能性が高いため、トンネル被覆による保温
を行う。被覆資材の利用においては、農ポリは日中の温度上昇による葉焼け等の被害が
懸念されるため、不織布がよい(図2)。
【成果の活用・留意点】
1 慣行作型との組み合わせにより、管理作業の労力分散を図ることが可能となる。
2 肥培管理及び病害虫防除は「宿儺かぼちゃ研究会」の栽培方法に準ずる。
3 早期作型の育苗を行う際は、ハウス内において電熱温床を使用し、トンネル被覆で保
温を行う。
4 不織布のトンネル被覆による最低気温の昇温効果は、0.7℃~1.4℃程度であるため、
最低気温が-1℃を下回る場合は、二重被覆にするなど保温効果を高める必要がある。
5 早期作型では、雌花開花の 70 日後を収穫の目安とする。

- 26 -
【具体的データ】
図1 作型の違いによる開花期及び収穫期の変化(平成 29 年)
育苗法 :48 時間浸漬、24 時間 30℃にて催芽を行ったのち、10㎝ポットに播種、
ハウス内トンネルで電熱温床による保温を行った
栽植密度 :畝幅 4.5m×株間 0.9m(247株/10a)
施肥方法 :N:P2O5:K2O=14.8:12.5:14.4(kg/10a)
仕立て方法:子蔓3本仕立て
表1 作型の違いが収量、果実重、糖度に及ぼす影響
年度 28 29
作型 早期 慣行 晩期 早期 慣行 晩期
総収量(kg/10a) 1,650 1,330 637 1,787 1,625 733
果実重量(g/果) 2,229 2,018 1,376 2,516 2,145 1,636
糖度(Brix%) 5.9 5.9 4.9 6.1 4.9 4.8
図2 防霜用被覆資材の違いとトンネル内温度の変化(H29.11.12~11.13)
研究課題名:「宿儺かぼちゃ」の機能性成分探索と安定生産(平成 28~29年度)
研究担当者:石橋裕也
被覆トンネル内温度 (℃)
:播種
:定植
:開花
:収穫

- 27 -
リンゴ「ふじ」のミツ入り状態を判別する市販の判定機で長期貯蔵向け果実を判別できる
【要約】リンゴ「ふじ」のミツ入り部分は長期貯蔵中に変質しやすく、貯蔵向けにはミツ
入りの少ない果実が適する。ミツ入り状態を非破壊で判別する市販の廉価な判定機を用いる
ことにより、低コストで長期貯蔵向けのミツ入りが少ない果実を判別できる。
中山間農業研究所 試験研究部 【連絡先】0577-73-2029
【背景・ねらい】
リンゴのミツ入りは嗜好性に大きく関与しており、ミツ入りの多い果実は消費者から求めら
れているが、果肉のミツ入り部分は長期貯蔵中に変質しやすいため、貯蔵向けにはミツ入りの
少ない果実が適する。そこで、「ふじ」果実のミツ入りを非破壊で判定できる市販の2種類の
判定機について比較し、長期貯蔵向け果実の判別法を検討した。
【成果の内容・特徴】
1 判定機A(S社製、価格約 36 万円(写真1))は、測定値「4」と判定した果実を選別
することにより、94.4%の高精度でミツ入り指数2以上(図1)のミツ入りが多い果実を
判定できる(表1)。
2 判定機Aよりも低価格な判定機B(T社製、価格約1万円(写真2、写真3))は、測定
値「0」と判定した果実を選別することにより、88.9%の高精度でミツ入り指数1以下の
ミツ入りの少ない果実を判定でき、判定精度は判定機Aよりも高い(表2)。
3 長期貯蔵向けのミツ入りが少ない果実の判定は、判定機Bを用いることにより、低コスト
で判別できる。
【成果の活用・留意点】
1 判定機Aと判定機Bは、ともにミツ入り果実は光透過性が高い性質を応用してミツ入りを
判定している。判定機Aは受光センサーとミツ入り判定モジュールが組み込まれており、
判定機がミツ入りを判定するのに対して、判定機Bは果実の光透過状況を目視で確認し、
作業者がミツ入りを判定する必要がある。
2 判定機Aは、測定時に発光窓とゴム製丸穴との間に隙間ができないように果実を設置する
ことで、判定精度が向上する。
3 判定機Bは測定を屋内で行い、連続して測定を続ける場合は、室内の明るさを一定に保つ
ことで判定精度が向上する。

- 28 -
【具体的データ】
表1 判定機Aによる測定値と実際のミツ入り指数との適合率(平成 26~28 年)
実際のミツ入り指数 判定機Aの測定値
0・1 2 3 4
指数2以上 16.5% 48.7% 73.3% 94.4%
指数1以下 83.5% 51.3% 26.7% 5.6%
供試果数 測定値0:8果、1:77 果、2:109 果、3:105 果、4:124 果
表2 判定機Bによる測定値と実際のミツ入り指数との適合率(平成 28 年)
実際のミツ入り指数 判定機Aの測定値
0 1 2
指数2以上 11.1% 39.3% 71.1%
指数1以下 88.9% 60.7% 28.9%
供試果数 測定値0:27 果、1:28 果、2:97 果
研究課題名:飛騨産リンゴの長期保存技術の確立(平成 26~28年度)
研究担当者:水野文敬
写真3 判定機Bの測定基準
写真1 判定機Aの外観(左)と測定時(右)
写真2 判定機Bの外観(左)と測定時(右)
発光窓と果実の間に空間が生じないように
果実を設置する
測定結果が0~4の数値で表示される
測定値0・1:ミツが少ないと判定
測定値2・3:ミツが多少あると判定
測定値4 :ミツが多いと判定
図1 ミツ入り程度指数(青森県りんご生産指導要項より引用)
0 1 2 3 4
発生なし 極小 小 中 大
基準0(ミツ少) 基準1(ミツ有り) 基準2(ミツ多)
果実下部 赤道部の少し下 肩部の少し下 ※点線は判定基準の位置

- 29 -
フランネルフラワーの発芽率を低下させない種子の貯蔵法
【要約】フランネルフラワーの種子は、採種直後の播種で約 60%の発芽率であり、常温貯蔵
では6か月後にはほぼ発芽しなくなるが、採種後ただちに低温乾燥条件下で貯蔵することに
より、半年~1年後においても 40~50%の発芽率が得られる。
中山間農業研究所 中津川支所 【連絡先】0573-72-2711
【背景・ねらい】
県育成花き「フランネルフラワー」は、県の主要鉢花品目として生産拡大され、中山間地域
においてもシクラメンとの組み合わせ品目として導入が進んでいる。しかし近年、生産現場で
は種子の発芽不良により計画出荷できないケースが散見されることから、発芽率を保持できる
有効な種子の貯蔵方法を明らかにする。
【成果の内容・特徴】
1 採種直後に、充実種子を選別して播種し、表1の条件で播種 30日後に調査した結果、62%
の発芽率が得られ、取り播きが可能である(図1)。
2 種子を常温(冷暖房がある直射日光のあたらない事務所内)で乾燥貯蔵した場合、3ケ月
後の播種から発芽率が低下し始め、6ケ月後にはほぼ発芽しなくなるが、5℃の冷蔵庫内で
乾燥貯蔵すると、1年後においても 50%の発芽率が得られる(図1)。
3 常温貯蔵すると6ケ月貯蔵以降にやや赤みを帯びた変色がみられるが、5℃貯蔵すると
種子の変色は無い。
【成果の活用・留意点】
1 採種後に圃場で種子を保管すると、さらなる発芽率の低下が予想されるため、採種直後
から乾燥低温貯蔵に心がけること。
2 当試験では培養土に播種用培土を使用したが、実際は栽培マニュアルに従った用土を使用
すること。

- 30 -
【具体的データ】
表1 試験条件
実施場所 中津川支所 恒温機内
供試品種 エンジェルスター
採種日 H28.5.13
培養土 播種用培土
試験区 冷蔵貯蔵(5℃冷蔵庫内で乾燥貯蔵)
常温貯蔵(冷暖房がある直射日光があたらない事務所内で乾燥貯蔵)
播種方法 5号鉢に培土を入れ、各区 50 粒を播種
覆土 同一培養土を5mm 程度
図1 種子の貯蔵方法の違いが発芽率に及ぼす影響 (平成 28~29 年)
研究課題名:フランネルフラワーの中山間地域に適した栽培技術の確立(平成 25~29 年度)
研究担当者:浅野正
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5月13日 6月13日 7月12日 8月12日 11月24日 5月16日
発芽
率(%
)
播種日
5℃貯蔵
常温貯蔵

- 31 -
基幹種雄牛として選抜された「孝た か
隆りゅう
平だいら
」の特徴
【要約】飛騨牛の肉質向上に大きく貢献した「白清 85 の3」の後継種雄牛として造成した
「孝隆平」は、脂肪交雑、ロース芯面積、腿の肉質及び霜降りの細かさの改良に貢献する
ことが期待される。
畜産研究所 飛騨牛研究部 【連絡先】0577-68-2226
【背景・ねらい】
岐阜県では、飛騨牛ブランドを支える能力の高い種雄牛群を造成し、12頭の基幹種雄牛とし
て選抜利用している。これまでに「安福」の優れた遺伝能力を引き継ぐ種雄牛として「白清 85
の3」が活躍し、子牛市場や枝肉市場共に高値で推移し、飛騨牛の肉質向上に大きく貢献して
きた。しかし、「白清 85の3」が高齢(平成 22年当時 11才、平成 28年 10月死亡)となった
ため、平成 22年度から「白清 85の3」の後継種雄牛造成に取り組んだ。そのうちの1頭で、
平成 29年度に飛騨牛改良推進事業専門委員会で基幹種雄牛に選定された「孝隆平」について、
基幹種雄牛としての利用推進を図るため、産子調査や現場後代検定成績等から特徴を解析する。
【成果の内容・特徴】
1 「孝隆平」の血統は、父が「白清 85の3」、母方祖父が「安晴王」、母方曾祖父が「安平」
である。
2 (公社)全国和牛登録協会が定める種雄牛産肉能力検定法のうち直接検定法で検定した
結果、増体量は 1.15kg/日、終了時体高は 128cmである。
(同期牛9頭の平均:増体量 1.07kg/日、終了時体高 125.5cm)
3 「孝隆平」の現場後代検定調査牛 27 頭の枝肉成績(平成 27 年3月~平成 29 年5月)を
表 1 に示した。各枝肉形質の平均値は、県内で平成 13~28 年度に現場後代検定を実施した
種雄牛 52頭の平均値と比較し、いずれも上回る成績である。
特に、脂肪交雑(BMS)No.9.1 及びロース芯面積 62.0 ㎠は、これまで県内で現場後代検定
を実施した種雄牛の中で最高の成績である。
4 「孝隆平」の6ヶ月齢時 43 頭の産子の生育状況を調査し、(公社)全国和牛登録協会が
定める外貌記載法審査基準に準じた5段階で評価した結果、発育、前・中・後躯の移行、
体上線、均称、資質及び品位に優れる(図1)。
5 産肉能力の育種価については、特にロース芯面積、脂肪交雑、腿脂肪交雑※1、腿肉色※2、
肉色、歩留基準値及び小ザシ距離※3が優れている(図2)。
※1(公社)日本食肉格付協会の牛脂肪交雑基準に基づき、12段階で半膜様筋断面を流通関係者が評価した評価値
※2(公社)日本食肉格付協会の牛肉色基準に基づき、7段階で半膜様筋断面を流通関係者が評価した評価値
※3脂肪割合を考慮した上で評価した霜降りの細かさを示す評価値〔岐阜県集団のロース芯1cm2中の細かい脂肪
(0.01~0.49cm2)の数と脂肪割合から得られた標準回帰式を作成し、その直線からの距離を求めた値〕
【成果の活用・留意点】
1 体高、体伸、後躯、資質、脂肪交雑、ロース芯面積、腿脂肪交雑、腿肉色、肉色及び
霜降りの細かさの改良が期待できる。
2 体の幅・深み及び腿の厚さに欠ける産子が散見されたため、体積があり後躯の充実した
繁殖雌牛への交配が望ましい。

- 32 -
【具体的データ】
表 1 「孝隆平」現場後代検定調査牛の産肉成績
出荷 枝肉 枝肉 ロース芯 ばらの 皮下脂肪 歩留り BMS BCS
月齢 格付 重量 面積 厚さ の厚さ 基準値
(ヶ月) (kg) (cm2) (cm) (cm) (%) (No.) (No.)
去勢 花清国 光平福 安福 29.1 A5 514.7 59 9.5 3.4 73.9 10 4
去勢 糸福 安福 糸晴 28.2 A5 480.8 62 9.1 1.9 75.8 9 4
去勢 羅威傳王 飛騨白清 光平福 28.7 A5 456.4 66 8.1 2.5 75.4 10 4
去勢 糸福 護煕王 安福 27.9 A4 490.3 57 8.1 3.6 72.8 7 3
去勢 利優福 白清85の3 平茂勝 28.3 A5 562.3 74 10.3 3.5 75.7 10 3
去勢 福栄 安福 藤桜 28.6 A4 450.1 58 7.0 3.2 73.1 7 3
去勢 天晴白清 平茂勝 飛騨白清 29.0 A5 488.0 86 9.1 1.7 79 10 4
去勢 花清国 糸福 安福 28.4 A5 474.0 61 8.3 3.0 74.2 12 3
去勢 平茂勝 安福 富士桜 28.4 A4 485.3 57 8.0 3.1 73.3 7 4
去勢 花清国 利優福 糸福 28.8 A5 464.8 55 8.2 2.9 73.6 9 3
去勢 百合茂 北国7の8 安福 28.4 A5 491.1 56 9.0 3.7 73.2 10 4
去勢 茂重安福 平茂勝 安福 28.8 A5 467.4 90 9.0 3.0 78.5 11 3
去勢 安福 平茂勝 神高福 28.8 A5 466.0 55 7.4 2.5 73.4 9 3
去勢 利優福 羅威傳王 安福 28.3 A5 467.6 73 7.6 2.8 75.6 12 4
去勢 茂重安福 晴姫 安金 28.4 A5 493.6 58 8.5 1.8 74.8 9 3
去勢 平茂勝 広順 紋次郎 27.8 A4 485.5 60 9.0 3.4 74.1 7 4
去勢 百合茂 安平 平茂勝 27.8 A5 473.3 62 8.4 3.3 74.2 8 4
去勢 飛騨白真弓 飛騨白清 北国7の8 27.6 A5 477.0 66 8.8 2.9 75.2 8 4
去勢 平茂勝 北国7の8 紋次郎 27.5 A3 483.9 67 7.5 2.7 74.6 5 5
去勢 安平 隆桜 菊安 27.4 A5 452.7 54 8.1 3.1 73.4 9 3
去勢 羅威傳王 平茂勝 安福 27.2 A5 430.8 66 7.2 2.3 75.3 11 3
去勢 糸福171の8 飛騨白清 糸北鶴 27.4 A5 452.5 67 8.3 2.7 75.6 9 4
去勢 花清国 白清85の3 光平福 26.6 A5 432.7 59 8.2 2.7 74.7 9 4
去勢 第1花国 糸福 安福 28.8 A5 483.3 62 8.6 2.0 75.4 9 3
雌 福茂王 真福 安福 30.6 A5 372.6 60 8.7 3.9 74.9 12 4
雌 糸福 安栄 安福 28.0 A5 394.6 46 6.3 2.8 72.1 9 3
雌 光平福 安平 隆桜 27.6 B5 330.5 37 7.2 3.3 71.9 8 4
平均値 28.2 463.8 62.0 8.3 2.9 74.6 9.1 3.6 81.5%
去勢平均 28.1 476.0 63.8 8.4 2.8 74.8 9.0 3.6 79.2%
めす平均 28.7 365.9 47.7 7.4 3.3 73.0 9.7 3.7 100.0%
429.5 54.1 7.8 2.6 74.0 6.5 3.9 34.1%
※県内で平成13~28年度に現場後代検定を実施した種雄牛52頭の平均値
母牛 産肉成績
現場後代検定種雄牛平均値※
性別一代祖 二代祖 三代祖
5等級率
※BMS(脂肪交雑):肉質を評価する指標の1つで「霜降り」「サシ」とも呼ばれる。
十二段階で評価し、数値が高いほど評価高い。
研究課題名:飛騨牛産肉能力検定事業
研究担当者:高原伸一
図1 産子調査結果(数値:評価値)
(平成 26年度)
※3を標準とし、数値が高いほど良い
図2 産肉能力の育種価(数値:σ値)
(育種価は H29.9 月解析)
※図は外に向くほど良い

- 33 -
過剰排卵処理と経腟採卵を組み合わせた乳用牛胚の大量生産技術
【要約】泌乳中の乳用牛において、過剰排卵処理と経腟採卵を組み合わせて、体内胚と体外
胚を作出することで、過剰排卵処理のみ行う従来法よりも移植可能な乳用牛胚の生産個数を
増加させることができる。
畜産研究所 酪農研究部 【連絡先】0573-56-2769
【背景・ねらい】
酪農家にとって、牛群の中で泌乳能力が上位の牛の子孫を後継牛とする必要があるが、雌牛
が一生に産む産子の数は限られている。胚移植技術を活用することで、特定の雌牛の産子を
たくさん生産することが可能となるが、一般的に泌乳中の乳用牛の過剰排卵処理(SOV)により
回収される移植可能胚数は和牛と比べ少ないため、胚移植技術を活用しても必ずしも計画
どおりに泌乳能力の高い後継牛を確保できない。
そこで、泌乳牛において、SOVの直前に経腟採卵(OPU)を行い、SOV処理を行っている期間
に、OPU により回収された卵子を体外受精(OPU-IVF)し、さらに体外発生培養(図 1:OPU と
SOV の組合せ)する方法を検討し、乳用牛胚大量生産技術を確立する。
【成果の内容・特徴】
1 SOVのみの従来法(図1)による採胚成績と OPU実施後の SOVによる採胚成績(表1)は、
平均正常胚数において、従来法が 4.0±4.4 個、OPU 実施後が 4.4±4.5 個でほぼ同程度で
あった。また、正常胚率も低下してないことから、SOV の直前に OPU を行っても、採胚成績
に影響がない。
2 OPU-IVF 1回当たりの移植可能な胚盤胞発生数は、3.3±2.4個(表2)であった。SOVに
よる採胚成績に差がないことから、OPU-IVF で生産された胚数だけ、移植可能な胚数は増加
する(図2)。
【成果の活用・留意点】
1 経腟採卵を実施するには超音波診断装置と経腟採卵用プローブ及び炭酸ガス培養器等の
機器が必要である。
2 体外胚は一般的に体内胚より耐凍性が劣るが、超急速ガラス化保存することで高い受胎率
が得られる。
3 体外胚により受胎した産子は、稀に、出生体重が増加することがあるが、適切な分娩管理
を行うことで、分娩事故を防ぐことができる。

- 34 -
【具体的データ】
図1 処理開始前から胚生産まで
表1 SOV による採胚成績(平成 26~28 年)
採卵延頭数 回収胚数 平均回収胚数 正常胚数 平均正常胚数 正常胚率
従来法 249 2225 9.0±7.0 984 4.0±4.4 44.2%
OPU 実施後 8 70 8.7±6.3 36 4.4±4.5 55.7%
表2 経腟採卵成績と体外培養成績(平成 28 年)
OPU 実施頭数 平均回収卵子数 平均卵割数
(卵割率%)
平均胚盤胞発生数
(発生率%)
8 10.0±4.7 5.2±2.6
(60.8±23.7)
3.3±2.4
(28.9±10.1)
図2 移植可能胚の生産個数(平成 28 年)
研究課題名:性判別精液を活用した乳用種雌受精卵の大量生産技術の確立に関する研究
(平成 26~28年度)
研究担当者:眞鍋典義
O P U S O V
O P U O P U 終了後C ID R in 0 C ID R in+ E B
媒 精 1
(
2
発 F S H ×2 3
生 F S H ×2 4 F S H ×2
培 F S H ×2 5 F S H ×2
養 F S H ×2+ P G + C ID R out 6 F S H ×2
)
G nR H 7 F S H ×2+ P G + C ID R out
体外胚発生 人工授精 8 G nR H
9 人工授精 C ID R:膣内留置型黄体ホルモン
10 E B:エストロゲン
11 C ID R in:C ID Rを膣内に挿入
12 F S H :卵胞刺激ホルモン
13 P G :プロスタグランディン類縁体
14 G nR H :性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁体
体内胚採卵 15 C ID R out:C ID Rを膣内から抜去
16 体内胚採卵 媒精:精子と卵子をシャーレ内で混合
従来法(SO Vのみ)O P U とS O Vの組合せ
D A Y

- 35 -
県内で生産される牧草のミネラル組成と土壌化学性
【要約】牧草のミネラル組成と土壌化学性は、生産地域によって異なり、特にオーチャード
グラスやリードカナリーグラスを生産している地域では、草地にカリウムが過剰に蓄積して
いるため、牧草のカリウム含量は高く、ミネラルバランスは崩れている。
畜産研究所 酪農研究部 【連絡先】0573-56-2769
【背景・ねらい】
自給飼料の利用は飼料費を削減し、畜産経営の安定に寄与する。しかしながら、本県で生産
される飼料の一部では、ミネラルバランスの崩れた(ミネラルバランスを表すテタニー比が 2.2
以上)牧草が確認されており、これらは家畜の生産性を低下させる懸念がある。
そこで、県内で生産される牧草及び土壌の成分分析を実施し、牧草のミネラル組成と土壌
化学性について調査を行う。
【成果の内容・特徴】
1 県内草地は、河川敷草地、イタリアン草地、オーチャード・リード草地の3つに区分でき、
牧草のミネラル組成と土壌化学性は、それぞれ異なる特徴がある(表1)。
(1)河川敷草地
土壌は、ミネラルが全体に不足している傾向にある(表2)。
牧草についてはオーチャード・リード草地に比べてカルシウム(Ca)含量が高く、
カリウム(K)含量が低いことから、テタニー比は 1.67と低く、バランスの良好な牧草が
87%を占める(表2、表3)。
(2)イタリアン草地
土壌は、K含量が平均 1.5(当量比)と基準値の約3倍多く含まれており、K含量の
高い土壌が 85%を占める(表2)。
牧草については、ミネラルバランスの崩れた牧草が 50%を占める(表3)。
(3)オーチャード・リード草地
土壌の 50%においてCa飽和度が基準値を下回る。一方、K含量は平均 1.8(当量比)
と基準値の約3倍多く含まれており、K含量の高い土壌が 83%を占める(表2)。
牧草については、他の草地に比べてK含量が 3.30%と高く、Ca含量は 0.21%と低い。
そのため、テタニー比は 3.33 と高く、ミネラルバランスの崩れた牧草が 87%を占める
(表2、表3)。
【成果の活用・留意点】
1 土壌のK含量は、主に堆肥や尿、化成肥料の施肥量に影響を受けていると考えられる。
このことから各草地の特徴を参考にし、施肥改善の検討に活用されたい。
2 生産した飼料は飼料分析を行い、成分値を把握したうえで牛に給与するのが望ましい。
3 高K牧草を牛が摂取するとマグネシウム(Mg)やCaの吸収が阻害され、低Mg血症や
低Ca血症といった疾病を引き起こす可能性がある。特に高Kのオーチャード・リード草地
の牧草は、単体での給与を避け、低K粗飼料や濃厚飼料と組み合わせて給与する等の対策が
必要と考えられる。

- 36 -
表1 牧草のミネラル含量およびミネラルバランス (乾物中)
河川敷草地 イタリアン草地 オーチャード・リード草地(n=15) (n=34) (n=30)
Ca (%) 0.46±0.122)a3) 0.38±0.09a 0.21±0.07b
P (%) 0.27±0.10b 0.37±0.09ab 0.45±0.11a
K (%) 2.39±0.61b 2.54±0.62b 3.30±0.81a
Mg (%) 0.18±0.04 0.16±0.04 0.20±0.06
テタニー比1) 1.67±0.49b 2.10±0.54b 3.33±1.07a
テタニー比≧2.2の割合(%)
13 50 87
1) K/(Ca+Mg)(当量比)2) 平均値±標準偏差3) 各項目の異符号間に有意差あり (P<0.01)
項目
表 土壌分析値が基準値外であった土壌の割合 (%)
以下 以上 以下 以上 以下 以上
pH 6.0-6.5 80 0 41 21 47 10
Ca (当量比) (5以上) 20 - 0 - 13 -Mg (当量比) 1.0以上 0 - 0 - 0 -K (当量比) 0.4-0.6 80 13 12 85 0 83P (当量比) 10以上 67 - 3 - 10 -
Ca/Mg (当量比) 5-10 93 0 82 3 93 0Mg/K (当量比) 2以上 0 - 0 - 10 -
Ca飽和度 (%) 50-70 33 0 21 32 50 10塩基飽和度 (%) 60-80 20 13 12 47 33 50
塩基置換容量 (当量比) (10以上) 13 0 0 0 0 0
1) 基準値は関東中部地域における鉱質土壌の暫定値(日本草地協会1996)を使用 カッコ内の数値は小面積の草地のみを対象にした場合の基準値
イタリアン草地 オーチャード・リード草地(n=34) (n=30)(n=15)
基準値項目 基準値1)
河川敷草地
【具体的データ】
表1 各草地区分と土壌化学性及び牧草のミネラル組成
草地区分 地域 草地形態 牧草種類 土壌化学性 牧草の
ミネラル組成
河川敷草地 西濃、揖斐 河川敷 イタリアンライグ
ラス主体
ミ ネ ラ ル が
全体的に不足
ミネラルバランス
の良好な牧草
イタリアン草地 西濃、可茂、
中濃、恵那、
東濃、下呂
転作田等 イタリアンライグ
ラス主体
Kが過剰 ミネラルバランス
の崩れた牧草
オーチャード・
リード草地
恵那、下呂、
飛騨
転作田及
び永年草
地
オーチャードグラ
ス、リードカナリ
ーグラス主体
Kが過剰、
Caが不足
ミネラルバランス
の崩れた牧草
研究課題名:飼料分析データ等を活用した自給飼料の品質向上に関する研究(平成 27~30年度)
研究担当者:岩島玲奈
表2 土壌分析値が基準値外であった土壌の割合(平成 27~29年) (%)
表3 牧草のミネラル含量及びミネラルバランス(平成 27~29年) (乾物中)

- 37 -
肥育豚への精米給与が豚肉のおいしさに及ぼす影響
【要約】配合飼料の 60%を占めるトウモロコシを精米に置換えて給与した肥育豚のロース
肉 中の脂肪酸組成は、オレイン酸割合が増加しリノール酸割合が低下する。また、「香り」
「ジューシーさ」が向上し、消費者に好まれる豚肉が生産できる可能性が高い。
畜産研究所 養豚・養鶏研究部 【連絡先】0574-25-2185
【背景・ねらい】
飼料用米による飼料自給率の向上が推進されている。しかし、養豚農家は飼料用米を利用
するメリット(飼料用米の利用よる生産コストの低減や高品質差別化販売)を十分に認識出来
ていない。これまでに、飼料用米を用いた豚肉の食味向上技術について検討した結果から、
飼料用米を飼料の 60%配合した飼料を肥育後期の肉豚に給与した場合、発育はトウモロコシ
主体の慣行飼料を給与した肉豚と同等で、豚ロース肉の脂肪酸組成はオレイン酸割合が多く、
リノール酸割合が少なく、食味官能試験結果から「食感」や「ジューシーさ」において食べて
違いが分かる食味となる豚肉が生産できる可能性が考えられた。
そこで、主要飼料原料を精米 60%とした配合飼料を給与して生産した豚ロース肉とトウモロ
コシを主体とした飼料を給与した豚ロース肉を用いて食味官能試験を実施し、再現性を検討し、
精米給与が食味に与える影響について明らかにする。
【成果の内容・特徴】
1 食味官能試験で用いた精米区の豚ロース肉の脂肪は、対照区よりもオレイン酸割合が高く、
リノール酸割合が低かった(表1)。
2 一定の形状でカットした豚ロース肉(図1)を4%の食塩水に5分浸漬後、230℃の IH
ホットプレートにて 60 秒ローストし、食味官能試験に供試した(パネリスト構成は表2の
とおり)。
その結果、精米区が対照区に比べ「香り」が有意に好ましいと回答され、「ジューシーさ」
は好ましいと回答される傾向が観察された。一方、「食感」については、対照区の方が好ま
しい結果であった(表3)。
3 以上のことから、精米給与によって豚ロース肉中のオレイン酸割合が増加し、リノール酸
割合が低下することによって豚ロース肉の「香り」が好ましくなる。
【成果の活用・留意点】
1 豚ロース肉中の脂肪酸組成の違いが香りにどのような作用機序で影響を与えているのかは
不明である。
2 豚肥育後期飼料に精米を 60%配合することによって豚肉の「香り」が向上する可能性が
示唆されることから、銘柄豚肉の生産において食味(特に「香り」)で差別化する際に活用
されたい。
3 養豚生産者によってはペレットもしくはクランブル(ペレット化した飼料を破砕)形状の
豚肥育後期飼料を使用している場合がある。精米を 70%配合した飼料をペレット化すると
加熱膨化によってペレット化が困難な場合があり、本成果を活用する際は飼料メーカーとの
事前協議を推奨する。

- 38 -
【具体的データ】
表1 各区の背脂肪内層中脂肪酸組成
表2 食味官能試験参加者の年齢、性別構成 表3 食味官能試験結果
研究課題名:国産豚肉差別化のための「おいしさ」評価指標と育種改良技術及び飼養管理技術
の開発(平成 28~32年度)
研究担当者:吉岡豪
25.5 ± 0.911) 26.2 ± 1.20
16.2 ± 0.98 B 2) 17.9 ± 1.31 A
39.6 ± 1.55 b 3) 41.4 ± 1.47 a
12.5 ± 1.74 A 8.7 ± 1.21 B
0.59 ± 0.08 A 0.46 ± 0.07 B
0.64 ± 0.08 A 0.45 ± 0.07 B
43.3 ± 1.73 b 45.7 ± 2.16 a
42.1 ± 1.61 b 44.0 ± 1.60 a
13.8 ± 1.88 A 9.6 ± 1.32 B
1)平均値(%)±標準偏差
2)異符号間に1%水準で有意差あり
3)異符号間に5%水準で有意差あり
多価不飽和脂肪酸
飽和脂肪酸
一価不飽和脂肪酸
α -リノレン酸(C18:3n-3)
エイコサジエン酸(C20:2n-6)
オレイン酸(C18:1)
リノール酸(C18:2n-6)
パルミチン酸(C16:0)
ステアリン酸(C18:0)
項 目 対照区 (n=12) 精米区 (n=12)
図1 供試した豚ロース肉の形状
男性 女性 合計
10代 19 19 38
20代 1 1 2
30代 1 1 2
40代 4 0 4
合計 25 21 46

- 39 -
採卵鶏における飼料用米(籾)の長期給与
【要約】飼料用米(籾)を 10%添加した市販配合飼料は、銘柄差はあるものの産卵成績、
卵質成績からみて、560日齢まで長期給与することが可能である。
畜産研究所 養豚・養鶏研究部関試験地 【連絡先】0575-22-3165
【背景・ねらい】
鶏は飼料用米を籾のまま粉砕することなく利用することが可能であり、他の畜種よりも低
コストで利用できるため、飼料用米は鶏での利用拡大が最も有効である。これまで飼料用米の
飼料への混合は自家配合が主体であり、今後更に利用拡大を図るには、自家配合していない
市販配合飼料農家への普及定着が必要である。そこで、採卵鶏に対し一般農家で取り組みやす
い市販配合飼料に上乗せ添加する方法で長期給与(560 日齢まで)し、産卵成績及び卵質成績
への影響を明らかにする。
【成果の内容・特徴】
1 A銘柄の飼料要求率が市販配合飼料に籾を 10%添加した飼料用米区で市販配合飼料のみの
対照区と比較し有意に高いが、その他は飼料用米給与による影響はみられない(表1、表2)。
2 産卵率は、A及びB銘柄とも産卵後期には飼料用米区が対照区と比較して低い傾向である
が、産卵ピークまで飼料用米区と対照区でほぼ同等であり、飼料用米給与による影響はみら
れない(図1、図2)。
3 卵質は、飼料用米給与により卵黄色のカラーファン値及び a*値が低くなる傾向がみられる
が、卵黄色以外では飼料用米給与による影響はみられない(表3、表4)。
4 B銘柄では飼料用米区、対照区ともに飼料摂取量は同じで、飼料用米を添加することに
より飼料単価が安くなる飼料用米区の方が、飼料費を試算すると安くなる。
5 鶏卵の MS、M及び L規格(高取引価格帯)の占める重量割合は、飼料用米区が卵重の大き
くなる産卵後期において対照区と比較して高くなる傾向がみられ、高卵価が期待できる
(表5、表6)。
6 以上のことから、市販配合飼料への飼料用米(籾)の 10%添加による 560日齢までの長期
給与は、産卵成績、卵質成績からみて活用可能である。
【成果の活用・留意点】
卵黄の淡色化が懸念されるが、目視で卵黄色の大きな違いは分からず、飼料用米(籾)の
10%添加程度までなら卵黄色改善のためのパプリカ粉末等の添加は不要である。

- 40 -
表3 A銘柄の試験期間中の卵質成績(8回実施)
対照区 飼料用米区
卵重(g) 62.3 62.2
卵殻強度(kg/cm2) 4.2 4.2
ハウユニット 89.1 91.0卵黄色 カラーファン値 12.9 12.0* L*値 50.7 52.1 a*値 13.5 10.8 b*値 76.0 77.4
*P<0.05各区 n=50羽
表4 B銘柄の試験期間中の卵質成績(8回実施)
対照区 飼料用米区
卵重(g) 60.8 60.0
卵殻強度(kg/cm2) 4.1 4.2
ハウユニット 89.0 89.0卵黄色 カラーファン値 12.9 12.3 L*値 50.3 51.9 a*値 13.4 11.3 b*値 76.1 76.6
各区 n=50羽
【具体的データ】
対照区、飼料用米区各 100 羽 対照区、飼料用米区各 100 羽
研究課題名:採卵鶏と特殊卵用鶏への飼料用米長期給与方法及び飼料用米多給時の卵黄色改善
手法の確立(平成 28~29年度)
研究担当者:園原浩昭
(平成 28~29年)
図表の使用データ
:平成 28~29 年度

- 41 -
アユの遡上のない河川でのアユ早期小型放流技術の有効性
【要約】アユの遡上がない河川で早期小型放流と晩期大型放流の費用対効果を比較した結果、
早期小型放流は放流数の増加による利点が河川での減耗リスクを上回り、晩期大型放流より
費用対効果が高い。
水産研究所 下呂支所 【連絡先】0576-52-3111(内 405)
【背景・ねらい】
県内のアユ漁獲量はピークである平成4年の3割程度に減少し、河川のアユ資源を増やす
ための効果的な方策が必要である。特にアユの遡上がない河川では、漁業協同組合が放流する
アユがアユ資源のすべてであり、放流方法がより大切になる。
近年、冷水病対策としてアユの放流時期は以前より遅くなるとともに、放流から解禁までの
成長期間短縮を補うため、大きなサイズのアユが放流される傾向にある。大型化に伴い放流
尾数は減少するため、漁獲量減少の一因と考えられる。
そこで、早期に小型のアユを放流(早期小型放流)し、河川に長期間いることによる減耗
リスクと、晩期に大型のアユを放流(晩期大型放流)することに伴う放流尾数の減少を比較し
(図 1)、より効率的な放流方法を検討する。
【成果の内容・特徴】
1 放流アユは重量単位で取引されることから、同経費での放流尾数は、早期小型放流が晩期
大型放流より多い。
2 アユ解禁日の漁獲調査で、早期小型放流も友釣りで釣れるサイズに成長しており、小型の
アユでも早期に放流すれば河川で十分に成長することがわかった(図2)。
3 1 人 1 時間当たりに釣れる尾数(CPUE)は漁期を通して、早期小型放流群の方が高い
(図3)。
4 早期小型放流における放流尾数の増加による利点は、河川に長期間いることによる減耗
リスクの欠点より大きく、費用対効果が高い(図表 1)。
【成果の活用・留意点】
1 冷水病菌を保菌していない種苗を使用する。
2 河川水温8℃未満での放流は、漁場からの移出のリスクがあるため控える。
3 放流尾数を多くすることを重要視して、放流サイズをあまり小さくしすぎると解禁時に
十分成長していない可能性がある。
4 カワウの河川への飛来時期が早い漁場では、早期小型放流による減耗リスクの方が放流
尾数増加の利点を上回る可能性がある。
5 成果をまとめたものを漁業協同組合が使いやすい形でマニュアル化する。

- 42 -
【具体的データ】
図 1 早期小型放流と晩期大型放流
表 1 早期放流と晩期放流の費用対効果の結果
河川※1 竹原川① 竹原川② 大洞川 白川
費用対効果 早期:晩期 早期:晩期 早期:晩期 早期:晩期
2.78※2:1 4.76:1 2.28:1 1.63:1
※1 竹原川①(平成 18 年)、竹原川②(平成 19 年)、大洞川(平成 27 年)、白川(平成 28 年)
※2 費用対効果比=
研究課題名:岐阜県先進技術(遡上予測、子持ちアユ生産)活用による河川漁獲量及び
養殖生産量の増大(平成 26~30年度)
研究担当者:德原哲也
図2 漁獲魚の体重の推移(平成 28年) 図3 1人1時間当たりに釣れる尾数
の推移(平成 28 年)
早期放流の再捕尾数÷放流種苗費
晩期放流の再捕尾数÷放流種苗費