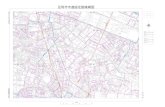03 Internship reportjupiter2.jiu.ac.jp/books/academy/2009/welfare/03.pdf27...
Transcript of 03 Internship reportjupiter2.jiu.ac.jp/books/academy/2009/welfare/03.pdf27...

─ 27 ─
平成21年度福祉インターンシップレポート
担当教員:福田順子 矢木公子 米山恒雄 家富誠敏 国武陽子
20世紀は経済が飛躍的に拡大し,人々は豊かになりましたが,地球環境問題とコミュニティの崩壊
という負の遺産が遺されました。そのため,福祉,医療,環境,教育などの社会サービスへのニーズ
が拡大し,多様な広がりを持つようになりました。そうしたニーズを満たし,心の豊かさ,生活の豊
かさが実感できる社会にしていくためには,特定の専門家だけではなく,多様な人々が社会サービス
に係わっていけるように,産業構造を変えていく必要があります。
そのような背景から,国内外を問わず新しい発想で新しい社会サービスを開発し,定着させている
企業や NPO が増えてきています。それらの組織の共通点は,よい社会をつくりたいという強い想い
や信念を持つ暖かいリーダーが存在することと,問題の本質をとらえ,地域の持つ力をうまく引き出
して,現実的に解決していく仕組み,仕掛けを用意していることです。ニーズが多様化していく中で,
社会サービスの専門家もそうした新しい発想や仕組みを取り入れたり,連携したりすることも大切に
なってくると考えられます。
福祉インターンシップは,その様な新しい取り組みをしている企業や NPO の業務,例えば知的障
害者と共に働くことなどを体験することによって,「知的障害者が集中力や責任感において自分たち
を超える能力を持つこと」や「その人たちが生きいきと働けるように行動しやすい仕組みや仕掛けが
あることに気づくこと」など,固定観念にとらわれないものの見方を身につけ,専門知識を学ぶ能力
を高めることを目的としています。そのため,就業体験を目的とする一般のインターンシップとは異
なり,2~3年次に配当しています。
この科目は通年の科目で,研修に行く前,研修時,研修後の3段階の学びで構成されています。
研修に行く前の事前学習では,福祉経営を先駆する企業に関する基礎知識とそのような企業で働く
意義,職場における心得などを学ぶとともに,研修先企業に関する情報収集を行います。
実際の研修は,夏休みを利用した実質10日間を充てて行います。5名の担当教員が手分けをして,
この10日間の研修中に研修先を訪問し,学生たちの動向を把握するとともに,研修先からお話を伺い,
研修生が残りの研修を恙無く,意味あるものにする手助けをしています。
研修後の後期授業期間中には,自分たちの体験を振り返るとともに,他の研修先でのインターンシッ
プの話を互いに聞きながら,福祉インターンシップについての情報共有を行ないます。教員にとって
もその報告は楽しみの一つです。
今回の研修先は以下の企業・団体です。学生を派遣するに当って説明した企業・団体の特色やポイ
ントを含めて紹介します。順番は五十音順です。

─ 28 ─
*アミタ(株) 京丹後の森林の牧場:
森林酪農と食品リサイクルシステムによる循環型の地域づくり
*アミタ(株) 那須の森林の牧場:
森林酪農を核とした首都近郊の高 QOL ライフスタイルの地域づくり
* 大里綜合管理(株):
学童保育や環境保全などの地域貢献に力をいれる不動産管理会社
* (株)中洞牧場:
家畜福祉の概念を導入し家畜に優しく環境保全にも力を入れる牧場
* ビーアンビシャス(NPO):
障害者が自立できるスキルと給与を,蕎麦屋と受託事業で実現するNPO
*(有)ヴィ王子:
障害者と健常者がともに働くベーカリー,カフェ,焼き立てパンの宅配も
* ワタミ(株):
食とサービスに関して人気の高い有料老人ホームを経営する外食企業
今年度の研修先は「個人を対象とした新しいサービスを提供している事業所」と「新しい発想で地
域と共生し,地域づくりに貢献している事業所」という2つのグループに分けて考えることができます。
1.個人対象の新しい社会サービス [ビーアンビシャス,ヴィ王子,ワタミ]
ビーアンビシャスとヴィ王子は,いずれも障害者と健常者が「共に働く」場をつくり,障害者が自
立できるだけの給与を支払えるように経営している NPO,企業です。障害者の自立支援を行う店は,
今日では全国各地にありますが,ヴィ王子はその草分けの一つです。また,ビーアンビシャスは,障
害者の自立のための技能(そば打ち)の習得まで踏み込んだ先進的な事例といえます。
ワタミは外食産業の経験を生かした有料老人ホームの経営を行っています。例えば嚥下できない人
向けの食事を,できるだけ形を残して柔らかく仕上げる技術により,食事が楽しめるようにするソフ
ト食を提供するなど,外食産業の経営ノウハウが様々に生かされています。
2.地域との共生,地域づくり [大里綜合管理,アミタ,中洞牧場]
大里綜合管理は,本業の不動産管理の延長上に,学童保育や,地域の清掃,コンサートの開催など,
70を超える地域貢献活動をごく自然に行っている企業で,企業経営と社会貢献が決して矛盾するもの
ではないことを学びとることができます。
アミタと中洞牧場は,いずれも失われてしまった自然と人間,産業・社会のつながりを取り戻すこ
とによって地域社会を生きいきさせようとしている企業です。アミタの2つの森林の牧場は,森林と
牛との共生を利用して森林の手入れを容易にし,生きいきした自然の恵みを乳製品や,教育,都市住
民の憩いの場等に生かしています。中洞牧場は,牛を通年放牧する山地酪農の先駆者であり,人と自
然との本来のつながりを消費者に示して,共感の輪を広げています。

─ 29 ─
福祉インターンシップレポート「アミタ那須の森林ノ牧場」
福祉総合学科2年 遠藤 美沙希
1.はじめに
私は,8月17日から26日までアミタ那須の森林ノ牧場で研修をさせていただきました。私がアミタ
那須の森林ノ牧場を実習先に選んだ理由は,森林の牧場という新しい試みに興味があったからです。
一般の牧場と何がどのように違うのか,なぜ企業がそういう取り組みをしているのか,これからの社
会や私たちの生活にどのように係わってくるのかいろいろ知りたいと思いました。
2.会社の概要
(1)会社の目的
アミタグループの会社名は,サンスクリット語の「限りない命(アミターエス)」「無限の智慧(ア
ミターバ)」に由来し,持続可能な社会を実現したいという強い想いを表しています。その目的を果
たすために,人類が自ら破壊してきた自然と社会と人間とのつながりを回復する,新たな「循環型シ
ステム」を形成することを事業の基本理念としています。
例えば,「資源リサイクル」という言葉さえ一般的ではなかった1977年,廃棄物から亜鉛を取り出
し再資源化したのがアミタの歴史の始まりですが,これは廃棄物を発生する会社と原料を必要とする
会社とをつなぐ資源の循環システムを形成し,廃棄物を「地上の資源」に変えたという成果です。こ
れが「リサイクルオペレーション」事業の始まりだったわけです。
それ以来,アミタグループは,鉱物資源にとどまらず,農林水産業,食,エネルギーなど多様な分
野に「つながり」をつくることによって,新たな価値を創りだす事業を展開しています。
(2)事業の内容
アミタグループの事業は,現在,大きく分けて3つの分野があります。
① 価値がないと見なされ,捨てられた廃棄物を再資源化する地上資源事業
これは上に述べたように創業以来の事業分野です。
② 自然資本を活用した事業創出などにより,地域の持つ価値を引き出し,豊かな地域づくりを目
指す自然産業創出事業
今回研修させていただいた那須の森林の牧場の事業はそのひとつです。
③ 責任ある適切な資源の利用を推進するための認証サービスやコンサルテイション・アウトソー
シングを実施する環境ソリューション事業
以上のようにアミタグループは,創業時の資源リサイクル事業に始まり,環境リスク対策,農林水
産業,エネルギー,食といった様々な分野で「循環型システム」をつくってきました。絶え間なく変

─ 30 ─
化し続ける生態系のようにアミタグループはこれからも進化し,世の中にとって欠かせない「つなが
り」をつくり続けていくそうです。
3.那須に於けるアミタの事業
森林の牧場とは,牛を森林の中に自然放牧することを指しています。わが国は国土面積の約67%を
森林が占める森の国ですが,木材価格の低迷や林業従事者の高齢化で手入れが行き届かず,木が育た
なくなって土砂崩れや洪水が心配される状況になっています。森林に牛を放牧すれば,牛が下草を食
べてくれるので,森林を管理する仕事が楽になります。定年退職した方や,ハンディキャップを持た
れた方が働くこともできますので,雇用や福祉に役立つ場にもなります。また,乳製品の販売などで
収益があげられます。更に手入れが行き届いた美しい森林は,子供たちの教育の場ともなり,人々の
憩いの場ともなって地域に貢献することができます。
アミタグループには,京丹後と那須の2か所に森林牧場があり,那須の森林の牧場の開設に当たっ
ては,先行している京丹後のノウハウが十分に生かされているそうです。京丹後と違うところは,首
都圏に近いリゾート地にあることで,地域の自然から生まれた乳製品を地域のレストランや宿泊施設,
教育機関に提供し地域循環型の地域づくりにつなげ,同時に首都圏の人々との交流の場を提供するこ
とによって,持続可能で心豊かな,QOL の高いライフスタイルを那須から発信したいとしていると
ころです。
4.実習内容
●朝の搾乳体験
搾乳体験は一番長く牛と接する時間でした。初めての搾乳では,驚くことがいっぱいありました。
まず,搾乳の時間になると牛たちが自然に集まってきて順番を待っているのです。また,牛の乳をな
めると,そのときの牛の状態を把握できるということが意外でした。味がいつもと違うと病気になっ
ているかもしれないので,味を確かめて搾乳してよいかどうか確認するのだそうです。搾乳の場所は,
一番大切なところなので,常にきれいな状態でなければならないということもよくわかりました。
●パドックの清掃
パドックは,朝の搾乳のときに牛が集まるところです。ここでは,牛のいろいろな体調を調べると
ころでもあります。たとえば,妊娠しているかを調べるときなども使用します。ここも常にきれいな
状態でなければなりません。念入りに掃除をするように心がけました。
●森林の整備
牛たちが食べる牧草がなくなりかけているので,新しく牧草を生やしたり,芝植えをしたり,新し
く植えた木などを牛が食べないように補強したりしました。
森林の整備をしていて感じたことは,牛の糞が臭くなかったことです。また,牛は常に群れでいる

─ 31 ─
動物ということもわかりました。集団でまとまっていることは,管理がしやすい面もあると思いまし
た。森林の牧場といっても,人が全く手をかけないわけではありませんが,牛のおかげでその手間も
少しで済んでいるようです。
●プレート作成
出来たばかりの牧場内の看板製作をしました。電動のこぎりなど,日常では使わないものを使うこ
とができ,とても貴重な体験ができました。
●キノコ植え
キノコ植えでは,木にキノコの液を注入して,それをラップでくるみ,それを植えるという作業を
行いました。はじめての経験だったので,とても楽しくできました。
5.実習で学んだこと
インターシップに行く前は,一般の牧場となにが違うのか,企業がなぜ森林の牧場を作ったのか,
これからの社会や私たちの生活にどうかかわってくるのかということを知りたいと思っていました。
森林の牧場の概念は事前学習である程度は分かったつもりでしたが,沢山の事柄がつながっているの
で,いま一つイメージがはっきりしないという状態でした。
実際に実習していて思ったことは,「つなげる」ことの大切さです。これまでの社会では,林業は林業,
酪農は酪農というように専門に分かれて行っていましたが,木材の価格の低下,輸入飼料の値上がり
や,食品安全性の問題などで行き詰まりを見せています。森林の牧場はその林業と酪農をつなげるこ
とによって,両方とも元気になれることを示していると思います。もともと荒れて間伐されずにいた
森に牛がいることで,多くの人手を使わずに,森林が本来の姿になり,輸入飼料を使わずに牛乳が生
産できるのです。これが,一般の牧場との根本的な違いです。
牛乳の味も違っていました。市販の牛乳とくらべて,この牧場の牛乳は低温殺菌でさらりとしてい
てコクがありおいしかったです。これが本来の牛乳の味なのだと思いました。森林の牧場にいる牛た
ちの牛乳やアイスを牧場内のカフェや,提携しているお店に販売することで,利益を出す工夫をして
いました。食の安全が重視され自然志向が強まっていることもあって,注目度は高いようです。
それだけではなく,森林の牧場にいる牛たちは,ずっと外にいるのに見た目がとてもきれいでした。
とても可愛かったです。傾斜地を行き来して足腰を鍛えた健康な牛は本当に美しいと思いました。ま
た,間伐の行き届いた森は明るく木や草が生きいきとしていてすがすがしい感じでした。森林の牧場
の周辺は環境も良く,住みやすい場所となり,子供の自然教育の場や高齢者にとってアニマルセラピー
の場にもなり,福祉にもつながっていると感じました。この牧場のそばに高齢者住宅を建設する計画
があるとも聞きました。
このように,基本は森林と酪農とのつながりでしたが,それが食品事業にもつながり,優れた住環
境づくりにもつながり,次々につながっていくことによって,大きな費用を使わずに豊かな環境を創

─ 32 ─
りだすことができるという実感を持つことができました。アミタグループがこの事業に取り組んでい
るのは,そのためであり,持続可能な社会を創るために循環システムの形成を目指すという企業理念
の表れだと思います。
また,つながりを創るということは,信頼感につながると思います。森林の牧場の牛乳が少し高い
のによく売れるのは,本当に健康に育っている牛からもらったものという安心感,信頼感と,この事
業を行っている人々への共感があるからではないでしょうか。つながりを大事に広げていくというこ
とが,これからの社会,私たちの生活に求められていると思います。
6.まとめと今後の課題
今回のインターシップでは,今までに経験しなかったことを経験することができ,とてもいいイン
ターシップになりました。つながりということを大切にしていきたいと思いました。現代社会は経済
の成熟,環境問題,コミュニティの崩壊などの問題を抱えて行き詰まっています。それを打開するた
めには,これまで別々に歩んできたものをつなげることが大切だということを,今回の研修で学びま
した。これから様々な活動に生かしていこうと思います。
今後の目標は,福祉にかかわる仕事をしたいと思っているので,ここで学んだことを活かし,役に
立てたいと思います。また,これからもさまざまなボランティア活動を行って,より多くのつながり
を持てるようにしていきたいです。
福祉インターンシップ研修レポート「NPO 法人ビーアンビシャス」
福祉総合学科3年 秋葉 剛
1.はじめに
私は,8月19日から29日まで NPO ビーアンビシャスで研修させていただきました。私がビーアン
ビシャスでの研修を希望した理由は,障害を持った人と一緒に働いて,健常者と障害者の違いを理解
したうえで協力しながらどのように働けるのかを学びたかったからです。
2.研修先の概要
(1)ビーアンビシャスの目的
NPO 法人ビーアンビシャスは,障害者の方が協力して働く場を作りその人たちが自立できるよう
に支援することを目的としています。実際の仕事は製麺作業・お菓子の製造・接客・受託業務の四つ
に分けられています。それぞれの仕事にみなさんは毎日取り組んでいます。

─ 33 ─
(2)業務の内容
四つの業務の内容は次の通りです。
・製麺作業:蕎麦の実の製粉,蕎麦・うどん粉のこね,麺棒での延し
・お菓子の製造:洋菓子製造の計量,成型,焼き上げ,袋詰め作業,真空パック
・接客:直営店「まごころ庵」で注文,接客サービス,レジ打ち
直営店「まごころ庵」で社員の方が打った蕎麦や,作ったお菓子を販売し,店内でも障害者が注
文を受けて,レジもしています。11時半から14時まで営業をして,三万円以上の売り上げを目指し
ています。
・外部企業からの受託業務:飛行機内のヘッドフォンクリーニング
3.実習内容
・製麺作業体験(蕎麦の実の製粉,蕎麦打ち,麺棒での延し)
製麺体験では,社員の方に,蕎麦を混ぜる作業やこねる作業,切る作業を教えていただきました。
混ぜる作業では,最初からすぐに混ぜることができました。しかし,麺棒での延しの作業や切る作業
では,なかなか,うまくできませんでした。麺棒での延しの作業は,何回もやり直して,やっとでき
るようになったのですが,切る作業は,まだうまくできませんでした。この作業に取り組んで,社員
の方,障害者の方が,真剣にかなりの時間をかけて訓練していることがわかりました。皆さんは,と
てもすばらしい蕎麦打ちの能力を持っていました。
・接客指導(注文の指導,店内での接客サービス)
接客指導に関しては,直営店「まごころ庵」のが開店する前に,接客のしかたを社員の方と副理事
長の中村さんに教えていただきました。食事の提供の基本は,ドリンクサービスは右から,食事(そ
ばなど)は左手からであり,そして,笑顔でのサービスが重要であることも学びました。社員の方に
接客指導もさせていただきました。店内での接客サービスは,はじめてやりました。少し緊張してし
まいましたが,自分から動きはじめ,中村さんに教えていただいたとおりに,働くことができたと思
いました。その後,お客さんの前では,緊張感を持ち,気を使うことが必要と思いました。
・受託業務の作業指導(飛行機で使われるヘッドフォンのクリーニング作業指導)
受託業務の作業指導では,飛行機で使われるヘッドフォンのクリーニングを行いました。作業する
前に絡まっているコードの解き方,消毒の仕方,ヘッドフォンについているスポンジの確認の仕方,
コードの巻き方などの作業の仕方を教えていただきました。ヘッドフォンクリーニング作業は,何回
もやってキレイにできるようになりましたが,社員の方は,それ以上の素早い作業がよく見られ,真
剣に働く姿勢がすごいと思いました。
・他事業所見学(世田谷区民営作業所・東京カペナント教会のぞみ園)

─ 34 ─
のぞみ園という専務の五十嵐さんのお姉さんが都内で経営しているところを見学しました。のぞみ
園は,一日に100枚以上のクッキーやパウンドケーキを作って販売しています。のぞみ園では,とて
も静かな環境で作業を行っていることと,作業への真剣な姿勢がとても印象深く感じられました。
4.実習後の感想
はじめて障害者の方と仕事をしてみて,健常者と障害者との作業への取り組みの違いや,障害のあ
る人たちの持つ個性に気がつきました。五十嵐専務,理事長,中村さんが,障害のある人をサポート
する時,長い目で見るということが大切であると教えてくださいました。みんな,それぞれの個性に
合わせて,十分に仕事ができていました。たとえば,障害のある人が4年掛けて蕎麦を作れるように
なるのも,本人の努力や,経営者が長い目で見ていたからだと思います。
僕たち以上に責任感を持ち仕事をしている障害のある人たちの姿を見て,どんな仕事でも一生懸命,
みんな必死で仕事をしていると強く感じられました。僕たちは,その姿を見習いたいと思います。
福祉インターンシップレポート「有限会社 ヴイ王子 スワンベーカリー十条店」
福祉総合学科2年 伊藤 智恵
1.実習先の概要
私は今回,福祉インターンシップで有限会社 ヴイ王子 スワンベーカリー十条店で実習を行いまし
た。
スワンベーカリーは,パンの製造販売を行うフランチャイズチェーンで,一部店舗では喫茶店も経
営しています。その目的は,障がい者の雇用および収入の確保,自立支援であり,平成10年にヤマト
運輸とヤマト福祉財団が「株式会社スワン」を設立し,スワンベーカリー銀座店が直営第1号店とし
てオープンしました。その後,平成13年に赤坂店がオープンし,オープニングセレモニーには小泉首
相,ベーカー駐日米大使も来店し,マスコミの注目を喚びました。翌年の平成14年には本格的なカフェ
スタイルのカフェ銀座店がオープンしました。ディナータイムには,生ビール,本格的なワイン,カ
クテルなども楽しめるお店です。
私が今回実習した十条店は,スワンチェーン店として平成11年にオープンしました。東京都北区上
十条で「王子養護学校の卒業生を応援する会」が母体となった「有限会社ヴイ王子」が経営を行って
います。十条店の特色は,外販にあり,厚生労働省等官庁・病院・学校等に積極的に出張販売をして
います。
さらに翌12年には落合店,広島県三原市港町で三原店をオープンさせ,現在直営店3店,チェーン
店は23店を超え,各地に展開しています。働いている障がい者の数は,全店で273名を超え,知的・精神・

─ 35 ─
身体に障がいのある方を雇用し,その7割以上は知的障がいの方たちです。スワンベーカリーの命名
者は故・小倉理事長で,みにくいアヒルの子と思っていたら実は「白鳥=スワン」だったというデン
マークの童話作家アンデルセンの作品から命名をしたそうです。
2.実習の内容
インターンシップは8月6日~10日および8月21日~26日の計10日間の日程で行いました。
私はまず,インターシップに行く前に目標を立てました。いつもは客として何気なく商品を買ってい
ますが,今回のインターンシップではパンの製造から包装,そして商品を販売する側になります。職
場では障がいを持った方達がそれらの仕事をこなしているわけですから,一緒に働くことでスワン
ベーカリー独自の仕組みなどを理解し,作業をしていきたいと思いました。また,インターンシップ
を通して,障がい者との接し方や商品提供側として大切なこと,大学で学んだことの活かし方,パン
の製造工程なども学びたいと思いました。これらのことを踏まえインターンシップに挑みました。
実習では障がい者とともに大きく分けて3つの作業を行いました。パンの袋詰め・掃除・出張販売
です。パンの袋詰めは出勤して最初に行う作業です。毎日いろいろな所へ出張販売に行くので,販売
する分のパンを袋詰めします。この作業では,綺麗に袋詰めすることはもちろん,菓子パンなど砂糖
を使っているので袋詰めする際に袋にくっついてしまいベタベタになってしまうことがあったので,
お客さんが食べやすいように袋詰めすることに苦労していることがわかりました。
掃除は店内や調理場を清掃しました。店内はお客さんに気持ちよく利用してもらえるように綺麗に
掃除をしていました。調理場ではパンを焼く釜の焦げを取りましたが,少し熱かったので大変な作業
でした。
出張販売では都庁・霞ヶ関・淑徳大・老人ホーム・スポーツセンター・クロネコヤマトへの出張販
売に同行しました。特にインターンシップ初日に行った霞ヶ関では自分が袋詰めしたパンを買っても
らう光景を見ることができ,とても嬉しく思いました。
3.実習をふりかえって
・初日はパンの袋詰めと掃除などを行いました。初日ということもあり,緊張していてあまり動けず
に迷惑をかけてしまいました。
・2日目はできるだけ自分から積極的に動こうと心がけました。作業的には初日と同じでしたが出張
販売で都庁に行きました。普段入ることがない場所なので,興味深い経験ができました。
・3日目も同じ作業でしたが,周りの雰囲気にも慣れてきて,だんだん作業スピードが速くなりまし
た。出張販売では淑徳大に行き,たくさんのパンを買ってもらいました。
・4日目はスワンベーカリーでの作業はなく3日目と同じ淑徳大に行きました。パンもたくさん買っ
てもらえて良かったです。また,従業員の方とも打ち解けて話ができるようになって嬉しかったです。
・5日目は前半最終日でした。パンの袋詰めから始めましたが,慣れてきたつもりで,袋詰めしにく
いパンもあり,単純でも難しい作業であることを再認識しました。出張販売では,また都庁に行か

─ 36 ─
せてもらい,普段と違う雰囲気を味わうことができました。
・後半の6日目もパンの袋詰めから行いました。久しぶりだったので心配でしたが無事に袋詰めも終
わり,老人ホームに出張販売に行きました。しかし,この日は老人ホームで,一つミスをしてしま
いました。それは,老人の方にコーヒーを頼まれたとき,コーヒーをテーブルに置く際に不自由な
手の方にコーヒーを置いてしまったことです。一瞬でも気を緩めてはいけないと感じました。
・7日目はお昼からの出勤でした。出張販売はスポーツセンターに行き,パンもたくさん買ってもら
うことができました。前の日にミスをしていたので,この日はこれまで以上に気を引き締めて作業
を行いました。
・8日目は出張販売がなく,パンの袋詰めと掃除を行いました。お客さんも少なく,静かな一日でした。
・9日目は特に掃除に力を入れました。トレーやトングなど細かいところまで気を付け,お客さんが
いつでもきれいな状態で使えるように心がけました。出張販売は提携しているクロネコヤマトに行
きました。スワンベーカリーと同じように,障がい者の方が30人ほど働いている光景が新鮮に感じ
ました。
・最終日の10日目もパンの袋詰めをし,掃除をし,クロネコヤマトへ出張販売に行きました。この日
はすべての作業をいつも以上に気を引き締めて行いました。最後,終わった時は大きな達成感を感
じました。
4.実習を終えて
毎日,電車で2時間半かけて出勤するのは,普段の大学生活と異なり大変でしたが,その分,達成
感は大きく,成長を実感できました。また,同じ仕事をしながら,障がい者の方と接することで,自
然なコミュニケーション方法について学ぶことができたとともに,その働く姿に触れて福祉を学ぶ気
持ちがさらに深まりました。スワンベーカリーの皆さんにはインターンシップの時間を作ってもらい,
とても感謝しています。今回,学んだ知識や経験はこれからの大学生活や勉強に生かしていきたいと
思います。
福祉インターシップレポート「ワタミの介護株式会社 介護付有料老人ホーム レストヴィラみつわ台」
福祉総合学科2年 小田部 翔太
1.はじめに
私は,平成21年度福祉インターシップにおいて,8月17日から8月30日の日程で「ワタミの介護株
式会社」の経営する介護付有料老人ホーム「レストヴィラみつわ台」で研修を行いました。ワタミの
介護株式会社は,ワタミグループの農場で野菜・動物を育てることで,食材の安心・安全を追求し,“ご

─ 37 ─
入居様”にあわせた調理法で温かい料理を提供しているのが特徴です。私は,この魅力的な食事を提
供しているワタミの介護に興味を抱き,研修先に希望しました。
2.ワタミグループについて
「ワタミの介護株式会社」はワタミグループに属しています。ワタミグループのスローガン,ミッショ
ンは以下の通りです。
1)スローガン:地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう
2)ミッション:地球人類の人間性向上のためのよりよい環境をつくり,よりよいきっかけを提
供すること
また,ワタミグループは以下の6つの部門で構成されています。
部門名 基本理念・提供内容
外食 お店のお客さまのためだけにある
介護 ご高齢者の方からも,たくさんのありがとうを集めること
農業 食の基本である安全・安心を追求し,次世代に良い環境を残し,人々の幸せに貢献する
環境 様々な施設の「生む~創る~守る」を一貫して行い,施設の価値を最大限にするととも
に地球環境へ貢献する
MD バラエティ豊かで,常に変化し続けるメニューを支え,安全で,衛生的で,フレッシュ
な製品を,均質に圧倒的な安価で提供し続けること
社会貢献 より多くに人々に幸せへのきっかけの提供
以上の6つの部門が協力して,ワタミグループのスローガン・ミッションの実現に取り組んでいます。
3.ワタミの介護について
ワタミグループの介護部門を担っている「ワタミの介護株式会社」では,次の理念に基づき介護を
行っています。それは『ひとつ屋根の下で似たような生活リズムで過ごすことに成りがちな老人ホー
ムで,ワタミの介護では家庭的で居心地の良い清潔な空間で“ご入居様”一人ひとりの自分らしく自
由で豊かな時間が流れる暮らしを目指し,「美味」「楽しみ」「快適」「安心」の4つを総合的に行い,“ご
入居様”が主役の介護を実践する』という考えです。
また,ワタミの介護は食事へのこだわりがあります。ワタミグループでは,安心・安全な商品を提
供したいという想いのもと,土づくりからこだわったワタミファーム(野菜・動物)で生産された有
機農産物を積極的に導入しています。食事内容も援助内容も「個人差」により様々であり,介護技術
と食の知識をベースとして,一人ひとりに寄り添うことが必要であると考え,家族それぞれの体調や
好み,障がい等をしっかりと把握した「料理自慢の主婦が提供する季節の安心食材を使った変化のあ
る豊かな食卓」を目指しています。これを実践する食事がワタミの介護の特徴です。

─ 38 ─
4.インターシップの目標
ワタミの介護が経営する有料老人ホーム「レストヴィラみつわ台」でインターシップを行うにあた
り,私は,研修先のホーム長,受け入れ担当者の方,施設のスタッフの方からのアドバイスをもとに,
以下のような目標を掲げました。
目標
1)「テレビなどで報道されている介護の現状とレストヴィラみつわ台の介護の違い」について知
ること
2)「子どもの保育と高齢者介護の共通点」について考えること
3)「認知症の方とその他の方の接し方の違い」について学ぶこと
5.研修のスケジュール
研修スケジュールの概要は以下の通りです。
8月17日 9時 1階 老人保健施設と特別老人養護施設と有料老人福祉施設の違いについて
学ぶ
14時 1階 認知症,ワタミの介護について学ぶ
8月18日 10時40分 2階 ワタミ体操,脳トレ(ことわざ,四字熟語など)
13時40分 3階 日本列島パズル
15時30分 食堂 俳句を詠む
8月19日 10時00分 円居 “ご入居様”と会話(故郷,野球などの話)
13時45分 食堂 カラオケ
15時 食堂 “ご入居様”と一緒に納涼祭の準備で盆踊りの練習を行う
8月20日 10時 3階 “ご入居様”に納涼祭の準備で塗り絵や習字を書いてもらう
15時 食堂 キープアップ体操
8月21日 10時45分 2階 ワタミ体操
15時30分 2階 コーラス(椰子の実など)
8月22日 10時00分 円居 “ご入居様”と会話(働いていた時の話)
10時40分 2階 2・3階合同でワタミ体操,脳トレを行う
11時15分 2階 DVD(ドリフターズ)
8月24日 15時00分 食堂 キープアップ体操
8月25日 13時45分 2階 “ご入居様”に納涼祭の準備で習字を書いてもらう
8月26日 10時00分 円居 “ご入居様”と会話(娘や息子の話)
13時45分 食堂 カラオケ

─ 39 ─
14時45分 食堂 ピアノ・独唱(バッハ・荒城の月)
8月27日 15時00分 食堂 キープアップ体操
8月30日 納涼祭 当日
研修では,11時から1階食堂にて昼食,15時からおやつの準備を手伝い,その他の時間は“ご入居
様”と会話をしました。また,24日・25日・27日は納涼祭の準備を行いました。27日の研修最終日は
2・3階の方だけでなく1階円居の“ご入居様”とも会話をしました。
ワタミ体操や脳トレは毎日行っていました。脳トレでは「私が全く読めない」「計算できない」「知
識的に知らないこと」を“ご入居様”が簡単に解いていたのが印象的でした。
クラブ活動の俳句では,介助してもらいながらソフト食で食事をした“ご入居様”が俳句を詠んで
いました。「土曜の丑の日にお重箱で鰻を食べた」という気持ちを土曜の丑の日近くに詠んでいたこ
とが印象的でした。
6.研修で学んだこと
インターシップの11日間の期間で学んだことは大きく以下の3つでした。
① レストヴィラみつわ台の介護の特徴
インターシップの第一の目標は「テレビなどで報道されている介護の現状とみつわ台の介護違い」
について知ることでした。テレビでは,労働量と賃金のバランスが比例していないため,生活や将来
への不安があり,結婚や出産を諦める介護士が増えていると各局が報道していました。しかし,レス
トヴィラみつわ台で働いている介護士は,平均年齢も若く,家庭や子どもを持ち,また育児休暇中の
人もいて,テレビでの放送とは違った姿を見ることができました。
また,施設の雰囲気も違いました。3階は,自分で何でもできる“ご入居様”が入所しているので
自由な生活空間が提供されており,2階は,我が家の部屋にいるような空間を提供していました。ま
た,認知症の方だけは1階の円居の部屋で,みんな一緒に家族団欒のような空間を提供しており,そ
れぞれ自分の家で生活しているかのようなスタイルが特徴だと思いました。
② 子どもと高齢者の食事に関する共通点
インターシップの第二の目標は「子どもの保育と高齢者介護の共通点」について考えることでした。
子どもと高齢者の共通点はいくつかありましたが,その中でも自分が強く興味を持ったことがありま
した。それは「食事」形態です。子どもは咀嚼機能が向上していくと母乳,人口栄養,ごっくん期(5
~6ヶ月),もぐもぐ期(7~8ヶ月),かみかみ期(9~11ヶ月),ぱくぱく期・もりもり期(12ヶ月~)
と変化していきます。高齢者は咀嚼能力が低下していくため,子どもの食事形態とは反対方向に変化
していきますが,それぞれの段階で,ソフト食のように咀嚼機能が低下してもおいしく食べられるよ
うに,そして見た目にも工夫を凝らして,「一人ひとりに適した形態で食事を提供している」ところ

─ 40 ─
が同じだと思いました。子どもでも高齢者でも食事は生活の楽しみであり,それぞれの咀嚼機能に応
じた食事を提供し,美味しい食事を取れる工夫をしている点は全く同じだと気付きました。
③ 認知症の方への接し方
インターシップの第三の目標は「認知症のご入居様とその他のご入居様の接し方の違い」について
学ぶことでした。認知症の“ご入居様”と接するときは3つのポイントがありました。1つ目は,顔
を覚えてもらうことです。認知症の方には,名前を覚えてもらうよりも,まず顔を覚えてもらい,安
心感を持ってもらうことが重要だとわかりました。2つ目は,コミュニケーションの取り方です。認
知症の方とは言語コミュニケーションよりも非言語コミュニケーションを大切にして接することが重
要でした。3つ目は,スキンシップです。認知症の方の一部分でいいので触りながら会話などを行う
ことが重要でした。この3つをスタッフの方から教えていただきました。
7.まとめ
研修先のレストヴィラみつわ台の昼食は,“ご入居様”がレストランに到着されてから食事が出さ
れるので,いつでも温かいお料理を配膳していました。ところが私は,“ご入居様”の名前と顔が一
致しなくて,職員の方の仕事を止めてしまうことも多くありました。配膳が遅かったり,“ご入居様”
を間違えたり,研修中は,失敗や戸惑いも数多くありましたが,“ご入居様”は,自分の孫に対する
ように優しく教えてくれました。私も,できるかぎり,会話中に“ご入居様”の名前で呼んで顔と名
前を一致させるようにしました。研修が進むにつれて,“ご入居様”の顔と名前が一致し,気軽に会
話をして,食事の配膳ができるようになりました。
レストヴィラみつわ台では毎日,午前中にワタミ体操や脳トレがあり,午後には体操やカラオケ,
コーラス,俳句,詩吟などの1つが行われていました。その時間は“ご入居様”が今の気持ちや昔の
気持ちに戻られ楽しいひと時を送っていました。
今,振り返れば,“ご入居様”に何回「ありがとう」と感謝の気持ちを言っていただけただろうと
思います。何か一つ一つの行動をするたびに「ありがとう」という言葉を聞くことができました。
私は保育士を目指しています。今回は有料老人ホームでの実習でしたが,一人ひとりのことを考え,
その人に合ったものを提供している職員の方の姿勢が深く印象に残りました。一人ひとりのことを考
えて行動するという点において,子どもに接する時とも同様であることを実感しました。高齢者施設
で働くことで,保育実習では味わえないことも今回の研修で学ぶことができました。今回学んだこと
を次の実習やこれからの勉学に生かしていきたいと思っています。